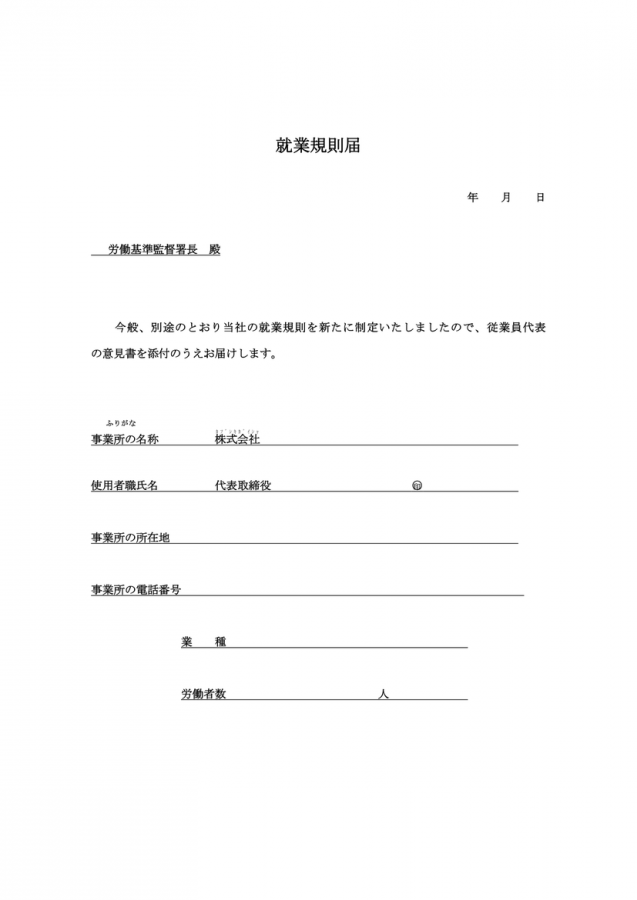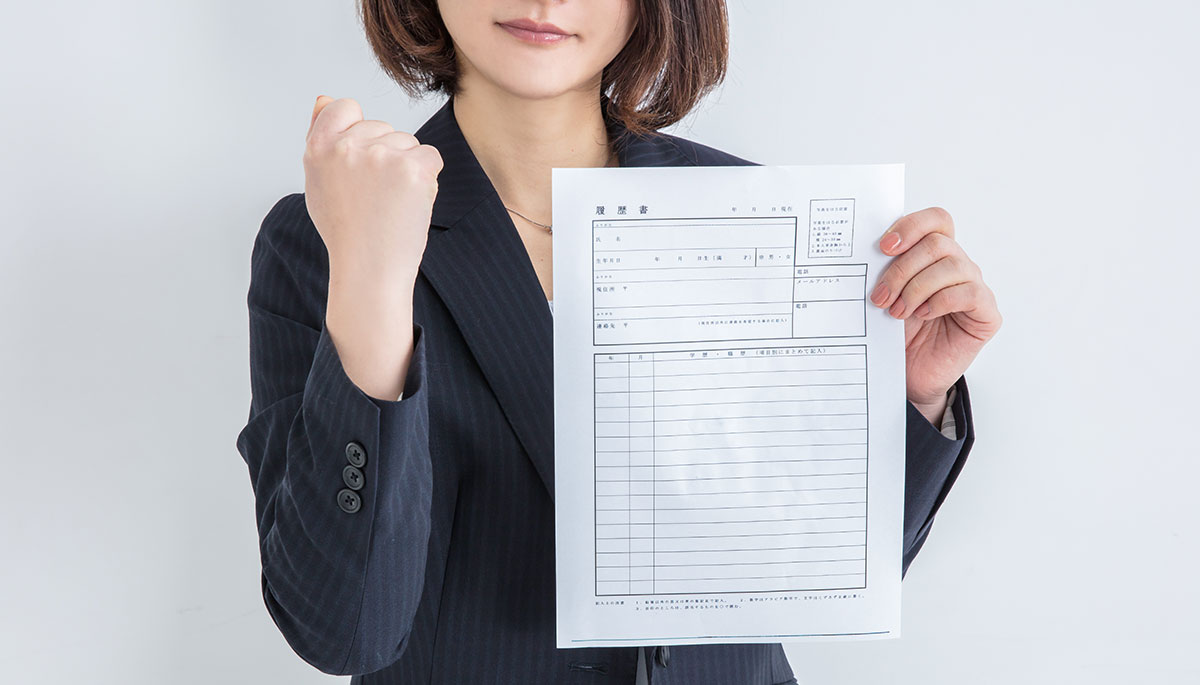長期間、労務の提供ができないパート社員の雇い止めについて
いつもお世話になっております。
弊社の事業所で3年4ヶ月、1度も私傷病により出勤していないパート社員の更新を繰り返している所長がいます。
パート社員に休職制度はありませんので、数か月間、雇用の継続を図り、療養期間を認めるとしても、復職が困難であるなら期間満了で雇い止めすべき事案かと思います。
ちなみに当社の就業規則では、正社員の休職期間は1年と定めていますので、それ以上の期間、労務の提供ができない期間が継続している状況です。
会社として十分、本人の回復を待ち、雇用の継続を図りましたので雇い止めは問題ないと考えてよろしいでしょうか(勤怠不良は就業規則の解雇事由にも該当します)。
また、このように就労できないパート社員を雇用し続けるリスクなどありましたら教えていただけますでしょうか(社会保険は未加入のため、給与マイナスのリスクはございません)。
投稿日:2025/10/16 17:55 ID:QA-0159577
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通りで雇止めされる事で問題はございません。
想定されるリスクとしましては、在籍されている事で何らかの従業員としての権利を主張される可能性がございますので、当人と個別に約束等されていないか念の為ご確認されるとよいでしょう。
投稿日:2025/10/17 09:46 ID:QA-0159587
相談者より
いつもお世話になっております。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2025/10/17 10:59 ID:QA-0159597大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
このような人事管理は所長の所管かと思いますので、その職務を果たしているのか厳重に確認して下さい。直接的な損害は無かったとしても、他の社員もずるずる会社の判断がつかないことを見ていますので、モラルハザードが懸念されます。
通常であれば雇止めだと思いますが、会社が何度も欠勤を認めてきた責任があるため、一方的ではなく復帰のめどがつかなければ退職してもらうよう説得するしかあいでしょう。
無管理状態はこうした交渉も難しくする恐れがあり、管理職の重大な職務怠慢の恐れがあります。
投稿日:2025/10/17 10:06 ID:QA-0159589
相談者より
いつもお世話になっております。
大変参考になりました。
確かに同様の事案が発生した際、雇い止めをしようとしたら、「あの人は3年4ヵ月も待ちましたよね?なぜ、私は6か月だけなのですか?」など収拾がつかなくなる可能性があるかと思います。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/10/17 11:04 ID:QA-0159600大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
結論、雇い止めは問題ありません。
長期私傷病が続き、労務提供がありませんので、適正な対応かと存じます。
また、雇用し続けるリスクの1つとして大きいのは、雇用契約が存続しています
ので、パート社員の方が働きたいと言った時に、雇用主は余程の合理的な理由が
ない限り、勤務を認める必要がございます。この点において、現場として困る
ケースが想定されます。
投稿日:2025/10/17 11:09 ID:QA-0159601
相談者より
いつもお世話になっております。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2025/10/17 11:20 ID:QA-0159604大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.現状整理と基本的考え方
ご提示のケースでは、
3年4か月間、1度も出勤実績がない
パート社員に休職制度がない
正社員の休職期間は1年
会社として回復を待ち、更新を繰り返してきた
という状況ですので、これは実質的に**「労務提供の不能が継続している」**状態に該当します。
労働契約法第19条(有期雇用の雇止め法理)は、
雇止めが「実質的に解雇と同視できる場合」や「更新を期待させる事情」がある場合に、合理的理由・社会的相当性を要求します。
しかし本件では、そもそも労務提供が長期間不可能であり、就労意思も確認できないため、契約の本旨が失われています。
このため、期間満了による雇止めは十分に合理的理由・社会的相当性が認められると判断されます。
2.雇止めを行う際の留意点
(1)形式上は「期間満了による契約終了」とする
就業規則の「勤怠不良による解雇」にも該当し得ますが、パート社員で有期契約の場合、「期間満了による雇止め」の方が紛争リスクが
低く安全です。
「契約期間の満了により更新を行わない」旨を明示し、30日前を目安に本人へ書面で通知します(労働契約法19条の趣旨に沿って)。
(2)説明・通知文書の作成
雇止め通知書には、以下のような記載が望ましいです。
あなたは〇年〇月〇日より私傷病のため出勤されておらず、これまで当社として療養の継続を見守ってまいりましたが、長期にわたり業務に従事できない状態が続いていることから、雇用契約をこれ以上更新することは困難と判断いたしました。
つきましては、現契約期間の満了をもって雇用契約を終了させていただきます。
医師の診断書等を求める必要は必ずしもありませんが、本人の就労意思を確認した記録があるとより安全です。
3.雇用継続を続けるリスク
長期にわたり労務提供がないパート社員を「籍上在籍」させることは、次のようなリスクを伴います。
区分→リスク内容
法的リスク→実態が「雇用関係の実効性を欠く」にもかかわらず契約を継続すると、後にトラブルが発生した際に整理解雇や雇止め判断の基準が曖昧となる。
労災・安全衛生リスク→労働者名簿に残る限り、労災保険上「在籍者」として扱われるおそれ(事故時の責任関係が不明確になる)。
助成金・雇用関連統計上の影響→実働ゼロで在籍を続けると、雇用実態の把握が困難になり、助成金等で実在労働者数との整合が取れなくなる。
人件費・人事管理リスク→いざ就労再開を申し出た場合に配置先・評価基準が不明確となる。就業規則上の勤続年数・退職金計算の扱いなどが不整合を起こす。
4.実務上の対応ステップ(推奨)
現契約の満了日を確認
更新しない旨を30日前目安で通知(文書で)
本人の健康回復・就労意思を確認(記録化)
期間満了により自然終了(雇止め通知書交付)
労働者名簿・雇用保険関係等を整理
5.補足:今後に備えた規程整備ポイント
パート・アルバイトにも、長期欠勤に備えた「短期休職(上限3か月)」や「雇止め基準(○か月以上の欠勤が続く場合は契約を更新しない)」などを、雇用契約書またはパート就業規則に明記しておくことをお勧めします。
6.結論
雇止めは法的に妥当・相当であり問題ない
長期間の雇用継続は、法的・管理的リスクが大きい
文書通知と記録化により、紛争予防措置を確実に行う
以上です、よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/10/17 12:11 ID:QA-0159608
相談者より
いつもお世話になっております。
わかりやすく整理していただき、ご回答いただき有難うございました。
とても参考になりました。
投稿日:2025/10/17 15:02 ID:QA-0159626大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
労働契約法
以下、回答いたします。
【御相談(1)】
会社として十分、本人の回復を待ち、雇用の継続を図りましたので雇い止めは問題ないと考えてよろしいでしょうか(勤怠不良は就業規則の解雇事由にも該当します)。
【回答】
(1)労働契約法第19条が関係すると考えられます。
(有期労働契約の更新等)
第十九条 有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。
一 当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。
二 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。
(2)「私傷病により出勤していないパート社員の更新を繰り返している」とのことですので、当該労働者が、上記二号の「当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由がある」と主張することが考えられます。
仮にこうした主張が認められた場合には、雇止めの可否については、いわゆる正社員の解雇に準じた検討(解雇権濫用法理の類推適用)が求められることになるものと認識されます。これに関しては、「正社員の休職期間は1年と定めていますので、それ以上の期間、労務の提供ができない期間が継続している状況です。会社として十分、本人の回復を待ち、雇用の継続を図りましたので雇い止めは問題ないと考えます。勤怠不良は就業規則の解雇事由にも該当します。」との御主張は「是」と認識されます。
【御相談(2)】
このように就労できないパート社員を雇用し続けるリスクなどありましたら教えていただけますでしょうか(社会保険は未加入のため、給与マイナスのリスクはございません)。
【回答】
(1)労働契約法第18条が関係すると考えられます。
(有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換)
第十八条 同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。以下この条において同じ。)の契約期間を通算した期間(次項において「通算契約期間」という。)が五年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。この場合において、当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件は、現に締結している有期労働契約の内容である労働条件(契約期間を除く。)と同一の労働条件(当該労働条件(契約期間を除く。)について別段の定めがある部分を除く。)とする。
(2)二以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間が五年を超えた場合には、当該労働者の申込みにより、無期労働契約に転換することになります。
なお、契約期間中の解雇については、労働契約法第17条が関係し、「やむを得ない事由」が求められることになります。
(契約期間中の解雇等)
第十七条 使用者は、期間の定めのある労働契約(以下この章において「有期労働契約」という。)について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
投稿日:2025/10/17 20:12 ID:QA-0159644
相談者より
いつもお世話になっております。
わかりやすく根拠を示していただき、今回の事案に関する考え方、リスクについて、とてもよく理解できました。
ありがとうございました。
投稿日:2025/10/20 09:17 ID:QA-0159667大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
パート社員の60歳以降の雇用について パート社員には、60歳定年制を就... [2017/12/15]
-
パート就業規則の記載事項 さて、就業規則(正社員に適用、パ... [2017/02/08]
-
正社員からパートへ変更した社員の、正社員雇用について 社員で、5年前まで正社員で勤務い... [2024/02/08]
-
パートの労働時間 当社では他社と掛け持ちで働いてい... [2005/06/07]
-
65歳超の雇用期間について このたび66歳の方を正社員で雇用... [2017/05/26]
-
育児休業中の雇用切替について こんにちは。どなたかご教示頂きた... [2021/12/02]
-
障害者の雇用 障害者を雇用する際の留意点を教え... [2006/12/05]
-
外国人労働者の雇用について 外国人の方を雇い入れる際の注意事... [2005/08/23]
-
就業規則・パート就業規則、嘱託就業規則について 就業規則ですが、無期雇用対策のた... [2018/03/08]
-
パートタイマーの雇用契約期間に関して② 以下のようなパートタイマー規程を... [2010/10/05]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
就業規則届
労働基準監督署に届出するための就業規則届です。是非ご利用ください。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント