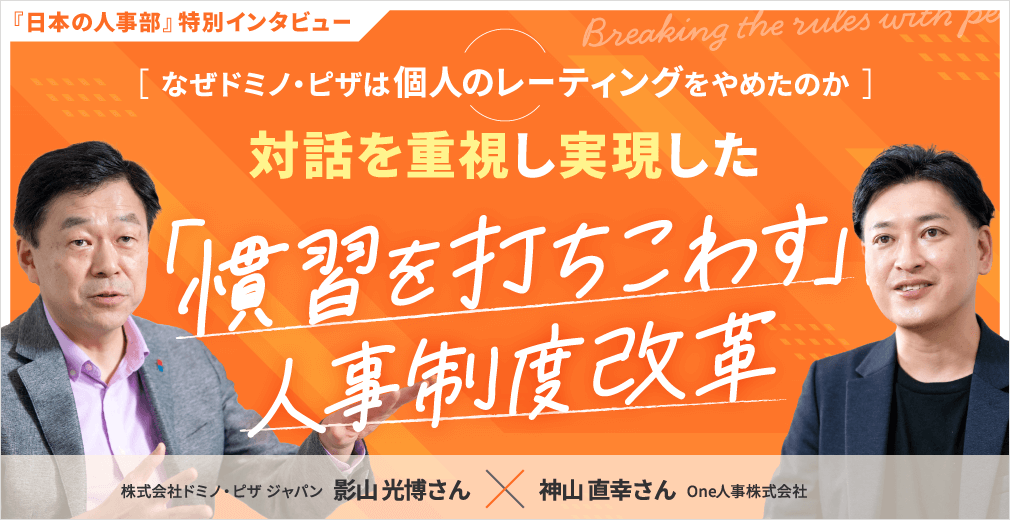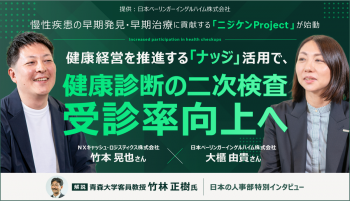多くの企業が導入しているMBO(目標管理制度)や人事評価制度は、従業員の成長と組織の発展に本当に貢献しているのでしょうか。株式会社ドミノ・ピザ ジャパンは、3年前、OKR導入を機に、個人評価制度を廃止するという大きな決断を下しました。その背景には、「最高の人財」を集め「団体競技」で勝つという考え方と、性善説に基づく従業員への信頼関係がありました。同社で人事の変革をリードするHRビジネスパートナーの影山光博さんに、One人事株式会社の神山直幸さんが、「攻めの人事」を支えるカルチャー、そしてサステナブルな組織の未来像について聞きました。

- 影山 光博さん
- 株式会社ドミノ・ピザ ジャパン HRビジネスパートナー
かげやま みつひろ/1989年日本マクドナルド株式会社に入社。米国シカゴで店舗経営を学んだ他、HR統括マネジャーとして戦略人事、HRBPロールなどを経験。株式会社シャノアール(カフェ・ベローチェ)を経て、2019年株式会社ドミノ・ピザ ジャパンへ入社。2024年からはグローバルのHRBPとして台湾のドミノ・ピザも担当。

- 神山 直幸さん
- One人事株式会社 HRTech SaaS事業部 フィールドセールス3部 部長
かみやま なおゆき/前職、株式会社HRBrainでは営業責任者としてSaaS型タレントマネジメント領域にて100社超の導入を支援。経営層との対話を通じた課題特定と戦略設計を強みに、組織変革と人的資本経営の実装を推進。2025年、One人事株式会社に入社。フィールドセールス部にてエンタープライズ企業を中心に人・組織の成長を軸に価値創出をリードしている。
OKR導入がもたらした人事制度改革
神山:MBOや個人をランキング付けする人事評価を廃止し、OKR(Objectives and Key Results)を導入した経緯についてお聞かせください。
影山:OKRは、人事部門が主導した人事施策というわけではありません。ドミノ・ピザのグローバル全体における経営方針として導入されました。「より短いスパンで会社の目標を立て、全社で取り組むべきことにフォーカスし、事業のスピード感を上げていこう」という意図です。ストレッチなゴールを掲げ、組織としてのアライメントを強化する狙いもありました。
神山:従業員から戸惑いの声はありませんでしたか。
影山:当社にはもともと、スピードを重視する文化が根付いています。のんびりしていたら、ピザが冷めてしまいますからね。その文化が土台にあったので、OKRも受け入れやすく、うまく機能したのだと思います。
導入にあたっては、OKRと人事評価制度とのマッチングが課題でした。四半期ごとに高い目標を掲げて全社で動くOKRと、半期に一度や年に一度、個人が目標を立てるMBOでは、時間軸が違い、目指すゴールの性質も異なります。この矛盾をどう解消するかが、人事部門にとって大きな課題として立ちはだかりました。
私はドミノ・ピザに入社した当初から、CEOに「従業員の評価を単純にAやBといった記号でランク付けするのはおかしいのではないか」と問われ続けていました。当時は「日本の企業は皆やっていることです」と答えていましたが、その問いがずっと心に引っかかっていたのです。その議論がすぐさま制度変更につながったわけではありませんが、OKR導入という大きな変化が、この根本的な問いと向き合うきっかけになりました。
神山:ある意味外部からの変化が、内部の課題を解決する引き金になったのですね。
影山:ただし、すぐに新しい制度を導入したわけではありません。経営の新しい方針を示した上で、私たちは従業員の声に耳を傾けました。「これからどうすべきだと思うか」という対話を重ね、人事としての方針を固めるプロセスを踏みました。

神山:従業員との対話を通して、具体的にどのような施策に取り組んだのでしょうか。
影山:三つの方針を打ち出しました。一つ目は「Pay for Job」。個人のパフォーマンスを比較して給与を決めるのではなく、職務の役割と責任の大きさに基づいて給与を支払うという、いわゆるジョブ型雇用の考え方です。二つ目は「No Rating」。仕事そのものに報酬を連動したことで、個人をランク付けするような評価をする必要がなくなったため、廃止しました。そして三つ目が「One Team/Profit Sharing」です。OKRの下ではビジネスは「会社対会社の団体競技」だと位置づけ、個人の評価ではなく、会社全体の成果として利益を分配するようにしました。
「最高の人財」の採用が、性善説に基づく組織を支える
神山:No Ratingを導入すると、「個人の成長をどう促すのか」「適切なフィードバックは可能なのか」が懸念されます。その点については、どのようにお考えでしょうか。
影山:ドミノ・ピザのオフィスは「最高の人財」で構成する、というのが私たちの基本的なスタンスです。最高の人財とは、入社時にすでに高い専門性を持っている、あるいは新しい分野を任された際に自ら学ぶ能力がある人財。つまり、「入社してから育成しよう」という発想があまりありません。そして、「人は自ら学び、成長する能力を持っている」「人は正しく働くはずだ」という、性善説が深く根付いています。この信頼があるからこそ、団体競技が可能になります。
「育成」という言葉は、裏を返せば「その人はまだできない。自ら成長しない。」という前提に立っています。私たちは「できている」ことを前提に対話するため、いわゆる集合研修のような機会は極端に少ないかもしれません。
神山:非常にユニークな考え方ですね。その考え方は、業界の特性とも関係があるのでしょうか。
影山:大いに関係があります。私たちのビジネスモデルは、ピザを焼き、配達して代金をいただく、という非常にシンプルなもの。したがって、会社の投資対象は、第一に店舗で働く人たちです。高校生で初めてアルバイトをするような若い従業員に対しては、手厚い教育投資を行い、定期的に表彰するなど、その成長と活躍を全力で応援します。
一方、私たちが働くオフィスは「本社(ヘッドクォーター)」ではなく、「SST(ストアサポートチーム)」と呼んでいます。店舗をサポートすることが私たちの役割なので、自分たちに投資するよりも、お客さまと直接向き合う店舗に投資する方が合理的である、という考え方が根底にあります。これは、現場第一主義の考え方で、多くの外食企業に共通する考え方だと思います。
神山:OKRは団体競技なので、手を抜く人も出てくるのではないでしょうか。
影山:確かに、OKRだけでは団体競技の色合いが強くなり、個人の動きに対するマネジメントや動機付けが弱くなる可能性があります。サッカーで言えば、同じピッチ内で一生懸命走っている選手と、そうでない選手が出てきてしまう。そういう例えができます。
「走っていない選手」をどうマネジメントするか。そのために導入したのが「CFR(Conversation, Feedback and Recognition)」です。継続的なConversation(対話)、Feedback(フィードバック)、そしてRecognition(承認)を繰り返すことで、チーム内での個人の貢献を可視化し、エンゲージメントを高めていくのです。特にフィードバックや承認といった文化は、もともと外資系企業である当社が得意とするところであり、スムーズに導入することができました。
バリューを体現する「Go Gemba!」やフラットな組織づくりの仕掛け
神山:貴社の五つのバリューの中に「慣習を打ちこわす」という言葉があります。このバリューをどのように体現しているのでしょうか。
影山:ひとつ例を挙げると「Go Gemba!」という、オフィスで働く社員が定期的に店舗を訪れて現場の業務を体験するプログラムです。
「Go Gemba!」はオフィス社員が店舗で働くプログラムです。最たる例として、CEOやCOOらの幹部が集まり、特に優秀な成績を収めた店舗を開店から閉店まで運営する、というものがあります。その間、本来の店舗スタッフは全員、会社が用意したバーベキューパーティーなどを楽しむのです。
店舗出身の幹部層は全員、ピザを焼くことができます。そして、彼らが運営するその日の店舗は、驚くほど高い顧客満足度(NPS)と売上を記録します。普段のクルーたちが見たこともないような数字を叩き出し、「このくらいできる」という基準を、身をもって示しています。
オフィスにいる幹部層や人事部門がどれだけ立派なことを言っても、「現場のことが分かっていない」と思われてしまえば、その言葉は届きません。「Go Gemba!」を通じて、経営と現場が一体となり、リアルな言葉で対話できる。これは、カルチャーを醸成する上で極めて重要なプログラムです。幹部やオフィス社員が現場の変化に気づけるかどうかで、従業員のエンゲージメントや売上は大きく変わります。
神山:人事部門も慣習を打ちこわし、変革しているのでしょうか。
影山:従来の階層的な組織構造を壊し、フラットな組織を目指しています。たとえば、部長や課長といった役職名を廃止しました。私は「HR部 部長」でしたが、現在は「HRビジネスパートナー」に変わっています。もちろん人事データ上は職務等級が存在しますが、日常業務において「〇〇部長」と呼ぶことはなく、「〇〇さん」と呼ぶようになります。
フラットな関係性が、私たちの組織のスピード感と率直なコミュニケーション文化を支えています。慣習を打ちこわすような人事制度は、他に「国際在宅勤務制度」「Domi Club(ドミクラ)」「つながるピザ」「WLB手当」「Domi Knows」など数多くあります。
「守りの人事」と「攻めの人事」のバランス感覚
神山:新しい制度を導入する際は、反対意見や不満の声が上がることが多いと思います。そうした声に、どのように向き合っていますか。

影山:新しい制度を導入した際の反応は、非常に注意深く観察しています。反対意見を無視することは決してありません。反対意見や課題を挙げてくれる従業員は、物事を深く考えていて具体的な対案を持っているので、ありがたい存在です。そうした人たちとの対話を恐れないことが、変革を進める上では不可欠です。
神山:「慣習を打ちこわす」という姿勢と、人財を扱う上で求められる慎重さとのバランスをどう取るかは、非常に難しい課題ではないでしょうか。
影山:推進のキーワードは「守りの人事」と「攻めの人事」だと思っています。私がこれまで話してきた取り組みは、すべて「攻めの人事」に分類されるでしょう。しかし、決して「守り」をおろそかにしているわけではありません。
人事部門に10人のメンバーがいれば、そのうち7人程度は「守り」を担っています。給与計算や労務管理といった基本的なオペレーションを、間違いなく、正確に遂行する。「守り」が盤石でなければ、そもそも組織は成り立ちません。
その上で重要なのは、強みを生かす役割分担です。私は人事を専門としてキャリアをスタートしたわけではないので、労務や法務といった「守り」は得意分野ではありません。その代わり、強みであるビジネスの視点から変革を仕掛ける「攻め」で価値を発揮したいと考えています。幸い、当社には非常に優秀な「守り」のプロフェッショナルが数多く活躍しています。私は「攻め」に集中できるよい環境にいると言えます。
まず強固に守りを固めた上で、攻めるべきポイントを見定めて仕掛けていく。このバランスが、変革を成功させる鍵だと考えています。
未来への責任感が、人事の変革を支える原動力
神山:新たな人事制度を導入して3年ほど経過しました。組織にはどのような変化がありましたか。
影山:「Pay for Job」「No Rating」「One Team/Profit Sharing」の導入当初は、たとえば「頑張ってもボーナスが皆と同じなのはおかしい」といった声が一部でありました。しかし、今ではそうした声は聞こえなくなりました。そもそも「ボーナス」という言葉も当社では使わなくなりました。私も大きな変化を感じています。
まず、「私たちはチームで戦っている」というカルチャーが浸透しました。私たちは常々、「あなたのライバルは社内の同僚ではなく社外にいる。他の会社の同じ役割の人だ」と伝えています。社内の人間と比較するのではなく、市場における自分の価値を意識する。その考え方が定着して欲しいと思います。
神山:今後さらに強化したい点はありますか。
影山:在宅勤務が普及するなど働き方が多様化する中で、従業員の働きぶりが見えにくくなっている側面は否定できません。そのため、CEOからは、パフォーマンスマネジメントを強化してほしいという要望が出てきています。
これは、レーティングを復活させるという意味ではありません。従業員一人ひとりが「どのような成果を残し、どう活躍し、どんな成長を遂げているのか。そして、どのようなキャリアプランを持っているのか」について、より丁寧に対話していく必要性を感じています。そのための新しい取り組みとして、「JP&R(Job Performance & Review)」の導入を検討しています。
JP&Rは、一般的な人事評価制度とは大きく違い、キャリアに関する対話をより構造的に行うための仕組みが特徴です。「キャリア」についての対話は四つのテーマで話し合います。一つ目は「プロフェッショナル開発」。現職での専門性を高めるために何が必要かを議論します。二つ目は「キャリア開発」で、次にどのポジションを目指すかといった話です。三つ目は「自己開発」。プライベートも含め、人としてどう成長したいかを話し合います。そして四つ目は、「バケーション」です。
神山:キャリアの対話に「バケーション」が含まれるのですか。
影山:単なる有給消化の話ではありません。昨今、ビジネスパーソンにはビジネススキルよりもアートのような感性(センス)が求められると言われます。質の高い休暇を取り、新しい物事に触れる経験を積むことで、その感性が磨かれます。従業員がどのように休み、それを自己成長にどうつなげていくかを一緒に考える。これもJP&Rの重要なファクターだと捉えています。
神山:最後に、影山さんが考える「サステナブルな企業文化」とは何かを、お聞かせください。
影山:「サステナブル」という言葉を考えるとき、常に意識しているのは「この施策は、10年後の後輩たちのためになっているか」です。今の従業員に満足してもらうだけではなく、将来の会社をつくる感覚が、人事部門には必要です。人事制度は定着までの時間を要します。だからこそ、目先の課題解決だけでなく、長期的な視点が不可欠です。たとえば、「自分の娘や息子が、将来ここで働かせたいと思えるような会社になっているか」と自問します。
5年後、10年後の後輩たちが、この会社に誇りを抱いて働けているか。その未来像を描きながら、今なすべきことを企画し、導入していく。それが、私たち人事パーソンに課せられた、サステナブルな組織づくりのための責務だと考えています。
神山:未来への責任感が、人事の変革を支える原動力なのですね。本日はありがとうございました。

One人事は、パーパス「すべての働く人を笑顔に。」を実現するため、人材管理から人材戦略までワンストップで企業の成長を支援する人事労務システム「One人事」を開発・提供しています。そのほか、公的機関向け人事DXソリューション「One人事[Public]」の開発・提供、受託開発・SESによるDX支援も展開し、民間・公共双方の人事DXを推進しています。

HRのトレンドと共に、HRソリューション企業が展開するさまざまサービスをご紹介。自社に最適なソリューションを見つけてください。
会員登録をすると、
最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント