HRテクノロジー(HR Tech、HRテック)とは

「HRテクノロジー(HR Tech)」とは、クラウドやデータ解析、人工知能(AI)、仮想現実(VR)など、最先端のテクノロジーを使って、採用・育成・評価・配置などの人事関連業務を行う手法のこと。担当者の「経験則」と「勘」によって支えられてきた人・組織関連業務において、テクノロジーの力で変革を求めるニーズの高まりを受けて、HRテクノロジーの活用が日本でも進んできている。(2019/12/23更新)
HRテクノロジーの定義
近年、「FinTech(フィンテック)」や「EdTech(エドテック)」「AgriTech(アグリテック)」など、「○○テック」という言葉を耳にする機会が増えてきた。こうした「○○テック」は、総称して「X-Tech(クロステック、エックステック)」と呼ばれている。
「Tech(テック)」とは「Technology」の省略形で、最新のテクノロジーを活用して既存の業界・分野にそれまでなかった画期的な価値をもたらすサービスや製品全般を指し示す名称が「X-Tech」となる。
そして今、HR関連領域でも高度なテクノロジーと人事関連業務を融合させた「HRテクノロジー(HR Tech、HRテック)」(Human Resource × Technology)が注目されている。「HRテクノロジー」とは、クラウドやデータ解析、人工知能(AI)、仮想現実(VR)、拡張現実(AR)、ロボティクスなど最先端のテクノロジーを使って、採用・育成・評価・配置などの人事関連業務を行う手法を意味する。
人事部門が担う「10の業務分野」
「HRテクノロジーを活用したいが、何から手をつければいいのかわからない」と悩む人事担当者は少なくないだろう。現状でも数多くのサービス情報へ容易にアクセスできるが、その前段として、まずは「テクノロジーを用いてどの人事課題を解決するべきなのか」を明確にしておく必要がある。例えば、下記の10の業務分野などが考えられる。
- (1) 戦略立案
- (2) 採用
- (3) 異動・配置・昇進
- (4) 育成・研修
- (5) 評価・組織サーベイ・従業員満足度・エンゲージメント向上
- (6) リテンション・退職
- (7) 健康管理・メンタルヘルス
- (8) 業務効率化
- (9) リモートワーク・働き方
- (10) 社内コミュニケーション
10の分野それぞれにおいて、業務を効率化し、人的対応を超えた大きな成果をもたらすために存在するのがHRテクノロジーである。もちろん組織によって上記の分類が変わったり、人事以外の部門が関連したりすることもあるだろう。そうした個別事情にかかわらず重要なのは、分類された業務分野それぞれに対応するテクノロジーがあることを認識しておくことだ。
HRテクノロジーの活用は「業務分野と課題」から検討するべき
「HRテクノロジー」の一般的な定義は、冒頭で示した通りだが、本稿ではそれに加えて「人事業務の分野ごとに存在する課題を技術によって解決し、効率化と成果拡大をもたらす」ものを「HRテクノロジー」と捉えて論を進めていきたい。
AIに機械学習、ビッグデータ解析、IoT(Internet of Things)、AR、VR、さらにはロボティクスまで、HRテクノロジーに関連して登場する技術分野は非常に幅広い。今後も日進月歩で新たな技術トレンドが到来し、それに伴って斬新なサービスが開発されていくはずだ。
そのため、HRテクノロジーの活用を「技術面から」検討していくことは非常に難しい。効率化と成果拡大が必要な業務分野はどれか。どんな技術・サービスを活用することでそれを実現できるのか。あくまでも「業務分野と課題から」HRテクノロジーの活用を検討していくことが望ましいと言えるだろう。
HRテクノロジーが求められる背景
ICTの進化は、ありとあらゆる市場に構造変化をもたらしている。「第4次産業革命」ともいわれるこの現象は人事の分野も無縁ではなく、HRテクノロジーという言葉は瞬く間にトレンドワードとなった。その背景を紐解いてみたい。
画一的大量生産から、個々に異なるニーズを持つ消費者への対応へ
「産業革命」といえば、もともとは18世紀後半のイギリスで始まった工業化を指すが、ドイツ政府はインダストリー4.0と呼ばれる技術戦略の中で、その後の技術発展段階を四つに分けた。蒸気機関などを利用して工場の機械化を成し遂げた第1次産業革命に始まり、20世紀に入ってからは電力による大量生産を可能にした第2次産業革命へ。1970年代以降は情報技術の発展によって、さらなるオートメーション化が進んだ。
そして現代。インターネットがもたらしつつある第4次産業革命を前に、企業活動は根本から変わりつつある。新たに生み出した製品には一般消費者からの無数のレビューが寄せられ、瞬時に集約された口コミによってその評価が定められるようになった。企業の宣伝活動は必ずしも意図した通りの効果を生み出せなくなっているが、一方では資力の乏しいスタートアップでも、ものづくりの本質を追求することで大企業と十二分に戦える時代となった。
こうしてビッグデータがあらゆる局面で活用される時代には、従来のような画一的大量生産のビジネスモデルはそぐわない。多様性に富み、個々に異なるニーズを持つ消費者に対して、いかに最適な商品を提供していくか。ECサイトでの絞り込みや比較に耐え、どれだけ選ばれ続けるブランドを作っていけるか。企業にはそんな生産活動が求められるようになっている。
限られたマンパワーで、より高いレベルの成果を求められる人事部門
多様化しているのは消費行動だけではない。昨今叫ばれ続ける「働き方改革」に見られるように、個人の働き方、そして生き方もまた多様化し続けている。人事は真の意味で一人ひとりと向き合わなければならない時代に突入しているのだ。
同時に、人口減少社会に突入した日本では、将来にわたって恒常的な労働力不足が避けられない状況となっている。深刻な採用難は、かつてのように景気の波に左右され、改善されるものではない。労働人口が減少し続けていく、世界でも類を見ない超高齢社会。従来の採用手法を従来の採用ターゲットに向けて継続するだけでは人手不足を解消できないことは、多くの人事担当者が痛感しているだろう。
人事部門そのものも、これまでのように人員を割いて対応していくことは難しくなる。社内の多様性と向き合い、採用難時代と戦い続けながらも、マンパワーは絶対的に不足していくのだ。変化し続ける世の中を前に、かつての「経験則」や「勘」も通用しなくなっていく。このような環境の中、高いレベルでコンプライアンス強化を図りながら、激しい競争環境にさらされる企業の舵取りを担っていかなければならないのが現代の人事部門である。
人事部門が向き合っていくべき具体的な課題とは
多様性の時代に人事が向き合っていかなければならない課題とは何か。前述の業務分野に沿って挙げてみよう。
(1) 戦略立案
経済構造の変化に伴い、自社の事業戦略やビジネスモデルも刷新されていくはず。それに適合した組織や人事制度の設計を行い必要な人材の獲得と活用を可能にする柔軟な人事戦略の立案が求められる。
(2) 採用
売り手市場が続く新卒採用市場でどう戦っていくか(そもそも新卒一括採用という仕組み自体を維持し続けるのか)。中途採用の市場も限られる中で、費用対効果をどこまで追求していけるか。専門的なスキル・知識を持つ人材を確保するためには、定年退職者の再雇用にも幅広く対応していく必要がある。外国人の活用も喫緊の課題と言える。
(3) 異動・配置・昇進
働くことへの価値観は、個人によって大きく異なる。地方転勤や海外赴任、異動においても個々人のワークライフバランスやライフステージを一層考慮しなければならない。ダイバーシティ推進の観点では、女性管理職の登用に注力すべき企業も多いだろう。
(4) 育成・研修
多くの企業で優先課題として挙げられているのが次世代リーダーの育成。国内だけでなく、グローバルでも活躍できる人材を育てていく必要がある。従来型の一括研修では対応できないケースも多い。
(5) 評価・組織サーベイ・従業員満足度・エンゲージメント向上
企業活動の根本となる理念の浸透、次世代リーダーの特定、女性に対する差別的待遇の撤廃など、従来型の人事評価制度で測ることが困難な課題も増えてきた。エンゲージメント向上が事業発展に不可欠であると重視する企業も増えている。
(6) リテンション・退職
人手不足がさらに拡大していく将来、人材は企業の最重要資産となる。必要な人材の離職防止に向けた取り組みはもちろん、社内のキャリア選択の幅を広げ、個々人のキャリアプラン実現を支援する仕組み作りも求められる。
(7) 健康管理・メンタルヘルス
人生100年時代にあって、働く個人の健康維持を支援する「健康経営」が企業規模を問わず求められるようになった。欠勤や休職などで職場を離れざるを得ない状態を指す「アブセンティーズム」(absenteeism)や、出勤していても心身の健康上の問題により十分な成果を発揮できない「プレゼンティーズム」(presenteeism)の防止は、緊急性の高い課題の一つだ。
(8) 業務効率化
長時間労働の是正・抑制は企業の義務。短時間でこれまで以上の成果を上げるために、社内のあらゆる部署において業務効率化を進めていかなければならない。これは、一連の課題と向き合う人事部門においても、もちろん同様だ。
(9) リモートワーク・働き方
時間と場所に縛られることなく働きたい、と考える個人のニーズが高まり続けている。リモートワークは、出産や介護などと向き合う従業員の離職を防ぐためにも必要な仕組みと言える。働き方改革の波の中で新しい働き方が続々と発信され、企業の採用ブランディングにも大きな影響を与えている。
(10) 社内コミュニケーション
ダイバーシティの進展、ジョブ型雇用の増加とキャリアの複線化、リモートワーカーの増加によって、多くの企業で社内コミュニケーションの希薄化が顕在化した課題となっている。インナーブランディングを担う部門とも協働し、活性化を図っていく必要がある。
10の課題・分野それぞれに対応したソリューションが生まれ、進歩を続けている
こうした分野別の課題を改めて見渡すと、その多くがここ数年のうちに顕在化してきたものであることに気づくだろう。かつてない変化の波にさらされている現代では、人事部門の課題もまた、加速度的に増え続けていくことが予想される。
さらに、個別の課題は「それ単体だけで収束するものではない」ということも念頭に置いておかなければならない。新卒採用市場で勝ち残らなければ次世代リーダーは育成できず、ダイバーシティに富んだ多様性のある職場作りも実現しない。グローバルでは戦えない組織を引きずっていくことで業績悪化を招き、ただでさえ希少な人材が次々と離れていくことになるかもしれない。そうなれば新しい働き方を試みる余裕が失われ、長時間労働を余儀なくされた職場から発信された悲痛な叫びはネット上を駆け巡り、いつしか自社は「ブラック企業」として名をはせることになってしまうだろう。
HRテクノロジーとそれを具体化したさまざまなサービスは、こうした状況を踏まえて日々進歩を続けている。「お金のあり方」を大きく変えたFin Tech(フィンテック)のように、HRテクノロジーもまた職場における人のあり方(働き方、学び方)を激変させようとしているのだ。上に挙げた10の分野・課題のそれぞれに対応したソリューションが生まれ、し烈な競争環境の中で新たなプレーヤーが続々と誕生している。
HRテクノロジーに関わるテクノロジーの種類
一口に「HRテクノロジー」と言っても、そのカバーする領域は広く、対応する技術もさまざま。HRへの応用を考える上で、まずはそれぞれの技術特性を押さえておくことが必要となる。ここでは人事分野にとらわれることなく、各テクノロジーのトレンドをまとめてみたい。
AI――「学習」「推測」によって人間と同等の知能を目指す
まずは「人工知能(AI)」について取り上げたい。GoogleやAmazon、LINEといったインターネット業界を代表する企業から相次いで人工知能を搭載した「AIスピーカー」が発売され、話題となった。日常生活でもいよいよ、AIを身近なテクノロジーとして活用する時代に入ったと言えるだろう。
AIとは「Artificial Intelligence」の略称。これを日本語訳で人工知能と呼んでいる。人工的に人間と同等の知能を持たせようとする研究は1950年代から行われており、小説や映画でもたびたび取り上げられる「未来技術」だった。私たちがAIの進化に触れてSFの世界を想起するのは、その長い研究の歴史があってこそなのだ。
機械が人間と同等の知能を得るには――。そうした研究テーマの中で注目されてきたのが「学習」と「推測」という機能だ。例えば小さな子どもは、「道路に飛び出してはいけない」と繰り返し親から注意を受けて育つ。しかし注意されるだけでは、道路に飛び出してはいけない理由がわからない。実際に歩行者や自転車、自動車が行き交う道路を見て、ときには他者とぶつかりそうになるという危険な状況を体験し、「道路に飛び出すと怪我をする可能性がある」ことを学習する。そして次の機会からは、「道路の先に自転車が走っているかもしれない」と推測できるようになる。
このステップはAIも同じ。大量のデータをもとに物事の規則性や関連性を見つけ、機械自らが判断できるように育てていくステップを「機械学習」(Machine Learning)と呼んでいる。さらにこれを発展させ、人間が学習内容を細かく指示しなくても学んでいけるようにした仕組みが「深層学習」(Deep Learning)。人間の実際の脳神経回路をモデルにしたアルゴリズムによって、機械自らが学習を続け、推測する力を身につけていくのだ。
では、企業や人事部門がテクノロジーやAIを積極的に活用していく際に留意すべき点はあるのだろうか。慶應義塾大学商学部の山本勲教授は、データだけを集めて専門家にやってもらおうという意識ではうまくいかない可能性があるとしている。「重要なのは、何のためにテクノロジーを使うのかという目的意識です。実現するための課題は何なのか。課題を整理し、仮説を立てることが大切になってきます。ともすると、導入すること自体が目的になってしまうケースも見受けられます」
その上で、まずは簡単なものでいいので、自分たちで手を動かしてみることを山本教授は呼びかけている。「仮説を持ってデータを確かめてみたり、複数のデータを組み合わせてグラフを作ってみたり。自社でやってみることで、足りない部分が見えてくるはずです。会社について深く知っている人が、テクノロジーのリテラシーを身につけ、ビジネスと結びつけていくことが、テクノロジー活用を成功させる近道です」と語っている。
私たちの身近な存在となったAIスピーカーは、ディスプレイが組み合わされた「スマートディスプレイ」モデルが増えつつある。例えば、2019年6月にはGoogleから「Google Nest Hub」が、アマゾンジャパンから「Amazon Echo Show5」が日本国内向けに発売された。
いずれも、さまざまな情報を音声だけでなくディスプレイにも表示するのが特長といえる。AIスピーカーは、将来的には冷蔵庫内の食材ストックをチェックして買い物の指示を出したり(あるいは自身で「発注」したり)、来訪者を確認した上でドアを解錠したりといったこともできると言われている。家庭内のさまざまな家電製品を巻き込み、まさに「自立した知能」として人間の生活を変えていくかもしれない。
AR/VR――エンターテインメント分野を皮切りに、ビジネスでの応用も進む
テクノロジーの発展は私たちの視覚世界も変えようとしている。ここでは近年の大きな技術トピックスとなっている「AR」「VR」について述べたい。
AR(Augmented Reality)は「拡張現実」と訳される。拡張の対象となるのは実際に私たちが見ている風景だ。目の前にある「実際に見えているもの」に対して、「実際はそこにない、またはあり得ないもの」を組み合わせる。
この分野の非常にわかりやすい例としては、大ヒットしたゲーム「ポケモンGO」が挙げられる。スマートフォンが映し出す実際の街並みの中にゲームキャラクターが現れるという仕組みで世界中にファンを作った。ビジネス領域では、事前のシミュレーションが重要な小売業での活用も進んでいる。例えばとある家具販売大手のオンラインショップでは、購入を検討している家具を自分の部屋に「仮想レイアウト」できる機能を持たせている。従来は買って配置してみなければわからなかった色合いなどをシミュレーションできるようにしたのだ。
一方のVR(Virtual Reality)は「仮想現実」と訳す。バーチャルリアリティも仮想現実も、SFの世界では古くから使われてきた言葉だ。空想の世界や風景の中に人間が飛び込むことで、通常ではあり得ない体験を可能とする。こちらもエンターテインメント分野での活用が顕著で、ゲームの世界では恐竜が住む惑星を探検したり、戦闘機のコックピットに搭乗したりと、日常ではあり得ないことを疑似体験できるようになった。映画やアニメの世界でも、VRを活用したコンテンツ制作が進んでいる。
ビジネスにおいては、観光分野での活用も進む。仮想空間を360°見渡せるというVRの特徴を生かして、写真やテキストだけではなかなか伝わりにくい観光地の魅力をPRしているのだ。国内の自治体には、VRアプリを開発してPRに活用している例もある。

RPA――単純作業の代替だけでなく、企業の意思決定にも影響を与える
人口減少社会にあって、「いかに職場の生産性を向上させるか」といったテーマは、今やすべての企業の共通課題であると言える。これは日本だけでなく、先進諸国の多くが抱える悩みでもある。そんな状況の中で注目を集めるのが「RPA」(Robotic Process Automation、ロボティック・プロセス・オートメーション)だ。
RPAとは、主にホワイトカラーの業務を自動化するテクノロジー(ソフトウエアロボット)を指す。別名「デジタルレイバー(Digital Labor):仮想知的労働者」とも呼ばれる。わかりやすい例としては「データ入力」が挙げられる。決められたアプリケーションを使い、一定のルールに従って標準化された業務を行うプロセスでは、往々にして複数名、ときには大量の人的リソースが割かれ、ヒューマンエラーも起きやすい。こうしたバックオフィス業務を自動で処理させることにより、効率化とともにミスを防ぐことにもつながっていくのだ。
さらにRPAは進化を続けている。前述のAI技術とも連携し、より大量のデータを処理・分析できるようになった「EPA(Enhanced Process Automation)」や、データ分析結果を踏まえて最適な対応の提案までできる「CA(Cognitive Automation)」といったテクノロジーも登場している。企業の意思決定にも大きな影響を及ぼすようになるだろう。
こうして自動化される業務の範囲は非常に幅広い。経理部門であれば請求書の作成や入金管理、情報システム部門ではソフトウエアのインストールや更新、そして人事部門では従業員情報や人事考課情報の入力・分析といった業務を機械に任せることが可能だ。
RPAのソリューション事業に参入する企業も急激に増加している。先駆けといわれているのが、RPA テクノロジーズ株式会社が提供する「BizRobo! (ビズロボ)」。2008年に前身のオープンアソシエイツ株式会社で事業が立ち上がり、業務自動化サービスとして始まったものだ。2016年7月には、RPA テクノロジーズ代表取締役社長の大角暢之氏が代表理事となり、一般社団法人日本RPA協会が設立され、RPAの啓蒙活動が行われている。
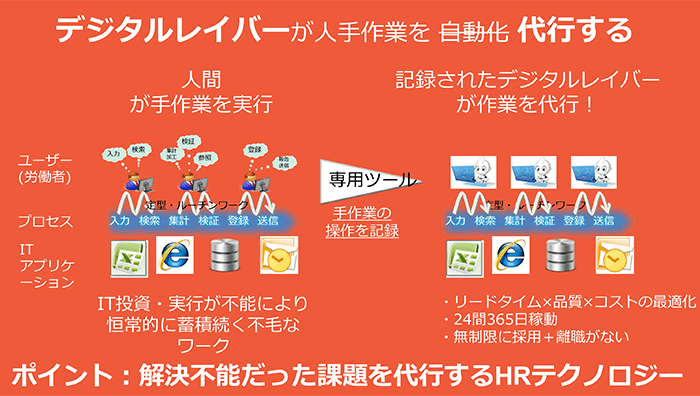
デジタルレイバーが人手作業を代行する(「一般社団法人日本RPA協会」資料より)
クラウド――企業で必要とされる多くのアプリケーションが移行
「クラウドコンピューティング」という言葉が使われるようになって久しい。テクノロジーとして特に意識する機会がなくても、知らず知らずのうちにその恩恵に預かっている人も多いだろう。
クラウドとは、ハードウエアを所有したりソフトウエアをインストールしたりしなくても、インターネットを通じて必要なサービスを使えるようにした技術を指す。身近な例としてはGoogleが提供するメールサービス「Gmail」が挙げられる。かつてはメールソフトと言えばパソコンにインストールして使用するのが当たり前だったが、Gmailに代表されるクラウドサービスによって「アカウントを持ち、ネット環境と端末さえあればどこでもメールにアクセスできる」環境となった。これによって働き方の常識が大きく変わったのは論をまたないところだ。
クラウドそのものの信頼性やセキュリティー向上は、企業内のシステムにも大きな変化をもたらした。従来は自社のデータセンターで運用してきたさまざまな業務が、クラウドサービスを介して進められるようになったのだ。前述のコミュニケーション手段はもとより、マーケティングや顧客管理、営業支援、経理支援、もちろん人材管理といった分野まで、企業に必要とされる多くのアプリケーションがクラウドへ移行している。
人が活用する「デバイス」の進化に支えられている部分も大きいだろう。日々忙しく出先から出先へと飛び回る営業担当者が、移動中の電車内でメールをチェックし、必要な経費申請を済ませ、企画書を作成する。これらの作業がスマートフォン1台でできるようになった。
ニューロテクノロジー――「脳科学」に基づいたマネジメントも
人間の脳の仕組みは、かつては「わからないことだらけ」の未知の領域だった。しかし近年では脳に関する研究が急速に前進し、人間の情報処理機能が少しずつ明らかになってきている。こうした脳科学分野の研究成果を技術開発に応用しているのが「Neurotechnology(ニューロテクノロジー)」だ。
ニューロテクノロジーは医療の分野だけでなく、ビジネスにおいても幅広い領域で活用されている。組織作りやマネジメントといった人間の心が密接に関わる分野をはじめとして、このテクノロジーはこれまでにない価値をもたらそうとしている。
例えばヘルスケアにおいては、メンタルヘルスと脳の関係に着目した研究が行われ、健康経営につながる予防医療や予測医療に応用されている。脳に関わる疾患といえば脳卒中や認知症が挙げられるが、うつ病など働く人のパフォーマンスに大きな影響を及ぼす症状についてもニューロテクノロジーによって防ごうとする研究が続いているのだ。
人間の脳には「限界」があるのも事実。ヒューマンエラーによる事故やインシデントを防ぐためのリスク対策としてもニューロマネジメントは注目されている。一方で人間の学習能力や、モチベーションを高める機能などについても研究が進められており、職場でのマネジメントに大きく寄与することが期待されている。
脳科学を人事領域ではどのように生かせるのか。早稲田大学研究戦略センター 教授の枝川義邦氏は脳科学を、「脳の仕組みや働きにアプローチする学問」であると定義付ける。「現在、脳科学は企業経営や人事分野への応用に向けても関心が高いといえます。かつては人や脳は一種の『ブラックボックス』とされていたものの、脳科学によってどんなインプットに対してどんなアウトプットがあるのかを一気通貫で説明できるようになったからです」と枝川氏はいう。
さらに現在において、HRテクノロジー領域はAI(人工知能)が注目されているが、AIのディープラーニングと脳科学にはどのような関係があるのか。枝川氏は「現在のAIは第三世代といわれており、『ディープラーニング』という技術がカギになっています。これにより、AIが自発的に学習できるようになり画像認識がかなり進化しました。もちろん、まだまだ発展途上であることは否めません」と説明している。
ピープル・アナリティクス――人の主観をはるかに超えたデータ収集と分析
その名の通り、この技術は主に人事部門での活用を想定して開発されているものだ。「ピープル・アナリティクス」は、従業員のさまざまな行動データを収集し、その分析によって高い成果を出す人材モデルを明らかにしたり、そうした人材が活躍しやすい組織のあり方を導き出したりする技術を意味する。これは、従業員のエンゲージメントを高めることにもつながる。
従来は、自社で活躍する人材モデルを定義したり、そのための職場環境作りを進めたりすることは、人事の「経験」や「勘」、あるいは人為的な「観察」によって進められていた。マネジメント層を巻き込んで取り組んでいたとしても、やはりそこには人間の感情が入り混じってしまう。ピープル・アナリティクスは「職場の人間科学」とも言われるが、客観的なデータによって職場の現状を分析するためには欠かせない技術と言えるだろう。
データ収集の方法は日進月歩で進化を続けている。最近ではウェアラブル端末を専用アプリと連携させ、従業員の出退勤記録はもちろん、「オフィス内でどれくらい歩いているか」「どんな人とどれくらいの時間会話しているか」「どのように休憩時間を過ごしているか」といった行動履歴をビッグデータとして取得できるようになった。これを分析することで得られる情報は貴重だ。誰と誰を組ませるべきか、チームは何人くらいの規模で構成するべきなのか、成果を出せるオフィス環境とは……。こうした職場作りをエビデンスに基いて進められるようになる。
統計家で株式会社データビークル代表取締役の西内 啓氏も、人事部門にデータの活用をうながしている。「データを活用する企業と活用しない企業とでは、15年間でパフォーマンスに倍ほどの差が生まれます。生産性の違いも2倍、3倍、あるいはそれ以上になります。それほど重要なことなのに、想像以上にデータ活用は進んでいません」と西内氏はいう。
特に人事領域でデータ活用が必要・有用とされる施策は何なのだろうか。西内氏は「優秀な人材を採用する」「優秀な人材に離職されないようにする」ためのデータ活用と、「今いる人材のパフォーマンス向上」「一人ひとりの売り上げ数字と評価との連動」を挙げる。その上で、「現状では日本を代表するような大企業でもデータを見て終わり、というケースがまだまだ多いようです。せっかくグローバルの従業員のパフォーマンスやエンゲージメント、さらには関連する多くの項目のデータを集めているのに、きちんとデータ分析をしないため、どれが一番重要なデータかがわからず、効果的な施策を実行できずにいるのは残念なことです」と語っている。
HRテクノロジー活用のメリット
人事の業務分野へHRテクノロジーを導入することは世界的な趨勢となっている。このトレンドを見て「自社でも活用を急がなければ」と考える人事担当者も少なくないだろう。HRテクノロジーを活用するメリットとは何なのか。AIを事例として整理してみたい。
業務効率化によって本来の人事ミッションへ
HRテクノロジーを実際に導入している企業で、まず大きな効果として挙げられるのは「業務の効率化」だ。それまでは人が担っていた作業をテクノロジーが代替することで、大幅に工数を削減できる。自身が学習して推測能力を高めていくAIの活用も、業務効率化に大きく貢献している。
採用シーンにおいては、AIとピープル・アナリティクスを掛け合わせることで新たな手法が生まれている。自社で活躍している人材のデータを収集し、それに基づいたターゲット設計ができるようになった。選考プロセスではさまざまなデータをもとに個人の適性を判断し、従来のように幾度にもわたる面接や試験を経るといった「無駄」を削減することにつながっているのだ。
人事のもとに寄せられる「社内問い合わせ」への対応も、AIが得意とするところだ。イントラネットにあふれる膨大な情報を整理し、チャット機能などで自動回答するAIソリューションも登場している。こうした業務効率化は、人事が本来向き合うべき人や戦略への特化を可能とする。
「バイアス」にとらわれないマッチングができる
前述したような選考プロセスにおけるAIの活用は、採用活動の重点項目である「マッチング」の効率化にもつながっていく。AIが参照するデータは適性検査結果などの数値化できるものだけではない。面接時の映像や口述記録といった情報も最大限に活用し、自社に合う人材かどうかを判断できるのだ。
マッチングの効率化は採用時だけでなく、人材配置や異動においても効果を発揮する。従業員の過去の業務実績や評価履歴、本人が申告するキャリアプランの希望などを集約して、最適な人材配置を提案するサービスも研究されている。
AIと人の大きな違いは、「バイアス」(ゆがみ)の有無だ。従来のように人が判断するマッチングでは、面接者のバイアスは避けられなかった。客観的な情報に加えて面接者本人の好みや偏見も判断に影響を与えてしまうからだ。AIは不必要なバイアスを排除し、最適なマッチングに向けて学習を重ねていく。
多様化に対応する「能力開発の個別化」が可能に
HRテクノロジーを活用することは、従業員一人ひとりのデータをより子細に把握し、活用できるということにつながる。これは、人的資本投資そのものを効率化していくために欠かせないピースと言えるだろう。
従来の人的資本投資と言えば、ある程度の母数を対象とした画一的な研修と、上司や先輩による職場内訓練(OJT)の組み合わせだった。しかし働き方やキャリアプランに対する個人の考え方が多様化している現代では、これまで通りの方法で人的資本投資を最適化することが難しくなっている。HRテクノロジーの活用によって、この課題を解決することができるのだ。
AIは、本人の実績やキャリア志向を膨大なデータによって把握することができる。これを社内のキャリアパスプランとひも付け、個々人に合わせて受講すべき研修を提案したり、本人の実際の仕事の様子を録画して改善点を判定したりするサービスが現実に考案されてきている。能力開発を個別に実施していくことは、これからの企業の成長に欠かせない要素と言える。
AIは、従業員や組織全体の生産性を明らかにする
このようにして従業員一人ひとりをつぶさに観察し、データ収集・分析による最適解を提案できるAIの強みは、組織全体の生産性向上にも活用できる可能性がある。AI研究の第一人者である東京大学大学院特任准教授の松尾豊氏は、「AIに『目が見える』という機能が加わることで、生産性を向上させるパッケージを作ることも可能」と語る。
画像を認識できる、つまり「目が見えるAI」を職場に導入することで、オフィス内の誰がどんな表情で仕事をしているのかがわかるようになる。従業員の表情と集中度合いを日々観察し、データを積み重ねていくことで、「この従業員(部署)は○時○分になると生産性が低下する」ということも診断できるようになるのだ。管理者は集中力が落ちた従業員をその場で判別し、「今日はもう帰ってもいいよ」と呼びかけることもできる。
学術研究レベルでの可能性にとどまらず、アメリカにおいては、すでにAIを活用したサービスを実用化した企業もある。従業員のメールやチャット、カレンダー情報、電話、さらには従業員が身につけるウェアラブルセンターによる情報などを集め、人々が組織内でどのように対話しているのか、どのように仕事を進めているのかを分析するサービスだ。この分析結果は、業務プロセスの改善やオフィスレイアウトの変更といった具体的な提案につなげられている。
一方、日本でもライフログのような膨大な情報の取得とAIによる解析によって、今後個人や組織における応用可能性を期待される製品がある。メガネ型ウェラブルデバイス「JINS MEME(ジンズ ミーム)」だ。これは、端的にいうと「眼の動き」や「まばたき」「姿勢」を測定することで「脳のはたらき」を推測できる眼鏡。このデバイスを今オフィスで利用しようという動きが進められている。用途は、個人の採用や配置、育成・研修、日常業務、リテンション、メンタルケア、組織においても働く環境づくり、リモートワーク、安全管理・作業管理と多岐に及ぶ。「それらは相互に結びついているだけに、課題を横断的に捉えていくことがポイントになってくる」と株式会社ジェイアイエヌ JINS MEMEグループ 事業開発担当の井上一鷹氏は語っている。

JINS MEME(ジンズ ミーム)

ハピネスの測定に寄与する加速度センサー
また、AIの研究・活用に長年取り組んでいる株式会社日立製作所研究開発グループ技師長の矢野和男氏は、「AIが働き方改革に貢献できる」と強調する。働き方改革の目的は、生産性の向上だ。分母を労働時間、分子を生み出した価値として測定するのだが、価値は簡単に測れないという問題がある。そこで、矢野氏が普遍的な指標として提唱しているのが、働く人の「幸福感=ハピネス」という概念。実は既に多くの職場でハピネスが生産性と相関することが実証されている。日立では試行錯誤の末に、ハピネスを客観的に測定できるようにしただけでなく、どのような条件になればハピネスが高まるのかをデータから見いだせるAIを開発した。「ハピネスが向上する要因は、人ごと、組織ごとに多様です。だからこそ、AIの技術が重要になるわけです」と矢野氏は語る。
HRテクノロジー活用の注意点
前述したように、HRテクノロジーを活用することで得られるメリットは大きい。一方で人事の課題は、テクノロジーを導入するだけで解決できるような単純なものばかりではないのも事実だ。安易にHRテクノロジーを導入しようとすることで、新たなリスクを呼び込んだり、デメリットを生じさせたりする可能性もあるため、注意する必要がある。
AIやデータの活用では、バイアスが伴うことを留意すべき
HRテクノロジーの進化によって、人事は社内に眠る多種多様で膨大なデータを整理し、その分析結果に基づいた科学的な打ち手を検討できるようになった。経験や勘といった属人的なスキルに頼らざるを得ないことが多かった人事の世界が大きく変わりつつある。人事部門内での人材育成も、明確な基準を持って進めていけるようになるのではないだろうか。
とは言え、新たなテクノロジーやサービス、システムを取り入れるだけで必ずしも課題解決につながるわけではないことも事実。そもそも、「何の課題を解決しようとしているのか」が明確になっていなければ、なぜ自社にテクノロジーを導入する必要があるのかもまた不明瞭なままだ。
また、英国の政治経済誌『The Economist』では2018年3月31日号にて、「AIの利用は、経営者による社員への統制力をとてつもなく大きくしてしまう恐れがある」「アルゴリズムがプログマー自身のバイアスから逃れられないだけに、AI活用の便益には潜在的なリスクが付随する」「AI技術が職場に浸透する際には、個人情報保護と成果の両方を満たすことができないという問題にぶつかる」と警告している。AIが社員を縛り付けて非人間化するようであってはいけない。そのためにもAI技術を導入する際には、可能な限りデータを匿名化し、透明性を確保するほか、国に対する個人情報の開示請求を国が認めるべきだと提案している。
人事データの学術利用を進める産学連携プロジェクト「人事情報活用研究会」を主宰する、早稲田大学政治経済学術院教授の大湾秀雄氏(2018年3月までは東京大学社会科学研究所教授)は、2018年2月26日付の日本経済新聞で「新技術であるAIは誰でも使える訳でなく、弊害が全くない訳でもない」と語っている。なぜなら、使う側に統計的な素養とデータ分析の経験が求められる上に、データ活用には計測誤差や統計的バイアスが伴うのでどのようなバイアスが起こり得るかを理解しておかないと大きな間違いを犯してしまうからだ。加えて、AIを導入する際に、どんなデータを与えて学習させるのかということも大事だ。例えば、過去の採用審査結果を学習させる場合、そこに間違いがあれば、AIにも同じ間違いを繰り返させてしまう。データ活用が新たな統計的差別をもたらす可能性がある点も危惧されるという。ほかにも大湾氏は、『日本の人事部』のインタビューに答え、「大前提として欠かせないのは『人事の問題意識』。会社をよくするために何ができるのか、何をすべきなのかと絶えず問いかけながら現場に目を向け、社員の声に耳を傾けなければ、組織や人事制度のどこに問題があるのかを自覚することはできない」と指摘している。
憲法学の視点から見たプロファイリングの問題点
ビッグデータ社会やAI社会では、プロファイリングの技術がかなり向上しており、自己像が予測されやすくなっている。こうしたなか、憲法学者である慶應義塾大学法科大学院教授の山本龍彦氏は、プロファイリングを進める過程で二つの問題が生じることを指摘している。
「一つは、特定の個人を識別する情報を抜いて収集しても、属性がいくつも重ね合わされると誰がデータセットであるかがわかってしまうことです。二つ目の問題は、プロファイリングによって個人の私的・内的な側面が高い確率で予測されてしまうことです。これは、プライバシー権や自己情報コントロール権の観点から大きな問題をはらんでいます」。人事データを収集するにしても、それがどのような目的のもとで行っているプロファイリングなのかを従業員にしっかりと説明しておく必要があるといえよう。
テクノロジー導入を徒労に終わらせないために、まずは「データの振り返り」を
人事が現場を見て、社員の声を聞いて抱いた問題意識は適切なのか。それを検証するために有効なのがデータであり、改善点が明確になった際に効果を発揮するのがテクノロジーだ。大湾氏は、人事がまず始めるべきこととして「企業内での意思決定に用いられる情報を、すべてデジタルデータとして保存する仕組みとルールを作るべき」とアドバイスする。
採用時の適性検査や面接の評価点、異動や昇進・昇格を発令した情報など、後々の分析において有用となるデータはできる限り人事システム上に保存し、一元管理しておきたい。データ活用に明るい、「統計リテラシーの高い人材」が人事部門内にいることも重要。もし現状の人事部門メンバーが人文学系出身者で固められているなら、統計学を学んだ理系出身者や計量経済学を学んだ経済学部出身者を迎え入れることも効果的だろう。
こうしたプロセスを経ることは、HRテクノロジーの活用を考える前にまず、自社の人事データの管理状況を振り返ってみることにつながる。例えばエクセルで管理しているデータがあるならば、それをどんな目的で、どのように活用できているのかを振り返りたい。もし現状の段階でデータの活用目的が曖昧になっているとしたら、テクノロジー導入が徒労に終わる可能性もある。
グラフ1枚で自社の課題や改善点が明確になることも
現在では数多くのHRテクノロジー関連スタートアップが誕生し、さまざまなサービスが生み出されている。便利なパッケージングを伴うサービスであれば、何も考えずに使い始めることができるかもしれない。しかし、すべてをベンダー任せにしてしまうことで、本来の目的とはかけ離れた状況を呼び込んでしまう恐れもある。
逆の見方をするならば、HRテクノロジーの導入を検討することは、自社の現状を見つめ直す好機とも言えるのかもしれない。
しかし、やみくもに導入・活用すれば良いというものではない。東京大学大学院の柳川範之教授も、テクノロジー活用を進めるにはテクノロジーを扱う人間に科学的観点をもって定義する力、データを適切に評価する力が求められると述べている。「例えばエンジニアを採用するにあたり、優秀なエンジニアという判断軸では、あまりに漠然としています。クリアな軸を持っていなければ、目の前に出された結果に対して適切な判断はできないはずです」と語る。
また、ディープラーニングの領域では、人間にはAIの出した判断の根拠がわからないブラックボックスの問題もある。だからこそ、人間サイドが軸を持つことが重要だというのが柳川教授の意見だ。「組織や経営のあるべき姿から基準軸を落とし込むことと並行し、仕事や働き方、組織運営の枠組みをデザインし直すことが、テクノロジーとうまく付き合う第一歩だと思います」
安易に「トレンドに乗り遅れてはいけない」「HRテクノロジーを活用する体制を整えなければいけない」と焦るのではなく、本当にテクノロジーが必要なのか、課題解決にテクノロジーが活用できるのかを考えるべきだろう。 テクノロジーに頼ることなく、グラフ1枚で自社の課題や改善点が明確になることもあるはずだ。案外、その課題は今の体制でも解決できることかもしれない。
(記事監修:早稲田大学政治経済学術院教授 大湾秀雄氏)
※「HRTech」は株式会社groovesの登録商標です。
- 【参考】







