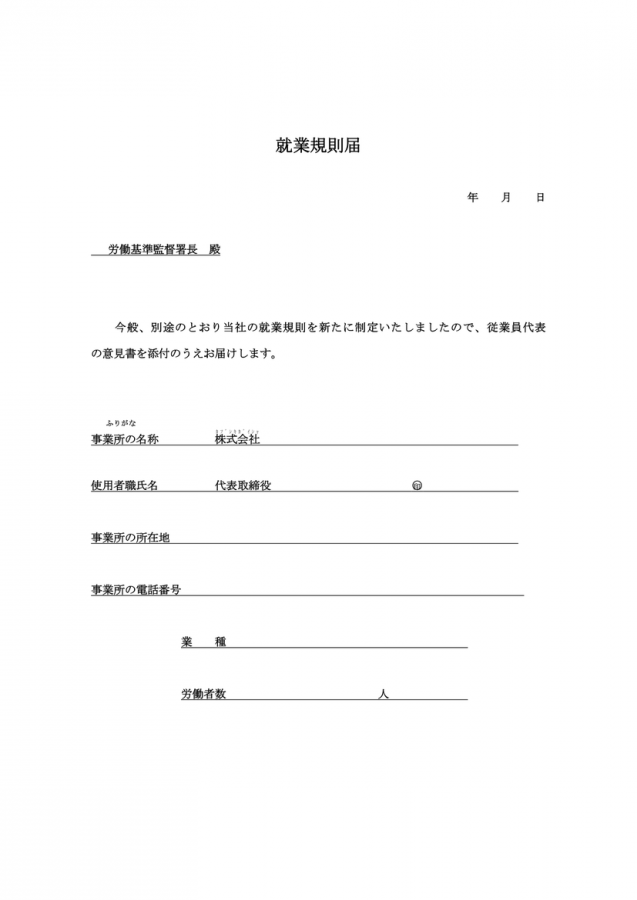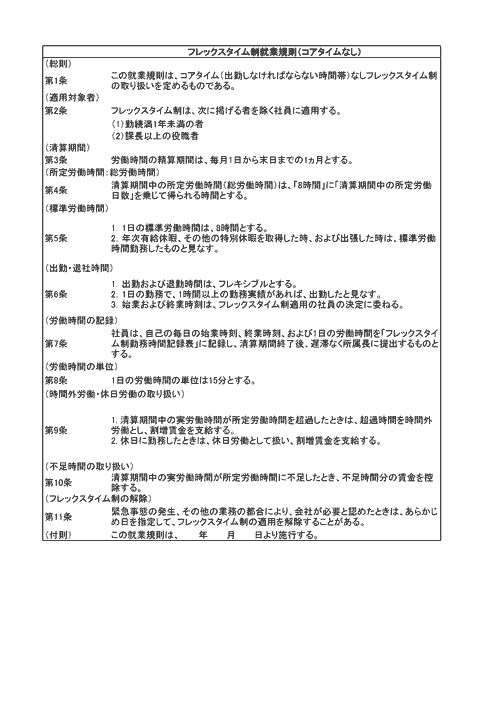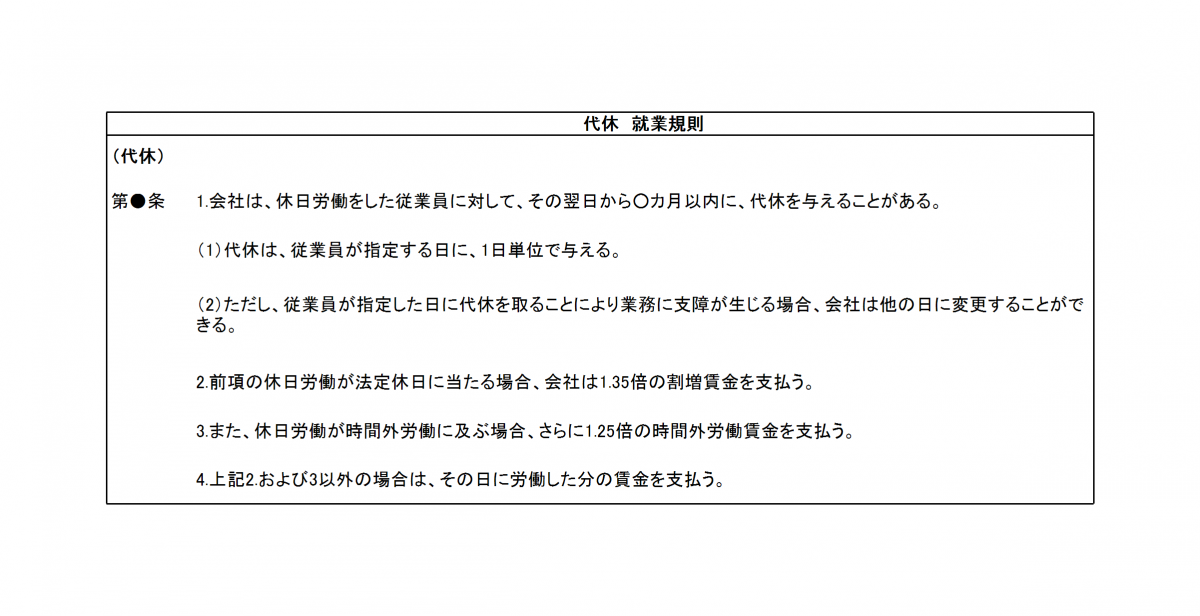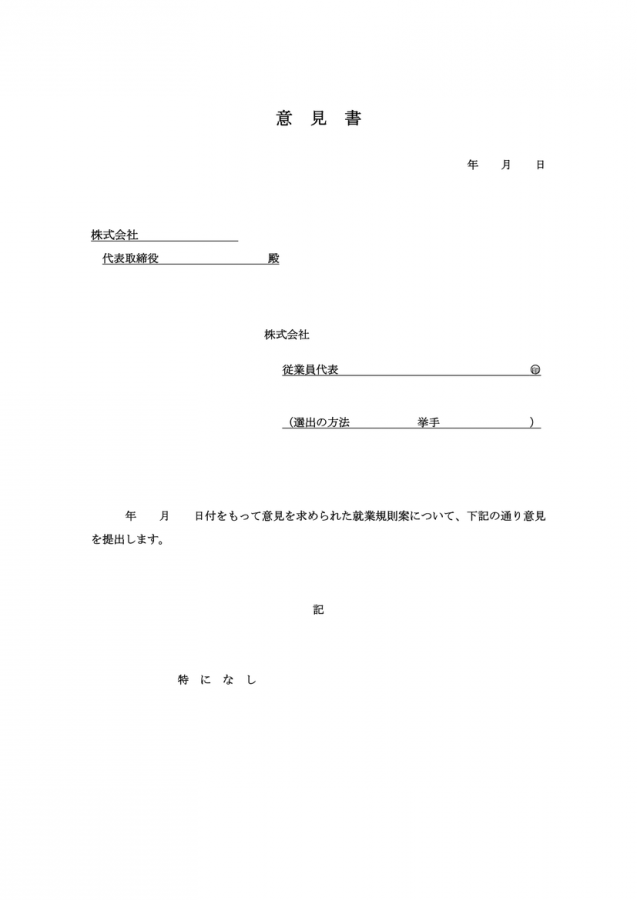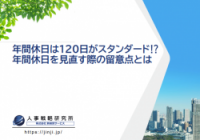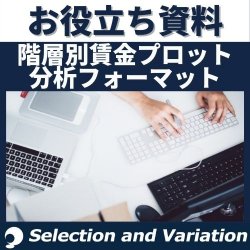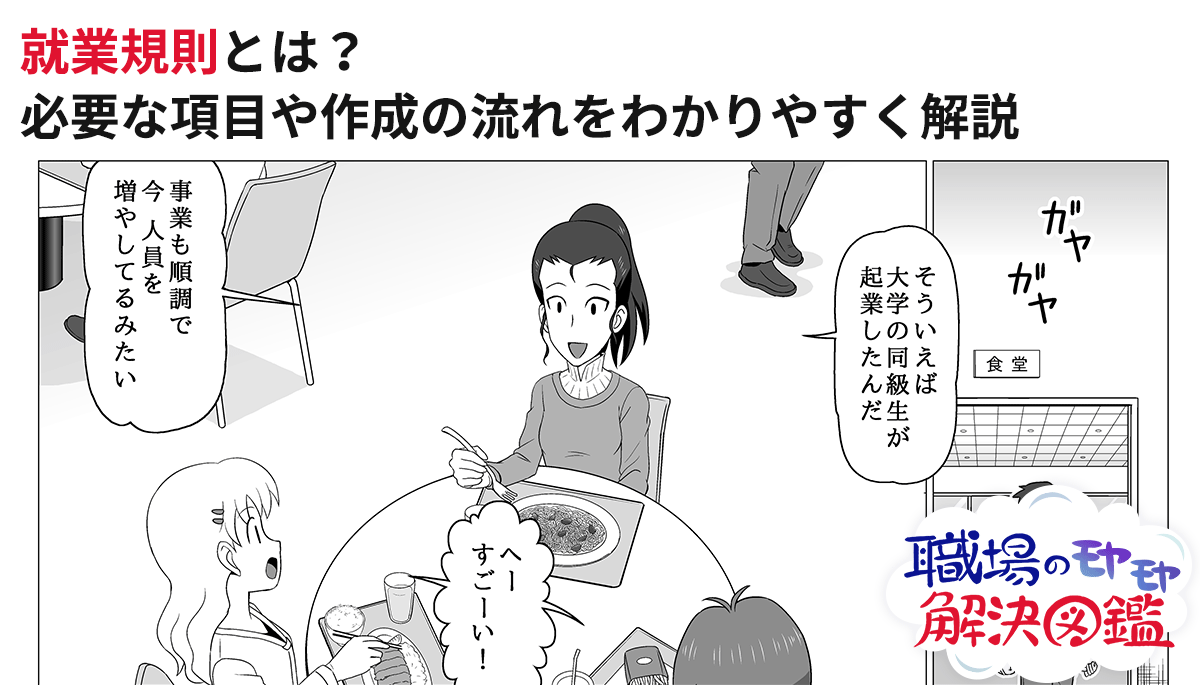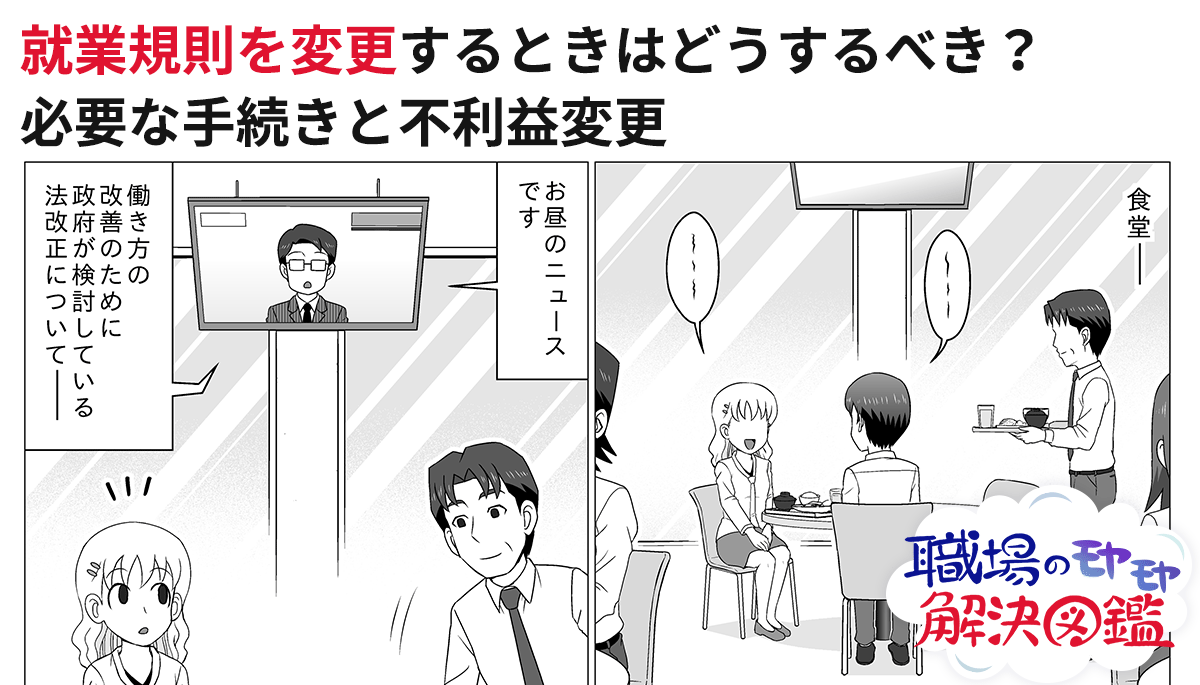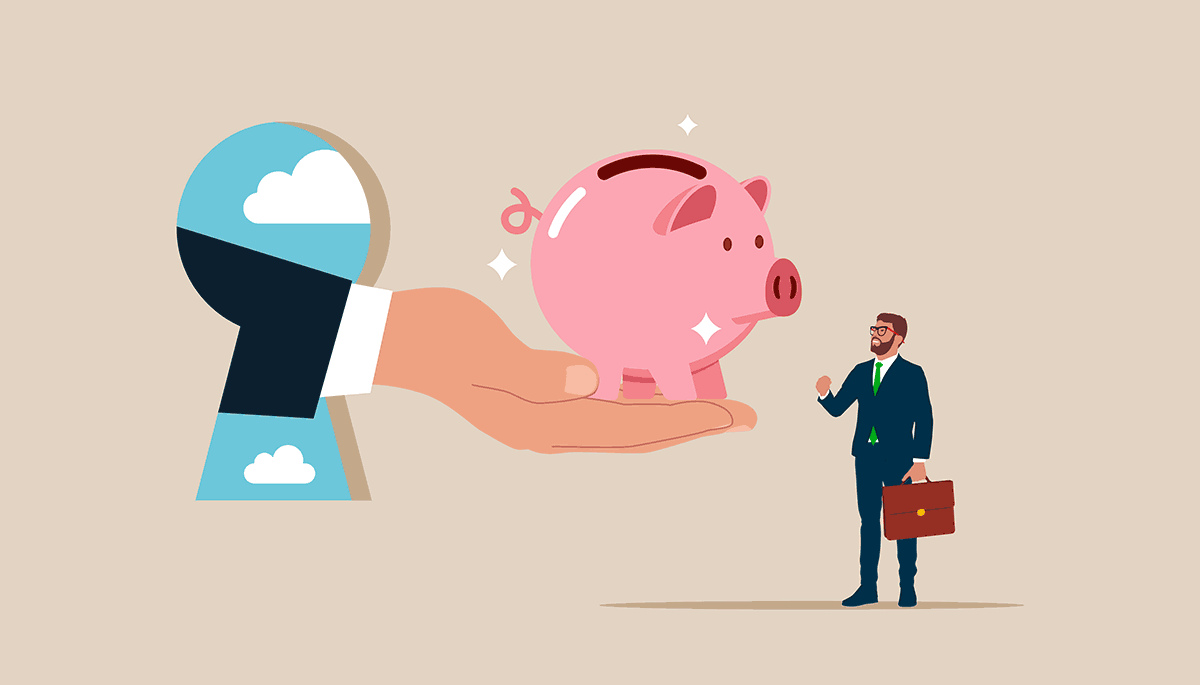所定労働日数について
いつも参考にさせていただいております。
就業規則に所定労働日数の記載がありません。
当社は「1ヶ月単位の変形労働制」「日給月給制」です。
所定労働時間は7時間45分。休憩45分。
就業規則の休日は、日・祝・12/29~1/3です。
土曜日は基本休日(月1回程度出勤)で、出勤する際は代休を付与しています。
給与規程の日割額の算出方法は、
(基準内賃金✕12ヶ月)÷(52週×40時間)×当該日の所定労働時間=日割額
日割額を当該日の所定労働時間で除した金額を時間単価とする。
欠勤控除はこの式を使用して計算しています。
育児休業給付金の賃金支払基礎日数は、日給月給制の場合は「就業規則等にある所定労働日数」と見たことがあるのですが、その所定労働日数がわかりません。
上記のように運用している場合、所定労働日数は何日になるのでしょうか?
また、就業規則には所定労働日数の記載をした方が良いのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/10/24 22:12 ID:QA-0159911
- うさとらさん
- 埼玉県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
所定労働日数は、就業規則で定める休日数を引いた日数となります。
規定上、土曜日を休日としているのであれば、月1程度の休日出勤が
あったとしても、休日数にカウントします。
休日数はカレンダーを印刷して、数えるのが分かりやすいでしょう。
また、就業規則に所定労働日数を記載することは望ましいですが、
暦の関係で、所定労働日数は変動しますので、就業規則では、
所定労働日数は、毎月定める勤務カレンダーによるものとするとして、
勤務カレンダーを社内周知する方法でも問題ありません。
投稿日:2025/10/27 08:56 ID:QA-0159928
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.「所定労働日数」とは何か
「所定労働日数」とは、
就業規則や労働契約などで会社が定めた、1か月あたりの労働義務日数のことです。
労働基準法では明確な定義がないため、会社の休日規定や勤務割により決まる日数で判断します。
2.ご質問の会社の勤務形態の整理
内容を整理すると次のとおりです。
項目→内容
労働時間制度→1か月単位の変形労働時間制
賃金形態→日給月給制
所定労働時間→7時間45分(休憩45分)
休日→日曜・祝日・年末年始(12/29~1/3)
土曜→原則休日だが、月1回程度出勤(代休付与)
この場合、
「土曜日は原則休み」なので、基本は週5日勤務が所定です。
ただし、変形労働制により月ごとの勤務日数に変動があります。
3.「所定労働日数」の算定例(目安)
(1)年間の休日数を推定する
年間休日:
日曜52日+祝日(約16日)+年末年始6日 = 約74日
土曜は月1回出勤 → 年間約12日出勤、40日程度休日化
→ 年間休日 約 114日(365-251)
(2)年間労働日数
365日 − 年間休日114日 = 251日(年間の所定労働日数)
(3)1か月平均
251日 ÷ 12か月 = 約20.9日(≒21日)
したがって、この会社の「所定労働日数」は
おおむね月21日程度と考えるのが妥当です。
(週5日勤務×52週=260日−祝日等=約250日前後となるため、ほぼ一致します)
4.日給月給制における育児休業給付金の「賃金支払基礎日数」との関係
育児休業給付金における「賃金支払基礎日数」は、
賃金支払の基礎となる日数=所定労働日数の範囲内で実際に出勤・有休した日数を指します。
したがって、日給月給制の場合でも、
「就業規則上または勤務カレンダー上の所定労働日数(例:月21日)」
が基準となります。
「所定労働日数が記載されていない」場合は、
会社のカレンダー(勤務表)で通常想定している勤務日数をもって代替できます。
5.就業規則への明記について(推奨)
現行法では「所定労働日数」の明記義務はありません。
しかし、次の理由から明記を強く推奨します。
【明記のメリット】
育児休業給付・雇用保険・社会保険の基礎日数の根拠が明確になる
パート・契約社員との比較基準が明確化する(週所定労働日数との区別)
勤務カレンダー変更時の説明責任が果たしやすい
【記載例(就業規則への追記例)】
(所定労働日及び所定労働日数)
第○条 所定労働日は、会社の勤務カレンダーによる。
2 所定労働日数は、原則として月平均21日程度とする。ただし、業務の都合により変動することがある。
3 所定労働時間は1日7時間45分とし、休憩時間は45分とする。
このように記載しておくことで、給与・社会保険・助成金などの根拠として整合性が取れます。
6.まとめ
項目→回答
所定労働日数→月平均 約21日(年間約251日)
算定根拠→週5日勤務、日祝休・土曜月1出勤・年末年始6日休
就業規則記載→明記を推奨(勤務カレンダー+平均値で記載可)
給付金関係→育児休業給付金等ではこの所定労働日数を基礎とする。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/10/27 09:15 ID:QA-0159934
プロフェッショナルからの回答
就業規則
以下、回答いたします。
(1)労働基準法(第89条)では、就業規則における絶対的必要記載事項の一つとして、「休日に関する事項」が定められています。
具体的には、「休日」に関して、「休日の定め方は、休日の日数、与え方(一週一回、又は一週の特定日例えば日曜日等)のほか、休日の振替、代休等の制度がある場合はそれらの制度について具体的に記載しなければならない。」とされています。(「令和3年版 労働基準法 下」厚生労働省労働基準局編)
(2)その一方で、「所定労働日数」「労働日」については記載が義務付けられていません。
(3)以上を踏まえれば、「所定労働日数」については、「当該年の歴日数」から上記(1)「休日の日数」を差し引いて得た日数になるものと認識されます。
投稿日:2025/10/27 18:30 ID:QA-0159971
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、所定労働日数=暦日数-所定休日で計算が可能です。
御社の場合ですと、就業規則上の休日は勿論、土曜も同様に休日として扱われているという事でしたら、実態が優先しますのでこちらも所定休日に含めて計算される事が求められます。
投稿日:2025/10/27 18:40 ID:QA-0159972
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
就業規則と服務規程 お尋ねします。就業規則と服務規程... [2018/06/22]
-
就業規則と法令の関係について 数年ぶりに就業規則を修正していま... [2019/04/19]
-
就業規則の成功事例 就業規則を改訂しようと考えていま... [2007/06/30]
-
在宅勤務規程について 弊社では・正社員用就業規則・契約... [2020/11/12]
-
所定労働日数に会社休日は含めるか? 弊社は月俸制ですが、時間単価の算... [2024/09/02]
-
いまどきの就業規則 現在、就業規則の改訂を検討してお... [2012/01/25]
-
就業規則の届出について 就業規則の届出について教えてくだ... [2013/02/14]
-
半日代休について 半日代休について就業規則に記載し... [2022/06/06]
-
平均所定労働日数の端数処理 表題の件についてご教示ください。... [2025/04/09]
-
運用の柔軟性が高く、かつシンプルでわかりやすい就業規則 できるだけわかりやすく、シンプル... [2005/04/18]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
就業規則届
労働基準監督署に届出するための就業規則届です。是非ご利用ください。
フレックスタイム制就業規則
フレックスタイム制における就業規則の例です。コアタイムあり・なしの二例をそろえています。
代休の就業規則
代休制度を就業規則に記載するときの追記案です。
意見書
就業規則の作成・改訂の際に使用する意見書です。どうぞご利用ください。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 調査
調査 人事辞典
人事辞典 イベント
イベント