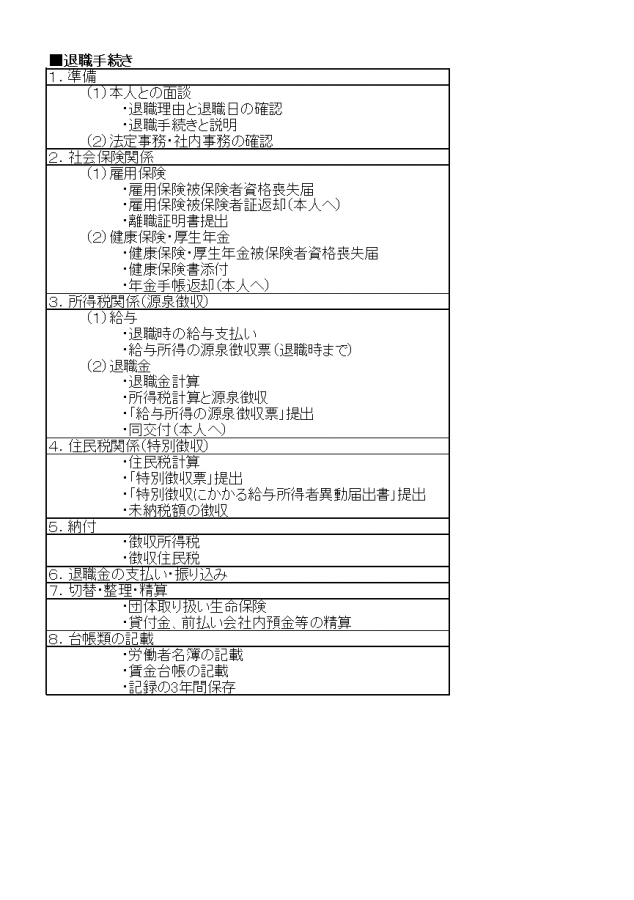途中退職の場合の日割り計算について
途中退職の場合の日割り計算について。以下のケースではどのように給与を計算したほうがよいでしょうか?
・7月の日数31日のうち、所定労働日数は25日。公休は6日。
・基本給は18万円。
・ある社員が退職を申しでた。7月18日に退職する。
・7月1日~7月7日のうち、出勤は5日で、公休を2日取得してる。
・7月8日から10日間の有給を使用。18日退職
この場合の「暦日数」と「所定労働日数」のいずれを使用するのが一般的でしょうか?
仮に「所定労働日数」を使用する場合「支給額」の計算方法は 以下のいずれが正しいでしょうか?(取得済みの公休を含めるか否か、未取得の公休を除外してよいのか否か)
① 18万円×(出勤5日+公休2日+有給10日)÷25日=122,400円
② 18万円×(出勤5日+有給10日)÷25日=10,8000円
投稿日:2025/07/06 17:58 ID:QA-0154971
- 金城ケンジさん
- 沖縄県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 11~30人)
この相談を見た人はこちらも見ています
-
退職者の有給 退職した社員の有給が残っていたのですが本人から申請されなかったのでそのままにしておいて良いでしょうか? [2025/12/15]
-
退職者の有給について パートで退職された方がいますが、有給が残ったままの状態です。退職は自己都合による退職で、有給は付与されたばかりのタイミングでの退職の申し出だったので、有給... [2024/08/23]
-
退職 有給が33日残ってます。会社が退職時に残ってる有給は買取になりますが、出勤日数以上の有給を1ヶ月で買いとる事はできるのですか? [2025/03/13]
-
退職日前の退職金一部(または全部)支払について 3月末付で退職予定の従業員に対し、通常は翌4月中に退職一時金の支払いをしておりますが、3月中の支払いができないかとの問い合わせがありました。退職所得として... [2009/02/13]
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、こうした日割り計算に関しましては、法的に計算方法が定められておりませんので、会社が任意に定めて運用する事柄になります。
従いまして、特に定めが無ければいずれの計算方法も可能といえますが、一貫性を持たせる上で常に同じ計算方法を用いられるべきといえるでしょう。
投稿日:2025/07/07 09:47 ID:QA-0154986
相談者より
有難うございます。
就業規則では暦日数か所定労働日数かが明確に定められていなかったため、今後の方針としてどちらを採用するほうがより一般的で、より合理的で、会社および社員双方の納得度が高く紛争のリスクが低いか、悩んでおりました。慎重に検討して一貫した方針を決めていきたいと思っております。アドバイス感謝します。
投稿日:2025/07/07 10:23 ID:QA-0154998あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
→一般的には「所定労働日数」を用いるケースが多いです。
実務上、月給制の社員が途中退職した場合は「所定労働日数」基準で日割り計算を行う企業が多数です。
ただし、「暦日数(31日など)」を用いる方法も合法であり、会社の給与規程に従って統一されていればどちらでも可です。
2.前提となる条件
項目→内容
月額基本給→180,000円
月の暦日数→→31日
所定労働日数→25日(公休6日)
退職日→7月18日
勤務状況→出勤5日、公休2日、有給10日(合計17日分在籍)
3.計算方法の考え方
ポイント(1):有給休暇は「労働したものとみなす」
→ よって「有給10日」は「勤務日数」としてカウントされます。
ポイント(2):「公休」=就業規則上の休日
「休日」は労務提供義務がないため、在籍中の休日は通常どおり給与支給の対象に含めます。
ただし、未到来の休日(退職日以降の公休)については支給対象外です。
4.2案の比較
案→内容→正当性→コメント
(1)18万円 ×(出勤5+公休2+有給10)÷25日= 122,400円→妥当→在籍中の公休も含めて支給される考え方
(2)18万円 ×(出勤5+有給10)÷25日= 108,000円→ 要注意→公休を除外しているため、未払リスクあり
5.推奨される支給方法
→ 在籍中に発生する公休日も労働契約上の給与対象となるため、
(1)の「出勤5+公休2+有給10」=17日分を25日で割った日割計算が最も適切です。
6.補足:暦日数での計算はダメなのか?
例えば 180,000円 × 18日 ÷ 31日 = 104,516円 という暦日ベースも理論上可能ですが、
→ 賃金規程に明記がなければトラブルになるリスクが高いため、あまり推奨されません。
7.まとめ
項目→回答
日割計算の基準は?→ 一般的には「所定労働日数」方式が多い
支給額の計算方法は?→ 出勤+公休+有給(在籍期間内)÷所定労働日数 × 基本給が妥当
今回のケースでの支給額は?→ 122,400円(案(1)が正解)
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/07/07 10:04 ID:QA-0154990
相談者より
詳細説明をいただき誠に有難うございます。大変勉強になります。
所定労働日数を使用する企業が実務上は多いということですね。その方向で考えておりましたので、それを聞けて安心しました。こちらを採用する方向で進めたいと思います。
ただ一点、どうしても案①において違和感が残る点があります。
有休を勤務日数に含めて計算するのはまったく違和感がないのですが、「公休」を日割り計算の勤務日数に含めるという点です。
といのも、暦日31日から公休6日を引いて、所定労働日数を25日と計算したにも関わらず(すなわち18万円は公休を除外した25日分の勤務日数の対価であるとする)、退職前に取得した公休2日を勤務日数にカウントして日割り計算する・・・この点に違和感を感じてしまいます。
極端な話ですが、今回の例で7月1~7月7日の期間の内訳が「出勤1+公休6」だった場合でも同様に「出勤1+公休6+有給10=17日分」を25日で割って日割計算するとなってしまい、18万円が所定勤務日数の対価であるという前提が崩れてしまいます。
もちろん案①が従業員にとって有利で嬉しいですし、会社としても余計な言い争いもなく、スムーズにお別れができるのは間違いありません。
実務上、そういったメリットを優先して会社としては多少整合性が合わない点は「例外」として割り切って考える…そうことでしょうか。
・18万円は「公休6日」を除いた所定労働日数25日の対価である。
・よって日割り計算は退職する前の「勤務日数(有給含む)」を所定労働日数で割って計算する。
・但し、退職前に使用した「公休」については例外的に「勤務日数」としてカウントする。
投稿日:2025/07/07 11:36 ID:QA-0155012大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
まず、日割り計算方法については、あくまで貴社の定めによって処理すべき
ものであり、法令上の取り決めはございません。
貴社の会社規定に沿って、計算を行っていただくものとなります。
その上で、「歴日数」と「所定労働日数」のいずれを使用するのが一般的かに
ついては、後者の「所定労働日数」を用いて計算する割合の方が多いものと
思案いたします。
また、「所定労働日数」を使用して計算する場合、所定労働日数25日に、
公休日数は除かれているのであれば、分子となる支払対象日数からも、
公休日数を除きませんと、分母(所定労働日数)の日数算出概念と、
整合性がとれないものとなります。
投稿日:2025/07/07 10:30 ID:QA-0155001
相談者より
有難うございます。
まさにその点が疑問でした。
「所定労働日数の分母から公休が除かれている以上、分子も公休を含めないで考えないといけない」というのが整合性の面からはスッキリする気がします。そうなると本件では案②が正しいとなります。
退職前の公休を支給対象に含めるのであれば「暦日日数」を分母にして計算(すなわち18万円は暦日全体の対価)したほうがまだ整合性が取れる気もします。
そうなると退職後の所得できなかった公休(今回の場合は4日)も支給対象に含めるべきかという議論が出て参りますが…悩ましいです。
投稿日:2025/07/07 11:47 ID:QA-0155014参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
給与規定によりますが、
退職時は、2が多いと言えます。
15日が所定労働日であり、10日間は退職により、労働義務がなくなるからです。
投稿日:2025/07/07 15:49 ID:QA-0155037
相談者より
有難うございます。
やはり②かな…と思ってます。
アドバイスを参考に弊社の方針を固めて参りたいと思います。
投稿日:2025/07/11 13:12 ID:QA-0155295参考になった
プロフェッショナルからの回答
2回目のご質問
ただ一点、どうしても案(1)において違和感が残る点があります。
有休を勤務日数に含めて計算するのはまったく違和感がないのですが、「公休」を日割り計算の勤務日数に含めるという点です。
といのも、暦日31日から公休6日を引いて、所定労働日数を25日と計算したにも関わらず(すなわち18万円は公休を除外した25日分の勤務日数の対価であるとする)、退職前に取得した公休2日を勤務日数にカウントして日割り計算する・・・この点に違和感を感じてしまいます。
極端な話ですが、今回の例で7月1~7月7日の期間の内訳が「出勤1+公休6」だった場合でも同様に「出勤1+公休6+有給10=17日分」を25日で割って日割計算するとなってしまい、18万円が所定勤務日数の対価であるという前提が崩れてしまいます。
もちろん案(1)が従業員にとって有利で嬉しいですし、会社としても余計な言い争いもなく、スムーズにお別れができるのは間違いありません。
実務上、そういったメリットを優先して会社としては多少整合性が合わない点は「例外」として割り切って考える…そうことでしょうか。
・18万円は「公休6日」を除いた所定労働日数25日の対価である。
・よって日割り計算は退職する前の「勤務日数(有給含む)」を所定労働日数で割って計算する。
・但し、退職前に使用した「公休」については例外的に「勤務日数」としてカウントする。
について、ご回答申し上げます。
ありがとうございます。
考え方につきましては、ご説明申し上げました通りです。
ご質問の「そういうことか」否かは、最終的には所轄の労働基準監督署の判断となります。「そういうことか」否かについては、所轄の労働基準監督署の監督官にご質問されることをお勧め申し上げます。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/07/08 02:28 ID:QA-0155058
相談者より
ご返信有難うございます。
いただいたアドバイスをもとに、方針を決めて、最終的には労基署にも確認するようにしたいと思います。
この度は詳細説明をいただき本当にありがとうございました。
投稿日:2025/07/11 13:15 ID:QA-0155296大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
公休日は計算に含める必要はありません。
退職する月の所定労働日数が25日、退職するまでの実労働日数+有休取得日数が15日ということで、②180,000×25分の15=108,000で支払えばよろしいでしょう。
ただしこの場合、有給休暇取得時の賃金が「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」で支払われていることが前提になります。
投稿日:2025/07/08 07:19 ID:QA-0155063
相談者より
アドバイス感謝申し上げます。
有給休暇取得時の賃金を「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」としつつ、②の方針で進めていきたいと思います。
有難うございました。
投稿日:2025/07/11 13:19 ID:QA-0155297参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
退職者の有給 退職した社員の有給が残っていたのですが本人から申請されなかったのでそのままにしておいて良いでしょうか? [2025/12/15]
-
退職者の有給について パートで退職された方がいますが、有給が残ったままの状態です。退職は自己都合による退職で、有給は付与されたばかりのタイミングでの退職の申し出だったので、有給... [2024/08/23]
-
退職 有給が33日残ってます。会社が退職時に残ってる有給は買取になりますが、出勤日数以上の有給を1ヶ月で買いとる事はできるのですか? [2025/03/13]
-
退職日前の退職金一部(または全部)支払について 3月末付で退職予定の従業員に対し、通常は翌4月中に退職一時金の支払いをしておりますが、3月中の支払いができないかとの問い合わせがありました。退職所得として... [2009/02/13]
-
退職日 当社は退職の申し出があった者に対し、退職届(退職願)を提出させています。この際、退職日を確定するのですが、退職日は当社の営業日としています。1.これは合法... [2010/05/15]
-
退職日を決定するにあたっての有給日数の最終日 例えば12/30退職する際の有給が20日残っている場合、12/10までを業務、その後20日を有給とするのか、公休を含め(週休2日、月8日あると)12/2ま... [2005/11/17]
-
64歳11ヶ月退職について 来年65歳になる社員から、失業保険を受給したいので65歳になる前に退職したいといわれました。誕生日が1/18なので退職日は1/16にしたいということですが... [2025/10/17]
-
退職と有給消化 [2010/06/25]
-
退職率 よく退職率 何%と表示がありますが、算出方法はどのように行うのでしょうか?単純に年度末の人員÷退職者数でいいのでしょうか? [2006/11/24]
-
希望退職募集の場合の退職金 経営がかなり逼迫している状況で、希望退職を募る場合、退職金の上乗せはどれくらいが妥当でしょうか? [2010/11/30]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント