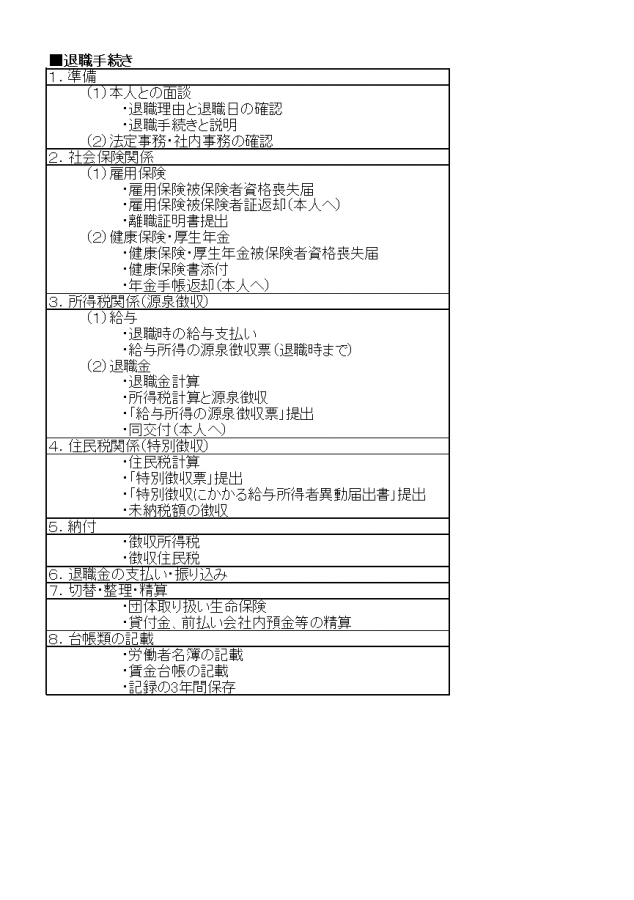早期優遇退職施行について
当社は創立20年の企業です。創立時から3年程度大量採用したのですがその後業績低迷により採用人数をしぼりこんだため、現在年齢構成が大変いびつになっています。当社は精密機器工場であることからこのままでは、身体的能力の低下により生産性が落ち込んでゆくこと、また将来発生するであろう勤務債務が爆発的に増加することから早期優遇退職制度を3年間限定で実施することを考えています。この準備のために3年前人事賃金制度を大きく変更し、査定に対するポイントを明確にし、従業員全員に対して必ず客観的な面談項目表をベースに査定の低いものに対してフォローアップ改善要求をし記録として残してきました。そこで今回は、早期優遇退職という制度はとりますが、実質は改善の見られなかったものをリストアップし退職勧奨という形で進めるつもりです。当制度の応募者には、会社都合による退職金支払いプラス割増退職金を支払います。この進め方について何かアドバイスがあったら御願いします。なお当社には組合があります。
投稿日:2006/03/15 11:43 ID:QA-0004058
- *****さん
- 秋田県/精密機器(企業規模 301~500人)
この相談を見た人はこちらも見ています
-
退職日前の退職金一部(または全部)支払について 3月末付で退職予定の従業員に対し、通常は翌4月中に退職一時金の支払いをしておりますが、3月中の支払いができないかとの問い合わせがありました。退職所得として... [2009/02/13]
-
退職日 当社は退職の申し出があった者に対し、退職届(退職願)を提出させています。この際、退職日を確定するのですが、退職日は当社の営業日としています。1.これは合法... [2010/05/15]
-
64歳11ヶ月退職について 来年65歳になる社員から、失業保険を受給したいので65歳になる前に退職したいといわれました。誕生日が1/18なので退職日は1/16にしたいということですが... [2025/10/17]
-
退職者の有給について パートで退職された方がいますが、有給が残ったままの状態です。退職は自己都合による退職で、有給は付与されたばかりのタイミングでの退職の申し出だったので、有給... [2024/08/23]
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
早期優遇退職施行について
■今後の経営負担を予測し、人事制度面において事前措置を講じらてこられ、これから本番を迎える段階だと理解致します。身体的能力と技術力を必要とする精密機器業ゆえに、尚更一層危機感は高いものと推測します。しかし、日本的リストラも、やりすぎると、技術やノウハウ、体験の継承を遮断し、企業のソフトパワ一の蓄積を妨げてしまいます。目先のやみくもな人件費カットは、社員から活力を奪い、会社を悪循環に落とし込んでしまうことに留意することが肝要です。
■ご検討中の人員削減策の看板は「早期優遇退職制の施行」となっているものの、実態は「指名解雇に近い希望退職の募集」と理解してよいのでしょうか。労使関係の信頼性レベルは分りませんが、減員措置による労使紛争を未然に防ぐために、募集要項を作成する段階で、いわゆる『整理解雇の4要件』を念頭において、精緻に作成しておかなくてはなりません。
■この『整理解雇の4要件』とは、判例の積み重ねによって事実上確立されてきた理論で、整理解雇は最後の手段であり、できるだけ回避されるべきであることを前提に、解雇権の乱用に当らないと是認される次の要件であるとされています。
① 人員削減の必要性⇒このまま推移すれば「高度の経営危機に陥る」ことの立証
② 整理解雇を選択することの必要性⇒打つべき手はすべて打って残された最後の選択肢が整理解雇であることの立証
③ 被解雇者選定基準の合理性⇒勤怠、勤務成績、貢献度などについての客観的な選定基準
④ 解雇手続きの合理性⇒労組や労働者への説明協議
■紙面の文字数制限により詳細説明は出来ませんが、リストラ成功の要諦としては、次の諸点が挙げられます。
① 経営トップの具体的姿勢
② 削減対象者への最大限の配慮
③ だらだら解雇は最低、スケジュールは人員削減から半年以内のタイムテーブルが必要
④ 一旦合意に至った後の労組執行部へのバックアップ体制
投稿日:2006/03/16 00:06 ID:QA-0004072
相談者より
早速のアドバイスありがとうございました。個人的にも「整理解雇の4条件」は念頭に入れておかなければいけないかなと考えておりました。ただしこのごろの判例では、4条件よりも高度な経営判断が優先されるとの話も聞こえてきます。現在は、業績も良くある程度体力もあることから、だからこそ将来に向けた構造改革をしなければならないという意志です。組合も現状の延長線上では、企業継続は困難であるという認識は共有しています。いずれにしてもアドバイスの内容を肝に銘じスタートをかけたいと思います。ありがとうございました。
投稿日:2006/03/16 10:44 ID:QA-0031662大変参考になった
プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
早期優遇退職施行について
「整理解雇の4条件」を文字通り受け取りますと、その会社には、もはや再浮上の余力が残されていない状況が想定されます。それでは、実際は遅すぎるのです。ご指摘のように「倒産必至」から「当面の経営危機回避」へ、更に「将来の危機回避のための予防措置」へと判断の軸足がシフトしてきています。一見、企業に有利に見えますが、解雇対象者にとっては、「業績も悪くないのに何故?」という疑問が膨らんできて、合意の取得が却って難しくなるという可能性にも十分配慮されるようお勧めします。
投稿日:2006/03/16 11:18 ID:QA-0004078
相談者より
重ね重ねのアドバイスありがとうございました。
投稿日:2006/03/16 15:55 ID:QA-0031664大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
退職日前の退職金一部(または全部)支払について 3月末付で退職予定の従業員に対し、通常は翌4月中に退職一時金の支払いをしておりますが、3月中の支払いができないかとの問い合わせがありました。退職所得として... [2009/02/13]
-
退職日 当社は退職の申し出があった者に対し、退職届(退職願)を提出させています。この際、退職日を確定するのですが、退職日は当社の営業日としています。1.これは合法... [2010/05/15]
-
64歳11ヶ月退職について 来年65歳になる社員から、失業保険を受給したいので65歳になる前に退職したいといわれました。誕生日が1/18なので退職日は1/16にしたいということですが... [2025/10/17]
-
退職者の有給について パートで退職された方がいますが、有給が残ったままの状態です。退職は自己都合による退職で、有給は付与されたばかりのタイミングでの退職の申し出だったので、有給... [2024/08/23]
-
64歳と65歳の失業給付金について 退職日を迷っておられる社員がいるのですが、64歳11か月で退職した場合と、65歳になってから退職した場合、雇用保険から受給できる失業給付金などの違いを教え... [2017/02/16]
-
退職率 よく退職率 何%と表示がありますが、算出方法はどのように行うのでしょうか?単純に年度末の人員÷退職者数でいいのでしょうか? [2006/11/24]
-
退職者の有給 退職した社員の有給が残っていたのですが本人から申請されなかったのでそのままにしておいて良いでしょうか? [2025/12/15]
-
退職金の精算 現在ある退職金制度を今後、なくしてしまいたいと思いますが、まずもって可能なのでしょうか?現在の在籍者にはすでに退職金の受給権が発生しています。この退職金を... [2009/04/13]
-
希望退職募集の場合の退職金 経営がかなり逼迫している状況で、希望退職を募る場合、退職金の上乗せはどれくらいが妥当でしょうか? [2010/11/30]
-
定年退職時の退職金 定年退職時の退職金支給について質問させてください。退職金規定支給表に自己都合、会社都合がある場合、定年退職の場合は会社都合支給でよろしいのでしょうか? [2008/02/14]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント