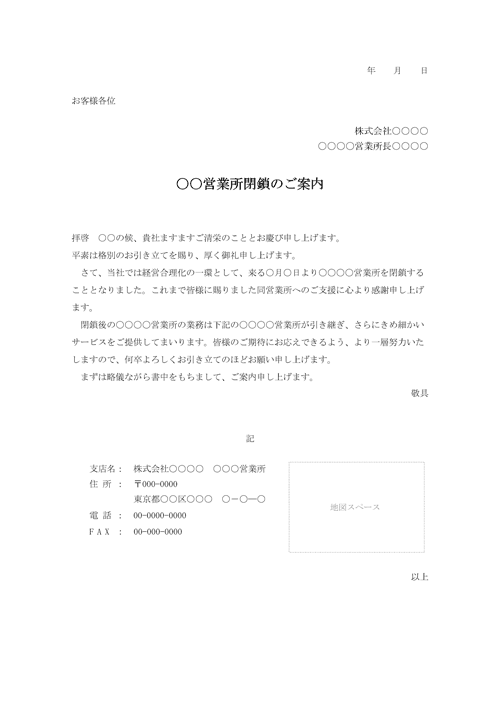自宅を事務所として勤務する形態の懸念事項について
いつもお世話になっております。
地方の営業所おきまして、以前は営業社員が10名在籍しておりましたが、近年退職者が相次ぎ、また、採用難により人員補充も困難な状況が続いておりました。その結果、現在では営業社員数が1名のみとなり、当該営業社員の売上規模では、営業所の運営・維持も難しいことから、本営業所を閉鎖する運びとなりました。
但し、その営業所を統括するブロック長(幾つかの都道府県の営業所を統括する部長)より、閉鎖後の当該営業社員の勤務形態につきまして、以下の提案がありました。
・工場から商品を自宅へ宅配便送付により、自宅にて保管・管理を行う。
・会社のロゴ入りの営業車を継続利用(自宅敷地内に駐車スペースあり)
・営業活動により売上が発生した場合、現金は本社へ直接入金。
・勤怠管理は、業務開始時と業務終了時に本社へ電話連絡させ、正社員として雇用を継続。
当社では、現在ICカードを営業所設置型カードリーダーにかざし、出退勤時刻を管理をしています。今後、そういったシステムを使用した勤怠管理が不可能となりますので、
外回りをする営業社員を自宅を倉庫兼事務所として使用させ、営業活動をさせるとなると、 営業所に出社し、上司・同僚・後輩と顔を合わせる訳ではありませんので、業務開始報告後、家でサボっていても会社としてはわからず、また、終業時間後、仕事をしていなくても、終業時間後に業務終了報告があれば、労働時間とカウントされ、余分な賃金の支払いリスクが発生します。
また、売上についても、売上計上後、本社のシステムに売上入力をしなければ、売上が上がっているかどうか本社では把握できませんので、契約未報告・未入力による着服や不正リスクもあるのですが、
36協定は、直近上位の組織で届出ということで問題ないかと思いますが、
労務管理上は勤怠不正の他、企業として発生する問題はございますでしょうか。
その他、下記のような運営上の懸念点もありますので、
・監視する人が居ませんので、ガソリン代も業務以外でプライベートで使用してもわかりません。
・たまたま、自宅に駐車スペースがあるとはいえ、会社として駐車場代を負担しなくてもいいのか。
正直、使用者の指揮命令下で働いている雇用契約ではなく、業務委託契約としての対応が望ましいのでは?と思っております。
投稿日:2025/10/06 12:23 ID:QA-0159192
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
この相談を見た人はこちらも見ています
-
営業所の新規開設について 初めまして。東京に本社があり関西と中部に営業所があります。東北に営業所を新設するのですが本社から1名が週1で2〜3日出張ベースで行くような形となります。営... [2022/01/22]
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが、勤務時間が0:00を跨ぐ場合で、翌日が休日の場合、0:00から5:00までは休日かつ深夜労働とみなすべきでしょうか?例え... [2005/11/10]
-
日をまたいでの退職日について 例えば深夜の契約で23時から朝の7時までの勤務契約をむすんでいる場合、11/22付け退職の場合は21日の夜23時から次の日の朝7時まででないとまずいでしょ... [2005/11/22]
-
26業務について 26号業務内で2つ以上の業務を行う契約書(○号業務と○号業務のような形式)は有効となるのでしょうか? [2007/02/06]
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
営業所閉鎖後に「自宅を事務所・倉庫として勤務」させる形態は、法的・労務管理上のリスクを多く含みます。
以下、1.労務管理上の懸念点、2.法的リスク、3.運用上の留意点、4.業務委託との比較に分けて整理し、ご回答申し上げます。
1.労務管理上の懸念点
(1)勤怠管理の実効性
出退勤報告を電話連絡で行う場合、実際の労働実態と報告の整合性を確認できないため、勤務時間の虚偽報告や、私的行動中の報告リスクがあります。
→ 厚労省はテレワークにおける勤怠管理について、自己申告制であっても、上長による内容確認や客観的記録(ログ・通信履歴など)での裏付けを求めるとしています(令和3年3月31日付「テレワークの適正な導入・実施のためのガイドライン」)。
(2)労働時間の算定
在宅勤務における労働時間の算定は「使用者の指揮命令下」にある時間で判断されます。
例えば、会社が業務開始・終了報告を求め、定期的に報告義務を課している場合には、その間の待機時間や電話待ち時間も労働時間に含まれる可能性があります。
→ 結果として、労働時間の過大計上・割増賃金の支払義務が発生するおそれ。
(3)業務管理・安全衛生管理
自宅が職場扱いとなる場合、安全衛生配慮義務の対象となる(労安法第3条)。
→ 労働災害発生時に「業務遂行性・業務起因性」の判断が困難。
→ 作業環境が会社管理下にないため、事故・転倒・火災等の際に労災申請トラブルが起こりやすい。
(4)情報管理
自宅に商品・帳票・顧客情報を保管する場合、個人情報・営業秘密の漏えいリスクが高まります。
→ 自宅内への第三者出入り・家族共有パソコン等による情報漏洩は、会社の管理責任が問われる可能性。
2.法的リスク
(1)労働基準法上の使用者責任
自宅勤務であっても、指揮命令・勤務時間の拘束があれば、使用者の管理下にあるため、労働基準法の適用を免れません。
「成果に応じて報酬」など業務委託に近い運用をしても、実態が雇用であれば偽装請負・労働者性の問題が発生。
(2)労働契約の実態と乖離
労働契約上の「就業場所」が営業所となっている場合、自宅勤務への変更は労働条件の不利益変更となり、労働契約法第8条・第9条に抵触するおそれ。
→ 労使合意と就業規則改定(「自宅を就業場所とすることがある」旨の条文追加)が必要。
(3)経費負担・設備提供
自宅を事務所として使わせる場合、光熱費・通信費・保管スペースの費用負担をどう扱うか明示が必要。
→ 全額本人負担とする場合は合理的範囲であることを説明しなければ、トラブルの原因に。
3.運用上の留意点・改善提案
勤怠管理の客観化
業務用スマートフォン・営業車GPS・クラウド打刻(GPS打刻や営業先チェックイン機能)などを導入し、勤務実態を補足。
売上・経理管理の仕組み
売上入力の遅延・不正を防ぐため、売上報告をシステム上リアルタイム共有化。
預り金の発生は原則禁止し、入金は全て振込方式へ。
情報セキュリティ対策
自宅保管品の管理規定(在庫記録・施錠保管・第三者立入禁止など)を明文化。
経費精算ルール
光熱費や通信費の定額手当(テレワーク手当)を支給することで、実費請求トラブルを防止。
就業規則・雇用契約書の整備
「就業の場所に自宅を含むことがある」旨を明記。
「テレワーク勤務規程」または「在宅勤務取扱要領」を別途策定。
4.業務委託契約とすべき場合の判断ポイント
ご指摘の通り、もし営業社員に対し、
業務時間・勤務場所の指定なし
成果(売上)に応じて報酬支給
自己判断で業務遂行
という運用ができるなら、業務委託契約(準委任・請負)の方が法的整合性は高いです。
ただし、現行の提案(勤務開始報告・終了報告・会社の営業車・商品保管など)を見る限り、
→ 実態は「明確な指揮命令下」であり、雇用契約(労働者性)を否定するのは難しいと思われます。
そのため、「雇用のままテレワークとして運用管理体制を整備する」方が現実的です。
5.まとめ:想定される主なリスク一覧
リスク区分→内容→対応策
勤怠管理→サボり・過少/過大申告→GPS打刻・定期報告・営業日報確認
労働時間→自己申告時間が過大→上長確認と報告内容の照合
安全衛生→在宅事故の労災トラブル→自宅環境チェックリスト導入
情報管理→顧客情報・商品紛失→鍵付き保管、情報持ち出しルール
経費→光熱費・駐車場費→テレワーク手当支給/規定整備
業務不正→売上未入力・着服→定期売上報告・二重承認制
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/10/06 14:30 ID:QA-0159202
相談者より
いつもお世話になっております。
私が気付いていなかった細部にまで目を配り、的確かつご丁寧にご回答をいただき、有難うございました。
とても参考になりました。
投稿日:2025/10/06 15:19 ID:QA-0159209大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
リスク観点では、労務管理に限らず、以下が実現できませんと多くのリスクが
生じるものと思われます。実施が困難な場合は、業務委託契約への切替も相談と
はなりますが、大きな選択肢の1つと言えるでしょう。
在宅勤務規定の策定:
労働時間管理の方法(始業・終業の具体的な報告方法、休憩の原則など)、
経費精算(ガソリン代、通信費など)、情報セキュリティ対策等、
在宅勤務に関する詳細なルールを整備し、就業規則に準じた規定として
明確化することが必須です。
労働時間管理システムの見直し:
電話連絡ではなく、GPS機能付きのスマートフォンアプリ、PCのログオン・
ログオフ、Web上の打刻システムなど、より実態に即した勤怠管理システムを
導入する必要があります。
業務指示と報告の明確化:
上司による日々の業務指示、進捗確認、週次でのWeb会議などを実施し、
指揮命令下にあることを明確にし、かつ孤立化を防ぐ対応が必要です。
投稿日:2025/10/06 16:03 ID:QA-0159223
相談者より
いつもお世話になっております。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2025/10/06 17:25 ID:QA-0159228大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
営業所の新規開設について 初めまして。東京に本社があり関西と中部に営業所があります。東北に営業所を新設するのですが本社から1名が週1で2〜3日出張ベースで行くような形となります。営... [2022/01/22]
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが、勤務時間が0:00を跨ぐ場合で、翌日が休日の場合、0:00から5:00までは休日かつ深夜労働とみなすべきでしょうか?例え... [2005/11/10]
-
日をまたいでの退職日について 例えば深夜の契約で23時から朝の7時までの勤務契約をむすんでいる場合、11/22付け退職の場合は21日の夜23時から次の日の朝7時まででないとまずいでしょ... [2005/11/22]
-
26業務について 26号業務内で2つ以上の業務を行う契約書(○号業務と○号業務のような形式)は有効となるのでしょうか? [2007/02/06]
-
インフルエンザの予防接種について 石川県に本社(製造拠点)がございまして、およそ90名が勤務しております。そして、東京、大阪、福岡に営業所があり、各営業所の従業員数は、東京営業所:15名、... [2023/10/03]
-
アルバイトの雇用契約について たとえば、週1日で8時間勤務でアルバイト契約(雇用契約書を締結)した場合週に2日(16時間)勤務させることは難しいのでしょうか? [2012/07/07]
-
日当について ありがとうございます。ご相談の内容ですが、今般、当社で2つの営業所を兼務する管理者がでました。A営業所で通常勤務しますが、週に1回はB営業所に移動し、業務... [2022/10/05]
-
事業所拡大による36協定の届出について 弊社は規模に応じて「支店」とその下位組織として「営業所」に分かれており、登記上も36協定の届出についても「支店」はおこない、「営業所」は「支店」直属という... [2020/02/04]
-
半休の場合の割増無の時間 派遣勤務者は、本社と勤務時間が異なります。半休を取得して残業を行った場合、派遣勤務先の勤務時間が9:00~17:00の7時間勤務、本社は8:30~17:3... [2017/06/26]
-
パートタイマーの雇用契約について パートタイマーの雇用契約を行う際に、週によって勤務日数や勤務時間が変動するケースがあると思います。その場合、例えば週の労働時間を「30時間から39時間」、... [2009/12/06]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
営業所閉鎖のご挨拶(見本2)
自社の営業所が閉鎖したことを他社に案内する文例です。引継ぎ先の営業所の案内と地図スペースがついています。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント