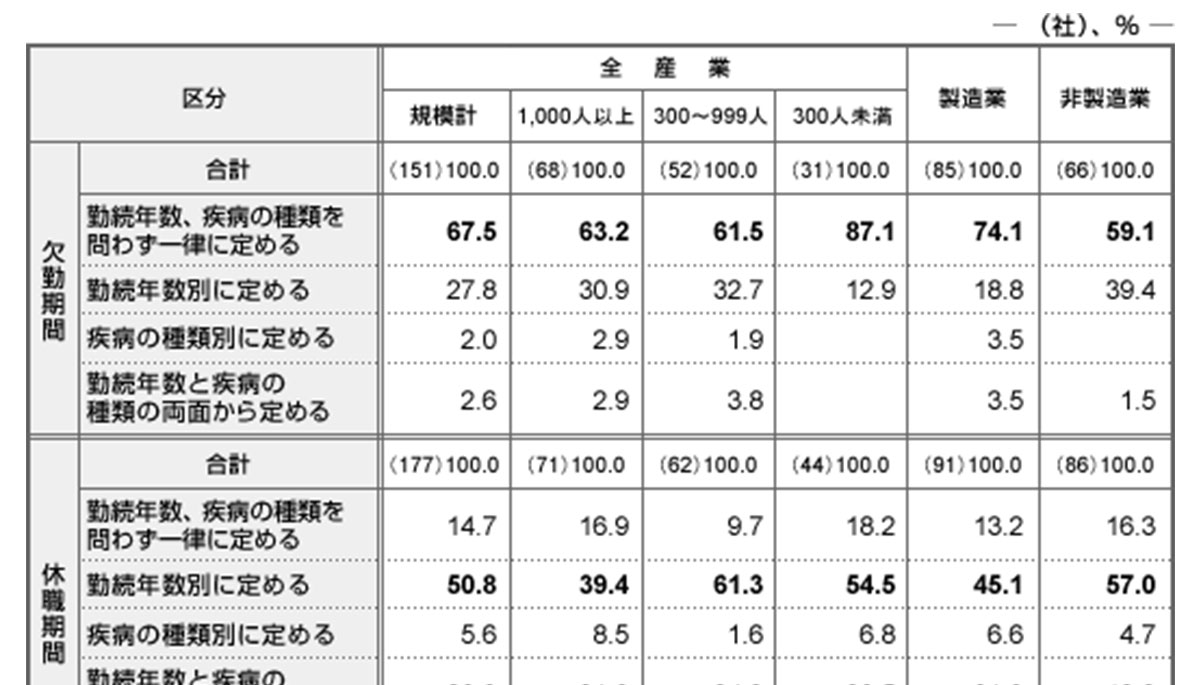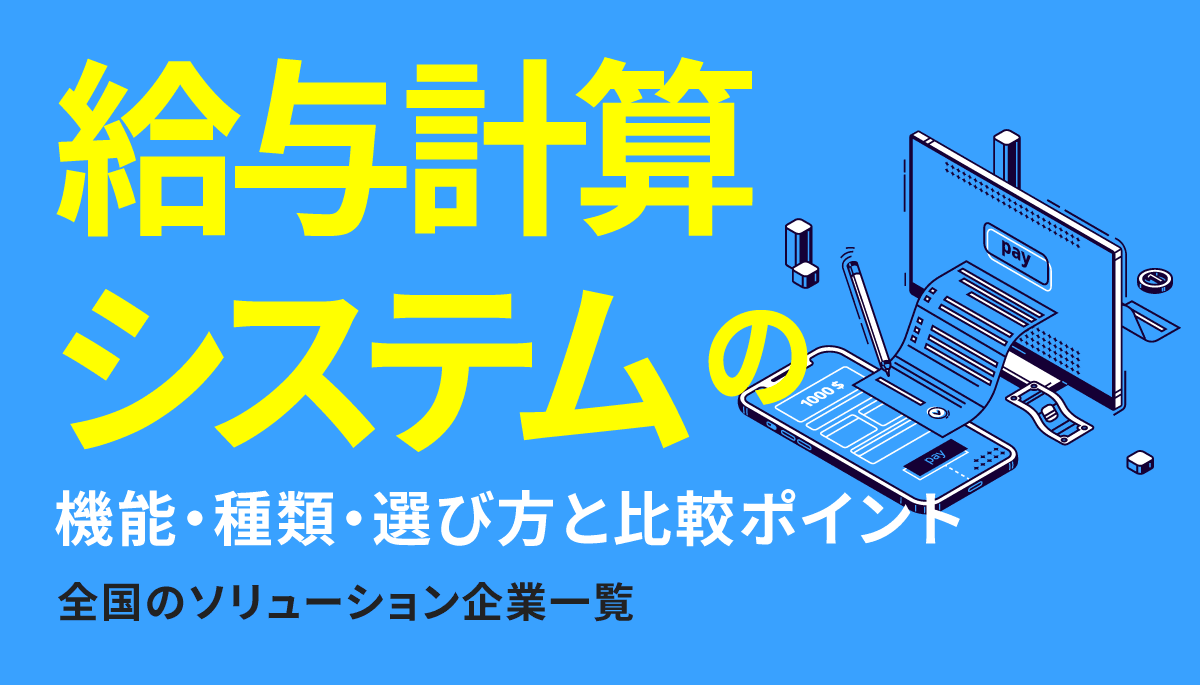有給申請システム作成時においての質問
結論から言いますと、、
社内有給システムを作るにあたり、
出勤率が80%以上でないと有給付与対象からは除外されます。
この処理を自動で行うようにしたいのですが、確定条件として1年の日本の祝日・土日はわかりますが、会社の休日で年末年始はカレンダーによって毎年誤差が出ます。
欠勤日で出勤率を出したいとき、数十年分の出勤率80%未満になる欠勤上限日を平均で出し、その日を基準に出勤率を判定してもよろしいのでしょうか?
専門的な回答が欲しく、質問させていただきます。
社長からの開発願いでありますので、成功させなければいけないのです。
以上です。回答お待ちしております。
投稿日:2025/06/13 14:53 ID:QA-0153947
- Rさんさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)
この相談を見た人はこちらも見ています
-
退職 有給が33日残ってます。会社が退職時に残ってる有給は買取になりますが、出勤日数以上の有給を1ヶ月で買いとる事はできるのですか? [2025/03/13]
-
退職者の有給 退職した社員の有給が残っていたのですが本人から申請されなかったのでそのままにしておいて良いでしょうか? [2025/12/15]
-
有給付与の件 4月1日入社の社員は、10月1日に有給が10日付与します。義務の有給は何日になりますか? [2021/09/07]
-
休養中の有給の更新 去年の10月後半から疾病により休養している者が有給を使い切り、改めて今年3月からの有給の更新を申請してきている。有給を改めて付与する必要がありますか? [2025/02/28]
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当該年度の出勤率に関しましては厳格に計算されなければなりませんので、過去の平均等の数値を用いる事は認められません。
加えまして、ご存知の通り実際に出勤されていなくとも会社都合の休業等であれば出勤扱いとされますので、そうした細かな条件もシステムに取り込んでおく必要がございます。
後はシステムに関わるテクニカルな問題になりますので、成功の為には人事担当だけではなくシステムの専門家を交えて検討される事が不可欠といえます。
投稿日:2025/06/13 15:55 ID:QA-0153952
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答させていただきます。
結論、以下のロジックはNGとなります。
仮に3年分(複数年分)の平均をとりますと、
A年の欠勤上限は50日、
B年の欠勤上限は51日、
C年の欠勤上限は52日 、
で平均の51日が採用されますが、年によっては、
欠勤52日がその年の欠勤日数上限に該当するケースもゼロではありません。
つまり、労働者不利になるケースが存在する限りはNGとなります。
会社の休日数に毎年変化が生じることが今後も継続的に続くのであれば、
毎年、システム内に持つ、年間所定労働日数のマスタ情報を更新の上、
出勤率判定を行っていただくしかございません。
補足までに、残業代の計算を行う際の時給単価計算に、
年間の月平均所定労働時間の数値を用いているのであれば、
年間の所定労働日数情報は、給与システムの内か外に保持されているかと
思いますので、その情報を上手く活用できるかもしれません。
投稿日:2025/06/13 15:57 ID:QA-0153953
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
過去平均ではなく、その時の「出勤日数/全労働日」で算出してください。
全労働日を出すにあたり、所定休日が毎年変わるようでしたら、
所定休日は毎年入力変更できるようにシステム設計してください。
投稿日:2025/06/13 16:28 ID:QA-0153960
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.法的な前提:出勤率の計算方法
労働基準法施行規則第24条の3によると、有給付与の出勤率は以下のように定義されています。
(1)出勤率 = 実際に出勤した日数 ÷ 出勤すべき日数
※「出勤すべき日数」とは、会社が定めた所定労働日数(=所定休日を除いた日)を意味します。
(2)「出勤」とみなされるもの
実際の出勤日
年次有給休暇取得日
労災休業、産前産後休業、育児休業、介護休業 など
→ これらは「出勤したもの」としてカウントされます。
(3) 問題点:年末年始などの変動的休日
おっしゃる通り、祝日・土日は固定でシステム化が可能ですが、会社独自の休日(例:年末年始・創立記念日など)は年によって異なるため、自動判定が難しくなります。
2.結論:平均欠勤日数を使う判断はNG(非適切)
「過去数十年の平均的な欠勤上限日数を基準として出勤率を判定する」という方法は、法的にも運用上も適切ではありません。
理由:
出勤すべき日数は年度ごと・個人ごとに異なるため、平均で代替するのは「実態を反映していない」とされるおそれがある
出勤率は個別に算定されるべきものであり、過去平均で一律判定すると、有給権利を不当に制限したと見なされるリスクがある
3.導入すべき実務的アプローチ(推奨)
(1)会社カレンダーを毎年登録(変動休日対応)
毎年、年度の所定労働日カレンダーを会社が人事システムに登録する形にします
各年の「出勤すべき日数(分母)」が明確になり、自動で個人別に出勤率を算出可能になります。
(2)欠勤・有休等のステータスを区別
出勤ステータスは以下のように分類して集計:
「○」出勤(カウントする)
「△」有給休暇、育休など(カウントする)
「×」欠勤、無断欠勤、遅刻早退による控除(カウントしない)
これをもとに、「分子=カウント対象の日数」「分母=出勤すべき日数」で出勤率を算出
4.システム要件(実装の方向性)
項目→内容
会社カレンダー管理→年次ごとに管理部が休日・出勤日を登録できる管理画面を用意
勤怠記録→各日ごとの出勤区分を入力(勤怠システムと連携が理想)
出勤率計算処理→対象期間の「出勤すべき日数」「出勤実績日数」を集計して自動計算
有給付与対象者抽出→年次ごとに出勤率が80%以上の従業員を抽出し、付与処理へ連携
5. まとめ(経営者・開発チーム向け)
ポイント→内容
平均値で代替して判定すること→不適切(法的根拠を欠く)
法的根拠に基づく正しい方法→年次ごとに実際の「所定労働日数」ベースで個人別に判定
必要なシステム要件→(1)会社カレンダー登録機能 (2)勤怠記録集計 (3)出勤率ロジック実装
リスク回避→過少付与のトラブル・労基署是正の回避には精度が必須
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/06/13 16:33 ID:QA-0153962
プロフェッショナルからの回答
全労働日の範囲
【御質問】
数十年分の出勤率80%未満になる欠勤上限日を平均で出し、その日を基準に出勤率を判定してもよろしいのでしょうか?
【回答】
(1)有給休暇の付与要件の一つは、「全労働日の8割以上の出勤」です。
(2)この「全労働日」については、所定休日のほか、以下についても算入しな
いことになっています。
・不可抗力による休業日
・使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日
・正当な争議行為で労務の提供が全くなされなかった日
・労働基準法第37第3項の代替休暇
・慶弔休暇等(就業規則所定の事由が発生したことを条件として使
用者が労働義務を免除する場合)
(3)以上を踏まえれば、「数十年分の出勤率80%未満になる欠勤上限日を平均
で出し、その日を基準に出勤率を判定」するという方法は、労働基準法上の
出勤率の計算になじまないと考えられます。
投稿日:2025/06/13 17:54 ID:QA-0153970
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
入社後の6ヵ月間、または以後の1年間ごとに出勤率が8割以上であることが、年休の取得要件になります。
数十年分の出勤率の平均を基準にするとした場合、前年度の出勤率が8割以上であっても、過去の平均値で計算すれば8割未満となる可能性もあり、前年度の出勤率が満たされているにもかかわらず、有給休暇を付与できないといった現象が起こる可能性もでてきます。
ただし、出勤率が8割未満であっても、法定どおり有給休暇を付与するとしてもそれはそれで問題はありません。
出勤した日を全労働日で除して出勤率を算出しますが、
「出勤した日」には、①遅刻・早退した日、②業務上の傷病による休業期間、③産前産後の休業期間、④育児・介護休業期間、⑤年休を所得した期間、が含まれます。
「全労働日」とは、6ヵ月、あるいは1年の総暦日数から所定休日を除いた日をいい、会社都合による休業や、休日労働をした日などは含まれません。
投稿日:2025/06/14 08:52 ID:QA-0153985
プロフェッショナルからの回答
ご相談内容について回答いたします
労働基準法 第三十九条には「使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。」とあります。
労働基準法は労働条件の最低限度を定めたものとなります。従いまして、有給休暇の出勤率8割の判定は、厳格に行う必要があります。
有給休暇の出勤率8割の判定は、実労働日をもとに個人単位・年単位での計算が義務となります。
平均やモデルケースを基準とすることは、法的な有給休暇の付与要件を満たさない判定基準となりえ、不適当と考えます。
投稿日:2025/06/16 09:40 ID:QA-0153998
プロフェッショナルからの回答
対応
>数十年分の出勤率80%未満になる欠勤上限日を平均で出し
重要な給与計算は個別に、正確に計算されなければならず、ざっくり平均などでは不適切です。必ず個人ごとに計算できるものにして下さい。
投稿日:2025/06/16 09:47 ID:QA-0154001
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
退職 有給が33日残ってます。会社が退職時に残ってる有給は買取になりますが、出勤日数以上の有給を1ヶ月で買いとる事はできるのですか? [2025/03/13]
-
退職者の有給 退職した社員の有給が残っていたのですが本人から申請されなかったのでそのままにしておいて良いでしょうか? [2025/12/15]
-
有給付与の件 4月1日入社の社員は、10月1日に有給が10日付与します。義務の有給は何日になりますか? [2021/09/07]
-
休養中の有給の更新 去年の10月後半から疾病により休養している者が有給を使い切り、改めて今年3月からの有給の更新を申請してきている。有給を改めて付与する必要がありますか? [2025/02/28]
-
有給休暇日の出勤について 弊社では半日有給休暇制度はありませんので、私用で午後から出勤してくる場合、又は午前のみ出勤する場合、有給休暇を申請して、例えば13時から出勤しましたと申請... [2007/03/05]
-
有給更新について 何度も失礼します。傷病手当金をもらいながら、私病の為、休んでいる場合ですが、もし休んでいる日数が多くて、出勤率が8割に満たない場合、次回の有給更新は行わな... [2021/08/25]
-
早退と有給について 掲題の件についてご教示いただけますと幸いです。8:30~18:30のシフトですが、体調不良で10:00に早退されました。8:30~10:00で勤務されてい... [2023/09/13]
-
半日有給を取得して欠勤した場合 半日有給の運用についての相談です。半日有給を使用して、1日を休むような運用(午前休+午後欠勤)は認められるのでしょうか?弊社従業員に半日有給を消化して1日... [2019/06/06]
-
有給付与について 有給付与についてなのですけど、7月21日が入社日なのですけど、毎年2月21日に有給付与されてるのですけでもしかして1月21日に付与の間違い?ですか? [2025/02/02]
-
出勤率8割に満たなかった場合の翌年の有給付与 出勤率8割に満たなかった場合の翌年の有給付与について、困っております。(現在は就業規則にはなにも謳っていませんが、付け加えようと思っております。)標準的な... [2009/01/19]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント