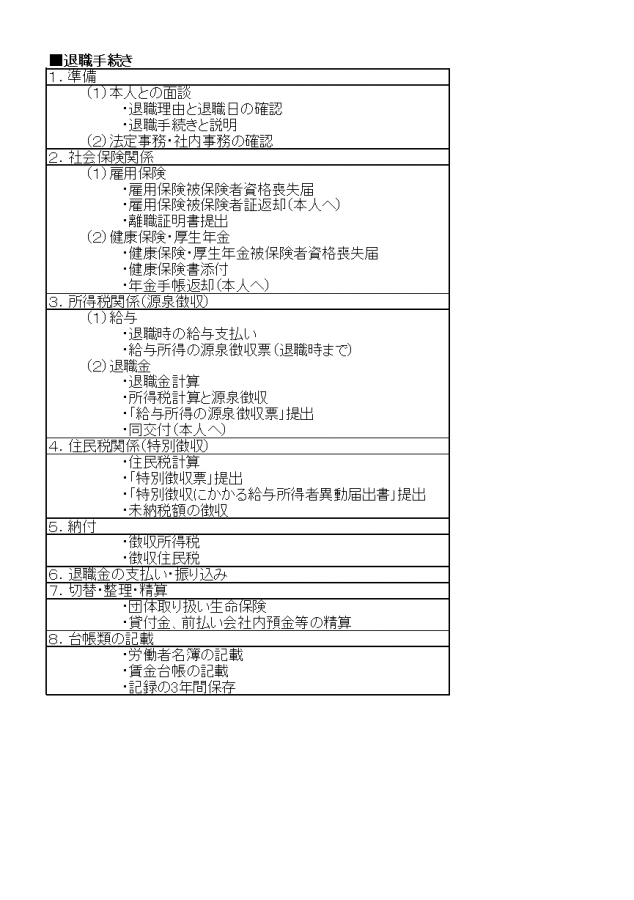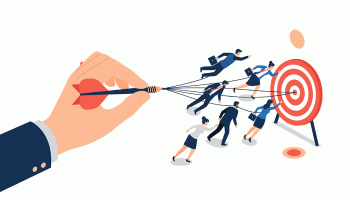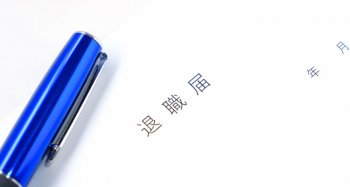退職時の控除
弊社は、
毎月25日締
翌10日払
です。
6/30に退職する従業員がいます。
月末の退職となるため、
❶社会保険料は2ヶ月分
❷住民税←翌月分からは転職先で特別徴収継続
❸所得税
の控除が必要になると思いますが、
弊社25日締のため、
最終給与は6/26~6/30の平日3日分程度しかなく、
上記の❶~❸を控除する金額に満たしておりません。
このような場合、どのようにすればよいでしょうか?
別途請求する以外で、例えばその前の月で控除するなどの対処法はありますか?
投稿日:2025/06/03 10:26 ID:QA-0153474
- ひとり事務さん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)
この相談を見た人はこちらも見ています
-
退職所得控除額を算出する勤続年数について 退職所得控除額を算出する勤続年数についてお尋ねします。例えば2004年9月30日に入社し、2014年9月27日に退職する場合の勤続年数は厳密に計算し9年1... [2014/08/08]
-
退職日前の退職金一部(または全部)支払について 3月末付で退職予定の従業員に対し、通常は翌4月中に退職一時金の支払いをしておりますが、3月中の支払いができないかとの問い合わせがありました。退職所得として... [2009/02/13]
-
退職日 当社は退職の申し出があった者に対し、退職届(退職願)を提出させています。この際、退職日を確定するのですが、退職日は当社の営業日としています。1.これは合法... [2010/05/15]
-
64歳11ヶ月退職について 来年65歳になる社員から、失業保険を受給したいので65歳になる前に退職したいといわれました。誕生日が1/18なので退職日は1/16にしたいということですが... [2025/10/17]
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
「最終給与で控除しきれない保険料等を、前月の給与から控除することは原則として可能」です。
2.状況整理
退職日:6月30日(=月末退職)
給与締日:毎月25日締め
最終給与:6月26日〜6月30日分(平日3日程度、非常に少額)
控除すべきもの:
(1) 社会保険料(5月・6月分)
(2) 住民税(6月まで当社で特別徴収)
(3) 所得税(退職月の精算)
3.各控除項目ごとの対応
(1)社会保険料(5月・6月分)
社会保険料は「当月分を翌月給与から控除する後払い方式」が一般的。
6月分の社会保険料は7月給与で控除すべきですが、退職で支給なしのため、最終給与で控除することになります。6月末退職の場合は5月分・6月分の2ヶ月分が最終給与から控除対象。
対処方法
5月給与で「5月分+6月分」を前倒し控除することは実務上可能。
ただし、本人の同意を得たうえで、給与明細に明記しておくことが重要です。
【注意】給与天引きの原則は「労使協定または本人同意に基づく控除」です。
→書面またはメールで「6月分社会保険料を5月給与で控除する」旨の同意を取得しておくと安全です。
(2)住民税(特別徴収)
住民税は6月分(=5月分給与で控除)が最後。
7月分以降は、転職先で特別徴収が継続されるので、会社としての控除義務はなし。
対処方法
特に追加対応は不要。6月分までを控除できていれば問題ありません。
(3)所得税
所得税は「給与支給時に源泉徴収」されます。
最終給与が少額で源泉徴収できない場合は、「その支給額の範囲内」で徴収するしかありません。
対処方法
差引支給額がマイナスにならない範囲で控除。
徴収しきれない場合は、本人が確定申告で精算することになります。
4.結論(まとめ)
項目→対処法
社会保険料→本人同意のもと、5月給与で2ヶ月分を前倒し控除が可
住民税→6月分まで控除でOK。7月以降は転職先に引継ぎ
所得税→最終給与の範囲内で控除。不足分は確定申告
5.補足:本人同意取得の文面例(メール等)
件名:社会保険料の前倒し控除について
内容:
○○様
6月末退職に伴い、最終給与が少額となるため、社会保険料(5月・6月分)の合計を5月分給与から控除させていただきたく存じます。
ご確認のうえ、ご同意いただける場合は「了承しました」とご返信いただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/06/03 10:47 ID:QA-0153475
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答させていただきます。
本人の同意を得ることで、その前の月の給与から控除することも可能です。
補足までに、退職金がある場合は、同様に、同意があれば控除可能です。
本人にとってみても、別途、振込手続きを行うことは、手間も振込手数料も
かかりますので、状況をご説明の上、同意を得た上で控除なさってください。
投稿日:2025/06/03 11:39 ID:QA-0153479
プロフェッショナルからの回答
対応
社員本人に、不足分支払いが必要になるので、前月給与などから天引きでよいか確認を取って下さい。普通はわざわざ支払いの手間となるより天引きを希望すると思いますが、まずは本人の意思確認をした証拠が必要です。
投稿日:2025/06/03 14:49 ID:QA-0153490
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、社会保険料についてですが、
6/30退社ということであれば、
6月分の社会保険料までがかかりますので、
原則通り、会社として翌月徴収しているのであれば、
7/10支給時に1月分控除すれば、完了です。
7月分の社会保険料はかかりませんので、8/10支給時には控除はありません。
投稿日:2025/06/03 15:22 ID:QA-0153497
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
本人の同意を得ることで、その前月分給与からの一括控除が可能です。
要は、別途振り込ませるか、前の月で2ヵ月分を控除するかの2択でしかありませんので、本人の手間や振込手数料負担を考えた場合、2ヵ月分一括控除のほうが本人にとっては手間が省けるわけですから、その旨本人に説明したうえで同意を得ておけばよろしいでしょう。
投稿日:2025/06/04 08:43 ID:QA-0153523
プロフェッショナルからの回答
ご相談内容について回答いたします
社会保険料、住民税、所得税の、給与からのそれぞれの控除につきましては以下の通りとなります。
1、
社会保険料は前月の給与で6月と7月の2カ月分を徴収します。
今回のケースでは7月10日に支給する給与より徴収することとなります。
日本年金機構ホームページには「従業員の方が、月末に退職した場合は、退職月の前月と退職月の2か月分の保険料を退職月の給与から控除することができます。」とあり、例外的に、退職月の前月と退職月の2か月分の保険料を退職月の給与から控除することを認めています。
2、
住民税は、既に転職先が決まっているとのことですので、翌月10日までに転職先に対して給与所得者異動届出書を送ることで、そのまま特別徴収を引き継ぐことができます。そのため当月分のみを支払給与から控除すれば良く、翌月分は控除する必要はありません。
3、
所得税については、毎月支給される給与額から源泉徴収することとなります。
給与から先に社会保険料等を控除した金額に対して一定の税率をかけたものを源泉徴収しますので、少額の給与であればそれなりの所得税となり、その月の給与から源泉徴収できないことは起こりにくいと考えられます。
なお税務に関するご相談につきましては、一度税務の専門家へご相談されることを推奨します。
投稿日:2025/06/06 19:00 ID:QA-0153647
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
退職所得控除額を算出する勤続年数について 退職所得控除額を算出する勤続年数についてお尋ねします。例えば2004年9月30日に入社し、2014年9月27日に退職する場合の勤続年数は厳密に計算し9年1... [2014/08/08]
-
退職日前の退職金一部(または全部)支払について 3月末付で退職予定の従業員に対し、通常は翌4月中に退職一時金の支払いをしておりますが、3月中の支払いができないかとの問い合わせがありました。退職所得として... [2009/02/13]
-
退職日 当社は退職の申し出があった者に対し、退職届(退職願)を提出させています。この際、退職日を確定するのですが、退職日は当社の営業日としています。1.これは合法... [2010/05/15]
-
64歳11ヶ月退職について 来年65歳になる社員から、失業保険を受給したいので65歳になる前に退職したいといわれました。誕生日が1/18なので退職日は1/16にしたいということですが... [2025/10/17]
-
退職者の有給について パートで退職された方がいますが、有給が残ったままの状態です。退職は自己都合による退職で、有給は付与されたばかりのタイミングでの退職の申し出だったので、有給... [2024/08/23]
-
給与控除の可否について 当法人には組合があり、給与控除については、控除協定にて項目を詳細に取り決めしております。このたび、看護部から個人で加入している看護連盟の年会費を現金で集め... [2021/02/08]
-
退職者への未払賃金支払時の控除について 退職者への未払賃金支払時の控除について、相談させてください。退職者の場合、年金と健康保険料は控除対象外、雇用保険と所得税は控除すると聞いています。所得税控... [2021/03/26]
-
退職時の社会保険料 退職時の社会保険料について確認させてください。弊社は、当月徴収、20日締めの28日支払、日給月給制です。ほとんど締日で退職します。9/1~9/20の退職な... [2014/09/22]
-
年末調整控除ミスについて。 年末調整で1名の社員が仕事納めの日に生命保険控除証明書を提出してきましたが、控除し忘れました。年末調整をやり直しは出来ないので税務署に生命保険控除証明書を... [2023/02/06]
-
希望退職募集の場合の退職金 経営がかなり逼迫している状況で、希望退職を募る場合、退職金の上乗せはどれくらいが妥当でしょうか? [2010/11/30]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント