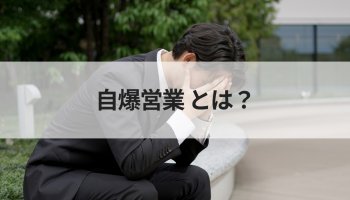働き方
ビジネスにおける「働き方」とは、どのような場所で、どれくらいの時間働くのかを指す言葉です。その中でも「ワーク・ライフ・バランス」「働き方改革」「テレワーク」といった問題で、「働き方」を強く意識するようになった人も多いでしょう。企業は、社会の求めに応じて働き方をどう変容させるべきか考える必要があります。続きを読む
ダイバーシティ&インクルージョン
人には人種や性別、年齢などの外見的な違いはもちろん、宗教や価値観、性格、嗜好など、内面にもさまざまな違いがあります。「ダイバーシティ&インクルージョン(Diversity & Inclusion)」とは、個々の「違い」を受け入れ、認め合い、生かしていくことを意味します。続きを読む
概論
属性
経営戦略
経営戦略とは、企業が置かれている経営環境の下、企業の目的(目標)を達成するためのシナリオ(打ち手)のこと。デジタル変革やAIの進展などの影響で、ビジネス環境が日々大きく変化する中、企業にとって、経営目標を達成するためのシナリオである「経営戦略」の策定が最重要課題の一つになっています。続きを読む
戦略人事
「戦略人事」とは、人事部門がこれまでのような管理的業務を中心とした対応から、経営戦略の実現を担う戦略部門へと転換すべきである、という考え方です。近年、人事部門が果たすべき重要な役割として、大変重要視されているテーマです。続きを読む
人材マネジメント
人材マネジメントとは、経営戦略を実現するために行われる人材管理上の制度・施策のこと。経営環境が激変する現在、その変化に対応して企業の競争力を高めるには、限られた資源と時間の中で制度・施策を組み立て、より最適な人材マネジメントを行うことが求められます。続きを読む
人事管理
人事管理とは、人材を効果的に活用するために行われる、人材の処遇などの一連の管理体制のことです。極めて広い意味が含まれます。人事管理業務を遂行する際には、労働関連法規への適切な対応が求められるため、留意しなければならない点が数多く存在します。続きを読む
HRテクノロジー
「HRテクノロジー(HR Tech)」とは、クラウドやデータ解析、人工知能(AI)、仮想現実(VR)など、最先端のテクノロジーを使って、採用・育成・評価・配置などの人事関連業務を行う手法のこと。担当者の「経験則」と「勘」によって支えられてきた人・組織関連業務において、テクノロジーの力で変革を求めるニーズの高まりを受けて、HRテクノロジーの活用が日本でも進んできている。続きを読む
健康経営
健康経営とは従業員の健康を経営的視点から考え、戦略的に実施することをいいます。なぜ近年、健康経営がクローズアップされるようになったのか? その背景をはじめ国や省庁、経済界、自治体、企業、健保、各種団体などの取り組み施策や事例をご紹介します。また、健康経営が企業にもたらす効果やメリット、今後の課題についてもまとめてご案内いたします。続きを読む
コンプライアンス
コンプライアンスは、「法令順守」という意味です。しかし近年は、企業に対する社会的責任(CSR)の重要性の高まりの中、単に法令だけでなく、社会的規範や企業倫理など、企業が活動していく上で求められるさまざまな「規範」「倫理」を含めた内容となっています。続きを読む