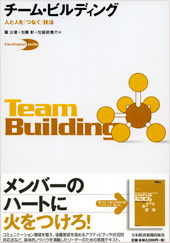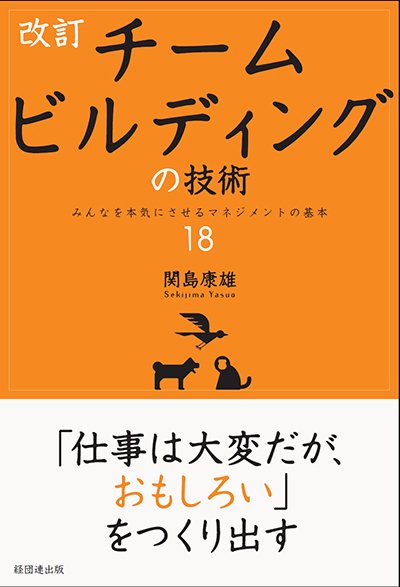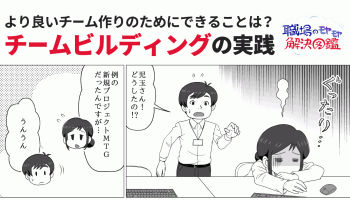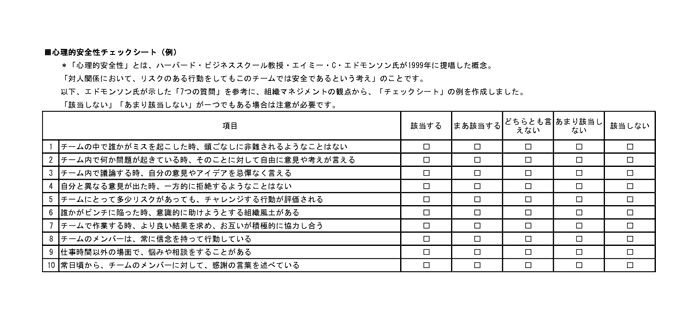チームビルディング
チームビルディングとは?
チームビルディング(team building)とは、メンバーそれぞれが主体的に能力を発揮しつつ、全員が一丸となって目標を達成するチームをつくるための手法のこと。チームビルディングのための取り組みは、日常業務や会議、研修、イベントなど、さまざまな場面で行われます。
「チームビルディング」に関する人事用語を絞り込む
1.チームとは何か
チームとは、共通の目標を達成するために、集結した団体のこと。チームを機能させるには、メンバー全員の判断基準となる目標を明確にすることが重要です。
チームと同じような言葉にグループがありますが、グループとは、単に区分けされた人材の集まりです。チームとグループとの最大の違いとは、共通の「目標」や「ビジョン」の有無です。共通のゴールが設定され、それを達成しようという思いが共有されたとき、グループははじめてチームになります。
2.チームビルディングとは
チームビルディングとは、メンバーそれぞれが協力し合いながらパフォーマンスを最大化させ、目標を達成できる組織を構築する取り組みのこと。個人の力だけで達成できる目標には限りがあります。メンバー一人ひとりは優秀でも、組織としてのまとまりに欠けると、個々のポテンシャルは存分に発揮されません。しかし、メンバー同士が協力し合えば、より大きな成果を生み出すことが可能です。
同じような言葉に、「チームワーク」があります。チームワークとは、同じチームとなったメンバー同士が協力し合うことです。一方、チームビルディングとは、協力するだけでなく、互いの強みや役割を尊重しながら、主体的に能力を発揮できるような関係性を作っていくことといえます。
3.チームビルディングの目的
ビジョンの浸透による、達成意識の醸成
チームの目指す方向性が明確になれば、目標達成への強い意識を醸成することができます。メンバーそれぞれが常に目標に立ち返り、それぞれの役割を発揮して協力し合うため、チームに一体感が生まれます。
仲間意識形成による、モチベーションの向上
一人では成し遂げられなかったり、諦めてしまったりすることも、目標を共にする仲間がいれば乗り越えることが可能です。互いに励まし合うことで、困難な場面でも解決に向けて動くことができます。
また、チーム内で役割を持ち、自分の強みを発揮することができれば、「チームに貢献している」という自己肯定感へとつながります。第三者からの評価を気にすることのない環境も維持できるでしょう。
イノベーションや新規アイデアの創出
チーム内で頻繁に意見交換が行われると、一人では思いつかないようなアイデアが生まれることもあります。相乗効果が生まれたり、企画がブラッシュアップされたりすることにより、通常では考えられないようなイノベーションが起こることもあります。
4.チームビルディングにおける「五段階プロセス」の考え方
良いチームを形成するためには段階に応じたチームビルディングが必要ですが、チームビルディングの参考になる考え方として知られるのが「タックマンモデル」です。組織の進化を表したモデルで、1965年に心理学者のブルース・W・タックマンによって提唱されました。チームは、人を集めるだけでは機能しません。チーム内で発生するさまざまな壁を乗り越えていくことで、理想のチームが作られると考えられています。もともとタックマンによるチーム形成のプロセスは四段階でしたが、1977年に目的を終えて解散する「散会期」が新たに加わり、五段階のモデルになりました。
タックマンモデル1.形成期(Forming)
「形成期」とは、チームが結成して間もない時期のことです。メンバーはお互いのことを理解しておらず、また、チームが目指すべき目標やメンバーの役割が定まっていないため、不安と緊張に包まれている状態といえます。この時期は、積極的にコミュニケーションを取り、メンバー同士の交流をはかることを優先するとよいでしょう。また、チームリーダーには、プロジェクトや組織の趣旨を説明し、メンバーに対して明確な指示を行うことが求められます。
タックマンモデル2.混乱期(Storming)
「混乱期」は、緊張がなくなったメンバーが仕事の進め方や役割に対して、意見を主張するようになる時期です。チーム内での考え方にズレが生じ、衝突が起こるようになります。また、チームの目標や目的ではなく、チーム内の階級や競争に目が向くことも増えてきます。ストレスを感じるメンバーも出てくるなど、人間関係に大きな影響を及ぼす可能性があります。
このタイミングのチームづくりで重要なのは、コミュニケーションの質です。回数を増やすだけではなく、お互いの考え方や不満に感じていることを表現し合い、対話を行う必要があります。
タックマンモデル3.統一期(Norming)
チーム内での衝突を乗り越え、目標を達成するためにチームが一致団結するようになる時期を「統一期」と言います。統一期では、メンバーがお互いの考え方の違いや多様性を受け入れるようになり、人間関係が安定します。自分たちの役割を再確認できるようになるのもこの時期です。混乱期のような対立関係は起こらず、チームをより良くしていくためのコミュニケーションが生まれます。
統一期では、お互いの仕事を助け合えるように仕事内容を開示したり、悩みがあれば皆で解決できるように議論したりするなど、より深いコミュニケーションが重要です。一方で、チームの関係が強くなるため、リーダーはチームが間違った方向に進まないようにすることが大切です。
タックマンモデル4.機能期(Performing)
チームが機能し、成果が出てくる時期が「機能期」です。チームへの信頼が高まっており、メンバーが自信・責任感を持つようになります。また、リーダーの細かい指示がなくても、自走できるようになっていきます。
リーダーには、メンバーが主体的に目標を定め、パフォーマンスを最大化できるための環境づくりが求められます。機能期の状態を維持するには、メンバー間のコミュニケーションが途絶えないように注意しなければなりません。また、メンバーがチームに貢献しようと努力しすぎる可能性もあるため、疲労が溜まらないよう、適度にリフレッシュをさせるとよいでしょう。
タックマンモデル5.散会期(Adjourning)
チームが解散する、終わりの時期を「散会期」と呼びます。各々のメンバーはスキルアップした状態で、新たな目標へ動き出していきます。散会期では、メンバーそれぞれが満足感や達成感を持っていることが理想です。
五段階プロセスでの注意点
チームビルディングの研修プログラムを開発・提供している、チームビルディングジャパン代表取締役の河村甚氏によると、日本企業の組織づくりには第2段階である「混乱期」を避けて、無理やり第3段階「統一期」に進もうとするパターンが目立つといいます。表面上は仲が良いけれど、お互いの考えを何となくしか理解できていないため、業務は進むが大きな成果は出せていない、という状態です。理想的なチームを形成するためには、お互いの考えや意見を深く知る機会が必要です。
5.チームビルディングの取り組み
チームビルディングの手法には、ワークショップやゲーム研修など、通常の業務から離れて行うものが多くあります。そのほかにも、通常業務の中でチームビルディングを意識した取り組みを行うことが可能です。
チーム内で共通のルールを設定する
チームビルディングにおいては、通常業務の中で一定のルールを設けることが重要です。例えば、「役立つ情報は積極的にアウトプットする」「ミーティング中に相手の性格や人格を否定しない」「疑問点は一人で抱えず、すぐに相談する」など。コミュニケーション活性化を意識し、誰でもすぐに取り組めるルールを設定することが有効です。
プロジェクト開始前は、キックオフミーティングを実施する
新しいプロジェクトを行うときに実施したいのが、「キックオフミーティング」です。キックオフミーティングとは、最初に関係者全員が集まり、プロジェクトの概要の共有や、メンバー同士の自己紹介などを行うミーティングのこと。このプロジェクトの目標は何か、参加メンバーがどのようなスキルを持っているのか、お互いにどのような役割で携わるのかを共有することで、チームが一丸となり、プロジェクトを推進していくことができます。
進捗・課題を共有したり、アイデアを出し合ったりする場を設ける
チームビルディングにおいては、業務上のどんなことでも、報告・相談できるような関係構築が求められます。ブレインストーミングや相談会を実施したり、リラックスして話すことができるようにランチミーティングを開催したりするともよいでしょう。
6.効果を出すチームビルディングのポイント・注意点
メンバー同士の多様な価値観を認め、相互理解を深める
メンバーそれぞれの価値観が大きく異なることもあります。チームの良い状態を維持するためには、ほかのメンバーの考え方や生き方を否定せずに、受け入れることが大切です。相互理解を深めることで、適切にサポートし合えるようになり、チームの団結力や結束力が高まります。
メンバーに押し付けない
チームとして目指すべき方向が明確になると、メンバーそれぞれがオーナーシップを持って自主的に業務に取り組めるようになります。その際、リーダーは強制的に目標を設定したり、業務を丸投げしたりしてはいけません。リーダーには、コミュニケーションの土台をつくったうえで、相談できる環境を整え、定期的な面談機会を設けることが求められます。
メンバーの役割を設定する
チームで成果を出すためには、メンバーそれぞれの役割や期待されている行動を、全員が理解していなければなりません。そのためにはまず、メンバーそれぞれが自身の役割について納得していることが大切です。各自の役割が明確であれば、自発的な行動が起こりやすくなります。
- 【関連記事】
- ダイバーシティ&インクルージョンとは|『日本の人事部』
7.チームビルディングの企業事例
株式会社ヤッホーブルーイング
業績悪化の影響でチームの士気はなくなり、メンバーのモチベーションが下がる一方だったヤッホーブルーイング。2004年から業績が回復し始めても、会社の雰囲気は悪い状態のままでした。そこで代表が自らチームビルディングを学び、社内改革に取り組むことを決意。従業員7名がチームビルディング研修の第1期生となりました。
繁忙期の中で研修を行ったため、他のメンバーからクレームが上がることもありましたが、代表がチームビルディングの重要性を訴え、取り組みを推進。メンバーはチームの力の偉大さを体感したことで、仕事に積極的に取り組むようになりました。第1期生がそれぞれの部署にチームビルディングの成果を持ち帰ったことで、他のメンバーも研修に興味を持つようになり、チームビルディングの効果が波及していきました。
8.チームビルディングに関するおすすめ書籍
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,400以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。
会員登録をすると、
最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 調査
調査 人事辞典
人事辞典 イベント
イベント