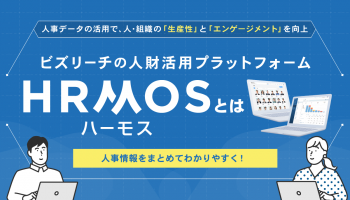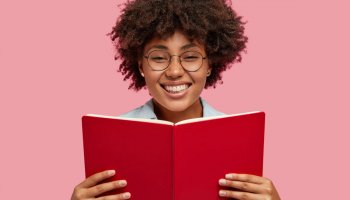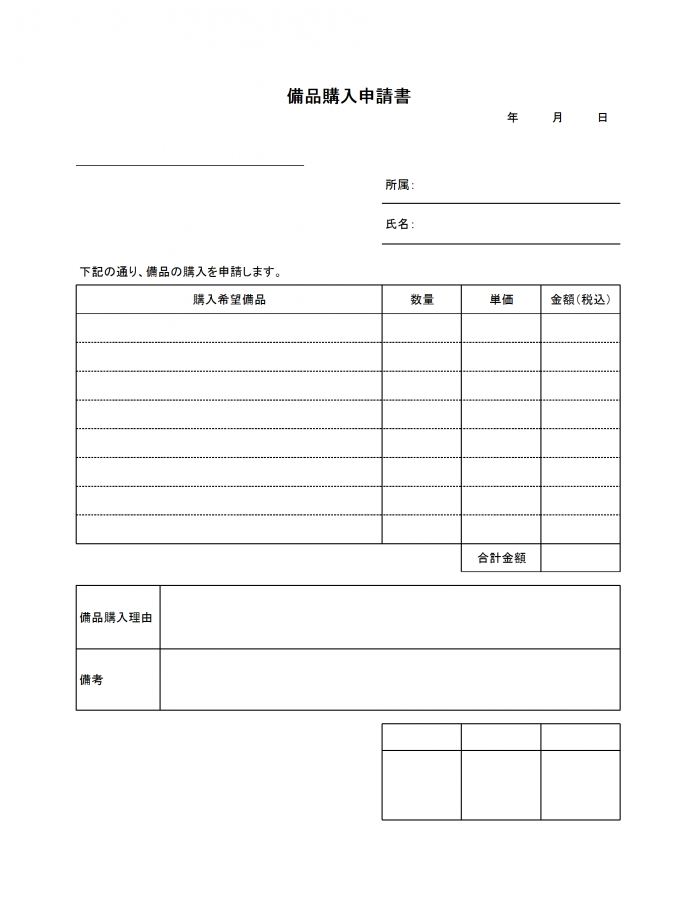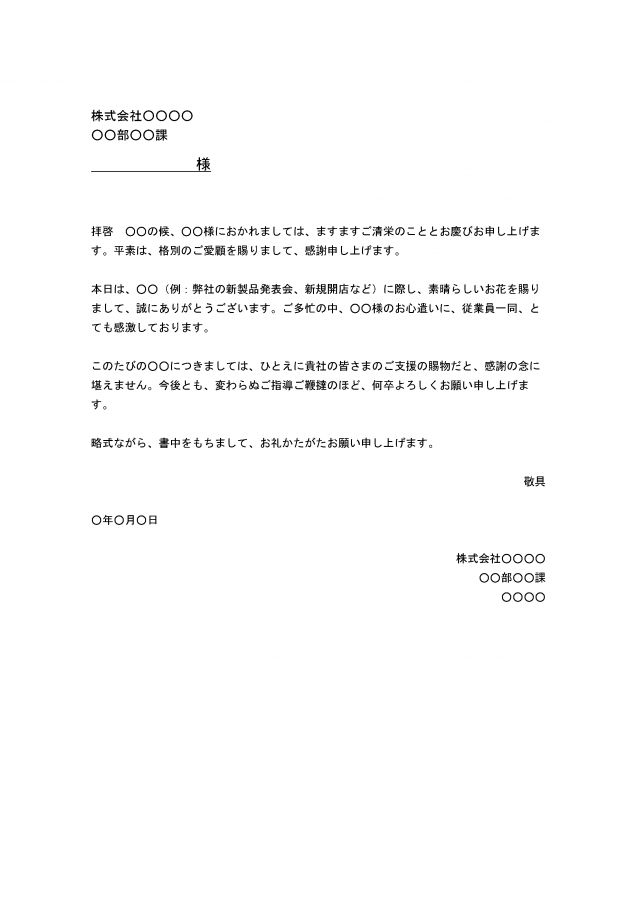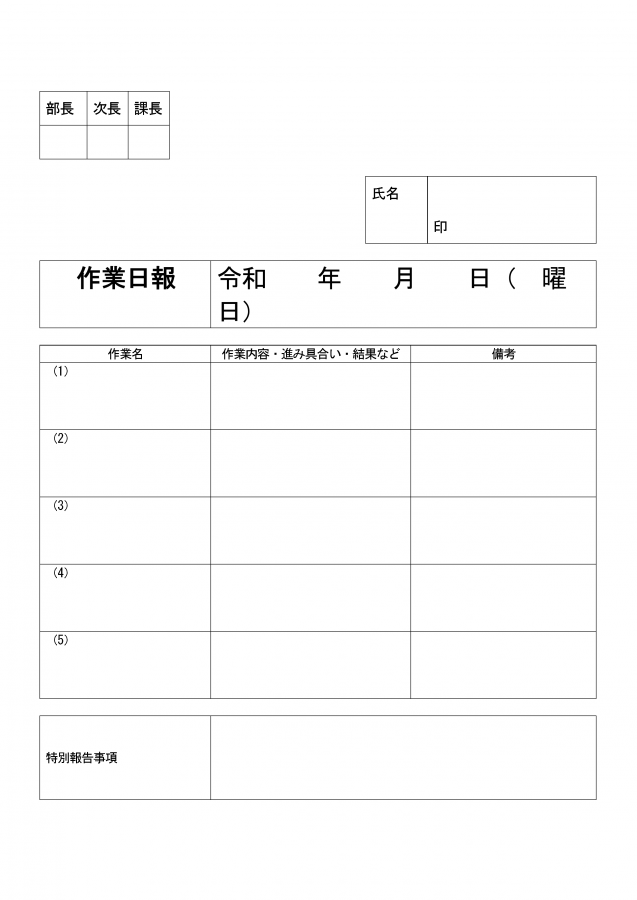人事データ
人事データとは?
従業員のあらゆる情報を体系的に収集・蓄積したものであり、人的資本経営の推進や戦略人事の実現において不可欠な要素です。単なる個人情報ではなく、採用から育成、配置、評価、離職に至るまで、従業員のライフサイクル全体にわたるデータを含みます。人事データを分析・活用することで、人員配置の最適化や従業員エンゲージメントの強化、人材育成・能力開発の推進を実現できます。テクノロジーを有効活用し、効率的かつ高度に人事データを収集、分析、活用することは、企業の持続的成長を実現する上で不可欠です。
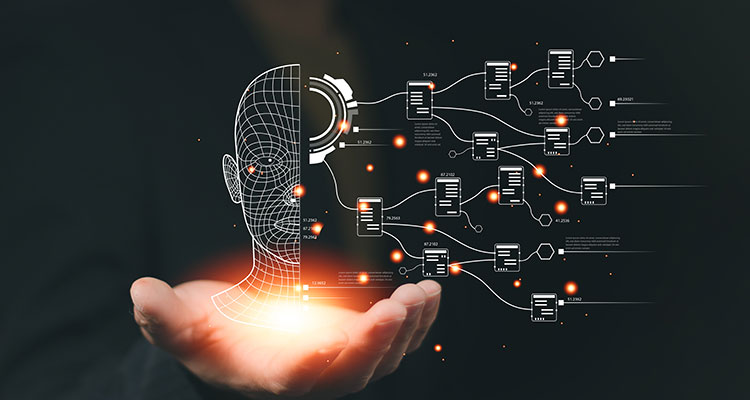
人事データとは
人事データとは、企業が収集・蓄積した従業員に関する情報の総称です。個人の属性情報(氏名、年齢、性別など)にとどまらず、入社日、所属部署の変遷、役職、給与、評価、研修履歴、勤怠情報、さらには従業員満足度調査の結果やキャリア志向性など、多岐にわたる情報を網羅します。単に個々の従業員を管理するためだけでなく、組織全体の人材状況を可視化し、適材適所な人材配置や、客観的な根拠に基づいた人事戦略を立案・実行するための重要な基盤となります。
なぜ注目されているのか
人事データの活用が近年注目されている背景には、いくつかの要因があります。
少子高齢化に伴う労働力人口の減少やグローバル化により、企業間の人材獲得競争が激化していることが挙げられます。優秀な人材の確保と定着は、企業の持続的な成長のために喫緊の課題であり、従業員一人ひとりのパフォーマンスを最大化し、エンゲージメントを高める戦略が求められます。
人的資本情報の開示:
ESG投資の重要性が高まる中で、企業が人的資本に関する情報を積極的に開示する動きが加速しています。日本では2023年3月期決算から、有価証券報告書における人的資本に関する情報開示が義務化されました。人事データは、人的資本の現状を客観的に示すための重要な根拠となります。
テクノロジーの進化:
特にビッグデータ分析やAIの発展が、人事データの活用可能性を飛躍的に高めています。膨大なデータの中から相関関係や傾向を抽出し、未来の予測や戦略的な意思決定に役立てることが可能になりました。
多様なキャリア観:
働き方の多様化や従業員の価値観の変化も、人事データ活用の重要性を後押ししています。従業員のニーズを正確に把握し、個々のキャリアプランやワークライフバランスに配慮した柔軟な人事制度を構築するためには、データに基づいた客観的な分析が不可欠です。
人事データの種類
人事データは多岐にわたりますが、大きく以下のカテゴリに分類できます。それぞれのデータが持つ意味合いと、人事戦略における重要性を理解することが、効果的なデータ活用への第一歩となります。
- 個人基本情報: 氏名、生年月日、性別、住所、連絡先など
- 入社情報: 入社年月日、採用経路、最終学歴、職務経歴など
- 配属情報: 所属部署、役職、等級、異動履歴など
- 出退勤時刻: 日々の労働時間、残業時間など
- 休暇取得状況: 有給休暇、特別休暇、育児介護休暇などの取得日数、残日数
- 遅刻・早退・欠勤回数: 勤怠状況の把握と問題の早期発見
- 基本給: 各従業員の基本給額
- 手当: 役職手当、通勤手当、住宅手当などの各種手当
- 賞与: 支給実績、評価との連動性
- 人事評価: 目標達成度、行動評価、コンピテンシー評価など
- 業績データ: 個人やチームの売り上げ、生産性などの数値
- スキル・資格: 保有スキル、取得資格、語学力など
- 研修受講履歴: 受講した研修プログラム、内容、受講時間
- eラーニング進捗(しんちょく): 学習状況、テスト結果
- 従業員満足度調査: 組織への満足度、職場環境、人間関係など
- エンゲージメントサーベイ: 組織への貢献意欲、愛着度
- パルスサーベイ: 短期間で見る従業員の心理状態の変化
- 離職理由: 自己都合、会社都合など、具体的な理由
- 離職率: 部署別、入社年次別などの離職率
情報管理にとどまらない活用法とは
人事データの活用は、単なる情報管理にとどまらず、企業の経営戦略と密接に連携し、さまざまな人事課題の解決と組織力強化に貢献します。
人事データ活用の目的
人材配置の最適化
個々の従業員のスキルや経験、キャリア志向、パフォーマンスデータを見える化し、分析することで、最適な人材配置を実現し、組織全体の生産性向上が期待できます。従業員の強みや弱みをデータに基づいて把握し、最適な部署やプロジェクトに配置することで、個人の能力を最大限に引き出すことが可能です。また、将来的な事業計画や組織戦略に基づき、必要な人員数やスキルセットを予測して、採用や育成の計画に反映することもできます。
従業員エンゲージメントの向上と離職率の低下
エンゲージメントサーベイや勤怠データなどを分析し、どのような要因が従業員のエンゲージメントを高めているのか、あるいは低下させているのかを特定し、具体的な施策につなげます。勤怠状況の変化、パフォーマンスの低下、サーベイ結果の推移などから、離職予兆を早期に把握し、個別のケアや対策を講じることもできます。
人材育成・能力開発の推進
組織全体や部署、個人が保有するスキルと、事業戦略上必要となるスキルのギャップを特定し、必要な研修や学習機会を提供。また、研修効果をデータで測定し、より費用対効果が高い研修プログラムの設計につなげます。
経営意思決定の支援
幹部候補人財の把握や後継者計画の策定、組織再編時の人員配置シミュレーションなど、経営層が迅速かつ的確な意思決定を行うための客観的な根拠を提供します。
採用活動の最適化
データに基づいた採用戦略は、採用プロセスの効率化と質の向上につながります。どの採用経路が最も優秀な人材を獲得できているか、費用対効果はどうかを分析し、最適なチャンネルにリソースを集中させると同時に、各選考ステップにおける通過率や辞退率を分析することで、ボトルネックを特定して改善策を講じることができます。
人件費の適正化
部署別、職種別、等級別などの給与・報酬データや勤怠データなどを分析し、人件費の現状を正確に把握。従業員のパフォーマンスを市場データと照らし合わせることで、公平で納得感のある報酬制度の設計が可能となります。
具体的な分析手法
人事データを効果的に活用するためには、適切な分析手法を用いることが重要です。ここでは代表的な分析手法を紹介します。
記述統計分析
収集した人事データの全体像を把握するための最も基本的な分析手法です。平均値や中央値、最頻値を使って給与、残業時間、勤続年数などの中心傾向を把握します。複数のデータ項目間の関係性(例:残業時間とストレス度、研修受講回数とパフォーマンス)を数値化し、関連性の強さを評価するには、相関分析が有効です。
傾向分析
時間の経過とともにデータがどのように変化しているかを追跡し、将来の予測や変化の要因を特定します。離職率、採用人数、エンゲージメントスコアなどの推移をグラフ化し、増減の傾向や季節性、突発的な変化などを把握する時系列分析などがあります。
セグメンテーション分析
従業員を特定の属性や行動パターンに基づいてグループ分けし、各グループの特性を比較分析します。年齢層別に分析すれば、各世代のニーズに合わせた施策を検討できます。パフォーマンスの高い従業員と低い従業員の属性、行動パターンなどを比較すれば、ハイパフォーマーの特徴や育成の成功要因の特定につながります。
予測分析
過去のデータパターンや傾向に基づいて、将来の事象を予測する手法です。過去の離職者のデータを分析して離職リスクの高い従業員を予測したり、事業計画と現状の人員構成から、将来的に不足するスキルや人材のタイプを予測したりします。
人事データ活用における課題と解決策
人事データの活用に伴う課題を認識し、適切な解決策を講じることが、成功への鍵となります。
課題1:データの散在と統合の困難さ
多くの企業では、勤怠管理、給与計算、人事評価など、異なるシステムで個別のデータが管理されており、データが散在している傾向があります。
- 人事情報システム(HRIS)の導入:採用から退職までの一連の人事プロセスを統合的に管理できるHRISを導入し、人事データを一元的に管理します。
- データ連係基盤の構築:異なるシステム間でのデータ連係を可能にするデータウェアハウスの構築により、データのシームレスな統合を実現します。
課題2:データ品質の問題(不正確性、欠損)
入力ミス、古い情報の放置、欠損データなど、データ品質の問題は分析結果の信頼性を大きく損ないます。
- データ入力ガイドラインの策定:全ての入力担当者が統一されたルールでデータを入力するためのガイドラインを策定し、周知徹底します。
- 定期的なデータ監査とクレンジング:定期的にデータの正確性をチェックし、不正確なデータや欠損データを修正・補完する作業(データクレンジング)を行います。
課題3:プライバシーとセキュリティーの問題
人事データは個人情報を含むため、漏えいや不正利用のリスクがあり、プライバシー保護とセキュリティー対策が極めて重要です。
- アクセス権限の管理: データを閲覧・操作できる従業員を限定し、職務に応じた適切なアクセス権限を設定します。
- データの匿名化・仮名化:分析目的で個人を特定する必要がない場合は、データを匿名化・仮名化して利用します。
- 情報セキュリティーポリシーの策定と周知:従業員に対して、個人情報保護に関する教育を徹底し、情報セキュリティー意識の向上を図ります。
人事データの活用事例
アフラック生命保険株式会社
アフラック生命保険は業界に先駆けて人的資本経営のためのデータ整備・活用に着手し、「経営層」と「現場」双方向でデータドリブンを浸透させました。
同社はデータ整備にあたり、まず人財に関する基本データを集約し、可視化できるダッシュボード(HCMダッシュボード)をつくりました。性別や年齢・勤続年数・入社退職実績などの基本データ、人員管理関係データ、そして時間外労働・有給休暇・出社率などの働き方関連データを一元的に集約し、適時適切に活用できる環境を整備していったのです。
HCMダッシュボードを使って、人財マネジメントがうまくいっているか、現場のマネジメントの課題は何かを把握。社長と統括役員で構成する「人財マネジメント政策委員会」では、「人員数・人件費」「異動・配置・ダイバーシティ」「採用」「退職」「評価」「人財育成プログラム」「人財エンゲージメント」「働き方」など、さまざまなデータのモニタリングに活用しています。
戦略人事の実践へ、定性データの活用が鍵
〈 プロフェッショナルに聞く 〉

- 西野 創志さん
- テックタッチ株式会社
執行役員 VP of Sales
デジタルアダプションプラットフォーム「テックタッチ」を開発・提供しているテックタッチ株式会社執行役員VP of Salesの西野創志さんは、多くの企業で人事データ収集は進んでいるものの、その活用段階でつまずくケースが散見されると指摘。経営戦略と連動した人事施策の実践に向けて、定性データの活用が鍵を握ると言います。
データは集めるだけでは意味がない──定性データ活用に立ちはだかる課題
人的資本経営や従業員エンゲージメントの重視が広がる中、企業は「数値に表れない人の情報」への理解をいっそう求められています。現在、多くの企業が人事データを収集している一方で、そのデータを経営戦略にひもづけて活用する段階で課題に直面しています。特に顕著な課題として3点が挙げられます。
まず、「データの質と統合の難しさ」があります。さまざまなシステムや部門から集められる人事データは、形式や定義がバラバラであることが多く、一貫性や正確性に欠けるため、統合・連携が容易ではありません。
特に、1on1の記録やコンピテンシー評価、エンゲージメント調査の自由記述といった定性データは、構造化されていないまま扱われがちで、分析可能な形に整えるのが難しい。さらに、そもそも必要なデータ項目が収集されていなかったり、粒度が異なっていたりという、データの「欠損」や「不足」も頻繁に見られます。こういった理由で、分析できる範囲や精度が限定され、十分な意思決定材料として活用しきれないのです。
2点目は「データ分析に関する知識・文化・ツールの不足」。人事部門の担当者が、どのようにデータを活用すれば良いかわからない、あるいはそもそも分析の必要性を実感できていないケースも多く見受けられます。
加えて、データに基づいた意思決定を行う組織文化が根付いていない企業では、仮に分析が行われたとしても、その結果が経営や現場のアクションに反映されないという“分析の空回り”が起きてしまうのです。また、データの可視化や分析を行うためのBIツール、HRアナリティクスツールが導入されていなかったり、導入されていても十分に活用されていなかったりと、ツールの整備と「使いこなす力」の両方が不足している現場も少なくありません。
最後に、「戦略との接続の難しさ」です。人事データ分析が、企業の経営戦略や事業目標と明確に結びついておらず、分析の目的が曖昧なままでは、得られた示唆を具体的な施策に変換することができません。多くの現場で、示唆を得ても行動に結びつかないという課題が見られます。
「人の声」から組織の本質をつかむために
勘と経験に基づく判断も多い人事領域において、人事データ、特に定性データを活用することで、より根拠に基づいた戦略的な意思決定が可能になります。従業員の声や行動の背景を“言語情報”として捉え、それを構造化・分析することで、数値では捉えきれない組織の実態に深く迫ることができるのです。
たとえば、1on1記録やアンケートの自由記述などから従業員のモチベーションや課題感を抽出すれば、エンゲージメントを高める効果的な施策が設計できます。また、コミュニケーションや心理的安全性に関する職場の暗黙知を読み解けば、目に見えづらい組織課題の兆しを可視化し、組織文化と風土の改善が進みます。マネジャーの言動やフィードバックの傾向を定性データから把握し、支援策を講じることで、マネジメント層の育成とパフォーマンスの向上にも寄与するでしょう。
このように、定性データを活用すれば、「人」にまつわる複雑で繊細な情報に対し、より深く、実践的にアプローチすることができ、結果として組織全体の活性化につながります。
「定性×定量」の融合が描く、人事の未来像
人事領域でも、AIを活用した高度かつ精度の高い分析が本格的に活用されつつあります。自然言語処理技術の進化により、定性データについても構造化や分類が可能になり、人の感情や行動の背景を、より深く理解する手がかりとなっています。たとえば、1on1議事録をAIで自動分類・要約し、感情分析を通じて「組織の沈黙」や「モチベーション低下の兆候」を察知するといった活用法も現実味を帯びてきました。
その結果、1on1の記録、エンゲージメントサーベイの自由記述、面談ログといった定性データと、勤怠、評価、離職率など定量データを統合的に分析することで、組織の実態を多面的に把握するアプローチが主流になると予測されます。この多角的な洞察に基づき、従業員の状態に即した施策をスピーディーに設計・実行することで、人事部門は「戦略的に組織をつくる部門」としての役割をより強く発揮することができるのです。
人事データ、特に定性データの活用は、単なる業務の効率化にとどまらず、組織文化や人材戦略の進化、透明性の高い意思決定やマネジメントスタイルの定着にもつながります。
- 参考になった1
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,400以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。
会員登録をすると、
最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!
- 1
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 調査
調査 人事辞典
人事辞典 イベント
イベント