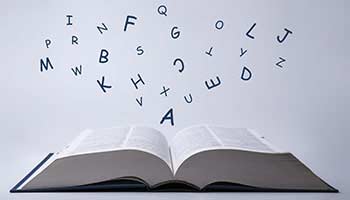アウトソーシング
アウトソーシングとは?
アウトソーシングとは、自社内の業務を外部に委託する行為をいいます。自社の業務の一部または業務プロセスをアウトソースすることで、コストの最適化や業務の効率化が期待できます。HR領域においては、採用や給与計算、福利厚生などのさまざまな分野でアウトソーシングの需要があります。
「アウトソーシング」に関する人事用語を絞り込む
1. アウトソーシングとは
アウトソーシングとは、「ある組織から他の組織に対し、組織の機能やサービスの全てまたは一部を委託すること」をいいます。自社ではない外部(アウト)から、業務リソースを調達(ソーシング)することで、業務の効率化や成果の拡大を狙う経営手法です。
アウトソーシングの手法を広めたのは、1988年にイーストマン・コダック社が米国IBM社と契約し、情報処理部門をアウトソースした事例といわれています。アウトソーシングは、事務系の業務からシステム開発まで、さまざまな分野で社内の経営資源の省力化と効率化を目的に取り入れられてきました。
現代でも、アウトソーシングをコスト削減の手段として取り入れることは珍しくありません。また、急速な技術革新など、ビジネス環境変化に対応するために、専門性の高いノウハウやスキルを外部から調達できる戦略的アウトソーシングも拡大しています。
アウトソーシングの類語
人材派遣
外部のリソース(人材)を活用するという点で、人材派遣とアウトソーシングは共通しています。しかし、アウトソーシングは「成果・業務を提供するサービス」であり、派遣は「人材を提供するサービス」という点に大きな違いがあります。
人材派遣では、企業が派遣元会社と労働者派遣契約を結び、派遣社員を受け入れます。自社の社員の指示のもと派遣社員が業務を行うため、人員補充や社内で完結する必要がある業務に適しています。
なお、書類上は業務委託契約や請負契約を結んでいるにもかかわらず、成果・業務の提供ではなく、委託や請負で働く者に直接指揮命令の下で働かせるような実態が労働者派遣であるものを「偽装請負」といい、違法となります。
業務委託
業務委託は、自社の業務を外部に任せるという点でアウトソーシングと共通しています。アウトソーシングとの大きな違いは、業務に関する意思決定者です。業務委託の場合、あくまでも外部の事業者やフリーランスなどに業務の遂行のみを委託し、業務の意思決定者は業務を依頼した自社にあります。一方で、アウトソーシングでは業務の遂行だけではなく、上流にある業務フローの決定にもアウトソース先の企業・事業主が関わります。
外注
外注とアウトソーシングの違いは、業務を外部に委託する際の目的にあります。外注とは、一般的にコスト削減を目的として行われることが多く、頼んだ業務をただ行ってもらうものです。一方、アウトソーシングの場合はコスト削減に留まらず、外部ソースの活用により成果の向上や企業価値の維持・向上を目指します。
BPO
BPO(ビジネスプロセスアウトソーシング)とは、アウトソーシングの種類の一つです。一般的なアウトソーシングよりも外部に委託する業務範囲が広いという特徴があります。企業の業務を外部業者に一括で任せるような方法であり、コールセンターサービスを外部に委託して「お客様相談窓口」を設置する事例は、BPOの代表例といえます。BPOは、業務で使用するITシステムの広がりとともに拡大し、人事や経理・総務といった間接部門のほか、営業支援にも広がっています。
2. アウトソーシングのメリット・デメリット
アウトソーシングの四つのメリット
アウトソーシングは、一部の業務を外部に出すことで、社内のリソースを効率的に活用でき、生産性向上が見込めます。
社員がコア業務に集中できる
アウトソーシングは、自社のリソースをコア業務に集中できるよう、ノンコア業務を外部に任せる考え方が一般的です。コア業務とは、利益を生むための直接的な業務を指し、ノンコア業務はコア業務を支援する業務を指します。
採用でいえば、応募者への合否連絡や面接日程の調整といった仕事は、ノンコア業務です。これらの採用関連業務をアウトソースすることで、人事は「面接での人材の見極め」「自社に必要な人材要件定義」「採用ブランディング」といったコア業務に集中できます。アウトソーシングを活用することで、競争力の強化や事業に必要な成果を向上させられるのです。
人件費の最適化につながる
アウトソーシングは、業務量に合わせて人件費を調整できる点も大きなメリットです。業務量が時期によって異なる場合、アウトソーシングを活用することで人件費を固定化せずに業務を遂行できます。また、情報通信部門やマーケティングなど、自社のリソースが乏しい領域をアウトソーシングすれば、ノウハウや専門性を有する人材を一人採用するよりも、コストを低く抑えられます。
人材の採用・引継ぎが不要となり業務が安定する
業務分担が特定の社員に集中すると、離職時に業務のクオリティが低下するリスクが高まります。アウトソーシングを行えば、人材の採用・教育の負担を軽減できるとともに業務の進行が安定します。
プロフェッショナルのスキル・ノウハウを活用できる
アウトソーシングの事業者は、特定の領域に特化して多くの業務を手掛けているため、豊富な知見を有しています。業務の質を高めることが可能になり、処理速度も上がります。自社で優秀な人材を一人採用する以上のスキルやノウハウを戦略的に活用できることも、アウトソーシングの魅力といえます。
アウトソーシングで考慮するべきデメリット
人件費の最適化や業務の効率化につながるアウトソーシングですが、社内人材の成長機会や情報漏えいといった点でデメリットがあります。
業務をコントロールできなくなる
アウトソーシングの受託先に依存しすぎるあまり、業務のコントロールを失ってしまうのは避けるべき事態です。また、受託先が高い専門性を有していたとしても、自社の経営戦略に基づいて業務を遂行してくれるとは限りません。
アウトソーシングに依存したことで業務内容を把握できず、品質管理のコントロールができなくなることがあります。特に主要事業との関連度の高い業務をアウトソースする場合は、アウトソーシング先の選定と、業務内容の可視化、関係性の構築に時間をかけることが重要です。
情報漏えいのリスク
業務をアウトソースする場合、情報漏えいのリスクが考えられます。アウトソーシング先のスタッフへのコンプライアンス研修の実施状況や、セキュリティ対策を確認することが重要です。
社内での人材育成の機会損失
業務の多くをアウトソーシングしていると、社員の成長機会が失われる可能性があります。ノンコア業務の経験をコア業務に活用できることは珍しくありません。業務に精通した人材は、将来的に全社視点で業務の課題を把握できるマネジメント層に成長する可能性があります。
3. HR領域におけるアウトソーシング
アウトソーシングは、1980年以降の情報通信技術の発展に伴い、製造やソフトウェア開発、データ入力やコールセンターなど、さまざまな領域で広がってきました。国内では1990年に地方自治体のノンコア業務を民間企業へ委託する動きが加速したこと、またICTの発展により沖縄など地方に設置されるコールセンターが増加しました。
人事・経理・総務のバックオフィス部門では、社員情報など機密情報を扱うため、情報漏えいのリスクからアウトソーシングは限定的でしたが、業務システムのクラウド化・セキュリティの強化により、業務単体のアウトソーシングやプロセス全体のBPOなど、アウトソーシングの業務・範囲ともに多様化しています。
HR領域でのアウトソーシングの活用
採用
採用領域におけるアウトソーシングは、RPO(リクルーティングプロセスオペレーション)と言われ、サービス形態が確立しています。1990年代以前からニーズがあり、当時は応募者のハガキ整理といった業務がアウトソースされていました。
1990年以降は採用領域における大手であるリクルートが新卒採用求人媒体の「リクナビ」を発表したことで、大手を中心に採用業務のIT化が急速に進行しました。アウトソーシングの需要は大手企業を中心に広がり、選考者データを効果的に管理するため、採用管理システムを用いた進捗管理とフォローの採用代行業務へと発展します。
1990年代から2000年代にかけては、人材定義や採用広報に注力する採用コンサルティング型など、さまざまなアウトソーサーが登場し、さらに業務システムのクラウド化によって、外注会社内でのリモート業務が可能となりました。
その結果、2020年代では採用業務アウトソーシングの細分化が進み、採用業務プロセス全体のアウトソーシングだけではなく、「求人媒体の投稿のみ」「応募者の面接業務のみ」と単体業務でのアウトソーシングが広がりを見せています。中小企業やスタートアップといった採用人数の少ない企業でも、アウトソーシングを選択する機会が増えています。
- 【参考】
- 採用とアウトソーシング(小宮健実、2007)|日本労働研究雑誌 No.567
- インタビュー レジェンダ・コーポレーション株式会社 採用支援事業部・牧野和治マネージャーに聞く 顧客の課題解決を目標に最新スキームを開発 経験と事例に支えられた採用のプロフェッショナル|新卒採用.jp
労務
社会保険・労働保険手続きを中心とした労務業務は、社会保険労務士がアウトソーシング先となっています。社会保険に関する申請書の作成や帳簿書類は社会保険労務士による独占業務です。とくに、社員の入退社にともなう健康保険や厚生年金保険の管理、出産育児一時金や傷病手当金など各種保険申請など、専門知識が求められる領域は、アウトソーシングの必要性が高い業務といえます。
福利厚生
自社の福利厚生制度を整える際、アウトソーシング企業を活用することで、コストを抑えつつ福利厚生内容の充実化を図れます。近年では、福利厚生のあり方が企業イメージに与える影響を重視し、戦略的に福利厚生を運営しようとする企業からのニーズも増えています。
福利厚生専門のアウトソーシング会社は、多くの会員企業を抱えることで広範囲のサービス内容を提供しています。健康経営やキャリア支援、託児所の提供など、自社が力を入れたい領域を選択できるのが特徴です。また、カフェテリアプランを取り入れれば、社員が一定の範囲内で自身に合った福利厚生制度を活用できます。
給与計算
給与計算業務では、毎月の給与の計算・支払いのほか、年末調整業務や住民税更新代行がアウトソーシングの対象です。給与計算業務では労務や税金に関する知識が求められるため、専門的な資格を有する会社にアウトソーシングすることが大切です。所得税など税金に関する手続きは税理士の資格が必要となるため、源泉徴収票の作成や年末調整など、どこまで任せることができるのかをよく確認する必要があります。
給与計算業務は毎月必要な業務である上に手間がかかるため、アウトソーシングすることで、人件費の抑制だけではなく、業務の安定化を図れます。頻繁に発生する法改正に正確に対応できるのも、アウトソーシングのメリットといえます。
安全衛生
安全衛生の領域では、従業員のメンタルヘルス対策である「EAP(Employee Assistance Program(従業員支援プログラム)」を利用する施策が定着しています。EAPは、厚生労働省の「労働者の心の健康の保持増進のための指針」において、「事業場外資源によるケア」として従業員のメンタルヘルスに重要な取り組みとして位置づけられています。また近年では、ハラスメント防止への事業主の責任も強化されており、人事部門での注目度も高い分野です。
アウトソーサーが提供するEAPの内容には、社員への個別カウンセリングや専門医療機関の紹介、定期的なストレスチェックの実施のほか、社員向けのメンタルヘルス関連研修があります。
4. アウトソーシング導入の注意点
アウトソーシングを導入する際は、委託する業務の判断のほか、委託のプロセスや契約形態についても注意が必要です。
アウトソーシングすべき業務の判断
アウトソーシングを行う際は、コスト削減以外の観点を持つことも重要です。ノンコア業務が増加しているケースでも、業務量によってはマルチタスクを得意とする社内の人材がカバーできる場合があります。とくに創業間もない企業や小規模の事業場では、一人の社員が複数の業務をカバーすることが珍しくありません。そうした場合、アウトソーシングをするよりも給与計算ソフトや労務管理ソフトを使用した方が、総合的なコストが安く抑えられる可能性があります。
社員の能力や人材育成の機会とあわせて、アウトソーシングの判断基準の一つとなるのが、ノンコア業務がコア業務を圧迫しているかどうかです。たとえば、人事担当者が社員の入退社手続きで残業をしており、新入社員向け研修の企画が十分に練れていないという課題があれば、労務管理をアウトソーシングする必要性があります。
単純な人件費削減ではなく、総合的に費用対効果を検討し、業務を効率化できるか、生産性を高められるかどうかを判断することが大切です。
偽装請負を疑われないような内容にする
契約が業務委託などで、アウトソーシングであるにもかかわらず、実態はアウトソーシング元の企業から作業する者への細かい指示があると、偽装請負となって違法行為に該当する可能性があります。アウトソーシングを行う場合は、委託・請負先の労働者に対して、自社から業務指示を行うような指揮命令系統になっていないかについても注意を払うことが必要です。
契約書が業務委託・請負のようなアウトソーシングだからといって安心はできません。偽装請負かどうかの判断は、契約ではなく運用面でなされます。そのため、実際の仕事の指揮を誰がしているかが焦点となります。
機密情報・個人情報の取り扱い
アウトソーシング先での機密情報や個人情報の取り扱いについて、プライバシーマークの取得をアウトソーサーの選定条件とするほか、定期的なセキュリティチェックをすることが重要です。機密情報の不正利用が起こらないよう、データの利用範囲や権限について、契約締結時に確認します。
許認可に注意
社会保険労務士など、独占業務となっている各種手続きや申請をアウトソーシングする場合、アウトソーサーの資格を確認しなければなりません。税務関係の処理をアウトソーシングする場合は税理士または税理士法人へ委託する必要があり、社会保険の手続き業務をアウトソーシングする場合は社会保険労務士または社会保険労務士法人へ委託する必要があります。
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,400以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。
会員登録をすると、
最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 調査
調査 人事辞典
人事辞典 イベント
イベント