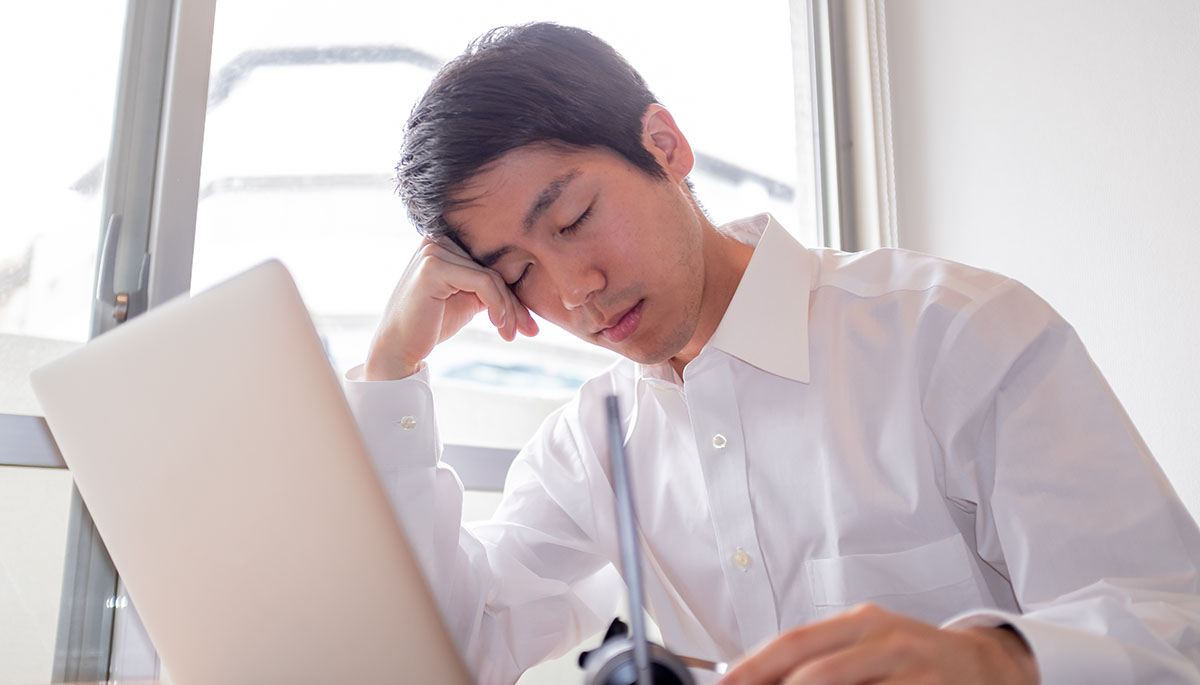テナントを設置している会社としての休憩室等の設置義務について
弊社は複数のテナント(個々のテナントごとでは、常時30人以上の規模のテナントはありませんが、合計すれば、優に30人を超えます)を管理する会社です。
1 休養室については、従業員の人数により、労働安全衛生法に設置義務が定められているようですが、休憩室(臥床するスペースはなく、飲食をしたり、喫煙したりなど、職場を離れて休憩時間を過ごすスペースです)については、法定の設置義務のようなものが課されているのでしょうか。
2 そもそも休憩室という概念は、労働安全衛生法規に定められているものではないように思料するのですがいかがでしょうか。なお、弊社は、2か所ある休憩室1か所について、簡易ベッド的な横になれるようなスペースを1床分だけ設けております。
3 このたび、2か所ある休憩室を、交代でリニューアル工事することになり、その間、現状でも狭隘なスペースがさらに狭くなり、テナントの場所によっては、距離が離れ、使い勝手が悪くなります。
前述のような状況にある弊社として、各テナントをまとめて一つの事業所と考えるのが法令の考え方となる場合には、法的に、テナントの従業員が誰でも利用できる休養室乃至休憩室の設置義務があることになり、一時的であっても代替の施設を設ける必要があることになるのでしょうか。もしあるとした場合、面積や利用時間(店舗開業時間については常に休養室乃至休憩室が従業員の誰もが利用できるようにしておくことなど)等について規定があるのでしょうか。
一方、各テナントがそれぞれ一つの事業所というのが法の考え方ということであれば、弊社に休養室乃至休憩室の法的な設置義務はないことになりますが、そうであっても、テナントの従業員様の労働安全衛生の観点から、現在の休憩室は重要な施設であると考えていつつ、工事期間中(1か所4か月程度)は、さらに狭隘になることについてやむを得ず受忍していただくことも含め検討しておりますが、もし判断にあたり留意点等ありましたら、ご教示いただけると幸いです(現状、休養室的な施設は、簡易ベッド1床分しかないことから、弊社としては、これまで、テナントの合計を持って一つの事業所という考え方には立ってこなかったということになります)。
よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2025/04/10 16:51 ID:QA-0150792
- akkunさん
- 東京都/不動産(企業規模 11~30人)
この相談を見た人はこちらも見ています
-
休憩時間について いつも利用させていただいております。さて、労基法では8時間超えの労働時間で1時間の休憩を与える義務があります。その後残業時間が長くなった場合に休憩時間を与... [2007/10/29]
-
休憩時間について 休憩時間について質問です。VDT作業を連続して60分以上行わせる場合は、10分~15分の休憩が必要とありますが(そもそもこれは努力義務ですか?それとも法で... [2008/10/23]
-
休憩時間は一時間だけで良い? まずはじめに弊社の勤務時間や休憩時間は以下のようになっております。勤務時間:8:30~17:00休憩時間:90分ここで月に3~4回ほど夜勤があります。その... [2020/06/29]
-
労基法の休憩時間について 労基法の休憩時間について教えてください。労働時間を6時間超えた場合に少なくとも45分の休憩とあります。以下のような場合、休憩時間とみなされますか?就業開始... [2019/12/16]
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
項目 法的義務の有無 補足
1.休憩室(飲食・喫煙等)× 法定の設置義務なし法律上の「定義」は特にありません(努力義務扱い)
2.休養室(横になれるスペース) 一定の条件下で設置義務あり常時使用する労働者が50人以上の事業場で必要
3.テナントの合算による「事業場」扱い 条件次第で「一体の事業場」と見なされる可能性あり実態次第
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
複数のテナント(常時30人未満)を管理する施設における休憩室・休養室の法的義務や、事業場の単位に関するご懸念、非常に丁寧に整理されていて素晴らしいと思います。以下に、法律の建て付けと実務対応の視点から、順を追ってご説明申し上げます。
【要点まとめ】
項目 法的義務の有無 補足
1.休憩室(飲食・喫煙等)× 法定の設置義務なし法律上の「定義」は特にありません(努力義務扱い)
2.休養室(横になれるスペース) 一定の条件下で設置義務あり常時使用する労働者が50人以上の事業場で必要
3.テナントの合算による「事業場」扱い 条件次第で「一体の事業場」と見なされる可能性あり実態次第
・休憩室と休養室の違いと法的位置づけ
【休憩室】
法的定義はありません(労働安全衛生法上の設置義務なし)
一般的には「従業員が休憩時間中に飲食・喫煙・会話などに使用する空間」
労基法上は「休憩時間を自由に過ごさせる義務」があるのみ(休憩場所の提供義務は明記されていない)
→ よって、休憩室(座って過ごす空間)について、法的な設置義務や面積・時間などの規定はありません。
【休養室】
労働安全衛生規則 第618条により、「常時50人以上の労働者がいる事業場」には休養室または休養の設備の設置義務があります。
「臥床(横になる)できるスペース」を意味します。
・「事業場」の考え方とテナントの合算可否
ポイント:法律上の「事業場」の定義は実態で判断されます。
労働安全衛生法における「事業場」とは、一つの場所にあって経済的・人的・組織的に独立性を持ち、かつ雇用管理が一体的に行われているものが該当。
本ケースでは、各テナントが独自に従業員を雇用し、就業管理・労務管理を行っている
貴社(施設管理会社)はそれぞれのテナントの労働者を直接管理していない
これまで休養室を1床のみ、共用扱いとしている
→このような実態であれば、「各テナントごとが独立した事業場」と見なされる可能性が高く、貴社がテナント合算で「1事業場」とされるリスクは低いと考えられます。
・工事期間中の「休憩スペース縮小」への対応とリスク
法的には、「休憩室」自体に設置義務はないため、縮小や一時的な不便があっても違法とはなりません。実務・配慮の観点では、従業員(テナント含む)の「安全・衛生・快適な職場環境」に配慮することは、労働安全衛生法の基本理念(第3条)に沿う重要な事項です。特に飲食や喫煙のスペースが限られると、共用スペースでのトラブルや衛生問題に発展する可能性もあるため、テナント各社に丁寧な説明を行う。
・工事期間中の代替案(仮設スペースの設置・近隣休憩スペースの利用案内など)を提示
必要に応じて簡易なパーティション等で区分けしてプライバシーを確保などの配慮が望ましいと思います。
まとめ
質問 回答
1.休憩室に法定の設置義務はある?× ありません(定義もなし)
2.休養室については? 常時50人以上の事業場に法定設置義務あり
3.テナント合算で事業場と見なされるか?× 実態上はそれぞれ別事業場と考えられる(現状維持でOK)
4.工事期間中の代替設置義務は?× 法的義務はないが、安全衛生配慮のため「努力義務として対応推奨」
補足:判断・対応のチェックポイント
項目 内容
現在の運用各テナントは独立管理、休養室は1床、休憩室は共用
リスク現状では貴社が設置義務を負う状況とは考えにくいと思います。
おすすめの対応といたしましては、テナント向け案内+仮設的措置+事後アンケート等によるフォローが考えられます。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/04/10 20:21 ID:QA-0150807
相談者より
大変詳細にかつ丁寧なご回答を頂戴し、本当にありがとうございます。
業務運営の参考にさせていただきます。
これからもよろしくお願い申し上げます。
投稿日:2025/04/11 09:44 ID:QA-0150846大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
おこたえ
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、休憩室の設置に関しましては努力義務にとどまっていますので、必ず設置しなければいけないというわけではございません。
2につきましては、労働安全衛生規則第613条で「事業者は、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければならない。」と定められています。
3につきましては、労働暗線衛生法の適用単位となる事業者は労働基準法と同じ概念になりますので、テナントを纏めて一つの適用単位として対応する義務まではございません。但し、法的義務は無くともご認識の通り現場事情に即した休憩場所の確保等を検討されるのが望ましいといえるでしょう。
投稿日:2025/04/10 22:45 ID:QA-0150818
相談者より
短時間にご丁寧な回答を賜り、誠にありがとうございました。
業務運営の参考にさせていただきます。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
投稿日:2025/04/11 09:46 ID:QA-0150847大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
休憩時間について いつも利用させていただいております。さて、労基法では8時間超えの労働時間で1時間の休憩を与える義務があります。その後残業時間が長くなった場合に休憩時間を与... [2007/10/29]
-
休憩時間について 休憩時間について質問です。VDT作業を連続して60分以上行わせる場合は、10分~15分の休憩が必要とありますが(そもそもこれは努力義務ですか?それとも法で... [2008/10/23]
-
休憩時間は一時間だけで良い? まずはじめに弊社の勤務時間や休憩時間は以下のようになっております。勤務時間:8:30~17:00休憩時間:90分ここで月に3~4回ほど夜勤があります。その... [2020/06/29]
-
労基法の休憩時間について 労基法の休憩時間について教えてください。労働時間を6時間超えた場合に少なくとも45分の休憩とあります。以下のような場合、休憩時間とみなされますか?就業開始... [2019/12/16]
-
休憩時間について さて、休憩時間に関する質問です。現在、勤務時間と休憩時間の変更を検討しており、以下のとおり考えています。 現在 8:30~17:00 7時間半 ... [2006/11/14]
-
休憩時間について 労働時間が6時間超は45分間以上の休憩、8時間超は60分以上の休憩を与えなくてはならないのは承知しているのですが、例えば、9時から12時迄、13時から18... [2005/06/23]
-
昼休憩について 当社の昼休憩は12時-13時の1時間です。13時からの他事業部での打ち合わせのため、所定休憩時間以前に休憩に行く部下に注意が出来るかという質問が上司の方か... [2010/10/22]
-
休憩時間が取れない場合 休日に12時~19時まで作業をしている場合、弊社の休憩時間は1時間与えています。しかし、ある従業員は休日出勤手当を7時間で申請しています。会社としては、6... [2013/03/06]
-
裁量労働制と休憩時間 さて、裁量労働制を導入した場合、「みなし労働時間」が8時間を超える場合、1時間の休憩を与えなければならないとされています。この場合、実労働時間が短時間の日... [2017/02/02]
-
定時前後の休憩時間について 弊社は就業時間が固定で9:00~18:00(昼休憩12-13)で、その前後に30分間の休憩が設定されています。業務の都合上、残業する社員も多いのですが、前... [2023/11/10]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント