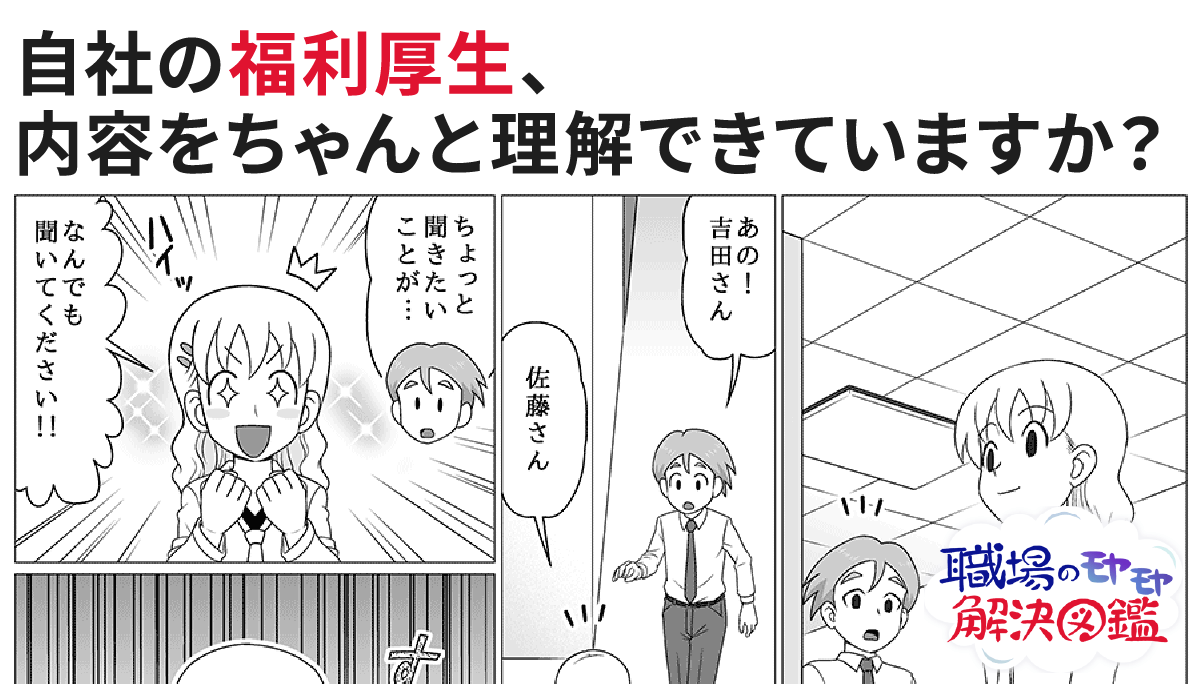療養専念義務の法的根拠について
社内規則において、「会社から休職を命じられた社員は療養に専念しなければならない」と記載があります。しかし実際にはメンタル疾患で数ヶ月単位で診断書が出されているにも関わらず、会社の福利厚生サービスを使い旅行に行っているらしい事例(本人は知らないのですが、福利厚生と労務担当が同じ部門なので宿泊割引券の利用歴などデータで分かる)、休職中であるのに正式な相談ではないといいつつ、職場の人間関係の不満を頻回に上席に連絡してくる、等周囲から見て療養に専念できているとは考えにくい、という職場からの不満を聞く事があります。
私的行為を止めるよう、休職中の社員に一概には言えないとは理解できるのですが、上席からは安衛法にある自己保健義務違反、あるいは会社に対する信用失墜行為に当たると言えないのか?と指摘を受けています。
療養専念義務はそもそも会社が社員への安全配慮義務を担保する措置の一つだと思いますが、自己保健義務や信用失墜行為と対になるものと考えて差し支えないでしょうか。また参照出来る法律条文があればご教示いただきたいです。
投稿日:2025/06/18 23:48 ID:QA-0154153
- 並木35さん
- 大阪府/公共団体・政府機関(企業規模 3001~5000人)
この相談を見た人はこちらも見ています
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論(概要)
「療養専念義務」は、あくまで会社の安全配慮義務(労働契約法第5条)に基づく措置であり、社員にも協力義務的な性質があるものです。
しかし、休職中であっても旅行などの私的行動が直ちに違法とは言えません。ただし、その行動があまりに逸脱している場合には、信義則違反や信用失墜行為に該当する可能性はあります。
一方で「自己保健義務」という言葉自体は法律用語ではありませんが、**労働契約に内在する信義誠実義務(民法第1条第2項、労働契約法第3条第4項)**として読み替えられることがあります。
参照法令は直接的には存在しませんが、関連する規範として以下を挙げられます。
2.関係する法律条文・法的根拠
規範→内容→コメント
労働契約法第5条→使用者は、労働者の生命・身体等の安全を確保しつつ労働させるよう配慮しなければならない(安全配慮義務)→休職命令はこの条文に基づく措置
労働契約法第3条第4項→労働者及び使用者は、信義誠実に従って労働契約を締結し、及び履行しなければならない→療養専念義務・職場規律維持の根拠
民法第1条第2項→権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない(信義則)→「社会通念に反する行動」はこれに抵触しうる
就業規則上の服務規律→信用失墜行為の禁止、職務専念義務、療養専念義務等→明文化されていることが大前提
3.「療養専念義務」と「信用失墜行為」の関係
(1)療養専念義務とは?
休職命令を受けた者が、一日も早く職場復帰できるよう健康回復に努めることを会社が期待する義務。
多くの就業規則では、「会社の指示で休職した者は療養に専念すること」と明記されています。
ただし、この義務は強制力のある法的義務ではなく、労働契約に内在する協力義務・信義則の一環と理解されています。
(2)旅行や不満の頻回な表明は義務違反か?
メンタル疾患による療養は「人と接する」「環境を変える」「気晴らしをする」ことも治療の一環となる場合があります。
したがって、「旅行に行った」というだけで療養専念義務違反とは一概には言えません。
ただし、
頻繁に職場へ連絡して不満を述べる(特に診断書で「業務不可」とされている中で)、
長期旅行を繰り返すなど、
回復の意思が見えず、社会常識から逸脱した行動が見られる
などの場合は、信義則に反する行動(=職場秩序や会社の信用を害する)と評価される可能性があります。
4.「自己保健義務」とは?
労働者が自らの心身の健康を保つ努力義務(特に精神的疾患において)が問われる場面で使われる実務用語です。
労働契約法や民法上の「信義則」に根拠があるとされています。
一般的に自己保健義務は、
自らの疾病や疲労を放置しない
就業困難な状態で出勤しない
上司・産業医の指導に協力する
といった文脈で語られます。
※従って、「療養専念義務」や「自己保健義務」が会社に対する義務違反=懲戒対象になり得るのは、重大かつ継続的な違反がある場合に限られます。
5.会社としての実務対応(ご提案)
記録化を徹底する
→ 本人の行動について、事実に基づく記録(福利厚生利用歴やメール等)を保存しておく。本人にまだ指導しない段階でも重要です。
状況ヒアリングの実施(診断書の更新依頼含む)
→ 状況を確認し、現在の治療状況・復帰見込みを本人・主治医に確認。必要に応じて産業医面談を提案。
職場との連絡方法の制限
→ 「療養に専念するため、会社との連絡は窓口(例:人事のみ)に限る」等、頻回連絡を制限する措置は可能です。
信義則違反または就業規則違反としての注意文書発出
→ 社内規程に基づき「信用失墜行為」または「療養専念義務違反」の可能性がある旨を指摘することも可能(ただし慎重に文面作成が必要)。
休職延長・復職不可の判断時期を明確化
→ もし現状から復職の見込みが見えない場合、休職期間満了→退職も見据えた対応が必要です。
6.まとめ
観点→内容
法的根拠→明文はなし。信義誠実義務、就業規則等が根拠
療養専念義務違反→私的旅行等は一概に違反とは言えない。ただし逸脱行為は信義則違反や信用失墜行為に該当し得る
自己保健義務→実務用語だが、民法・労契法上の信義誠実義務と解釈されることあり
実務対応→ヒアリング・産業医対応・連絡制限・注意喚起文書・復職可否の整理
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/06/19 09:26 ID:QA-0154166
相談者より
法律に明文化されていないなかで、どの条文に基づいて発生した概念かも示唆くださり大変参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2025/06/19 12:35 ID:QA-0154198大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
療養専念義務について定める法律はありません。また、裁判例においても療養専念義務を正面から認めるものはありません。しかしながら、私傷病によって休職(解雇猶予)するのだから、復職に向けて療養に専念すべきであることに異論はないと考えます。
他方、メンタル疾患の場合、「病気の性質上、健常人と同様の日常生活を送ることは不可能ではないばかりか、これが療養に資することもある」(マガジンハウス事件:東京地判平成20年3月10日)と考えられていますので、旅行に行ったり職場の人間関係を相談したりすることが療養に矛盾する行為とは直ちにはいえません(マガジンハウス事件では、うつ病等で休職していた原告は、趣味のSMプレイに興じ、その子細をブログで公開したり、オートバイでの外出、ゲームセンターや場外馬券売場への出入り、飲酒や会合への出席を繰り返すなど、健常人と異ならない日常生活を送っていました)。
今回のご相談の事案では、上記をふまえ、当該休職中の社員の同意を得たうえで、主治医に対して、旅行に行ったり職場の人間関係を頻繁に相談したりすることが療養に矛盾する行動ではないかについて意見照会することをお勧めいたします。そのうえで、それらが療養に矛盾する行動であるとの主治医の意見であれば、旅行や相談をしないよう注意します。主治医の意見が療養に矛盾する行動ではないとのことであれば、旅行や相談を禁止することはできません。そこで、「休職者が旅行に行っている事実などは、他の従業員から見ておかしいと思われてしまい、職場に悪影響を与えるので控えてほしい」旨注意することをお勧めいたします(SNSに旅行の画像などを掲載していれば、そちらは禁止を指示してよろしいかと思います)。
「自己保健義務」についてもご相談内容となっているようですが、「自己保健義務」は労働者が健康の保持増進に努めることを趣旨とする一般的な用語でありますので、今般の事案では、以上の観点からご対応いただくのが適当ではないかと考えます。
投稿日:2025/06/19 10:01 ID:QA-0154169
プロフェッショナルからの回答
対応
法律的な根拠については必ず専門家である弁護士の確認を受けて下さい。
人事的対応としてできそうなのは;
>休職中であるのに正式な相談ではないといいつつ、職場の人間関係の不満を頻回に上席に連絡してくる
という行為でしょう。
休職命令時に、休職中の対応についても取り決めがあると思います。例えば会社との連絡をどう決めているか、特に連絡頻度や方法など、休職を解する際の決め方なども含めて、まだ未定であればまず決める必要があります。当然病状については素人は加入できませんので、状況に応じて産業医の所見など根拠に基づき変更の可能性があることは当然となります。
その上で、そこでの取り決めに反する行動は人事的にも厳しい指導、場合によっては懲戒対象になり得ると考えます。特に連絡を受ける直属上長は、責任が発生していますので、個人的に対応したりせず、必ず連絡時は人事をCCするなど、常に情報公開して対応することを理解させる必要があるでしょう。
投稿日:2025/06/19 10:02 ID:QA-0154170
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働安全衛生法の内容につきましては、労基法等と同様に使用者に対して措置が義務付けられるものになります。
すなわち、考え方としましては同法で定められている健康診断等と同様で、直接労働者を律するものではないですが、対応してもらえなければ結果的に会社の法的義務が果たされない事になりますので、事実であれば注意指導等をされる事で差し支えございません。
但し、メンタル疾患に関しましては、例えば旅行へ行かれる等気分転換を図る事で症状が改善される事例もございますので、そのような行為をされたからといって療養に専念していないとは言い切れません。
従いまして、専門医または当人の許可を得て主治医の意見を聴かれた上で、療養効果が得られるものであるかを判断した上で対応されるべきといえます。
投稿日:2025/06/19 10:39 ID:QA-0154187
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント