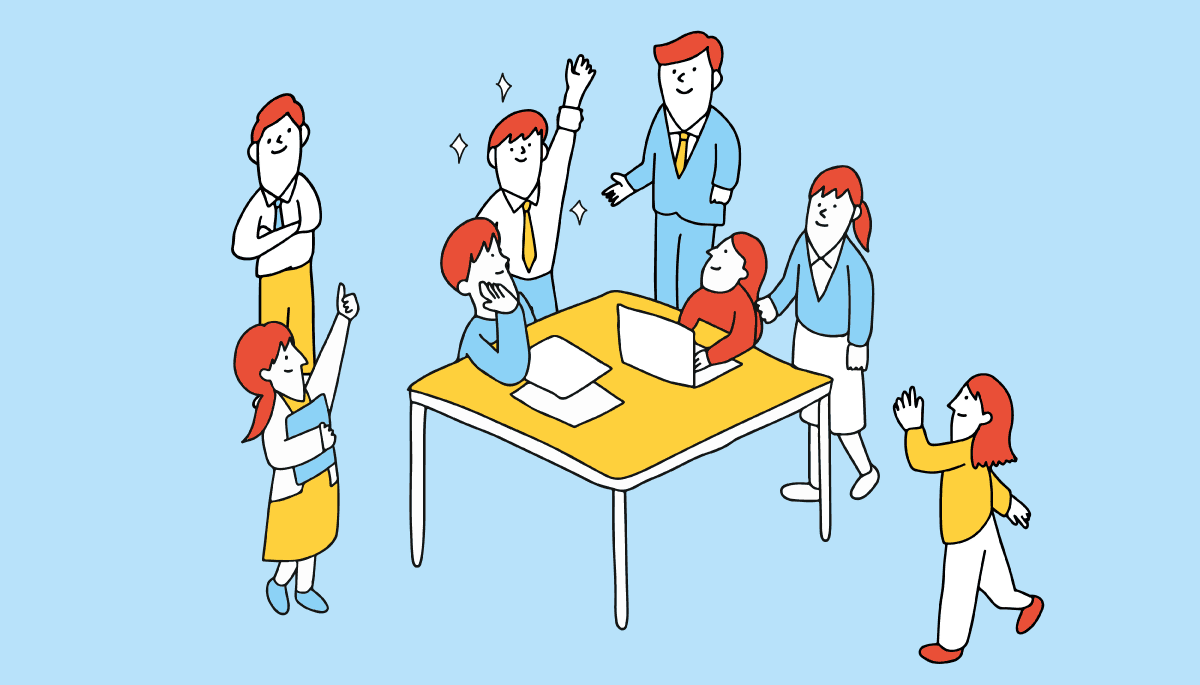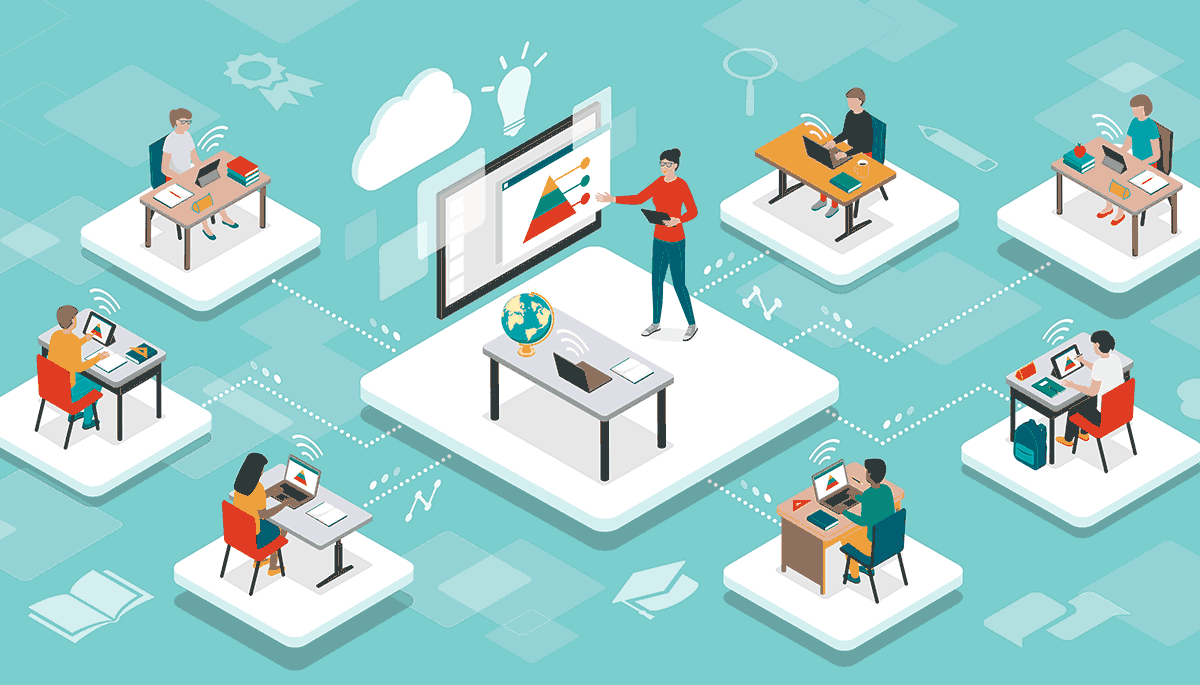停職期間の妥当性について
停職処分の期間について伺いします。
懲戒処分としての出勤停止期間の妥当性や一般的な運用の目安について、先生のご見解を伺いたくご相談申し上げます。
また、教育・改善を目的とした研修は、
(1)停職処分後の復職前に実施する
(2)停職処分決定前に反省・教育の機会として実施する
いずれのタイミングがより望ましいとされるか、一般的な実務上のご見解を伺えればと思います。
投稿日:2025/10/27 16:01 ID:QA-0159955
- cvbnmさん
- 東京都/販売・小売(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.停職(出勤停止)処分期間の妥当性の目安
(1)法的原則
停職(出勤停止)は懲戒処分の中でも比較的重い処分に分類され、就労義務を免除し、賃金も支払わないため、
過度に長い期間を設定すると「懲戒権の濫用」(労働契約法15条)にあたるおそれがあります。
裁判例では、懲戒処分の相当性(比例原則)の観点から、行為の内容や過去の処分歴を踏まえて「社会通念上相当」かどうかが判断されます。
(2)一般的な実務上の期間の目安
行為の程度→停職(出勤停止)期間の一般的水準→備考
軽微な服務違反(遅刻・欠勤等の反復)→1~3日→戒告や減給で足りる場合も多い
職場秩序を乱す言動・トラブル(顧客・同僚とのトラブル等)→3~7日→改善の機会を与える意図で用いる
業務上の不正・ハラスメント・虚偽報告等→7~14日程度→就業規則に明確な定めがあることが前提
重大な不正・背任行為等(懲戒解雇相当だが情状酌量あり)→15~30日程度→停職上限は1か月が通例
→実務上の上限は「30日以内」とする企業が圧倒的多数です。
(地方公務員法でも懲戒処分の停職期間上限は6か月とされていますが、民間では1か月を超えると懲戒権濫用のリスクが高まります)
(3)裁判例の参考
新潟鉄工所事件(新潟地裁昭54・6・15)
→ 出勤停止1か月を「やや重いが相当」と判断
昭和電工事件(東京地裁昭58・7・13)
→ 出勤停止2か月は「過重で懲戒権濫用」と判断
中部電力事件(名古屋地裁平5・6・28)
→ 出勤停止10日間は相当と判断
したがって、1~10日程度が一般的運用範囲、最長でも30日以内が妥当といえます。
2.教育・改善を目的とした研修のタイミング
ご提示の2つのタイミングのうち、目的によって使い分けるのが実務的です。
(1)停職決定「前」に実施する場合
(反省・改善の機会を与える目的)
行為が悪質であっても、本人が真摯に反省し改善の意志を示す場合、懲戒の軽減要素となる。
研修・指導記録を残すことで、「懲戒処分が教育的配慮を経たうえで行われた」ことを示せる。
よって、懲戒処分の相当性を高める意味で、処分決定前に実施するのが望ましいケースが多いです。
(例)
・職場トラブル後、面談・再発防止研修を行い、態度改善が見られない場合に出勤停止へ進む。
(2)停職「後(復職前)」に実施する場合
(再発防止・職場復帰支援の目的)
停職処分が確定した後、復職前に「再教育プログラム」「再発防止研修」を課す形。
社会的には「更生の機会を与える」処遇として評価されやすい。
実務上は、復職要件としての教育・誓約書提出を組み合わせる形が一般的。
(例)
・セクハラ・パワハラ事案で、復職前にハラスメント防止研修・誓約書提出を義務付ける。
(3)まとめ:両者の使い分けの考え方
タイミング→主目的→実務上の位置づけ→備考
停職決定「前」→改善・反省の機会→懲戒の相当性を補強→処分軽減要素になり得る
停職「後・復職前」→再発防止・再教育→復職要件として有効就業規則・通達で明示を
両方を段階的に組み合わせる(例:停職前に面談・指導 → 停職 → 復職前研修)運用も、コンプライアンス上・教育上、非常に理想的です。
3.実務的なアドバイス
就業規則に停職期間の上限を明示(例:「30日以内」)
懲戒処分前に必ず弁明の機会を付与(労働契約法15条)
研修・指導の実施記録を保存(懲戒の相当性証明に有効)
復職時に再教育・誓約書提出を行う(再発防止)
・参考例文(就業規則条文例)
第○条(懲戒の種類)
停職とは、30日を超えない範囲で就労を禁止し、その期間の賃金を支給しないものとする。
第○条(再教育)
停職処分を受けた者の復職にあたっては、会社は必要に応じ、再発防止研修等を受講させることができる。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/10/27 17:26 ID:QA-0159959
相談者より
お世話になっております。
ご回答いただきありがとうございます。
就業規則の記載例もご提示いただき大変参考になりました。重ねてお礼申し上げます。
投稿日:2025/10/27 18:13 ID:QA-0159969大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
出勤停止期間については、2週間~1か月程度を採用することが多い所感です。
勿論、処分の重さによっての判断となりますが、出勤停止期間は給与が不支給
となりますので長すぎる期間(概ね3ヶ月程度)は適切ではありません。
また、研修実施タイミングについては、ご提示のどちらもあり得ますが、
停職処分後の復職前に実施するケースがより望ましいとされる傾向にあります。
これは、懲戒処分という過去の行為に対する罰と、研修という将来の改善・教育
を区別し、処分を全うさせた上で、職場復帰の条件として再発防止を徹底させる
という流れが、処分の目的と教育の効果の両面からみて理にかなっているとされ
る為です。
投稿日:2025/10/27 17:46 ID:QA-0159962
相談者より
お世話になっております。
ご回答ありがとうございました。
停職処分後の復職前に実施するケースがより望ましいとのこと、承知しました。
今後ともよろしくお願いいたします
投稿日:2025/10/27 18:29 ID:QA-0159970大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、一般的な出勤停止期間は1週間程度といえるでしょう。また、運用上は職場でトラブルを起こす等出社される事でかなりの悪影響が懸念される場合に命じられるものといえます。勿論、あくまで就業規則の定めに従い、個別の事情に即して御社自身で判断されるべき事柄といえます。
そして、教育研修のタイミング等に関しましても、御社自身で決められるべきですが、「停職処分後の復職前」の場合ですとそれまでの期間での職場への悪影響も懸念されますし、加えてたとえ教育研修の場であっても労働時間扱いとされ賃金支払が必要になりますので、先に実施される方が望ましいといえるでしょう。
投稿日:2025/10/27 19:10 ID:QA-0159977
プロフェッショナルからの回答
対応
一般的に停職は、1日~6カ月の間で、行為の重大性から規定されます。
職務によってもその位置付けが異なるので、他社一般論より、貴社の業界同業の例に準ずるのが現実的でしょう。
教育についてはそもそも教育を実施するかどうか含めて、貴社の方針と事案内容によります。停職前は理解促進、停職明けは復職の準備的側面があり、これまた事案内容によって判断となるでしょう。
投稿日:2025/10/27 23:05 ID:QA-0159986
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
懲戒処分としての出勤停止は、権利濫用または公序違反の判断では期間は重要になります。
労基法の全身である工場法の下での行政通達では7日を出勤停止の限度としていましたが、7日間の出勤停止を裁量権の逸脱として無効とした裁判例がある一方で、3か月の出勤停止を有効とした事案もあります。
個別事案にもよりますが、実務上は1週間から10日~15日程度を上限としている場合がほとんどです。
(1)、(2)のどのタイミングが望ましいか、望ましくないかといった基準で考えるのではなく、諸般の事情を考慮したうえで、柔軟に実施すればよろしいでしょう。
投稿日:2025/10/28 08:45 ID:QA-0159992
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
研修期間の設定 弊社はアミューズメント施設を経営... [2006/11/08]
-
今春入社社員(学卒)の研修期間の残業 早速ですが、現在新入社員の研修(... [2010/04/19]
-
研修中の労災について 研修予定者から質問を受けました。... [2008/07/08]
-
休職期間の算定について 弊社では勤続期間5年以上の社員の... [2011/08/23]
-
懲戒免職処分の処分効力発生日について 懲戒免職処分の処分効力発生日につ... [2016/09/19]
-
懲戒処分における被処分者の経済的損失の軽重について いつもご指導いただき有難うござい... [2024/09/12]
-
研修について 当社では、様々な研修を行う機会を... [2007/06/01]
-
教育研修会社について 当社で若手社員を対象に研修を実施... [2006/06/12]
-
研修について 階層別研修等、ビデオ研修を用いた... [2005/09/20]
-
懲戒処分について 会員様各位初めての投稿となります... [2012/10/29]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント