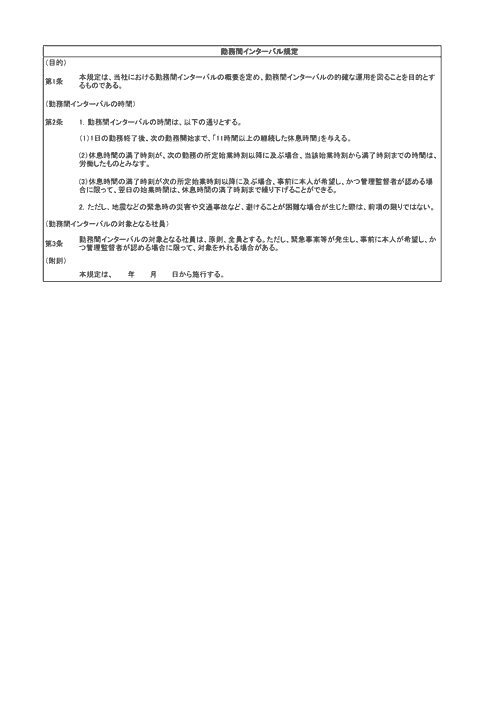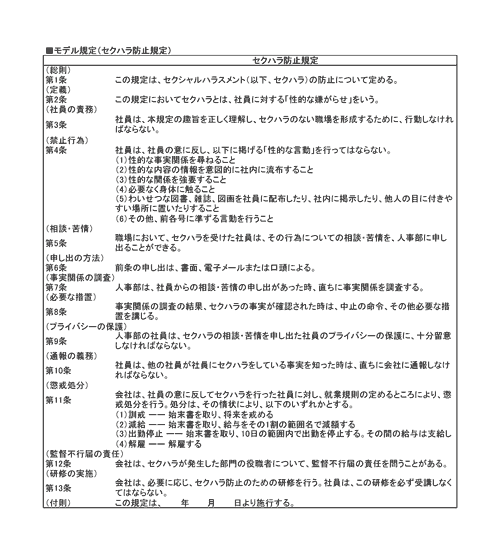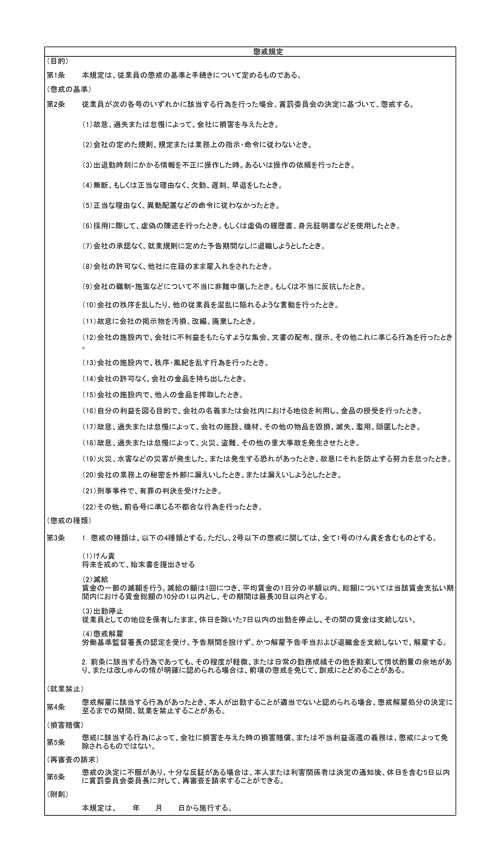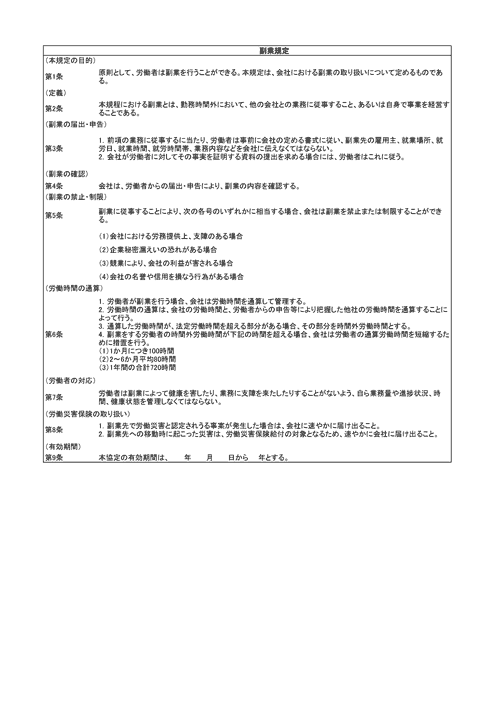会社独自の福利厚生の補助規定について
会社でインフルエンザ予防接種の補助をしています。
従業員立替後、給与外支給で支給しています。
しかし、明確な「補助規定」のようものものなく
毎年実施しています。
補助対象の範囲や金額、補助期間や申請方法など
規定がないのは不安なのですが、
なくても問題はないのでしょうか。
投稿日:2025/11/14 14:25 ID:QA-0160673
- ラオウさん
- 東京都/フードサービス(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
本件は税務観点と労務観点の2軸の観点がございます。
まず税務観点として、福利厚生費等として非課税処理を行っているのであれば、
規定が無ければ非課税処理に出来る理由(根拠)がありませんので、税務リスク
を負うことになるでしょう。詳細は、税務の専門家である、税理士へお尋ねを
いただくことをお勧めいたします。
労務観点では、規定がないことによりルールが不明確で、運用が煩雑になる
可能性が高くございます。また、毎年、支給される継続的な手当であれば、
給与規程等への規定が本来は必要です。規定をしておくことが良いでしょう。
投稿日:2025/11/14 14:45 ID:QA-0160677
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
そのようにしてみます!
ありがとうございます。
投稿日:2025/11/14 14:58 ID:QA-0160681大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
法令上、「必ず規定を作らなければならない」という義務はありません。
ただし、
規定なしで運用を継続することは
労務管理上・税務上・内部統制上のリスクが高いため、簡易な「福利厚生規程」または「実施要領」だけでも整備することを強く推奨します。
(1)法律上の義務の有無
インフルエンザ予防接種の補助は、
就業規則の絶対的記載事項ではない
法律上の義務制度でもない
福利厚生として任意で実施できる
したがって、
規定がない=即違法、ということはありません。
(2)しかし、規定がない場合に起こりうる問題
実務上は、規定なしで運用することのリスクが大きいです。
1. 不公平・恣意的運用とみなされるリスク
規定がないと…
誰が対象か?
派遣社員やパートは対象か?
家族は対象か?
上限金額は?
レシートがない場合は?
期間はいつからいつまで?
これらを「口頭」で対応すると
公平性が保てない → 労務トラブルの原因になります。
2. 税務上の「給与課税(課税扱い)」リスク
インフルエンザ予防接種の補助は
業務上必要な場合:非課税
福利厚生(任意):非課税(一定条件あり)
個人的理由:課税となる可能性
税務署が重視するのは以下の点:
・「対象者が適切に定められているか」
→ 規定なしだと“恣意的支給”とみなされ課税リスク
・「支給条件が明確か」
→ 実費精算で記録が残っているか
→ 社内で統一されているか
規定がないと、給与扱いにされる可能性があります。
2.会計監査・内部統制上のリスク
上場企業や大企業だけでなく、中小企業でも
誰の判断で支給したの?
基準は?
例外は?
と説明を求められることがあります。
規定がないと「社長の裁量」「担当者の判断」で処理されてしまい、
内部統制として脆弱です。
3.結論:規定は作ったほうがよい理由
法律では必須ではないが、次の点で「規定」または「実施要領」を整備すべきです。
(1)従業員への公平性
(2)税務リスクの回避(課税扱い防止)
(3)運用の明確化(申請ミス防止)
(4)新担当者でも運用継続しやすい
(5)従業員からの問合せ対応がラクになる
4.作成すべき規定の中身はこれだけでOK
最低限、以下の項目を規定化すれば実務は回ります。
(1)福利厚生規程:インフルエンザ予防接種補助(例)
目的
従業員の健康管理促進のため補助を行う。
対象者
正社員・契約社員・パート(週○時間以上)
※派遣社員は除く など
補助内容
実費相当、または上限○円
(1人につき年1回)
対象期間
例:毎年10月1日~翌3月31日
申請方法
領収書提出
申請書提出
給与外支給(雑給)
家族の扱い(※任意)
補助する/しない
上限・申請方法
例外規定
不正申請は対象外
領収書の期限切れは不可 など
5.質問者様のケースへの直接回答
補助対象の範囲や金額、補助期間や申請方法など規定がないのは不安
なくても問題ないでしょうか?
→ 法律上は問題なし。
→ しかし、実務上は規定がないことで次のリスクがあります:
不公平運用
税務署に課税扱いにされるリスク
労務トラブル
内部統制上の問題
企業説明責任が果たせない
したがって
簡易な規定(1ページ程度でOK)を作成されることを強く推奨します。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/11/14 15:02 ID:QA-0160682
相談者より
ありがとうございます。
詳細な内容まで教えていただきとても助かりました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2025/11/14 15:35 ID:QA-0160688大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
OB会規定について OB会を作るにあたり、規定類のひ... [2022/01/29]
-
規定の作成について 規定の種類が様々ありますが、マイ... [2016/04/26]
-
慶弔規定と慶弔見舞金規定 慶弔規定と慶弔見舞金規定に違いは... [2022/05/19]
-
住宅手当・借上社宅規定の明記 住宅手当・借上社宅規定の要項は社... [2006/01/15]
-
人事異動に伴う通勤時間・補助手当について 来年4月以降の人事で、ドアtoド... [2022/11/16]
-
休日の振替について 休日の振替についての質問です。弊... [2024/07/05]
-
出向者の時間外手当の給与計算について 出向元「甲」から出向先「乙」への... [2010/11/26]
-
賞与の規定について 一般的に、賞与額を決定する際、計... [2024/11/28]
-
家族手当の支給月 弊社給与規定では当月20日締め当... [2019/06/29]
-
就業規則の付属規定 以前、就業規則の変更届を出した... [2019/08/06]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
勤務間インターバルの規定例
勤務間インターバル制度を就業規則に規定するための例です。
セクハラ防止規定(モデル規定)
セクハラ防止に関するモデル規定です。禁止する行為と、懲戒処分の程度を含んでいます。
懲戒規定
懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。
副業規定
副業を許可制で認める場合に必要な規定例です。就業規則などに盛り込みお使いください。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント