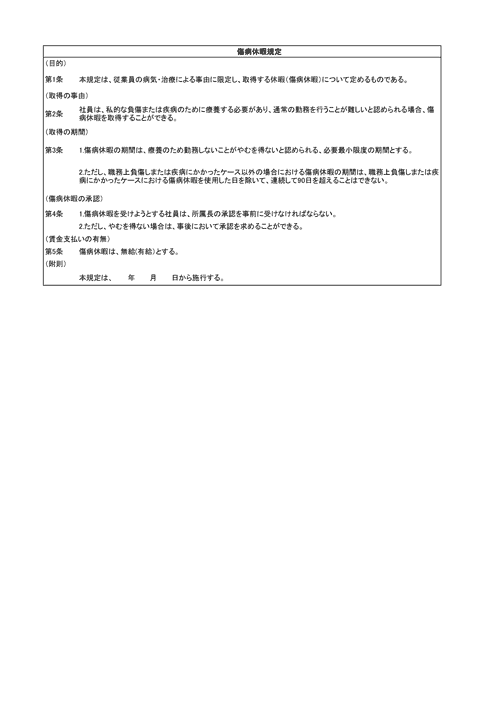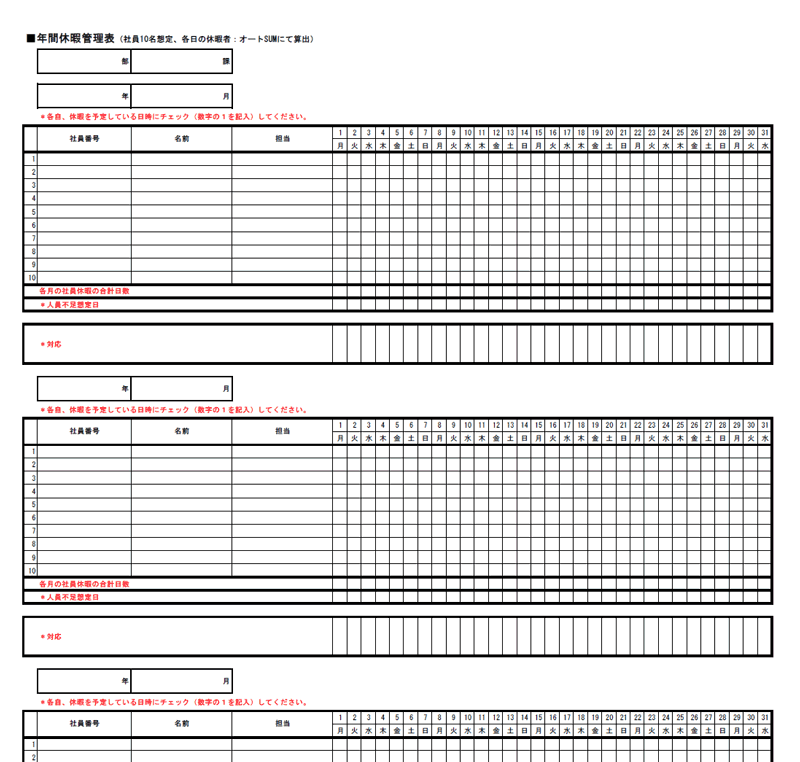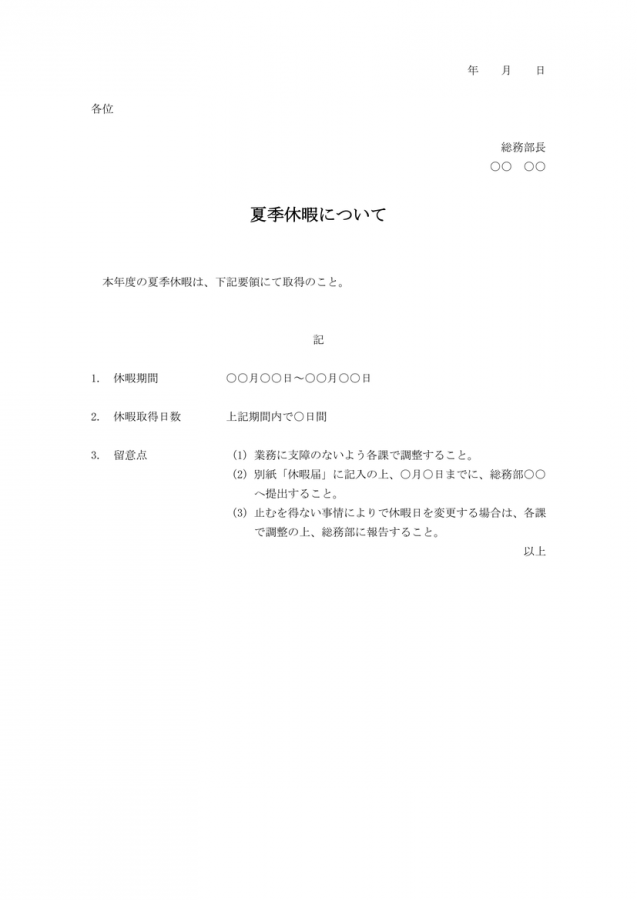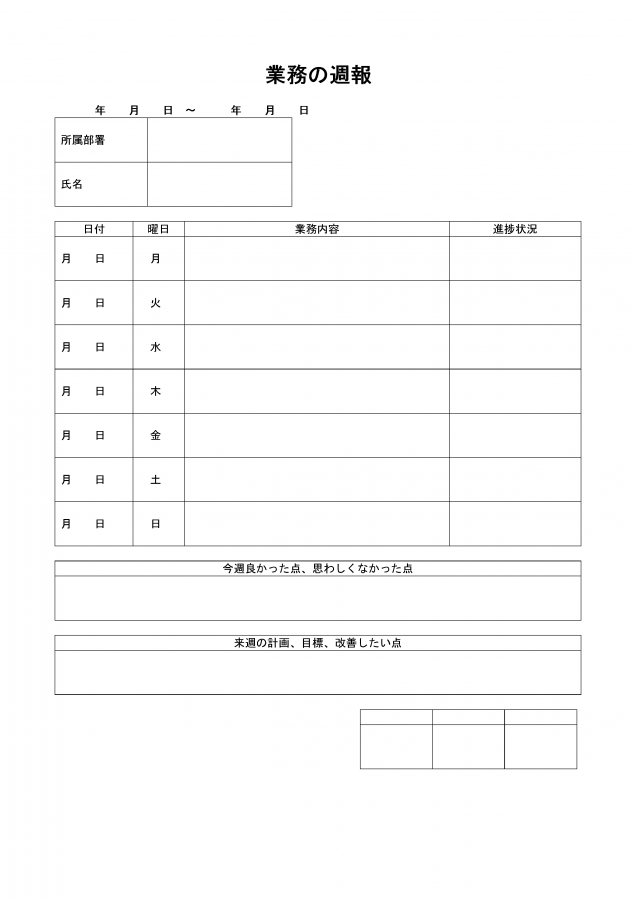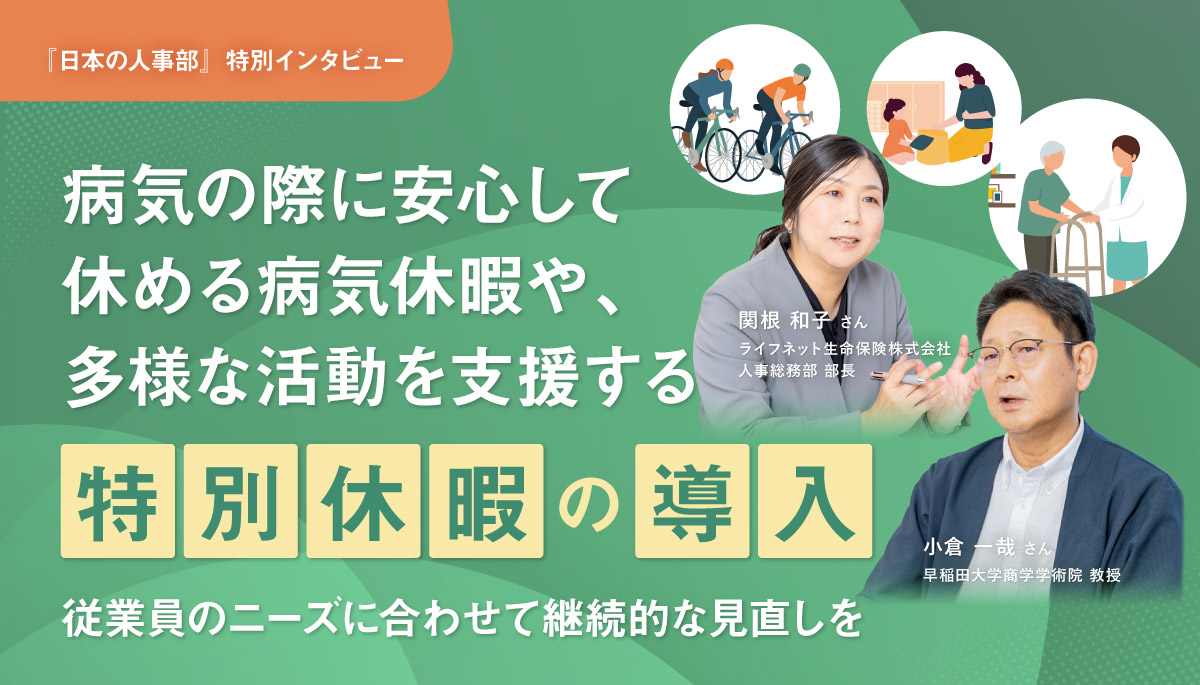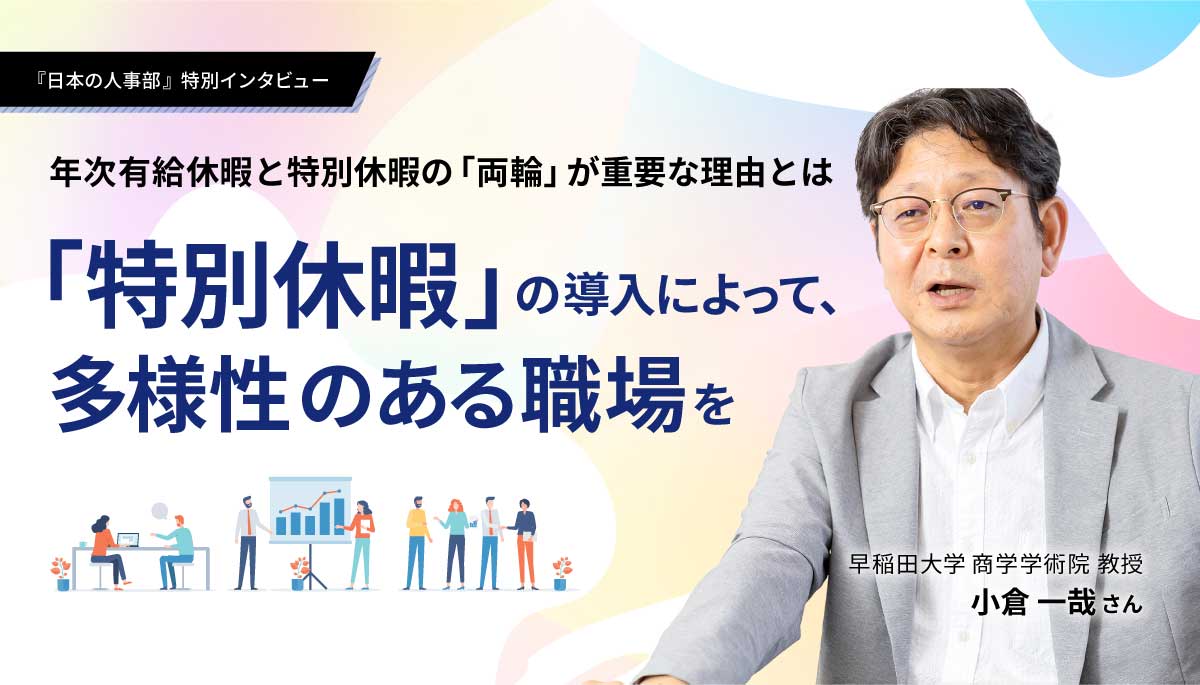男性の産前の業務配慮について
お世話になっております。
弊社社員で、奥様が妊娠しておられる方がおり
奥様のお手伝いをしたいとの事で、早退などを認めてほしいとの
申し出がありました。
育児休業規定を確認しましたが、出産後の休暇について
のみの記載で、産前の業務配慮については記載が無いのですが
会社の業務配慮は必要でしょうか。
休暇ではなくあくまでもお手伝いの為
早退したいとの申し出です。
投稿日:2025/07/23 09:24 ID:QA-0155759
- 総務の新人さん
- 千葉県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論:会社に法的な「配慮義務」は 原則としてありませんが、柔軟な対応を検討する余地はあります。
2.法的な義務の有無
● 労働基準法・育児介護休業法には、「妊娠中の配偶者を介助するための休暇」や「勤務配慮」についての定めはありません。
育児・介護休業法で規定されているのは、主に以下の内容です:
配偶者の出産時の「出産時育児休業(産後パパ育休)」
育児休業
子の看護休暇
→ いずれも「出生後」が対象であり、「妊娠中」の配偶者を支援するための時短・休暇制度は法定制度としては未整備です。
3.会社としての対応可能性(努力義務・裁量対応)
● 労務管理上の選択肢としては、以下が考えられます:
対応方法→説明
有給休暇の取得→本人の申出に基づき、通常の年次有給休暇を利用してもらう。
私用早退としての扱い(欠勤控除あり)→無給の早退を認める。私用扱いで、給与控除が生じる点を明示。
時差出勤・時短勤務の一時的容認→就業規則の範囲内または個別対応で、期間限定の配慮として認める。
※これらは会社の裁量による措置であり、義務ではありません。
4.社内ルール上の観点(就業規則等)
産前の配偶者介助に関する制度(例:配偶者出産準備休暇など)を創設する企業もありますが、これは企業独自の福利厚生制度です。
就業規則に明文化がなければ、個別判断での対応可否を決定することになります。
5.実務対応アドバイス
● 人事・労務担当者としての対応方針例:
「業務に支障のない範囲で、年次有給休暇または私用早退を認める」といった柔軟な対応が、労使関係の信頼構築にも寄与します。
今後、同様のケースが想定されるのであれば、「配偶者出産準備休暇」など独自制度を設けることも検討余地ありです。
6.まとめ
項目→回答
法的義務→妊娠中の配偶者の介助のための早退・時短に関する法的な義務はなし
勤怠処理→有給休暇消化、または私用早退(無給扱い)で対応可能
配慮の必要性→義務ではないが、就業規則や企業の方針に基づき柔軟な対応も可
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/07/23 10:00 ID:QA-0155761
相談者より
ご回答頂きありがとうございます。
法律的に認めるというものはないが、業務配慮をするという点において柔軟に対応すべきという事が学べました。
法例や詳しい解説を頂きありがとうございました。大変参考になりました。
本人と詳しくお話しし解決したいと思います。
投稿日:2025/07/23 10:37 ID:QA-0155764大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
ご質問の件、会社として法的な配慮義務はございませんが、
会社の裁量で業務配慮を行うことは望ましい対応と言えます。
但し、お手伝いの理由のみでは余りにも不明瞭ですので、
理由詳細を改めて聞いた上での判断が必要です。
なお、今後も同様の申し出が考えられる場合は、法的な義務はありませんが、
家族の妊娠に伴う、業務配慮等として会社規程に規定されることをお勧めを
いたします。
投稿日:2025/07/23 10:07 ID:QA-0155762
相談者より
ご回答頂きありがとうございます。
業務配慮することが望ましいとの事で
上席にも確認し対応したいと思います。
また今後の為にも会社規定の見直しの提案も視野に入れて参ります。
投稿日:2025/07/23 10:39 ID:QA-0155765大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
法律ではなく、正に人事政策の問題だと思います。
貴社がどのような政策を展開したいかで、男性も出産子育てがしやすい環境を提供・実現することが、経営上必要だと判断するのであれば、ぜひこうした要望にも法律ではなく会社として応えるべきものとなるでしょう。
一般論ではなく、経営方針ですので、貴社の経営判断だと思います。
投稿日:2025/07/23 10:36 ID:QA-0155763
相談者より
ご回答頂きありがとうございます。
お尋ねしたかったのは法律的に配慮する義務の有無でしたが、個々の会社の判断という事が学べました。
投稿日:2025/07/23 11:50 ID:QA-0155766参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
休日と休暇 休日と休暇の定義(違い)を詳しく... [2007/04/09]
-
特別休暇の申請について 追記 特別休暇についてですが、就業規則... [2019/10/31]
-
忌引休暇の扱い 当社では、従業員本人が喪主の場合... [2008/01/11]
-
裁判員制度と休暇 休暇中の賃金は、無給でよいか [2008/09/16]
-
26業務について 26号業務内で2つ以上の業務を行... [2007/02/06]
-
産前期間中の年次有給休暇 年次有給休暇を使い切った後,産前... [2007/11/29]
-
育児休業の期間等について 産前産後休暇を取得してから育児休... [2020/07/13]
-
産前休暇について 従業員より、産前休暇中に有休休暇... [2020/01/10]
-
半日休暇の制度化について 当社は、半日休暇の規定がないので... [2005/12/06]
-
忌引休暇について 忌引休暇の付与にあたり、叔母の配... [2009/02/04]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント