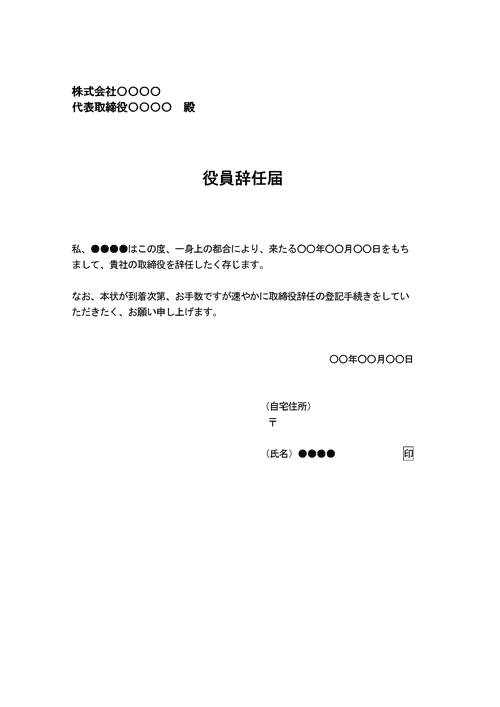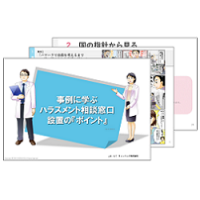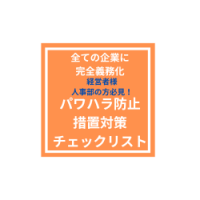ハラスメント相談者の不安対応
お世話になっております。
先日、セクハラとパワハラに関しての相談が社内専用フォームに寄せられました。(希望対応方法がメールの為、対面や電話でお話はしておりません)
質問は以下の3点です。
①
初期対応として、委員会への情報共有(事案認定するため)の許可を最初に説明し、証拠が有れば提供の依頼を行いました。
そうしたところ、証拠が何もなく、行為も二人っきりになるタイミングで行われ目撃者もいないとの事で、調査をしても行為者が否定をしてしまったら周囲から相談者自身が【嘘つき】と見られてしまうのではと不安から、窓口に訴えてみたが怖気づいてしまい、現在進展が無い状態です。
多分、これは相談者心理として、よくある事だと思うのですが、窓口としてどの様に寄り添って不安を晴らして上げれるでしょうか?
②
弊社は250名以下のオーナー企業でして、常勤役員も5名しかおらず、今回の事案発生現場に関わっている2名の役員は確実に委員としての活動から除外をしないといけませんが、この2名が最終事案認定者の為どうしたら良いかも悩みどころであります。
自身の支配下での事案の為、事案共有はすべきでないと私は考えておりますが間違っていますか?
③
一次報告者である上長には相談者の名前は伏せ、水面下での共有は行って委員会メンバーに制限がある事は予め伝えるべきかとも思うのですが、いかがでしょうか?
ご助言宜しくお願い致します。
投稿日:2025/08/07 10:53 ID:QA-0156502
- 従事者歴6ヶ月さん
- 千葉県/販売・小売(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
1について・・・
相談者が嘘つきと思われることを不安に感じるのは理解できます。
まずは、ご質問者様が伝えてくれたことへの感謝と共感を示すことで、
安心感を与えることが大切です。また、話は事実として受け止め、疑わない
姿勢を取ることが信頼構築に繋がります。プライバシー保護の約束も大切です。
調査の進め方は、一方的に決めるのではなく、相談者の意思を尊重しながら、
決定する工程が良いです。また、本人が社内調査を望まないこともありますので、
相談先は社外の外部機関にもあることを伝えてあげ、相談者ファーストの姿勢を
とっていただくことが重要ではないでしょうか。
2について・・・
ハラスメント事案では公平性が重要で、関係者(行為者やその上長)は、
調査・認定から除外すべきですであり、ご質問者様のご記載通りです。
3について・・・
異論は特段ありませんが、上長などへの情報共有は、名前を伏せる場合であって
も事前に相談者の同意を得たうえで行った方が良いでしょう。
投稿日:2025/08/07 12:21 ID:QA-0156516
相談者より
ご回答ありがとうございます。
現在、我が社には外部相談先を整備しておりません。ですが、相談者の意向に沿って出来る限りの支援が出来るよう、上層部にも掛け合ってみたいと思います。
投稿日:2025/08/07 14:01 ID:QA-0156521大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
1.ハラスメント事案処理に証拠は不可欠ではありますが、いきなり「証拠を出せ」と伝わってしまうのは、萎縮を呼びます。
ハラスメント通報対応の第一弾はまずは面談でしょう。面談の上で、頃合いを図り、証拠の有無などについても聞き出すことになります。
当然ですが、証拠なしの対応は限りなく不可能に近く、また社内での管理部門・担当者での情報共有も欠かせません。しかし関係のない取締役など、ハラスメント管掌者以外への無駄な情報開示はしない、通報の秘密は絶対に守るといった、会社の姿勢は必ず伝える必要があります。
このような高度なカウンセリング技術含めた対応能力が、通報管掌部門には求められます。ここを間違えると通報がされなくなり、リスク潜在化という一番会社にとって危険を呼ぶ恐れがあります。
2.事案当事者を判断や決済から外すのは当然です。どこぞの自治体や企業でも、自分自身への通報を、自分が決済する例がありますが、犯人が自分で警察と裁判官を兼ねるようなもので、絶対に関与は避ける必要があります。
代表に対する通報であれば、別の代表や取締役が主管するようにしなければなりません。かなり可能性のあることですので、方針を再度経営陣で共有して下さい。
3.個別の内容ではなく、通報事案への取り扱い方針を定めておく必要があります。
特に守秘義務について、まちがってもうっかり漏らすようなことがあれば、重大な服務違反として厳しい処罰がされることなど、ハラスメント取り扱い手順に沿った対応。
そうした取り決めがない場合は、今からでも対応担当者で委員会を開き、方針確認をして進めるべきでしょう。
ハラスメント対応を内製化する例は多数ありますが、起こりえる事態をできる限り想定し、規定通りに対応するという方針決定は必須です。
「ハラスメント防止研修」ではなく、「ハラスメント対応」方針などについては、外部専門家で、法律面以外の人事的知見を持つ専門家のアドバイスを一度お受けされることをお勧めいたします。
投稿日:2025/08/07 14:37 ID:QA-0156524
相談者より
ご回答ありがとうございます。
1についてですが、今回は相談者から「メールでの対応を希望」されており、まだ面談の機会を設けることができていない状況です。
証拠についても、最初から「出してください」と求めたわけではなく、**目撃者や記録が何かあれば教えていただけますか?**という確認の範囲にとどめました。
2についてですが、当該役員は行為者として名指しされているわけではありません。
ただ、その方の管轄内での発生ということもあり、委員から外すべきかどうか、私の判断が妥当かを後押ししてほしかったという意図です。
3についても、認定に関わる委員が限定される可能性があり、報告者(一次窓口)の上長に水面下で事情を共有してもよいかについて、手続き上問題がないかの確認でした。
守秘義務を前提にしたうえで、慎重に進めたいと考えています。
まだ手探りな部分も多いですが、相談者の不安に寄り添いつつ、窓口として慎重に進めていければと考えています。
投稿日:2025/08/07 15:50 ID:QA-0156525参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご相談いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 相談者が怖気づいて進展しない場合の窓口対応
相談者心理として、怖気づいてしまうのはよくあることですが、どのように寄り添って不安を晴らすべきか?
はい、非常によくある心理状態です。ハラスメント相談では以下のような配慮が大切です。
→ご提案:相談者への対応ポイント
相談者の「不安」は正当なものとしてまず共感する。
「誰にも見られていない」「証拠がない」「相手が否定したらどうしよう」といった不安は極めて一般的で、非難することなく、「そのように感じるのは当然です」と伝えることが信頼につながります。
「あなたの不安を第一に考えます」と明言する。
相談者にとっては「味方がいる」と感じられるだけで心理的負担が軽くなります。
会社として秘密を守る姿勢と対処方針を明確に説明する。
例えば以下のような文言を用います:
「証拠の有無に関わらず、あなたの訴えを軽く扱うことはありません。匿名性を保ちつつ、慎重に調査を進める方法もありますので、安心してください。」
選択肢を与える(相談者の主導で進められることを伝える)。
相談者の意志に反して強引に進めるのではなく、例えば以下のように選択肢を提示することが重要です。
「このまま相談だけで終えても構いませんし、一定の調査や聴き取りを行う方法もあります。どうされたいか、もう少しお時間を取って考えてみてください。」
2. 事案の当事者に該当する役員が委員会の最終認定者である場合の取り扱い
支配下で起きた事案を当該役員に共有すべきではないという判断は間違っているか?
ご判断は適切です。
→ご提案:当該役員の取扱いについて
ハラスメントに関する調査・認定の原則は「独立性・中立性・公平性」です。
行為者本人またはその支配・管理下にある者(直属上司・ライン役員など)が調査や認定に関わることは厳に慎むべきです。
たとえ「形式上の決裁者」であっても、当該事案に関わりがある場合は利害関係者とみなされるため、調査・認定・決裁からは排除すべきです。
→実務上の解決策
臨時の認定体制の設置:常任役員とは別に、信頼できる社外弁護士や社労士等を含めた臨時認定体制を組むことが望ましいです。
調査・認定は人事部長や内部通報窓口責任者などの独立性のある者が行い、役員の決裁は「形式的確認」のみにとどめることもありえます(ただしこの場合でも、当該役員には報告しない措置が必要です)。
3. 上長(一次報告者)への匿名共有と委員会制限の事前通知について
上長に匿名で水面下での共有を行い、委員会メンバーの制限についてもあらかじめ伝えるべきか?
この対応も非常に適切な方向性です。
→ ご提案:情報共有に関する考え方
相談者の同意を得た上で、匿名での限定共有は必要です。
ただし、共有範囲・目的をあらかじめ説明する必要があります。
例文:
「必要最小限の関係者に、あなたの名前は伏せたまま、状況を把握してもらいます。これは再発防止や今後の配慮のためです。」
上長はハラスメントの再発や悪化を防ぐために必要な調整役を担うことがあるため、水面下での共有は実務上やむを得ません。
委員会メンバーの制限については、信頼性のある委員会であることの担保として、関係者には「構成に制限があること」を伝えるべきです。
その際、「なぜ制限するのか」の理由まで説明する必要はありません。
4.まとめ
項目→ご対応の方向性
(1) 相談者への寄り添い方→共感・秘密厳守・選択肢の提示がカギ。相談者のペースを尊重しながら継続的にフォロー。
(2) 役員が関係者である場合の取扱い→認定から外す判断は正しい。社外者を含む臨時体制の検討を。
(3) 上長・委員会への情報共有→匿名での限定共有は必要最小限に。委員制限は透明性ある伝達を。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/08/07 16:18 ID:QA-0156530
相談者より
ご丁寧なご回答をいただき、誠にありがとうございます。
いずれの点も非常に納得感があり、現場での対応に自信を持って進められそうです。
特に、相談者への寄り添い方や役員の取扱いについてのご助言は、実務に落とし込むうえで大変参考になりました。
引き続き、現場の安心と制度の信頼性の両立を目指してまいります。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2025/08/07 16:48 ID:QA-0156539大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.窓口としては、個人情報の保護と報復禁止を説明し、安心して相談できる
窓口であることを説明してください。
怖気づいてしまうということは、窓口に対する信頼がないということになります。
2.事案共有するのであれば、相談者の意向を確認してからになります。
3.これは事案によりケースバイケースでやり方は様々です。
個人情報の保護を念頭に、必要に応じ、相談者の意向を確認しながら進めてください。
投稿日:2025/08/07 16:22 ID:QA-0156532
相談者より
ご回答ありがとうございます。
基本的な方向性は理解いたしましたが、現場での対応を踏まえると、いくつか気になる点があり、率直にお伺いさせていただきます。
まず、「怖気づく=窓口への信頼がない」とのご指摘についてですが、相談者が不安になる背景には、証拠の有無や周囲の目、報復への懸念など、非常に複雑な心理があります。
窓口への信頼があっても、「相談後の影響」を気にして慎重になるケースもあり、単純に“信頼の有無”で判断するのは少し違和感がありました。
また、「相談者の意向を確認してから共有する」という点については、当然の前提として理解しております。
今回は自分の管轄下で起きた事案についてで、利害関係や影響範囲を踏まえた慎重な対応が必要と考えております。
守秘義務については、常に最優先で対応しております。
投稿日:2025/08/07 17:01 ID:QA-0156541参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、証拠有無に関係なく事実を申告して頂く事が重要といえます。その際、調査結果に関係なく秘密厳守の上で、明らかに虚偽の申告と判明した場合を除き、当人に不利益が及ばないよう対応する事(誹謗中傷者等に対しては厳しく対応する事等)を約束されるとよいでしょう。勿論、当人がどうしても話されたくない場合にまで無理にお尋ねされる事は慎まれるべきです。
2につきましては、当然ながら御社規定内容に関わらず事案の当事者については認定者から除外される必要がございます。
3につきましては、当人の同意が有れば可能ですが、会社側の判断のみで行われるのは避けるべきです。
投稿日:2025/08/07 22:37 ID:QA-0156550
相談者より
ご回答ありがとうございます。
ご指摘いただいた通り、事実申告においては証拠の有無に関わらず、通報者の心理的安全性を守ることが重要と認識しております。
特に、虚偽申告でない限り不利益が及ばないよう対応すること、また誹謗中傷への厳正な対応については、現場でも徹底してまいります。
また、共有に際しての通報者の同意確認についても、制度運用上の基本として再確認いたしました。
今回のケースを通じて、現場対応と制度の信頼性の両立を目指し、運用の見直しに活かしてまいります。
投稿日:2025/08/08 09:31 ID:QA-0156556参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
役員の辞任届
労働者の立場ではない役員が辞任をする際の届出です。


 サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 調査
調査 人事辞典
人事辞典 イベント
イベント