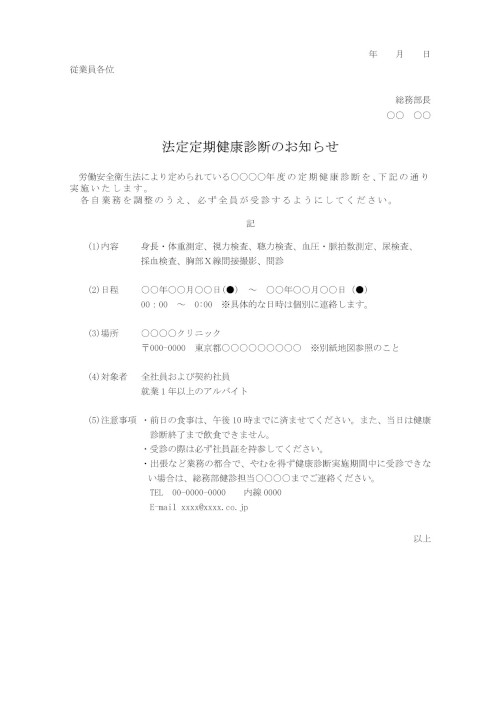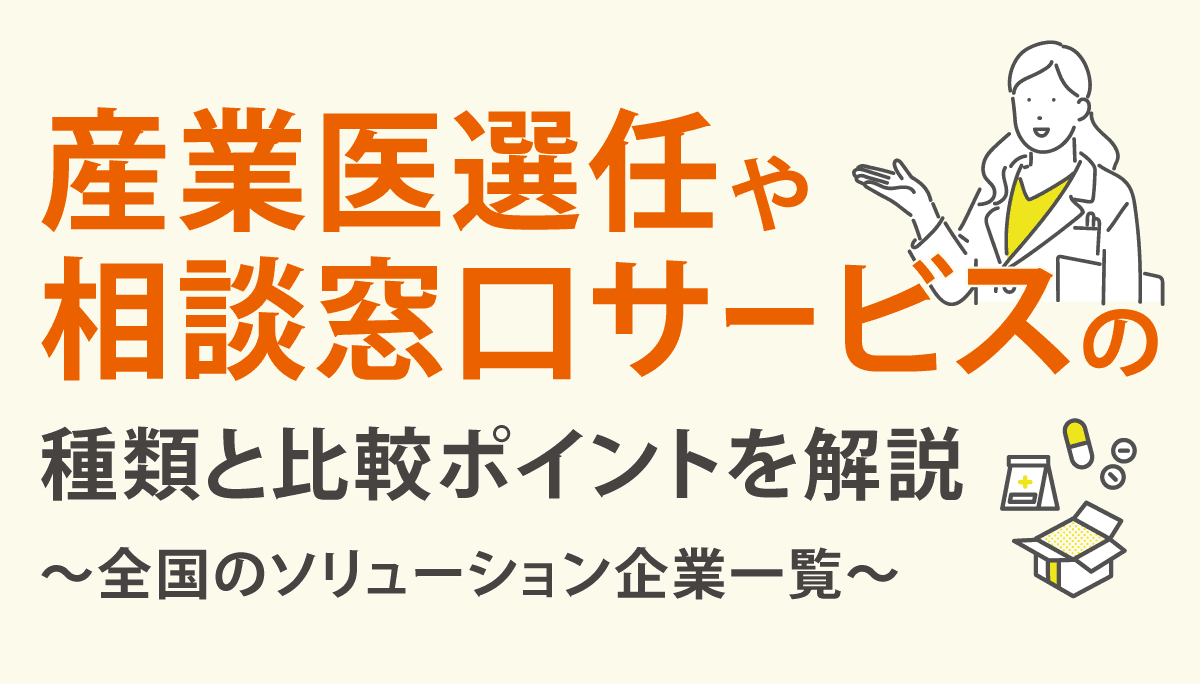騒音健診結果の異常者選別について
今回初めて騒音健診を実施します。
初めてのため、産業医も知識がなくどう判定をするのかで迷っております。
「騒音障害防止のためのガイドラインの改訂について」には「30dB の音圧での検査で異常が認められる者その他医師が必要と認める者」としか記載されていないので、1000Hz、4000Hzどちらかで異常があり、さらに片耳だけの異常者も対象者(例:1000Hz30db右耳異常のみ)となると二次健診の対象者の幅がかなり多くなってしまうと考えたのですが、これが通常の二次健診対象者判定となるのでしょうか?(耳の基礎疾患がある者も含めて)
一般的に騒音性難聴とは両側性であり、4000Hzに異常をきたすとされており、さらに弊社での騒音作業は片耳に偏るような作業ではないため、以下の記事に記載されている診断のポイントも踏まえて、https://www.jstage.jst.go.jp/article/jibiinkoka/120/3/120_252/_pdf
選別聴力検査で4000Hzが両耳に異常のある者に二次健診を受けていただくべきなのではないかと考えたのですが、これは間違いでしょうか?
アドバイスよろしくお願いいたします。
投稿日:2025/10/06 17:34 ID:QA-0159230
- ぞうねこさん
- 大阪府/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 法的根拠とガイドラインの趣旨
根拠となるのは
「騒音障害防止のためのガイドライン」(令和2年7月改訂、厚生労働省)および
労働安全衛生規則第458条〜第460条(騒音作業に係る特殊健康診断)です。
ガイドラインの記載では、
「30dB の音圧での検査で異常が認められる者その他医師が必要と認める者を二次健康診断の対象とする」
とありますが、この「異常が認められる者」の定義が明確に数値化されていません。
したがって、実際の一次選別基準は「医師(産業医)の判断」に委ねられており、判定の一貫性を確保するためには、事業場単位で実務基準をあらかじめ設定しておくことが重要です。
2. 騒音性難聴の典型的特徴(医学的知見)
ご指摘のとおり、騒音性難聴は以下の特徴をもちます。
項目→特徴
発症様式→原則として両側性・ほぼ対称性
障害部位→有毛細胞障害による感音難聴
周波数→4000Hz(C5-dip)に特徴的な聴力低下
進行→騒音曝露が続くと1000Hzなど低音域にも拡大
回復性→一般に不可逆性
したがって、「片耳のみ1000Hzで軽度異常」といったケースは、
むしろ伝音難聴や耳疾患(中耳炎・耳垢栓塞など)によるものである可能性が高く、
典型的な騒音性難聴とは区別されます。
3. 実務上の判定基準の目安(一般的運用)
実際の事業場では、以下のような実務運用基準を設けるのが一般的です。
・一次健診(選別聴力)で「異常」とする目安
周波数→判定基準→備考
1000Hz・4000Hzいずれかで→30dB超の聴力損失→ただし単独・片耳のみの軽度異常は要経過観察可
両耳4000Hzとも30dB超→典型的な騒音性変化の疑いあり → 二次健診対象
1000Hz・4000Hzいずれも正常だが、自覚症状(耳鳴・聴き取りにくさ)あり→医師の判断により対象可
片耳のみ異常(軽度)→原因を問診で確認。中耳疾患等が明らかなら経過観察扱い可
→ すなわち、「4000Hzで両耳に異常がある者」を原則対象とする運用は、
騒音性難聴の病態と一致しており、実務的にも非常に妥当です。
この運用は、厚労省ガイドラインの趣旨(“必要な者を医師が選別”)にも反しません。
4. 判定実務での具体的対応ステップ
聴力検査結果の確認
1000Hz・4000Hzともに30dBで判定。
両耳の対称性を確認
左右差が大きい場合(例:右40dB・左20dB)は、耳疾患の可能性を考慮。
問診・既往歴確認
耳疾患・突発性難聴・耳鳴・中耳炎歴などがあれば個別判断。
医師判定記録
「4000Hz両側異常」または「医師が必要と認める場合」に〇印。
→ 二次健診へ(オージオメトリなど精密検査)。
5. 二次健診の目的と範囲
二次健診では以下を実施します。
純音聴力検査(250〜8000Hz)
騒音曝露歴・業務内容の詳細聴取
耳鼻咽喉科専門医による診察
原因特定と就業上の措置判断
この結果、騒音曝露が主因と疑われる場合のみ「騒音性難聴」として事後措置対象(就業上配慮・作業環境改善)とします。
6. 実務上のおすすめ運用指針(まとめ)
区分→対応
4000Hz両耳30dB超→二次健診対象(標準)
4000Hz片耳のみ30dB超→医師判断(経過観察 or 二次)
1000Hzのみ異常(片側・軽度)→原則対象外(耳疾患の可能性)
自覚症状・訴えが強い場合→医師判断で対象可
両耳4000Hz+1000Hz異常→進行例として要精査(対象)
したがって、質問者様が示された
「選別聴力検査で4000Hzが両耳に異常のある者に二次健診を受けていただく」
という運用は、実務的にも医学的にも妥当であり、間違いではありません。
7. 参考文献・根拠資料
厚生労働省「騒音障害防止のためのガイドライン」(令和2年7月改訂)
労働安全衛生規則第458~460条
日本耳鼻咽喉科学会『騒音性難聴の診断基準』
井上雄一ほか「騒音性難聴の診断のポイント」耳鼻咽喉科臨床 120巻3号(2017)
J-STAGE論文(先生ご提示の文献)
8.結論(実務判断指針)
一次健診における二次健診対象者は、
「4000Hzで両耳に30dB以上の聴力低下が認められる者」を原則とし、
医師が必要と認める場合(片耳異常・強い自覚症状など)のみ例外的に追加する、
という運用が標準的かつ合理的です。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/10/06 19:06 ID:QA-0159234
相談者より
非常に詳しくご回答いただきありがとうございます。
検査を行う病院に1000Hzで両側有所見者に絞ることを提案したのですが、証拠となる書類を提出するよう要求されており、証拠がないのであれば、全員二次健診だと言われおりましたので、そのようなものをなかなか探し出すことができず、困っておりました。
ご回答いただいた内容を基に再度説明を行っていきたいと思います。
本当にありがとうございました。
投稿日:2025/10/07 12:00 ID:QA-0159245大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ガイドラインにもございますように、単に数値のみで判断されるのではなく、「耳科的既往歴、騒音業務歴、現在の騒音作業の内容、聴覚保護具の使用状況、自他覚症状等を参考にするとともに、さらに、生理的加齢変化、すなわち加齢性難聴の影響を考慮する必要がある」ものとされます。
従いまして、示された事案も含めまして、不安が有る場合には二次健診を勧められるべきといえます。
投稿日:2025/10/07 18:47 ID:QA-0159268
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
行政指導健診について [2021/03/09]
-
受け入れ出向者への健康診断 [2020/12/03]
-
雇い入れ健診の健診項目について この場合、会社指定以外の健診項目... [2021/08/03]
-
社員の健康診断について 定期健診と生活習慣病予防健診を受... [2025/02/24]
-
雇入れ健診(入社前)と定期健診について 弊社では定期健診を4月~翌年3月... [2018/04/19]
-
雇い入れ健診について 中途採用者を雇い入れする時、雇い... [2021/04/08]
-
定期健診結果後の2次健診時の勤怠について 表題の件、ご相談させて頂きます。... [2019/08/23]
-
出向者が帰任したときの特殊健診について 他社に出向していた方が帰任する時... [2020/10/06]
-
深夜業務健診について 深夜業務健診と人間ドックの受診時... [2024/08/06]
-
特定健診について [2021/04/28]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
法定健診のお知らせ
法令で定められた定期健診のお知らせ文例です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント