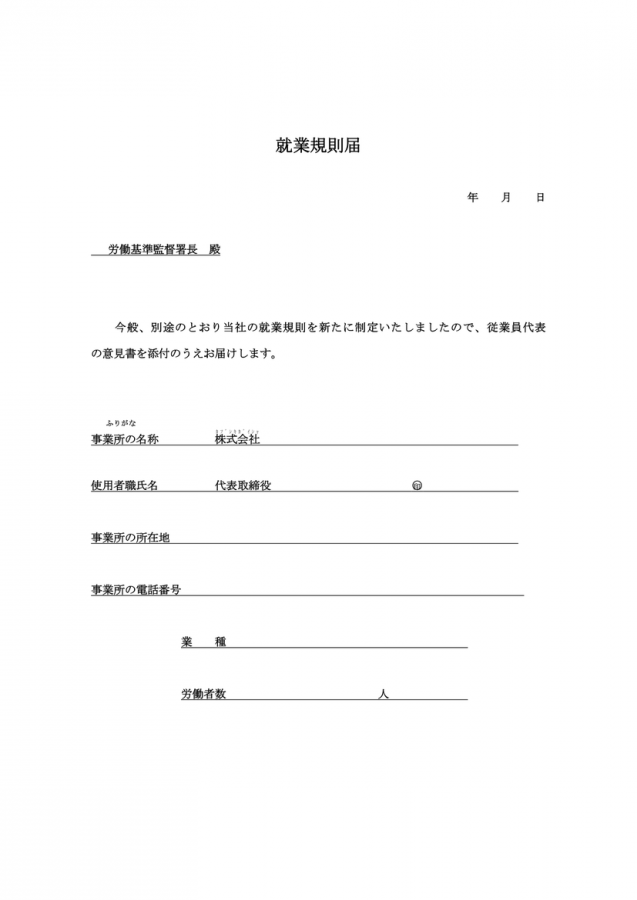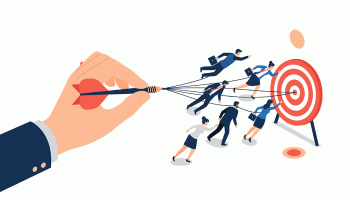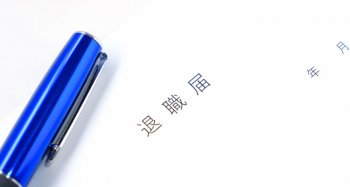退職届の効力と就業規則 どちらが優先か
お世話になっております。
・職員から月末付(例:3/31)の退職届の提出あり。
・就業規則に無断欠勤が 14 日以上続いた場合は、自己の都合による退職の意思表示があったものとみなし、退職の手続きを行なう旨記載があり。
上記の場合で、3月上旬から無断欠勤が続いた場合、
退職届の日付を生かす or 就業規則に則り無断欠勤14日以上の3月20日等で退職とする
のどちらで対応するのが望ましいでしょうか。
(現在ご本人と連絡が取れず、退職日の変更がお伝えし難い状況です。)
退職届と就業規則のどちらを生かすべきかご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/03/24 15:06 ID:QA-0125291
- ユウユウさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 5001~10000人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
退職届と就業規則
▼労基法第89条第3号に定める「退職に関する事項」は、就業規則の絶対的必要記載事項ですから、就業規則に必ず規定しなければなりません。
▼両者に軽重はありませんが、労基法に定めがあり、それを具体的に実現するのが就業規則の定めという関係あると思います。
投稿日:2023/03/24 17:34 ID:QA-0125307
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/04/06 21:42 ID:QA-0125791参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
退職届の提出がいつだったかによります。
会社が無断欠勤による退職の通知を
出していないようであれば、
本人の届出どおりにした方がトラブルのリスカ
はありません。
投稿日:2023/03/24 17:36 ID:QA-0125308
相談者より
退職届は2月の時点で提出されておりました。
会社は通知を出していないため、本人の申し出通り退職といたしました。
ありがとうございました。
投稿日:2023/04/06 21:44 ID:QA-0125792大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
3月上旬から無断欠勤が続き、現時点においても本人と連絡が取れないという現状を考慮すれば、あえて、就業規則の規定を優先させる必要はございません。
後日のトラブルを少しでも軽減させるためにも、こういう社員にはいかに円満に退職をしてもらうかを優先して考えるべきです。
3月31日付けで本人自筆の退職届けが提出されているのであれば、その方向で処理するのが賢明です。
投稿日:2023/03/25 09:14 ID:QA-0125320
相談者より
後々のリスクの考慮はやはり、大事ですよね。ありがとうございました。
投稿日:2023/04/06 21:45 ID:QA-0125793大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、「みなし」とは法律用語であって、事実に優先する強い効力を有するものになります。
従いまして、当事案の場合も14日経過した時点で優先的に自動退職になるものといえるでしょう。
投稿日:2023/03/25 18:44 ID:QA-0125331
相談者より
「みなし」についても大変勉強になりました。ありがとうございました。
投稿日:2023/04/06 21:45 ID:QA-0125794大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
本来なら早く対応してきた方が優先なので、就業規則だと思いますが、
>どちらを生かすべきか
という、人事視点であれば、なるべく揉めずに速やかに処理して形焼くするなら本人希望通りの退職だと思います。
投稿日:2023/03/27 11:03 ID:QA-0125342
相談者より
後々のリスクを鑑み、本人の申し出を尊重しました。ありがとうございました。
投稿日:2023/04/06 21:46 ID:QA-0125795大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
退職日前の退職金一部(または全部)支払について 3月末付で退職予定の従業員に対し... [2009/02/13]
-
退職日 当社は退職の申し出があった者に対... [2010/05/15]
-
64歳11ヶ月退職について 来年65歳になる社員から、失業保... [2025/10/17]
-
退職者の有給について パートで退職された方がいますが、... [2024/08/23]
-
退職者の有給 退職した社員の有給が残っていたの... [2025/12/15]
-
希望退職募集の場合の退職金 経営がかなり逼迫している状況で、... [2010/11/30]
-
64歳と65歳の失業給付金について 退職日を迷っておられる社員がいる... [2017/02/16]
-
退職率 よく退職率 何%と表示があります... [2006/11/24]
-
退職金の規定について 就業規則を作成するにあたり、2点... [2006/10/03]
-
定年退職時の退職金 定年退職時の退職金支給について... [2008/02/14]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
退職理由説明書
退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。
就業規則届
労働基準監督署に届出するための就業規則届です。是非ご利用ください。
退職証明書
従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。
退職承諾書
退職届を受理し、承諾の旨と今後の指示を記載した書類です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント