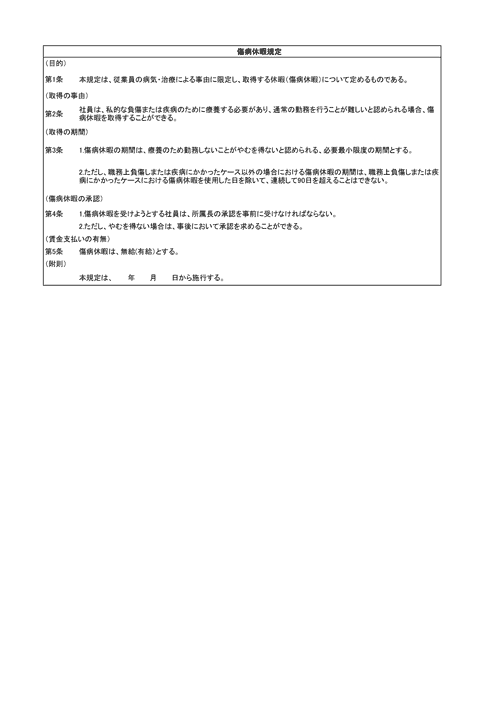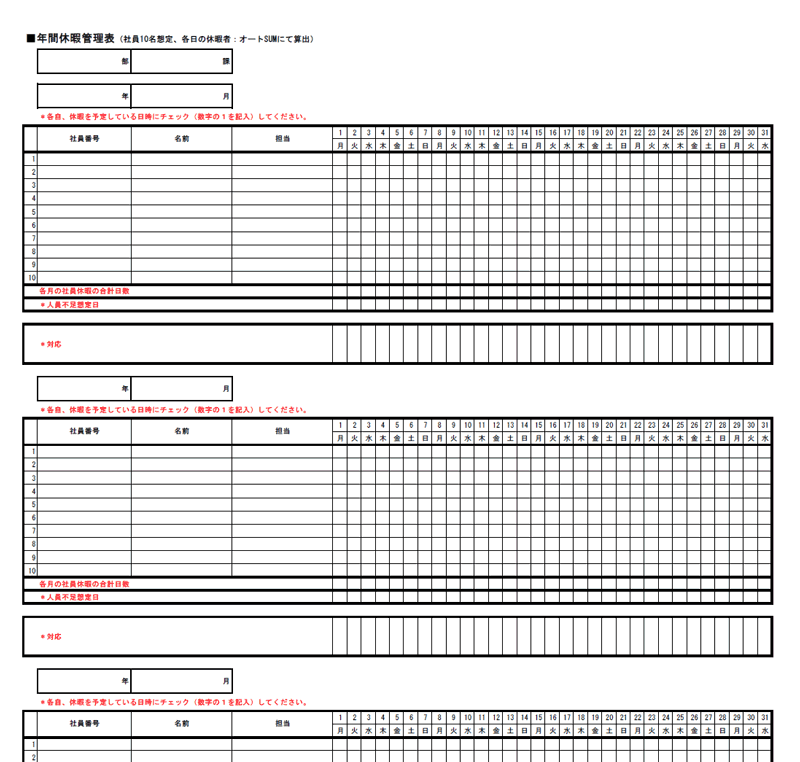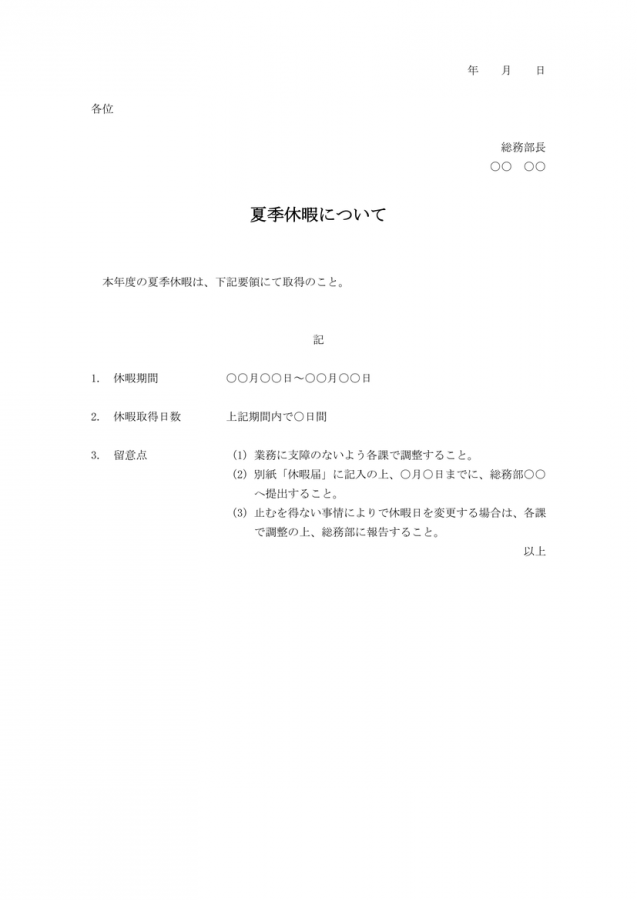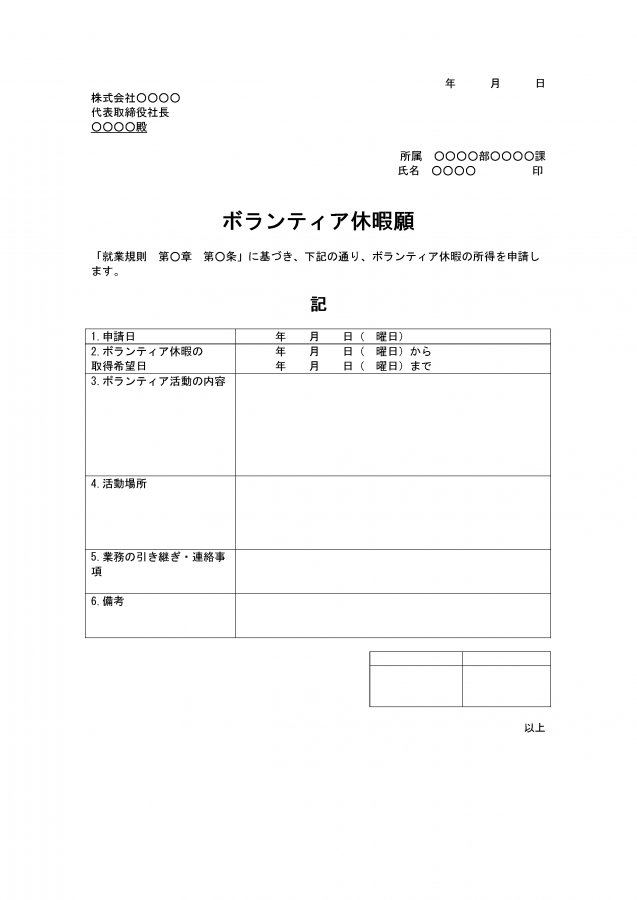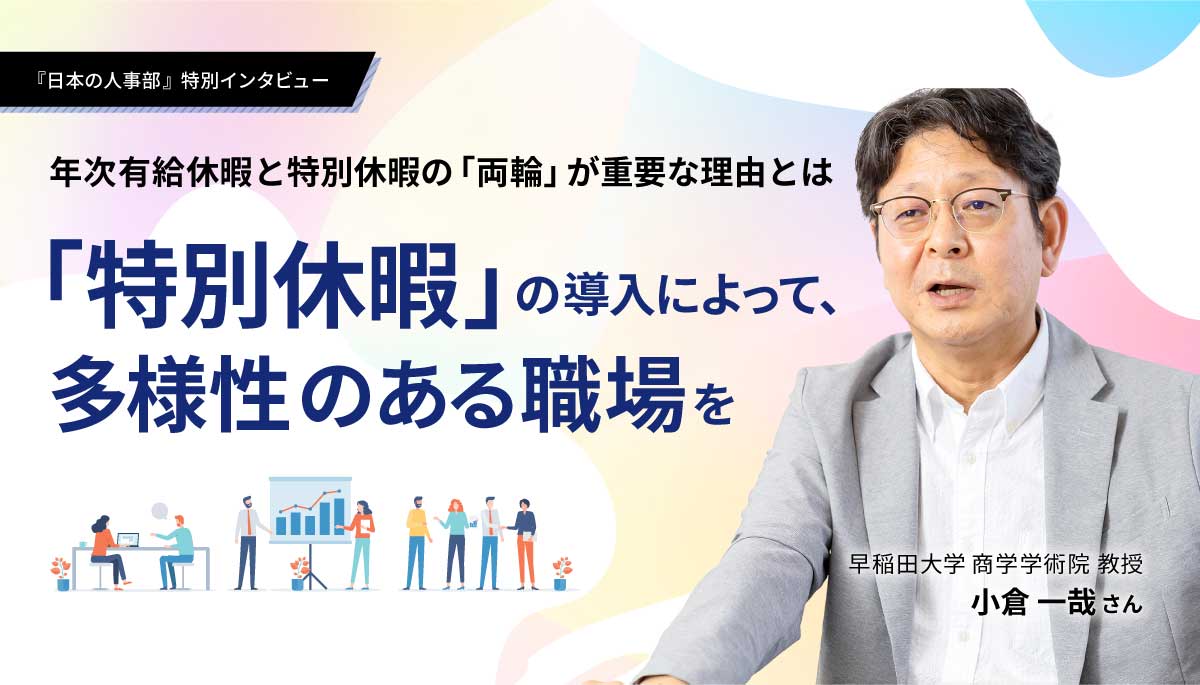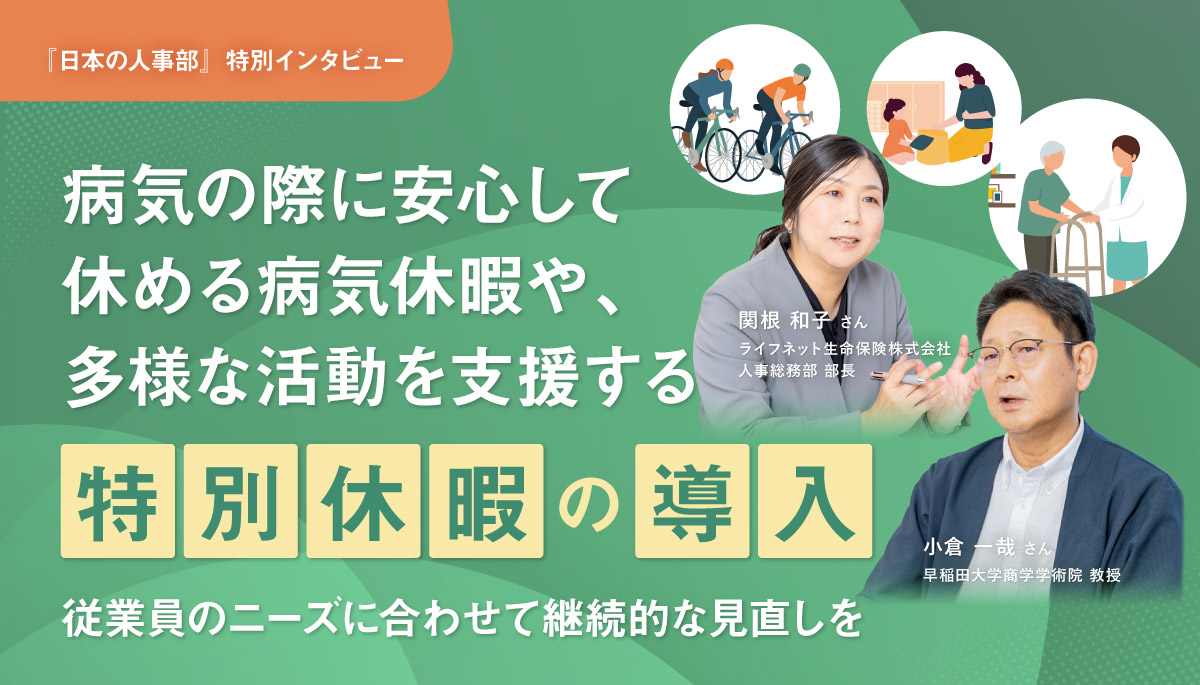養育両立支援休暇の申請書について
2025年10月1日から施行されます『育児期の柔軟な働き方を実現するための措置』の1つに『養育両立支援休暇の付与(10日以上/年)』がありますが、
こちらの申請書を作成するうえで、避けたほうが良い申告事由等はございますでしょうか。
できれば他の休暇と同様な書式で作成をしたいため、
お子さまのお名前や生年月日等を申請書の項目に含めたいです。
投稿日:2025/07/28 16:00 ID:QA-0155888
- nerianさん
- 神奈川県/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.養育両立支援休暇申請書の作成における留意点
・申告事由(理由欄)について:避けた方がよい表現
養育両立支援休暇は、法律上「育児との両立のために必要な休暇」とされていますが、理由をあまり詳細に書かせると私生活への過度な干渉と受け取られかねないため、以下のような記載は避ける方が望ましいです。
・避けた方がよい申告事由例:
「保育園でのトラブル対応のため」
「子どもが登園を嫌がって泣くため」
「育児ストレスが強いためメンタルの休息が必要」
「配偶者と喧嘩したため」など
これらは申請をためらわせたり、プライバシーの侵害と感じさせたりする恐れがあります。
2.推奨される表現(簡潔かつ柔らかく):
「育児との両立のため」
「育児支援のため」
「子の対応により勤務が困難なため」など
※可能であれば、「理由の記載は任意」とするか、「育児のため」にチェックを入れる選択式にすると、制度利用を促進しやすくなります。
3.お子さまの氏名や生年月日を記載することについて
こちらは制度の不正利用防止や対象者確認の観点から有効です。
以下のような項目は申請書に含めても差し支えありません:
子の氏名(漢字・ふりがな)
子の生年月日
続柄(例:長男・長女)
同居/別居の別(必要に応じて)
※ただし、扶養状況や健康状態など過度な個人情報は不要です。本人確認に必要な範囲にとどめるのが適切です。
書式の工夫例
【養育両立支援休暇申請書(例)】
項目名→内容
氏名→[記入欄]
所属部署→[記入欄]
申請日→[記入欄]
休暇希望日→[記入欄](例:○年○月○日)
休暇取得時間帯→[全日/午前/午後 など選択式]
利用理由→□ 育児のため(詳細記載不要)
対象児童氏名→[記入欄](ふりがな)
生年月日→[記入欄]
続柄→□ 長男 □ 長女 □ その他:______
上司承認欄→(印欄など)
4.補足:個人情報保護の観点
申請書に記載されたお子さまの情報は、目的外利用しないこと・適切に保管することが求められます(個人情報保護法の遵守)。
電子申請システムを利用する場合も、閲覧制限の設定等が必要です。
ご希望の形式に合わせて、他の休暇届と共通フォーマットにしつつ、「育児のための休暇」としての柔らかい申請様式にすることをお勧めします。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/07/28 17:42 ID:QA-0155897
相談者より
お忙しい中ご回答頂きありがとうございます。
過度な干渉を避ける表現に重きを置き書類の作成を進めていきます。
投稿日:2025/07/29 10:54 ID:QA-0155948大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
養育両立支援休暇は、あくまで子の養育に資する目的の休暇であり、
申請書の内容は 合理性をもって制度目的に合致すること・過度なプライバシー
収集を避けることが重要ですので、以下の内容は制度主旨から望ましくなく、
避けた方が良いでしょう。
・親等の記載
・同居の有無/扶養の有無
・診断書・証明書の添付欄
・家庭内の状況(家族構成、配偶者の勤務先等)
・証明としての写真やレシートなどのエビデンスの添付欄
以下は、適正な申請管理を目的として、問題ございません。
|お子さまのお名前や生年月日等を申請書の項目に含めたいです。
投稿日:2025/07/29 08:03 ID:QA-0155926
相談者より
お忙しい中ご対応いただきありがとうございます。
言葉の表現には十分注意し作成を進めていきます。
投稿日:2025/07/29 10:55 ID:QA-0155950大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、記載項目としまして必要性がないものは個人情報管理の観点からも省かれるべきといえます。
どうしても記載されたいという事でしたら、任意記入となる旨明記されるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2025/07/29 19:05 ID:QA-0155983
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
休日と休暇 休日と休暇の定義(違い)を詳しく... [2007/04/09]
-
特別休暇の申請について 追記 特別休暇についてですが、就業規則... [2019/10/31]
-
忌引休暇の扱い 当社では、従業員本人が喪主の場合... [2008/01/11]
-
裁判員制度と休暇 休暇中の賃金は、無給でよいか [2008/09/16]
-
忌引休暇について 忌引休暇の付与にあたり、叔母の配... [2009/02/04]
-
育児休暇一時金 来月から(第二子)産休に入る社員... [2005/07/04]
-
育児休暇中の年休は繰り越しできるか? 当団体では、消化できなかった年次... [2006/01/31]
-
赴任休暇と年次有給休暇 当社では夏季一斉休暇を労使協定で... [2011/07/22]
-
介護休暇・介護休業・育児休暇・育児休業の義務か否かについて ①介護休暇・介護休業・育児休業は... [2025/09/09]
-
産前期間中の年次有給休暇 年次有給休暇を使い切った後,産前... [2007/11/29]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント