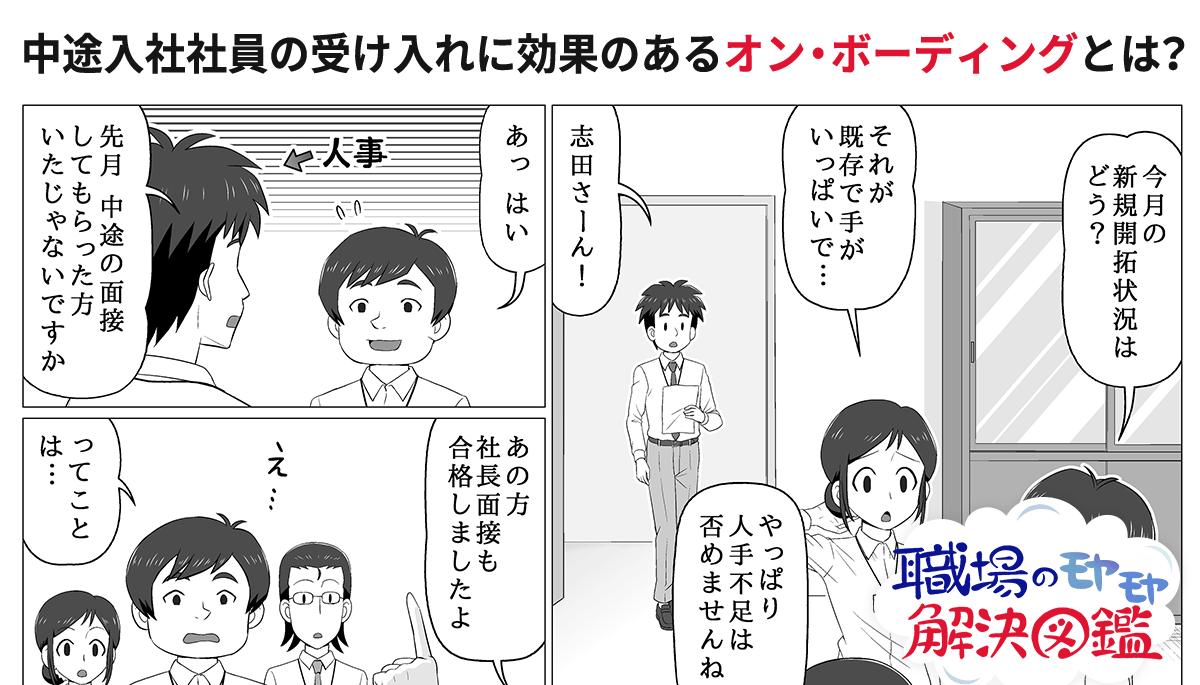新入社員に関する退職勧奨のご相談
2025年3月に入社した新入社員(中途)に関してご相談させていただきます。
お忙しいところ恐縮ですが、何卒ご確認のほどよろしくお願い申し上げます。
【ご相談内容】
① 「チームコミュニケーションスキルの著しい欠如」を理由とした退職勧奨は、法的・実務的に可能でしょうか?
可能な場合、会社のリスクを最小限に抑えるために、どのような手順を踏むのが最適でしょうか?
② 仮に「退職勧奨」が難しい場合、下記のようなケースに対して、他に有効な対応方法があれば、ご助言いただけますと幸いです。
【退職勧奨を検討している背景】
・該当社員は実務未経験であるため、誤った判断をする場面が多く見られる。しかし、上司(社長含む)や同僚がアドバイスしても、その指摘を受け入れず、自己流に固執する傾向がある。
結果として、合意形成に多くの時間を要するため、チームミーティング時間の延長、メンバーの疲弊など、業務進行に支障をきたしている。
・既に社長が決定し、メンバーに共有している方針に対しても、会議等の場で異議を唱えることがあり、チーム内に混乱が生じている。
・クライアントに対しても、「クライアントに対しても同様に主張する」と本人が発言しており、今後のクライアントとの信頼関係の毀損や業務への悪影響が懸念される。
・人事からは、これまで数回にわたり「チームコミュニケーションの取り方」について注意・相談を行ってまいりましたが、本人は「会社を良くするための行動である」「新入社員だから上の意見に従うのはおかしい」と主張し、「業務上の支障に起因する注意」にも納得を示していない。
・該当社員と同じチームになった複数の社員より、「言動・対応により精神的に疲弊する」「一緒には働けない」といった声が複数寄せられており、該当社員を含めたチーム編成が困難になっている。
・本人との面談において、「複数のメンバーから困りごとの相談が上がっている」と伝えた上で、「どのように改善できると考えるか」と問いかけても、自身の非は一切認めず、話し合いが平行線。
・社長との1対1の面談でも、働き方に関する改善要求をしているが、改善の余地がない
投稿日:2025/07/10 00:47 ID:QA-0155179
- ふくこさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
ご相談の内容は、非常に繊細かつ重要な労務問題であり、企業として慎重な対応が求められます。以下、法的観点と実務的観点から順を追って整理いたします。
1.「チームコミュニケーションスキルの著しい欠如」を理由とした退職勧奨について
法的に可能か?
→退職勧奨自体は法的に認められている手段です。ただし、次の点を遵守しないと「違法な退職強要」として、後にトラブルになる可能性があります。
(1) 退職勧奨の法的ポイント
本人の自由意思に基づく退職であることが絶対条件
威圧的・執拗・継続的な勧奨は「違法な強要」に該当する可能性あり(例:何度も呼び出し、断っても話を続けるなど)
勧奨の理由はできるだけ具体的・客観的に整理することが重要
実務的なリスクとポイント
「能力不足=即退職」は困難:コミュニケーションスキルは数値化しづらく、「客観的な基準」が必要
本件のように、指導歴があり、他の社員のメンタルにも影響が出ている場合、「配置転換」「育成計画の提示」「指導記録の蓄積」などを経て、「改善が見込めない」と合理的に説明できる土台を作る必要があります
(2) 退職勧奨を行う場合の最適な手順
事実の整理と記録
業務支障の具体例、会議での発言記録、他社員からの相談・苦情(可能であれば書面)
人事・社長との面談内容の記録(本人の発言を含めて)
改善のための指導歴を整理
いつ、どのような内容で注意・指導を行ったか
改善の機会を与えたか(指導書・育成計画の提示)
改善の余地がない旨を文書化
本人が指導に納得せず、改善の意思も示さなかった旨
他社員の精神的負荷やチーム維持の困難性も資料化
退職勧奨の面談
「退職せざるを得ない」とするのではなく、事実を丁寧に説明し、本人の選択肢として「退職」という道を示す
話し合いは1~2回にとどめる(執拗な継続はリスク)
同席者(人事、メモ係)を置く
合意退職合意書の締結
トラブル防止のため、合意退職書に署名をもらう(退職理由は「一身上の都合」など)
2.退職勧奨が難しい場合の対応方法(代替案)
(1) 配置転換・職種変更
チーム業務が困難であれば、個別作業が中心の部門や、対人関係の比重が低い部署への異動も検討
「能力に応じた配置」は企業の裁量に含まれるが、就業規則や雇用契約上の配慮が必要
(2) 業務指導計画の策定と「指導記録」の蓄積
「業務能力や協調性の改善計画」を明示し、進捗確認を定期実施
本人の否定的な発言や改善の拒否も記録に残す
こうした蓄積が将来的に**解雇(普通解雇)**を検討する際の判断材料に
(3) 就業規則に基づく懲戒処分の検討(要慎重)
業務命令違反や企業秩序違反とみなされる言動が明確に存在する場合は、戒告やけん責等の軽処分を段階的に行うことも可能
ただし、「異議を唱える行為」自体は正当な意見表明として保護される場合もあるため、行き過ぎた表現・迷惑行為・秩序の乱し方などに着目
3.補足:普通解雇の検討は時期尚早
現時点で「普通解雇」(勤務態度不良など)を検討するのは、かなりリスクが高いです。日本の判例上、能力不足やコミュニケーション不全を理由にした解雇は、よほどの記録と改善機会を与えた経緯がないと「解雇無効」とされるケースが多いためです。
4.まとめ
対応方法→実施可能性→注意点
退職勧奨→○(慎重に)→記録と事実に基づいた丁寧な進め方
配置転換→○ →配転命令の妥当性と業務上の必要性
指導記録→将来的検討→○→記録の継続と文書化が鍵
解雇(普通・懲戒)→△(現時点では非推奨)→高リスク。正当性の立証が難しい
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/07/10 09:00 ID:QA-0155182
相談者より
詳細にご教示いただき心より感謝申し上げます。
ここ数日毎日のように他社員からの苦情が相次いでいるので、上長と相談の上、早速対応を進めてまいりたいと思います。本当にありがとうございました。
投稿日:2025/07/10 09:49 ID:QA-0155186大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
企業秩序は、企業の存立と事業の円滑な運営の維持のために必要不可欠なものですので、企業は企業秩序を定立し維持する権限を有します。企業秩序を乱す言動については、就業規則の定めるところによって懲戒処分を行うことができます。懲戒処分を行ってもなお改善が無いようであれば、普通解雇又は懲戒解雇にすることになります。以下、退職勧奨に関して望ましいプロセスについてご説明いたします(当該新入社員の試用期間がすでに終了していることを前提とします)。
ご相談の事案に係る新入社員の言動は企業秩序・職場秩序を乱すものですので、まずは注意・指導を行って改善を促します。この点、「働き方に関する改善要求をしているが、改善の余地がない」とのことですので、口頭での注意・指導は行っているようですが、具体的な事実を示したうえでどのような点を改善すべきかを明示した書面による注意・指導はされていないことと推測いたします。最終的に退職(自己都合・解雇)という重大な結果が想定されますので、このタイミングで、将来的に争われることを想定して注意・指導・警告は具体的事実を明示した書面として証拠化します。
そこで、今後問題となる言動があった場合は、(過去の言動も含めて)問題となる言動の具体的事実を示した上で、改善を促すとともに、今後同様の言動を禁止する旨書面で注意・指示します。
それでも反省の態度を示さず、問題となる言動を繰り返す場合は、当該言動を明示したうえで、注意を聞き入れず業務上の指示に違反するものであるから、秩序を乱す言動が再び繰り返された場合は懲戒処分を検討せざるを得ない旨書面で注意・警告します。
そのうえで、やはり問題となる言動が繰り返された場合は、懲戒処分とします。
懲戒処分を行ってもなお、改善が見られないということであれば、再度同じプロセスを踏んで、一段階重い懲戒処分を検討せざるを得ない旨警告します。この時点で、「一度懲戒処分を行って反省を促したものの、貴殿に自らの言動を反省する態度が見られない。このままでは最終的に解雇も検討せざるを得ないことになる」と説明したうえで、退職勧奨するのが有効であると考えます。
退職勧奨に応じない場合は一段階重い懲戒処分とします。
その後も問題となる言動が繰り返されれば、いよいよ解雇を検討することになりますが、その段階で再度退職勧奨をします。退職勧奨に応じなければ普通解雇又は懲戒解雇することになります。
裁判所は、解雇に先立って指導をしたうえで改善の機会を十分に与えたかどうかを重視しますので、煩雑なプロセスではありますが、「急がば回れ」を実践いただくことをお勧めいたします(特にこのような協調性欠如の特徴を有する従業員は自己の正義を曲げない傾向がありますので退職勧奨には応じない可能性が高いと思われます)。
投稿日:2025/07/10 09:56 ID:QA-0155190
相談者より
貴重なご意見をいただきありがとうございます。参考にさせていただきながら進めてまいります。
投稿日:2025/07/10 21:13 ID:QA-0155235大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
退職勧奨の根拠となるのは、
就業規則の、服務規定、解雇規定、懲戒規定などです。
文面だけですと、
ご本人のポジション等不明ですし、
チームコミュニケーションスキルの著しい欠如とはありますが、
具体的な言動がわかりませんので、微妙な判断となります。
本人は自覚がなく。会社を良くするためと言っているようですので、
退職勧奨した場合には、トラブルに発展する可能性が大きいと思われます。
本人に注意、指導するにしても、
具体的に就業規則の〇条に抵触している、
具体的にどのように業務に支障が出ているのかを説明する必要があります。
また、注意、指導については、5W1Hでメモを残しておいてください。
投稿日:2025/07/10 10:08 ID:QA-0155194
相談者より
貴重なご意見をいただきありがとうございます。参考にさせていただきながら進めてまいります。
投稿日:2025/07/10 21:13 ID:QA-0155237大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
まず、退職勧奨は、解雇とは違い、あくまでも社員に対して自主的な退職を
促す行為であるため、法的には可能です。
ただし、強要・執拗な勧奨や、退職に応じなければ不利益を被るような言動
などがあれば違法となる(=退職強要)可能性があります。
言動に注意しながら、丁寧な対応が求められます。
また、退職勧奨に応じない場合、以下の対応策をご提示させていただきます。
↓ ↓ ↓
1)配置転換(所属異動)
人間関係による業務停滞が明らかであれば、個別作業中心の部署への異動が
適切です。配置転換は業務上必要性があれば、会社に一定の裁量が認められて
おりますので、法的リスクは抑えられます。
必要性については、コミュニケーションエラーの記録があれば、一定は、
立証できるものと思案いたします。記録は重要です。
2)コミュニケーション研修の受講指示
コミュニケーション力の改善を目的として、研修を受講させ、気付きの機会を
提供することも可能です。本人が受講を拒否する場合は、職務命令違反として、
今後の処分の根拠になります。
3)懲戒処分
他の社員の就業環境に支障を及ぼしている場合は、就業規則の協調性欠如や、
業務命令違反に基づき、けん責・減給など軽微な懲戒処分が検討可能です。
ただし、法的には懲戒解雇には極めて高いハードルがある為、あくまで改善を
促す目的で、段階的に処分を重くしていく対応が必要となります。
ステップを踏まず、急に解雇することは不当解雇に該当するものと思案します。
投稿日:2025/07/10 10:18 ID:QA-0155199
相談者より
貴重なご意見をいただきありがとうございます。参考にさせていただきながら進めてまいります。
投稿日:2025/07/10 21:13 ID:QA-0155238大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
理由がざっくりし過ぎていて、具体性がわかりづらいことが大きなリスクだと思います。
具体的に、いつ、どんな言動があり、それについて上長、人事、管理部門からどんな指摘と指導があり、それについて改善を誓約したにも関わらず、再三指示を無視していれば、懲戒処分が先です。
しかし指導しても本人が従わない、反抗的な態度に対して再指導しないなど、会社が適切な対応を取っていない、取った証拠(本人の署名入り改善誓約書など)がなければ、退職勧奨は危険だと思われます。
会社が裁判でも勝てるくらい、しっかり証拠と実績を固めて、その間にも懲戒処分が重なれば、解雇も可能になります。
投稿日:2025/07/10 11:12 ID:QA-0155201
相談者より
貴重なご意見をいただきありがとうございます。参考にさせていただきながら進めてまいります。
投稿日:2025/07/10 21:13 ID:QA-0155236大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。


 サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 調査
調査 人事辞典
人事辞典 イベント
イベント