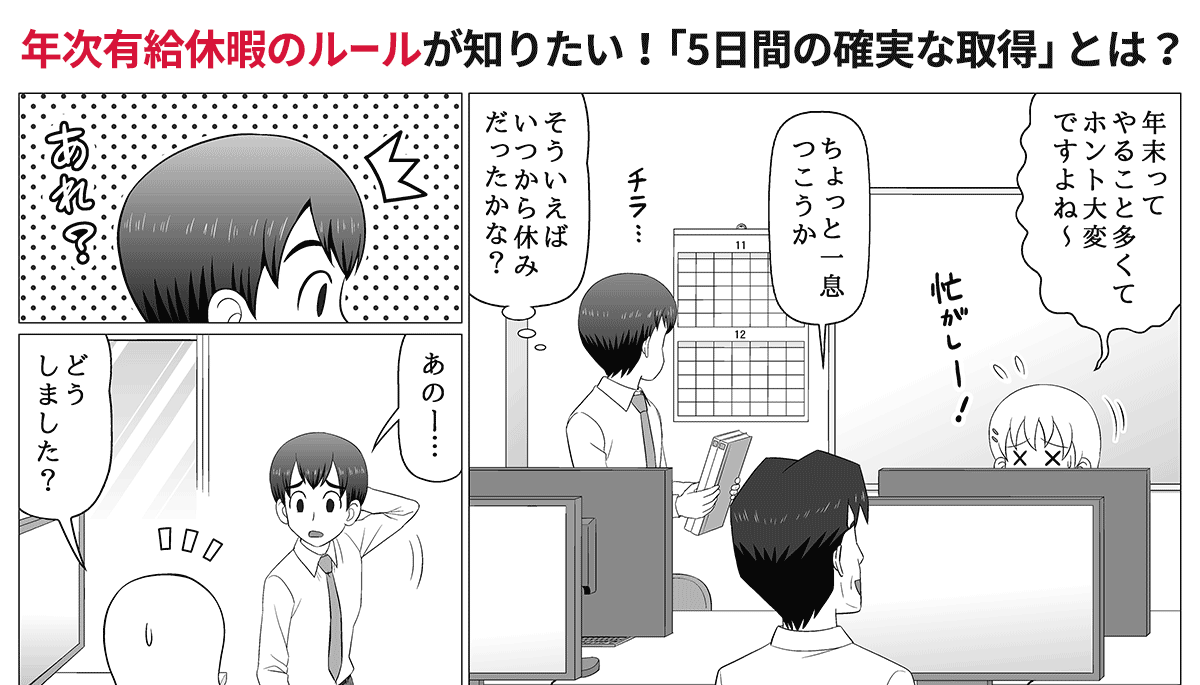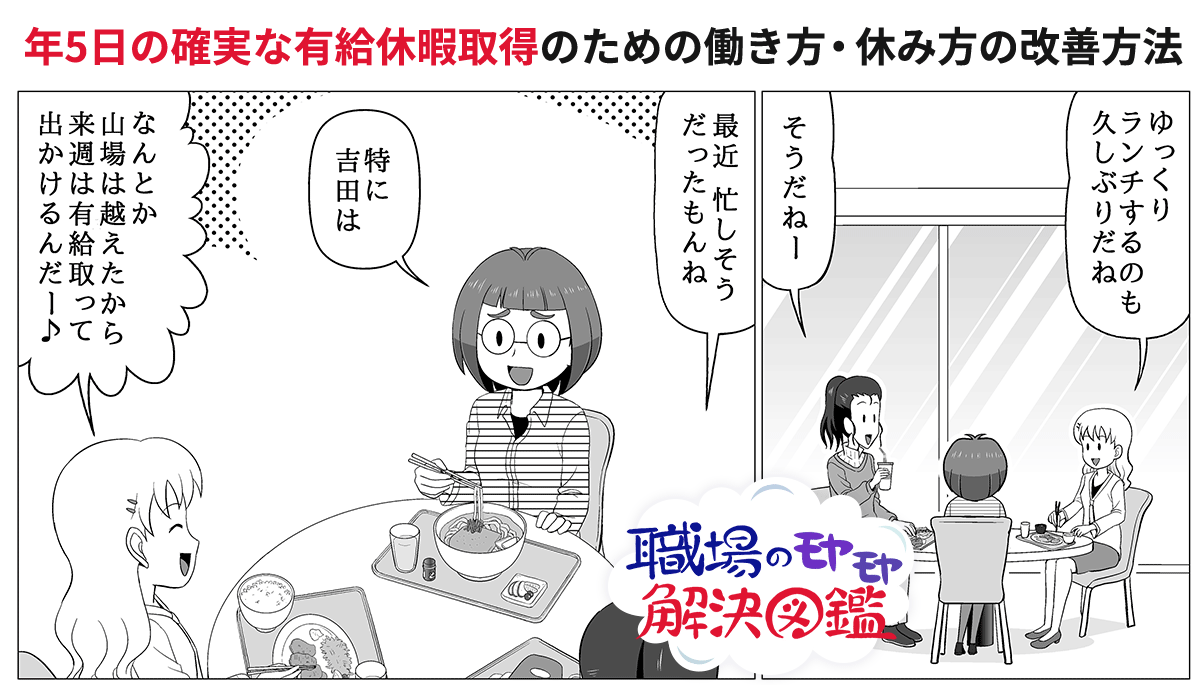有給休暇の年間消費日数について
弊社の場合、9/1に毎年一斉に年数に応じた付与を行います。
しかし、初年度に限っては10日以上2回に分けて付与される場合があります。
下記例を挙げさせていただきますが、このような場合は有給の年間消化義務数はどうなりますか?
■例
【2024/1/1に入社】
半年後の 2024/7/1→有給を10日取得
一斉付与時の2024/9/1→有給を11日取得
年21日取得
弊社の起算期間は毎年9/1~8/31となります。
この場合、2025/8/31までに有給は何日消化する形でアナウンスすればよろしいですか?
①付与日数に問わず、初年度も年5日以上消化
②月数÷12×5での按分計算
計算式:(14か月÷12)×5日=5.888888......
切り上げの「6日」を消化義務
①・②のどちらになるか、またはどちらでもない場合は、ご教示いただけますと幸いです。
投稿日:2025/07/01 17:54 ID:QA-0154753
- otamayaさん
- 東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 101~300人)
この相談を見た人はこちらも見ています
-
有給付与の件 4月1日入社の社員は、10月1日に有給が10日付与します。義務の有給は何日になりますか? [2021/09/07]
-
有給一斉取得にかかわる初年度の有給休暇付与について 4月1日に入社した場合10月1日に有給を10日付与しています。8月に一斉取得日として3日使用した場合、①10月1日の有給付与は、3日を差し引いて7日の付与... [2010/01/06]
-
有給付与について 有給付与についてなのですけど、7月21日が入社日なのですけど、毎年2月21日に有給付与されてるのですけでもしかして1月21日に付与の間違い?ですか? [2025/02/02]
-
有給消化中の有給付与について 2月になって退職を申し出てこられた契約社員の方がいらっしゃいます。1月31日の時点で年休残が20日残っていて、2月20日から有給消化を始めています。弊社は... [2013/02/27]
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
原則は1です。
例外として、就業規則に規定し、周知していれば、
2の按分付与でも可能ということになります。
投稿日:2025/07/01 19:40 ID:QA-0154759
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年休付与期間に重複が生じる場合には通算された期間に応じた日数を付与すればよいものとされています。
従いまして、2の方法で対応が可能です。
投稿日:2025/07/01 22:16 ID:QA-0154764
プロフェッショナルからの回答
期間重複
以下、回答させていただきます。
(1)2024/7/1と2024/9/1を基準日としてそれぞれ1年以内に5日の年次有給休暇
を取得させる必要があります。
(2)但し、管理を簡便にするため2024/7/1(はじめの基準日)から2025/8/31
(次の基準日から1年後)までの期間(14か月)に、6日以上の年次有給休暇を
取得させることも可能です(14÷12×5日=5.83)。
(ご参考)「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」
(厚生労働省)
9ページ目
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/content/000094019.pdf
投稿日:2025/07/01 23:07 ID:QA-0154770
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
御社のように「起算日:毎年9月1日」で年次有給休暇の付与・管理をしている場合でも、年5日取得義務は、労働者ごとの「有給休暇の付与日」から1年間で5日が基準になります。
つまり、
(1)の考え方:付与日数に関係なく、付与日から1年で5日消化が正解です。
(起算日である9/1~8/31ではなく、「直近の付与日から1年間」で判断します)
2.該当例での判断
ケース:2024/1/1入社
2024/7/1:初回付与(10日)
2024/9/1:2回目付与(11日) ← 一斉付与
→ この2回目の9/1付与を「基準」として扱います。
(なぜなら、上書きされて付与日がリセットされるため)
したがって、
「2024/9/1~2025/8/31」の1年間で、5日以上の有給取得が必要になります。
「7/1に付与された10日」については、その後2か月で「消滅」するわけではなく、
9/1付与で上書きされた11日と合算して「21日」ある状態と見なすこともあります(会社ルールによる)。
3.よくある誤解:(2)のような按分計算について
(2)の「14か月/12 × 5日=5.88日 → 切り上げ6日取得義務」という考え方は、法的には不要です。
この按分計算は、「管理簿の年間でまとめて管理したい」ときの便宜的な社内ルールとして一部の企業が独自に用いているものであり、法律上の取得義務には該当しません。
4,管理・アナウンス方法のポイント
御社のように一斉付与制度を採用していても、労働者ごとの「有給休暇の付与日」起算で5日取得義務が発生しますので、以下のようにアナウンス・管理されるとよいでしょう。
「あなたの有給休暇付与日は 2024年9月1日 です。これから 2025年8月31日 までに、有給休暇を 5日以上 取得してください。」
一斉管理用のシステムがある場合、「取得義務の基準日」を個別に紐づけておく。
5.まとめ
内容→回答
年5日の取得義務は?→個別の付与日から1年以内に5日(例:2024/9/1~2025/8/31)
初年度で按分する必要は?→不要。(2)は法的根拠なし
アナウンス時の注意→「直近の付与日から1年間」で案内
以上です。よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2025/07/02 01:25 ID:QA-0154774
相談者より
ご回答誠にありがとうございます。
2点程確認させていただきたく返信をさせていただきます。
(1)
>>>上書きされて付与日がリセットされるため
こちらは法的根拠はございますでしょうか?色々と調べてみたのですが中々該当箇所が見つからず・・・
(2)
>>>よくある誤解:(2)のような按分計算について
こちらについては労働基準法施行規則第二十四条の五‐2 に記載があると思うのですがいかがでしょうか。知識不足にてこちらの理解不足でしたら大変申し訳ございません。
以上 、度々の質問になり大変お手数ではございますが宜しくお願い致します。
投稿日:2025/07/08 12:10 ID:QA-0155092大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
先ず結論は、実務的には、ご質問者様記載の「2」の対応をとります。
1回目の付与は2024年7月1日におこなっているため、この日から1年以内に
有給を5日を取得させなければなりませんが、2回目の付与日を2024年9月1日
に本来の基準日よりも前に設定しているため、1回目と2回目に付与された有給
をそれぞれ5日取得させなければならない期間に重複期間が生まれています。
上記のケースに対する年休5日の取得義務の考え方は、以下の通りでOKと
通達されております。
1回目の基準日2024年7月1日から、2回目の基準日の2025年8月31日までの
14ヵ月間に、6日(14ヵ月÷12ヵ月×5日)の有給休暇を取得させる。
投稿日:2025/07/02 09:48 ID:QA-0154779
プロフェッショナルからの回答
ご相談内容について回答いたします
今回のケースは、入社から半年後(2024年7月)に10日間付与し、全社的に起算日を統一するために、次回の年次有給休暇の付与日(20249月)が入社時の付与日と異なることで、5日の指定義務がかかる1年間の期間に重複が生じる場合に当たるため、重複が生じるそれぞれの期間を通じた期間(前の期間の始期から後の期間の終期までの期間:今回で言えば、2024年7月〜2025年8月までの14カ月間)の長さに応じた日数(比例按分した日数)を当該期間に取得させることも認められるという、特例に該当するケースとなります。
従いまして、(2)の通り、 (14か月÷12)×5日=5.888888......を切り上げて、「6日」を取得させることになります。
投稿日:2025/07/03 08:45 ID:QA-0154843
プロフェッショナルからの回答
2回目のご質問
2点程確認させていただきたく返信をさせていただきます。
(1)
>>>上書きされて付与日がリセットされるため
こちらは法的根拠はございますでしょうか?色々と調べてみたのですが中々該当箇所が見つからず・・・
(2)
>>>よくある誤解:(2)のような按分計算について
こちらについては労働基準法施行規則第二十四条の五‐2 に記載があると思うのですがいかがでしょうか。知識不足にてこちらの理解不足でしたら大変申し訳ございません。
以上 、度々の質問になり大変お手数ではございますが宜しくお願い致します。
について、ご回答申し上げます。
改めてのご質問いただきまして、ありがとうございます。
本件についての考え方につきましては、説明させていただきました通りです。その上で、「法的根拠の有無」と「労働基準法施行規則第二十四条の五‐2 に記載があるか否か」につきましては、最終的には所轄の労働基準監督署の監督官の判断となります。よって、本件は、所轄の労働基準監督署の監督官にご質問されることをお勧め申し上げます。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/07/08 12:30 ID:QA-0155093
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2025/07/08 18:02 ID:QA-0155111大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
有給付与の件 4月1日入社の社員は、10月1日に有給が10日付与します。義務の有給は何日になりますか? [2021/09/07]
-
有給一斉取得にかかわる初年度の有給休暇付与について 4月1日に入社した場合10月1日に有給を10日付与しています。8月に一斉取得日として3日使用した場合、①10月1日の有給付与は、3日を差し引いて7日の付与... [2010/01/06]
-
有給付与について 有給付与についてなのですけど、7月21日が入社日なのですけど、毎年2月21日に有給付与されてるのですけでもしかして1月21日に付与の間違い?ですか? [2025/02/02]
-
有給消化中の有給付与について 2月になって退職を申し出てこられた契約社員の方がいらっしゃいます。1月31日の時点で年休残が20日残っていて、2月20日から有給消化を始めています。弊社は... [2013/02/27]
-
退職 有給が33日残ってます。会社が退職時に残ってる有給は買取になりますが、出勤日数以上の有給を1ヶ月で買いとる事はできるのですか? [2025/03/13]
-
産前産後期間中の有給一斉取得について 当社では8/15、16を有給一斉取得日に設定しております。今回、産前産後期間の中に有給一斉取得日が入る者がおります。この場合有給の2日分について支給するの... [2005/09/16]
-
退職者の有給 退職した社員の有給が残っていたのですが本人から申請されなかったのでそのままにしておいて良いでしょうか? [2025/12/15]
-
有給一斉取得時の給与に付いて 今年度有給一斉取得を4日実施しています。途中入社の方は、有給が無く一斉取得日にあたった場合、その分の給与は支給しないといけないのでしょうか。 [2006/01/16]
-
有給付与日前日に退職の場合、有給付与はされる? たとえば4/1に有給付与される場合とします。3/31で退職しようとしている場合、1年間の勤務タイミングで考えますと4/1に有給付与がされるのでしょうか?実... [2025/01/26]
-
有給の事項について 有給の事項についてお聞きしたいです。弊社は入社時に有給を10日付与しているのですが、その有給の事項は付与した時点(つまり入社日)から2年という考えで正しい... [2025/01/29]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント