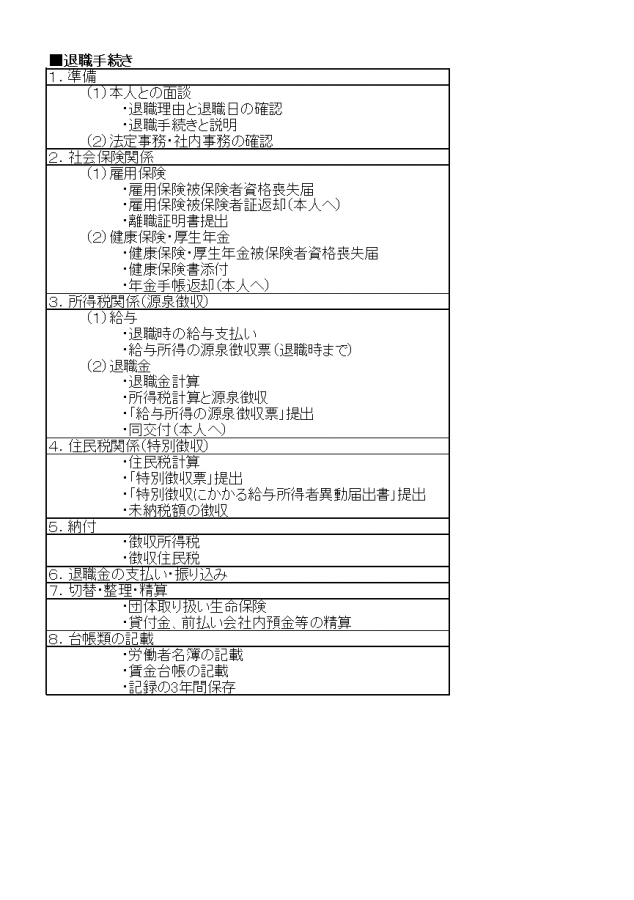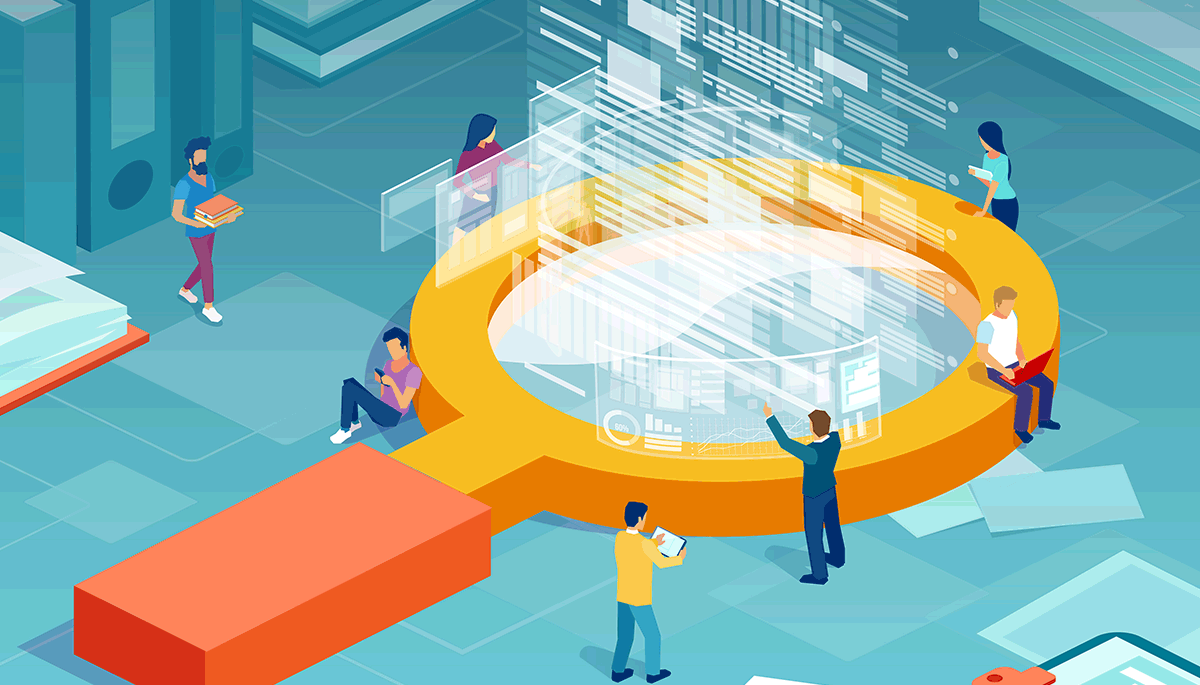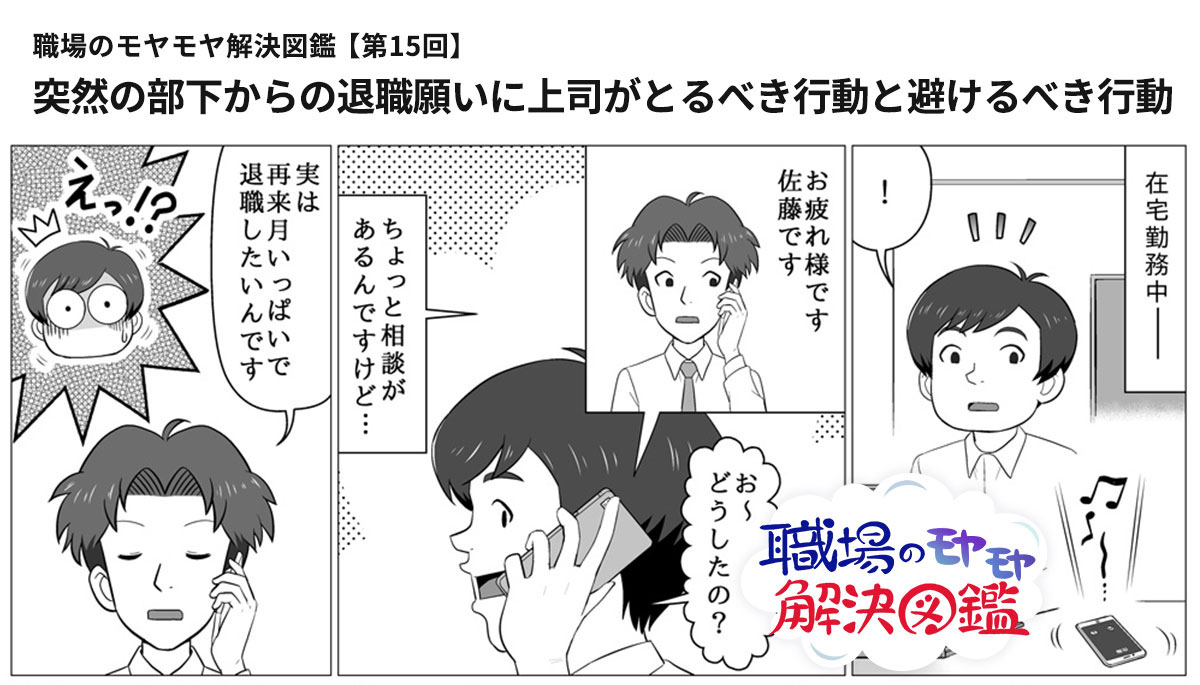退職予定者についての待遇について
退職予定者への社内の福利厚生についてご相談致します。
退職予定者について賞与などについては
就業規則に特別決まりがない場合、
賞与支払日に在籍している社員には退職予定者であっても賞与を支払う義務が生じるかと思います。
その他の会社独自の福利厚生についても
賞与同様在籍社員には平等に適用させなければならないのでしょうか?
福利厚生について例えば
社員のスキルアップを目的とした書籍購入費を補助する制度や
社員同士の交流の為の飲み会などにおいて飲食代の補助などです。
会社としては今後も会社で活躍する社員への投資の意味合いで
上記の様な福利厚生を設けており、
過去に退職直前に上記福利厚生を乱用した社員がいた為
予防策を検討したいと考えております。
ご回答の程宜しくお願い致します。
投稿日:2023/04/05 16:42 ID:QA-0125725
- あきおさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)
この相談を見た人はこちらも見ています
-
退職者の賞与分社会保険料について 先月弊社の従業員が、賞与の支払を受けた上で月中に退職致しました。ここで疑問なのですが、今回のように月中で退職の場合、当月分の社会保険料は発生しないと思われ... [2007/01/12]
-
退職日前の退職金一部(または全部)支払について 3月末付で退職予定の従業員に対し、通常は翌4月中に退職一時金の支払いをしておりますが、3月中の支払いができないかとの問い合わせがありました。退職所得として... [2009/02/13]
-
退職日 当社は退職の申し出があった者に対し、退職届(退職願)を提出させています。この際、退職日を確定するのですが、退職日は当社の営業日としています。1.これは合法... [2010/05/15]
-
64歳11ヶ月退職について 来年65歳になる社員から、失業保険を受給したいので65歳になる前に退職したいといわれました。誕生日が1/18なので退職日は1/16にしたいということですが... [2025/10/17]
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、福利厚生に関しましても、在籍されている以上当然に適用対象になります。
つまり、退職予定者であっても、それを理由に処遇の適用を除外される扱いについては、退職の自由を阻害する措置となりますので、原則認められないものといえます。
分かり易い例でいえば、退職直前に纏めて年休取得される場合がよく挙げられますが、福利厚生であれば、退職理由以外であれば当初から利用期間の範囲等を決める事も原則可能ですので、きちんと利用の詳細内容を定めておかれるべきといえるでしょう。
投稿日:2023/04/05 23:42 ID:QA-0125746
相談者より
ご回答頂きありがとうございます。
退職の自由にも配慮し、頂いた内容をご参考に社内検討させて頂きます。
投稿日:2023/04/07 13:11 ID:QA-0125806大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
乱用を予防するということでしたら、
事前申請で、上司の許可・承認が必要などとしておくべきでしょう。
投稿日:2023/04/06 09:44 ID:QA-0125757
相談者より
ご回答頂きありがとうございます。
上司の承認も視野に入れ、頂いた内容をご参考に社内検討させて頂きます。
投稿日:2023/04/07 13:11 ID:QA-0125807参考になった
プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
退職予定者に対する待遇
▼本来目的を逸脱した事例があったからと言って、折角、根付きつつある制度を廃止方向で検討するのは賢明ではありません。
▼かと、言って、相談事案の問題点を、具体的に知らずに、効果的な助言も難しい案件です。
▼会社の目が届き難い事案だけに、購入書籍、出席セミナー名、飲食代等の証憑類を、何方かが幹事として、取り仕切る仕組みが有効かと思われ得ます。
▼証憑類は、会社の損金処理にも必要です。
投稿日:2023/04/06 11:26 ID:QA-0125763
相談者より
ご回答頂きありがとうございます。
頂いた内容を参考に社内検討させて頂きます。
投稿日:2023/04/07 13:12 ID:QA-0125808大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
規定
退職予定者は対象としないとか、発効時点で在籍要件を課すなど、規定がない場合はすべての社員が対象になります。
対象から外すなら一刻も早く規定化して下さい。
投稿日:2023/04/06 13:15 ID:QA-0125766
相談者より
ご回答頂きありがとうございます。
頂いた内容を参考に急ぎ規定を社内検討させて頂きます。
投稿日:2023/04/07 13:13 ID:QA-0125809大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
退職予定者であっても、福利厚生については他の社員と差を設けることはできず、平等に扱わなければなりません。
退職直前に福利厚生を乱用した社員がいたため、その予防策を検討したいとのことですが、在先社員であっても乱用することもあり得るわけですから、予防策も全社員が対象でなければなりませんが、就業規則に福利厚生として規定している以上、それが労働条件を構成していますので、一定の制限を掛けるとなれば労働条件の不利益変更の問題も絡んできます。
そのため、予防策を検討するにあたっては、社員への丁寧な説明と同意を得ておく必要があります。
投稿日:2023/04/06 13:41 ID:QA-0125772
相談者より
ご回答頂きありがとうございます。
社員への説明も含め、頂いた内容を参考に社内検討させて頂きます。
投稿日:2023/04/07 13:14 ID:QA-0125810大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
退職者の賞与分社会保険料について 先月弊社の従業員が、賞与の支払を受けた上で月中に退職致しました。ここで疑問なのですが、今回のように月中で退職の場合、当月分の社会保険料は発生しないと思われ... [2007/01/12]
-
退職日前の退職金一部(または全部)支払について 3月末付で退職予定の従業員に対し、通常は翌4月中に退職一時金の支払いをしておりますが、3月中の支払いができないかとの問い合わせがありました。退職所得として... [2009/02/13]
-
退職日 当社は退職の申し出があった者に対し、退職届(退職願)を提出させています。この際、退職日を確定するのですが、退職日は当社の営業日としています。1.これは合法... [2010/05/15]
-
64歳11ヶ月退職について 来年65歳になる社員から、失業保険を受給したいので65歳になる前に退職したいといわれました。誕生日が1/18なので退職日は1/16にしたいということですが... [2025/10/17]
-
退職者の有給について パートで退職された方がいますが、有給が残ったままの状態です。退職は自己都合による退職で、有給は付与されたばかりのタイミングでの退職の申し出だったので、有給... [2024/08/23]
-
退職率 よく退職率 何%と表示がありますが、算出方法はどのように行うのでしょうか?単純に年度末の人員÷退職者数でいいのでしょうか? [2006/11/24]
-
64歳と65歳の失業給付金について 退職日を迷っておられる社員がいるのですが、64歳11か月で退職した場合と、65歳になってから退職した場合、雇用保険から受給できる失業給付金などの違いを教え... [2017/02/16]
-
退職者の有給 退職した社員の有給が残っていたのですが本人から申請されなかったのでそのままにしておいて良いでしょうか? [2025/12/15]
-
希望退職募集の場合の退職金 経営がかなり逼迫している状況で、希望退職を募る場合、退職金の上乗せはどれくらいが妥当でしょうか? [2010/11/30]
-
退職金の精算 現在ある退職金制度を今後、なくしてしまいたいと思いますが、まずもって可能なのでしょうか?現在の在籍者にはすでに退職金の受給権が発生しています。この退職金を... [2009/04/13]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント