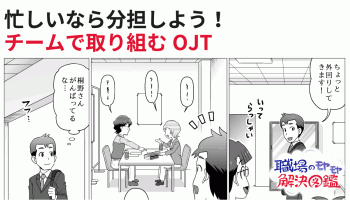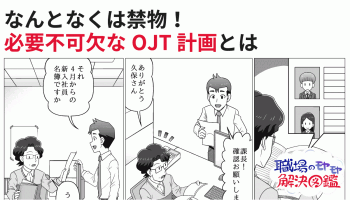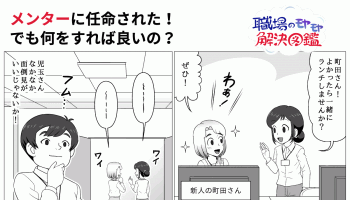人材育成の「仕組み」をつくり、「土壌」を耕す
「眼鏡市場」のメガネトップが注力する、人材育成の専門部門「教育部」
株式会社メガネトップ 人材開発本部 教育部・部長
舛井 達朗さん

「眼鏡市場」を展開し、「メガネのプロフェッショナル集団」として人々の生活を支える、株式会社メガネトップ。同社は長年にわたり、人材育成に並々ならぬ情熱を注ぎ、投資を続けてきました。象徴的なのが、人事部から独立した「教育部」の存在です。現場任せにしない、徹底した育成の「仕組み」は、新入社員の定着や早期戦力化をはじめ、全社員の成長につながっています。なぜ同社は、そこまで人材育成に注力しているのでしょうか。根底には、短期的な成果ではなく、会社の未来を創る「土壌づくり」という確固たる信念がありました。同社で14年にわたり教育に携わる、人材開発本部 教育部・部長の舛井達朗さんにお話をうかがいました。

- 舛井 達朗さん
- 株式会社メガネトップ 人材開発本部 教育部・部長
ますい・たつろう/2007年に株式会社メガネトップへ入社。「眼鏡市場」の店舗にて販売員、店長として現場の最前線を経験する。その後、社内公募制度を利用して教育部へ異動。以来14年間にわたり、人材育成の分野でキャリアを重ねる。現場経験を生かし、新入社員の定着率を劇的に向上させた「メンター制度」や、全社員の成長を可視化する「スキルチェックシート」の構築を主導。現在は教育部門の責任者として、未来の経営幹部候補の育成にも力を注いでいる。
技術と人間性を両立する育成哲学が「教育部」を生んだ
貴社が人事部から独立した「教育部」を14年も前から設置されている背景には、どのような哲学があるのでしょうか。
当社のパーパスは「お客様に最適なメガネを提供できる視生活のトータルアドバイザーであること」。これを実現するには、メガネに関する専門的な「技術」と、お客様に寄り添う「接客・ホスピタリティー」の双方を高い水準で両立させなければなりません。
メガネは、人々の生活の根底を支える大切なアイテムです。私たちには、お客様のあらゆる活動の基盤を支えているという自負があります。だからこそ、私たちの仕事は、医療的な側面を持つ専門知識や技術だけでは成り立ちません。顔の印象を大きく左右するファッションアイテムでもあるため、お客様に長期にわたって信頼していただくための「人間性」が不可欠です。技術とホスピタリティー、どちらか一方だけでは不十分なのです。
これらを実現するためには、各店舗での属人的なOJTに頼るのではなく、全社として体系的に人材を育成する機能が不可欠である、という経営判断のもと、教育部が設置されました。人事部ではなく、あえて「教育部」という独立した部署を置いていること自体が、会社からの強いメッセージだと捉えています。
教育部は、新入社員研修から店長研修、近年ではミドルシニア層のキャリア研修までを担い、人材の成長を支援し続ける役割を担っています。単なるスキル教育にとどまらず、社員一人ひとりが自ら学び成長できる風土づくりを推進しています。

「眼鏡市場」の店舗での接客には、高い技術とホスピタリティーが求められる
OJTとOff-JTの緻密な連携
育成の仕組みについてお聞かせください。
特に自信を持っているのが、新入社員向けのメンター制度、集合研修、スキルチェックシートの三つを連携させた育成の仕組みです。
仕組みが整う10年ほど前まで、育成は基本的に現場任せでした。店舗の都合が優先され、新入社員が半年や一年、店頭で声出しばかりしていて、専門スキルを学ぶ機会を得られないこともありました。昇格試験も受けられず、成長を実感できないまま、打ちひしがれて辞めていく社員も少なくありませんでした。
採用した大切な人材を確実に育て、定着させるために、約10年前にメンター制度を本格的に導入しました。選抜された先輩社員が新入社員一人ひとりにマンツーマンでつき、半年間にわたって業務指導とメンタル面のサポートを行います。
メンターは、単に業務スキルが高いだけでなく、人間性や後輩育成への意欲も重視して選抜。新入社員が相談しやすいように、比較的近い年齢の社員を選んでいます。加えて、メンター制度のもとで育った社員が、今度は次の世代のメンターになっていくという、育成文化の良い循環が生まれています。
メンターに任命された社員には、新入社員が配属される1ヵ月前に集合研修を実施し、育成計画や指導のポイントなどを共有します。「来月から新しい仲間が来る。半年間でこのように育てていくんだ」という心構えと具体的な計画を持って、入社日を迎えられる体制を整えているのです。
直近の実績では、2025年4月入社の新卒社員93人のうち、半年間での離職者はわずか一人でした。一般的な企業の離職率よりもかなり低いと思います。離職率の低さは、メンター制度というOJTと、教育部が実施するOff-JT(集合研修)が、単なる思いつきではなく「仕組み」として強固に連携しているからこそ生み出されたものだと考えています。
例えば、新入社員は入社後、まず静岡にある研修施設で5日間の集合研修を受けます。日常業務から完全に離れ、学びに集中し、仲間と切磋琢磨(せっさたくま)できる拠点として機能しています。一般的な貸し会議室での研修とは異なり、静岡県内にある寄宿舎で、研修期間中は寝食を共にします。
現代の若い世代の中には、そうした環境を窮屈に感じる人もいるかもしれません。しかし私たちは、あえてその時間と空間を共有することに大きな価値があると考えています。日中の研修時間だけでなく、食事やその後の時間を通じて同期同士の横のつながりが深まり、強固な仲間意識が醸成されるからです。この関係性は、全国各地の店舗に配属された後も、互いを支え合う精神的なセーフティーネットとして機能します。
新入社員だけでなく、2年目、3年目の社員や、次期店長候補、現役の店長など、さまざまな階層の社員が研修で施設を利用します。日常から離れて自身と向き合い、マインドセットを整える重要な機会です。

静岡県内で集合研修を行う際に使用する寄宿舎
研修で基本的な知識やマインドを学んだ後、各店舗に配属されますが、配属の際にメンターと本人に「スキルチェックシート」を渡します。スキルチェックシートは、メガネのプロとして習得すべきスキルを約130項目にわたってリスト化したものです。「次の集合研修までの3ヵ月間で、この項目をここまでクリアしましょう」という明確な「宿題」を出すのです。
3ヵ月後、再び全員に集まってもらい、フォローアップ研修で「答え合わせ」をします。そこで新たな課題を見つけ、また次の3ヵ月間に向けた「宿題」を渡す。OJTとOff-JTの歯車をかみ合わせるサイクルを繰り返すことで、現場での育成が場当たり的になるのを防ぎ、全国どの店舗に配属されても、一定のペースと質で成長できる環境を整えています。新入社員にとっても、「次はあの研修がある」というイベントが控えていることが、日々の業務のモチベーションや会社へのつなぎ止めにもなっていると感じます。
北海道から九州まで、全国の社員を何度も静岡に集めるのは、正直なところ費用も時間もかかります。非効率に見えるかもしれません。しかし、私たちは「仕組み」への投資を惜しみません。投資こそが、社員の着実な成長とエンゲージメントの向上を実現し、結果として高い定着率につながっていると確信しています。
OJTとOff-JT連携の要である「スキルチェックシート」について、詳しくお聞かせください。
スキルチェックシートは中途入社も含めた全社員が対象です。シートがなかった頃は、「一人前になるには、何をどれくらいのスピードで習得すればいいのか」がわからず、育成の進ちょくはあいまいでした。シートが導入されたことで、接客、技術、商品知識、管理業務など、習得すべき項目が130にわたって具体的に明文化され、誰もが自身の成長段階を客観的に把握できるようになったのです。
まさしく成長の羅針盤のようなものです。私たちはシートを基に、「入社1ヵ月目にはまずこの10項目を」「2ヵ月目には次の23項目を」というように、標準的な習得ペースを示しています。一つひとつクリアしていくことで、社員は「自分は着実に階段を上れている」という成長実感を得やすくなります。
あいまいになりがちな部分をあきらめず、細かい項目までリスト化することにも注力しました。これにより、店長やメンターは指導の抜け漏れがなくなります。進ちょくが標準ペースから遅れている社員がいれば、個別のサポートが必要だというサインになります。個人の課題発見ツールとしても機能していて、単なるチェックリスト以上の価値を生んでいます。
専門性を高め、お客様への提案の幅を広げるための取り組みも行っています。その一つが「パーソナルカラーアナリスト」の育成です。
メガネは視力矯正器具であると同時に、ファッションアイテムでもあります。お客様一人ひとりの肌や髪の色、瞳の色に調和するフレームやレンズの色を提案することで、その方の魅力を最大限に引き出すお手伝いができます。お客様への提供価値を高めるための専門スキルとして位置づけ、全社的に育成を推進しています。現在では約1300人の社員が資格を有しており、どの店舗でも高いレベルの提案ができる体制を目指しています。パーソナルカラーアナリストの育成も、技術とホスピタリティーの両立という私たちの育成哲学を体現する取り組みです。
仕組みづくりにこそ見いだす、仕事のやりがい
これほど緻密なメンター制度やスキルチェックシートといった仕組みを構築・運用される中で、舛井さんご自身の仕事のやりがいは、14年のキャリアでどのように変化したのでしょうか。
教育部に来た当初は、研修の場で目の前の受講者の目の色が変わる瞬間に、大きなやりがいを感じていました。最初は少し後ろにのけぞるように話を聞いていた人が、ぐっと前のめりになって「もっと聞かせてほしい」という姿勢に変わる。後日、「舛井さんの話、現場で生きています」と声をかけてもらえる。直接的な反応が、何よりの喜びでした。
今日お話ししたメンター制度やスキルチェックシートは、私が実務者として悩みながら構築してきたものです。部長という立場になり、視座が変わった今、やりがいの種類も変化してきました。
目の前の一人の変化だけでなく、5000人という組織全体をどう動かしていくか。全従業員が当社のパーパスに向かって同じ方向を向き、成長していくためには、「仕組み」が不可欠です。私が心血を注いで作ってきた仕組みを通じて、多くの従業員が着実に成長し、「視生活のトータルアドバイザー」になっていく。そのプロセス全体を支え、会社の進化に貢献できることに、今は大きなやりがいを感じています。個人の成長を支援する喜びから、組織を進化させる仕組みを創る喜びへ。やりがいの中身が変化してきたように思います。
未来へ向けた「全員底上げ」から「選抜育成」への転換
これまでの仕組みづくりを踏まえ、今後の人材育成についてはどのような展望をお持ちでしょうか。
今後の展望は大きく二つあります。一つは、「学び方の選択肢」を増やすことです。コロナ禍をきっかけにオンライン研修という手法が発達しましたが、これまでの集合研修、オンライン研修に加え、第三の手法として社員がいつでもどこでも学べる「動画教材」の整備に力を入れていきたいと考えています。時間を拘束されることなく、社員一人ひとりの学びたいという意欲に応えられる環境を構築します。
特に、既存のeラーニングコンテンツではカバーできない、メガネの専門知識や技術に関する動画を「内製」することに注力しています。なぜなら、メガネのプロとしての専門スキルは、世の中のどこにも完成された教材はないからです。また、動画教材を作れる人材が社内に育つこと自体が、重要なナレッジの継承であり、組織能力の向上につながる「教育活動」だと考えています。
もう一つは、「全員の底上げ教育」に加え、「選抜教育」への投資を強化していくことです。お話ししてきたように、私たちは全社員の基礎能力を高める仕組みに注力してきました。土台が整った今、次のフェーズとして、将来の会社をけん引するリーダー候補を早期に選抜し、集中的に育成していく必要があると考えています。
具体的には、店長の上に立つブロック長といった次世代の経営幹部候補です。かつては「最近、生きがいいね」といったあいまいな理由で登用されることもありました。しかし、5000人規模の企業が持続的に成長していくためには、常に「ネクストバッターズサークルで素振りをしている人材」を計画的につくり出すことが不可欠です。
全員を対象とした底上げ教育という土壌づくりを継続しながら、同時に、会社の未来を担う人材を選び、助走させるための特別な育成プログラムに注力する。これが、私たちの次なる挑戦です。
人材育成とは繰り返し成果を生む「土壌づくり」
最後に、読者である人事・人材育成担当者へ、メッセージをお願いいたします。
教育成果の可視化は、私たちにとって永遠の命題であり、常に抱えているジレンマです。研修の成果をどう可視化し、説明するか。業績が上がっても教育の成果とは言いきれず、逆に業績が厳しくなると真っ先にコスト削減の対象になりやすい。本当に難しい問題です。
難しさと向き合う中で、私がたどり着いた一つの信念があります。人材育成とは「土壌づくり」そのものである、という信念です。
良い土を耕すのには時間がかかりますし、一日二日では見た目はほとんど変わりません。しかし、時間をかけて豊かになった土壌があってこそ、種が芽吹き、おいしい野菜や果物が実り、しかも一度だけでなく、繰り返し収穫できるようになります。人材育成の醍醐味(だいごみ)は、耕した土壌が次年度以降にも引き継がれていく点にあると思います。
一つひとつの研修は、すぐに目に見える成果、例えば売り上げアップといった「果実」には結びつかないかもしれません。しかし、私たちは土を耕しているのです。活動を通じて豊かになった「人材」という土壌は、会社の資産として残り続け、さまざまな場面で繰り返し成果を生み出す基盤となります。
私たちは、その場限りの華やかな「打ち上げ花火」に目を奪われることなく、地道に「土」を耕し続ける。その信念が何よりも重要だと考えています。
※記事中の写真はメガネトップ提供
(取材:2025年9月26日)
この記事を読んだ人におすすめ

人事・人材開発において、先進的な取り組みを行っている企業にインタビュー。さまざまな事例を通じて、これからの人事について考えます。
会員登録をすると、
最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント