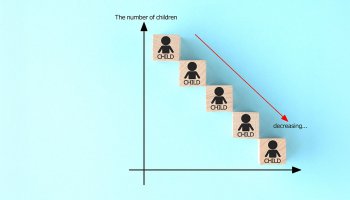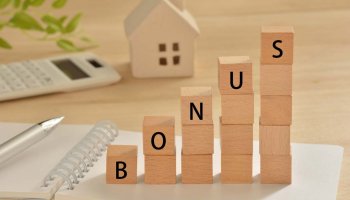-
テーマで探す
サービス
- サービス /人事の課題解決に役立つ各種ソリューションを紹介
- カテゴリ・課題から探す
- プロフェッショナルを探す
- HRソリューションの傾向と選び方
セミナー
資料
Q&A
記事
- 記事 /企業の事例や人事キーパーソンのインタビューからHRの最前線を学ぶ
- 注目の記事
- となりの人事部
- CHROの哲学
- キーパーソンが語る“人と組織”
- TOPインタビュー
- 職場のモヤモヤ解決図鑑
- オピニオンリーダーからの提言
- イベントレポート
- 編集部注目レポート
- 人事白書 調査レポート
- HR調査・研究 厳選記事
- HRソリューションの傾向と選び方
- プロフェッショナルコラム
- 人事基礎が学べる「3分ドリル」
- 研修体験ストーリー
ニュース
調査
人事辞典
イベント