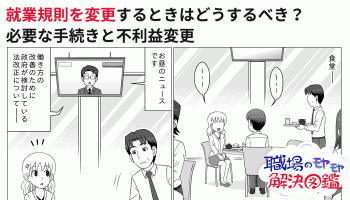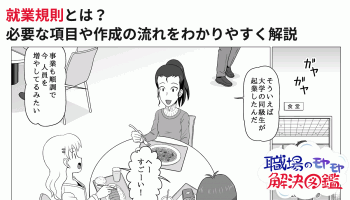今どきのサラリーマンはどれくらい残業している?「時間外労働」の長さでトップになった業種とは?
管理職ではないサラリーマンでも残業代をなくす制度を厚生労働省が検討しています。「賃金は労働時間の長さではなく、成果を中心に決められるべきだ」といった考え方が背景にあるようなのですが、その一方で、「それなりの仕事をしようとすれば時間がかかるはずだから、時間を基準に賃金を払うことにも一理ある」といった考え方の人も少なくありません。そのような議論のためには、まずは現在のサラリーマンの労働実態を把握しておく必要がありますが、では、今どきの会社員はどれくらいの時間、残業しているのでしょうか。業種によって残業の実態は異なるのか。「時間外労働」の事情について、労務行政研究所が行った調査から探ってみます。
陸運業の「時間外労働」は1人1カ月あたり30時間を超えている
まず、図表(1)をごらんください。これは、管理職を除いた社員(男女)が1カ月にどれくらい時間外労働をしているかを、企業の規模別に調べた結果です。
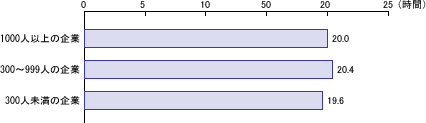
<注>対象は、2004年度の全社または本社における1人1ヶ月当たり平均値、管理職は除いて算出している。時間は十進法で示した。
1000人以上の企業では20.0時間、300~999人の企業は20.4時間、300人未満の企業では19.6時間となっています。これを見る限り、企業の規模が大きくなるほど時間が長いといった、はっきりした傾向は表れていません。全体の平均では、1カ月あたり20.1時間となっています。
ただ、これを業種別に見ていくと、時間外労働の長い業種とそれほどでもない業種があることがわかります。図表(2)をごらんください。
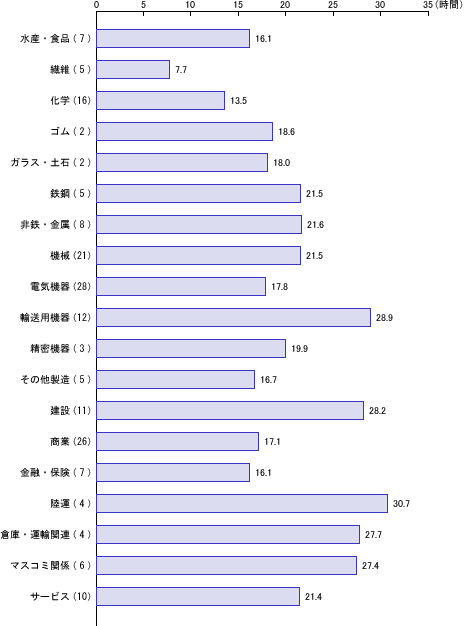
<注>全社または本社における1人1ヶ月当たり平均値。業種名の右の( )内は集計数。集計社数が1社の場合は掲載を省略した。
時間外労働の長い業種のトップは、陸運業。30.7時間と、ただ一つだけ30時間の大台を超えています。陸運業に続いて、輸送用機器28.9時間、建設28.2時間、倉庫・運輸関連27.7時間、マスコミ関連27.4時間となっており、輸送用機器以外は非製造業に集中していることがわかります。
工作物の建設や自動車の運転には「限度時間」の適用がない
労働基準法36条で規定する「36協定」では、時間外労働の限度基準が定められています(参考表)。
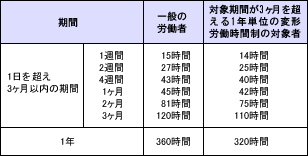
<注>限度時間は法定の労働時間を超えて延長することができる時間数を表すもので、休日労働は含まない。なお、「1日」の限度時間は特に定められていない。
しかし、この基準がすべての事業に適用されるわけではなく、以下の事業または業務については限度時間の適用はありません。
(1)工作物の建設等の事業
(2)自動車の運転の業務
(3)新技術、新商品等の研究開発の業務
(4)季節的要因等により事業活動もしくは業務量の変動が著しい事業または業務として厚生労働省労働基準局長が指定するもの
(5)公益上の必要により集中的な作業が必要とされる業務として厚生労働省労働基準局長が指定するもの
(ただし、(4)と(5)については、1年間の限度時間360時間は適用される)
とりわけ(1)と(2)について見れば、限度基準の適用を受けない陸運や建設などの業種が、図表(2)で示すように、時間外労働の長さで上位にランクされていることがわかります。
図表(2)で、業種によって偏りはあるものの、製造業・非製造業別に分けて、その時間外労働の平均を見ると、製造業が18.9時間、非製造業は22.0時間となりました。長時間労働の業種である陸運や建設などといった非製造業が、この平均時間数に影響を及ぼしています。
景気回復とともに2004年度の時間外労働は20時間以上に
では、時間外労働は数年前に比べて長くなっているのでしょうか。それとも短くなっているのでしょうか。図表(3)をごらんください。
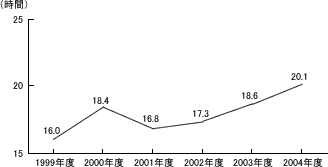
<注>2000年度までは全社、2001年度以降は全社または本社の男女計
年度により集計対象が異なるため、一概には比較できませんが、時間外労働は1999年度から2003年度までおおむね10時間台後半で推移しています。若干の増加傾向はうかがえるものの、大きな変動は見られません。
しかし、2004年度の時間外労働は20.1時間となり、13年ぶりに20時間を超えることになりました。これは、景気の持ち直しを反映するかたちで生産動向も上向いていることが背景にあると考えられます。
◆労政時報の詳細は、こちらをご覧ください → 「WEB労政時報」体験版
この記事を読んだ人におすすめ

人事の専門メディアやシンクタンクが発表した調査・研究の中から、いま人事として知っておきたい情報をピックアップしました。
会員登録をすると、
最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント