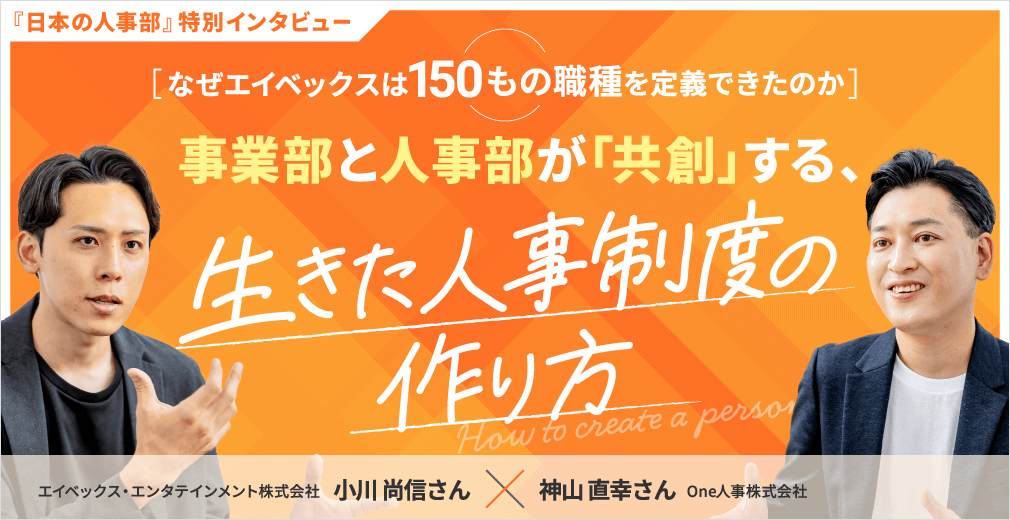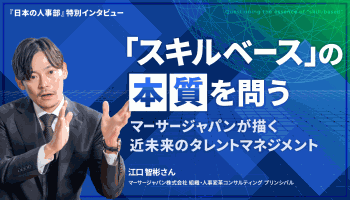企業の持続的成長において、人事部門の役割がますます重要になっています。一方で、「現場の実態に合わない」「作ったきりで形骸化している」といった人事制度の課題に直面している企業は少なくありません。そこで注目されるのが、エンタテインメント業界をけん引するエイベックスの取り組みです。同社は、グローバルな競争力の向上を目指し、大規模な人事制度改革を実行。その中心となっているのは、約150もの職種を定義したジョブ型人事制度や、従業員の自律的なキャリア形成を促す公募制度です。同社HRBPグループでゼネラルマネージャーを務める小川尚信さんに、One人事株式会社 神山直幸さんが、経営と現場、そして人事部門がいかに連携し、生きた制度を創り上げていったのかを聞きました。

- 小川 尚信さん
- エイベックス・エンタテインメント株式会社 事業戦略本部 HRBPグループ ゼネラルマネージャー
おがわ ひさのぶ/新卒でエイベックスに入社。営業を経験後、デジタル部門で音楽サブスクリプションサービスのローンチに携わる。2017年にCEO直下の新設部門でグループ全体の構造改革を推進し、人事制度設計や働き方改革、オフィスデザインなどを担当。現在は事業戦略本部で、人事全体の責任者とグループ各社のHRBP統括を担っている。

- 神山 直幸さん
- One人事株式会社 HRTech SaaS事業部 フィールドセールス3部 部長
かみやま なおゆき/前職、株式会社HRBrainでは営業責任者としてSaaS型タレントマネジメント領域にて100社超の導入を支援。経営層との対話を通じた課題特定と戦略設計を強みに、組織変革と人的資本経営の実装を推進。2025年、One人事株式会社に入社。フィールドセールス部にてエンタープライズ企業を中心に人・組織の成長を軸に価値創出をリードしている。
人事制度は経営ビジョンと共にある。多様な事業を成長させるための組織改革と人事部門の覚悟
神山:はじめに、エイベックスが人事制度の強化を行うに至った背景についてお聞かせください。「人」の重要性がますます高まる時代において、どのような課題意識をお持ちだったのでしょうか。
小川:もともと人事制度は、事業環境の変化に合わせてアップデートしていくべきものだと考えていました。その考えがより強固になったきっかけは、新たな経営計画である「avex vision 2027」を策定したことです。このビジョンでは、多様な地域や分野で愛されるIP(知的財産)を創出し、グローバルに展開していくことを基本戦略として掲げています。
この戦略を実現するためには、多様な人材が活躍できる環境と、グローバル企業と伍していくための競争力が不可欠です。その観点で当時の人事制度を評価したところ、ビジョンの実現に向けては、まだ改善の余地が大きいと感じたのです。当社経営陣も同様の課題意識を持っており、経営と人事部門が一体となって、より戦略的な制度改革へ本格的に取り組むことになりました。
神山:制度改革を進めるにあたり、まずは組織のあり方から見直されたと伺いました。
小川:はい。制度設計に着手する前提として、まず「人事部門自身が強くならなければならない」という考えがありました。当時のエイベックスは、持株会社であるエイベックス株式会社の下に各事業会社が連なる体制でした。事業が多岐にわたるため、どうしても意思決定のスピードが遅くなったり、各事業の個別事情に合わせた機動的な判断がしにくくなったりする側面があったのです。
そこで、より迅速な意思決定と事業責任の明確化を図ることを目的に、組織再編を行いました。持株会社の下に「音楽事業」「アニメ・映像事業」といった領域ごとの中間持株会社を設置し、権限を大幅に委譲したのです。そして、その各事業領域に寄り添う形で人事担当者、いわゆるHRBP(Human Resource Business Partner)を配置。各事業の戦略や文化に根差した人事施策を、より効果的に展開できる体制を構築しました。この組織改革こそが、後のジョブ型人事制度や公募制度といった具体的な施策の礎となっています。
150職種の定義は「人事部門だけで決めない」。事業責任者と膝詰めで生み出したジョブ型人事制度
神山:新たな体制の下で、具体的な人事施策として「ジョブ型人事制度」の導入を進めたのですね。制度に期待した効果はどのようなものだったのでしょうか。
小川:導入したジョブ型人事制度は、特に「仕事に対する報酬」と「仕事を通じたキャリア形成」に重点を置いています。最大の目的は、従業員一人ひとりが「どの職種で、どのようにキャリアを歩んでいきたいか」「どう成長したいか」を自分事として捉え、自律的にキャリアをデザインできる環境を整えることでした。自身の成長プランと会社の制度がしっかりと連動することで、仕事へのモチベーションが高まり、個々の能力が最大限に発揮される。そのような好循環を生み出すことが、制度に期待した効果です。

神山:ジョブ型人事制度の根幹となる職種の定義ですが、エイベックスでは150もの職種を定義されたと伺い、大変驚きました。この膨大な作業は、どのように進められたのでしょうか。
小川:かなりの労力がかかったことは事実です。このプロセスで私たちが最もこだわったのは、「人事部門だけで決めない」ということでした。
まず、社内にどのような職種が存在するのかを洗い出すことから始めましたが、当初は150どころではなく、さらに細分化された膨大な数の職種がリストアップされました。これらを一つひとつ精査し、類似するものを統合していく作業を、各事業の責任者である役員や部長クラスのメンバーと徹底的に議論しながら進めていきました。
職務の価値を客観的に評価するため、統一した基準で点数化する仕組みも導入しました。しかし、それだけでは現場の実態と乖離が生まれる可能性があります。そのため、点数化による序列をベースにしつつ、「業界の特殊性を鑑みると、この職種の価値はもっと高いはずだ」といった事業責任者からのリアルな意見を反映させ、微調整を繰り返しました。事業部と人事部が一体となって、まさに「共創」したからこそ、現場の納得感につながる職種定義が実現できたと考えています。
神山:報酬レンジの決定も大変な作業だったのではないでしょうか。
小川:はい。あらゆる業界の求人情報を徹底的に調査し、職種ごとの報酬水準を分析。外部の専門家から得られる情報も参考にしながら、自社の職種定義と照らし合わせ、一つひとつの報酬レンジを決定していきました。構想から含めると、制度の骨子が固まるまでに半年以上かかったと思います。
神山:現場の責任者を巻き込む上で、苦労された点はありましたか。
小川:事業責任者の皆さんは、当然ながら日々の事業運営で多忙です。人事制度という、普段あまり触れることのないテーマを理解し、議論に参加してもらうためには、相当な時間とエネルギーを要しました。それでもこのプロセスが不可欠だったのは、制度導入後に管理職以上の従業員が自分ごととして制度を理解していないと、制度は決して浸透しないからです。
私たちは、運用面においても、例えば部下のジョブグレードの変更といった重要な意思決定の権限を、事業責任者に大きく委譲しました。最終的には人事側でもきちんと判断し、事業と人事で決定するプロセスにはなりますが、従業員が自分たちで理解し、説明できなければ、適切な運用はできません。当事者意識が、皆さんの深いコミットメントにつながったのだと思います。導入後、部下から「なぜ私のジョブグレードはこれなのですか」といった厳しい質問を受け、大変な苦労をしたこともあると思いますが、その一つひとつに真摯(しんし)に向き合ってくれた管理職の皆さんには、本当に感謝しています。
制度の「透明性」が促す、真のキャリア自律とは
神山:ジョブ型人事制度と並行して、公募制度やFA制度も導入され、従業員のキャリアパスの選択肢を広げています。こちらの手応えはいかがでしょうか。
小川:非常にポジティブな反応が得られています。以前から、タレントマネジメントシステム上で自身のキャリア希望を表明する仕組みはありましたが、それが実際の異動に100%つながるものではありませんでした。公募制度という公式な仕組みができたことで、従業員が自らの意志でキャリアに挑戦できる道が、オープンに開かれたのです。
もちろん、課題もあります。人員が流出する側の部門にとっては、複雑な感情があることも事実です。また、会社として注力したい領域への人材配置という経営戦略と、個人のキャリア希望が必ずしも一致しない場面も出てきます。しかし、この制度の根幹は、あくまで「従業員のキャリアを最優先する」という思想です。その信念に基づけば、会社全体にとってプラスに働くと確信しています。

神山:制度の利用を促すために、特別な働きかけはされたのでしょうか。
小川:あえて大々的な利用促進キャンペーンなどは行いませんでした。まずは、従業員がこの制度をどのように受け止めるのか、自然な反応を見たかったからです。ただ、経営陣からは折に触れて、「自身のキャリアと向き合い、積極的にチャレンジしてほしい」というメッセージを発信し続けてもらいました。そうした土壌があったからこそ、自発的な応募につながっていったのだと思います。
神山:制度の透明性を非常に重視されている印象を受けます。職務要件定義書や報酬についても、かなりオープンにされているそうですね。
小川:はい。約150の全職種について、仕事の定義や求められる役割を記した職務要件定義書を作成し、社内のイントラネットで全従業員が閲覧できるようにしています。報酬についても、自身の職務におけるジョブグレードと、期待役割に応じた等級を組み合わせると、おおよその金額が計算できるような仕組みになっていて、その算出方法も開示しています。全てをオープンにすることが、フェアな制度運用の基盤になると考えているからです。
この透明性があったからこそ生まれた、象徴的な出来事がありました。公募制度を利用して異動した場合、職種によっては給与が現職より下がる可能性があります。ただ、さすがに給与を下げてまで応募する従業員はなかなかいないだろうと考えていました。しかし、実際に現れたのです。その従業員は、目の前の報酬が下がることを理解した上で、「それでも、この仕事がどうしてもやりたい」という強い意志を持って手を挙げてくれました。報酬だけではない、自身のキャリアに対する真摯な思いに触れ、深く感銘を受けました。これこそ、私たちが目指したキャリア自律の姿の一つです。
事業の最前線に立ち、経営と現場の「声」を翻訳するHRBPの役割
神山:制度を構築する上で、従業員の声を非常に大切にされていると感じます。どのようにして、現場のリアルな声を拾い、施策に反映させているのでしょうか。
小川:エイベックスはもともと、創業者のリーダーシップによるトップダウンの文化が強い会社でしたが、過去より現場の声を非常に大切にしています。また私を含め、事業部を経験してから人事部門に来たメンバーが多いこともあり、「仲間の声が重要だ」という意識が組織の根底にあります。
その声を拾う上で中心的な役割を担っているのが、先ほどお話ししたHRBPです。物理的にも事業部門の中で日々業務を遂行し、日々のプロジェクトに一緒に参加しています。会議で議論するだけでなく、共に仕事をする中で聞こえてくる「無言の声」や、ふとした瞬間に漏れる本音を拾い上げる。そうした一次情報こそが、本当に価値のあるインプットになります。
もちろん、寄せられる声の中には、単なる不満や要望も少なくありません。すべての声に等しく応えることは不可能です。そこでHRBPには、事業全体を俯瞰し、「この事業におけるキーパーソンは誰か」「どの意見が、事業の成長にとって本質的か」を見極めることが求められます。信頼するキーパーソンの意見を丁寧に拾い上げ、経営にフィードバックしていく。このプロセスが、施策の精度を高める上で極めて重要です。
神山:とはいえ、すべての従業員が制度をポジティブに受け入れるわけではないと思います。中には、変化に対してネガティブな感情を抱く方もいらっしゃるのではないでしょうか。
小川:おっしゃる通りです。特にジョブ型人事制度は、自身の仕事の価値が可視化されるため、ネガティブな感情を持つ従業員がいることも事実です。これは非常に難しい問題ですが、ある種の「えこひいき」も時には必要だと考えています。
個人的な感情で優遇するという意味ではありません。会社として「どこに資源を投下し、どの方向に進むべきか」という戦略に基づき、成長をけん引してくれる人材や、変化に前向きな人材を優先的にサポートしていく、という意味での「えこひいき」です。全員が100%満足する制度を作ることは、現実的には不可能です。会社としてどこに軸足を置くのか、その覚悟が問われているのだと思います。
幸いなことに、当社の従業員はエンタテインメントが好きで入社したメンバーが多く、エンゲージメントのベースが高い傾向にあります。その「好き」というエネルギーを、会社の成長ベクトルと一致させていくことが、人事部門の重要な役割です。会社の戦略の中でチャレンジする機会を豊富に提供し、その成長を後押しする。逆に、エンタテインメントへの魅力や仕事への想いを失ってしまった従業員に対しては、社内でのキャリアチェンジだけでなく、社外で新たな道を歩んでもらうことも含めて、真剣に向き合う必要があると考えています。

目指すは「夢のある会社」。結果を出した人材に、前例のない形で報いる人事部門の次なる一手
神山:最後に、小川さんが今後、人事部門として強化していきたいことや、ご自身の展望についてお聞かせください。
小川:短期的には、導入したジョブ型人事制度をさらに進化させていくことです。業界の状況や市場の報酬水準は常に変化します。その変化を敏感に捉え、競争力のある報酬制度を維持し続けるために、ドラスティックな見直しも躊躇なく行っていきたいと考えています。
そして、その先に見据えているのは、エンタテインメント企業らしく、「夢のある会社」を実現することです。会社に多大な貢献をし、素晴らしい結果を出した従業員に対して、既存の枠組みを遥かに超えるような形で報いたいのです。例えば、特定領域の第一人者であるエキスパート人材を認定し、特別な報酬体系を用意するなど、前例のない取り組みにも挑戦していきたい。個人の大きな成果が、青天井の報酬や登用につながる。そんな夢のある仕組みを構築することが、次の目標です。
神山:まさにエンタテインメントですね。
小川:ありがとうございます。もちろん、課題は山積しています。経営が描く理想と、現場の従業員の意識との間には、まだ乖離があることも事実です。事業が成長フェーズに入ると、ゆがみはさらに大きくなるかもしれません。そのギャップを埋めるために、人事部門のコミュニケーションは、まだまだ足りないと感じています。
人事の仕事に終わりはありません。事業責任者や従業員の声に耳を傾け、経営のパートナーとして、そして事業のパートナーとして、これからも変化を恐れずに挑戦を続けていきたいと思います。
神山:本日は、人事制度の設計から運用、そして未来の展望まで、示唆に富む貴重なお話をうかがうことができました。ありがとうございました。

One人事は、パーパス「すべての働く人を笑顔に。」を実現するため、人材管理から人材戦略までワンストップで企業の成長を支援する人事労務システム「One人事」を開発・提供しています。そのほか、公的機関向け人事DXソリューション「One人事[Public]」の開発・提供、受託開発・SESによるDX支援も展開し、民間・公共双方の人事DXを推進しています。

HRのトレンドと共に、HRソリューション企業が展開するさまざまサービスをご紹介。自社に最適なソリューションを見つけてください。
会員登録をすると、
最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント