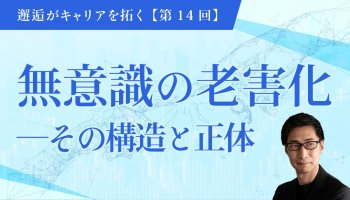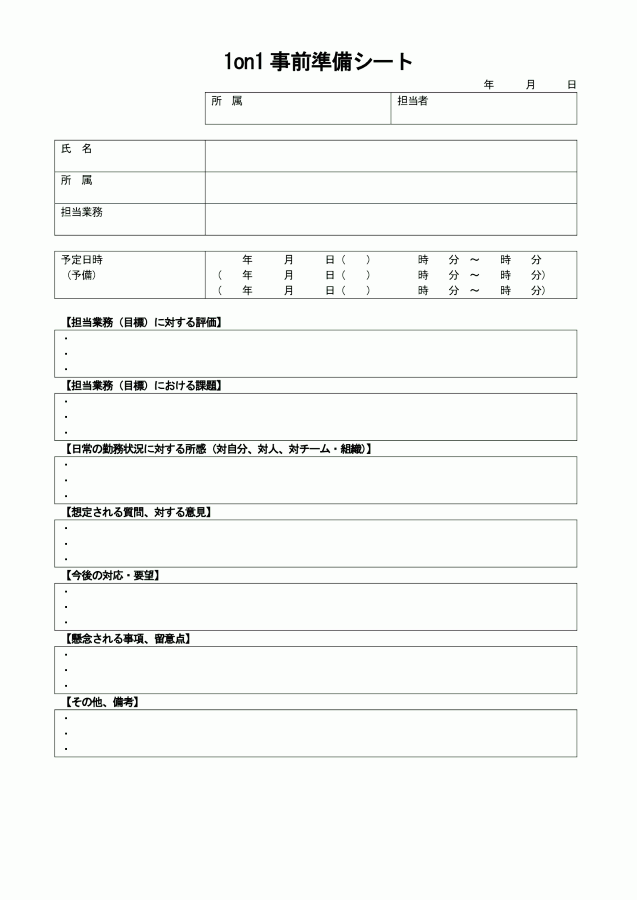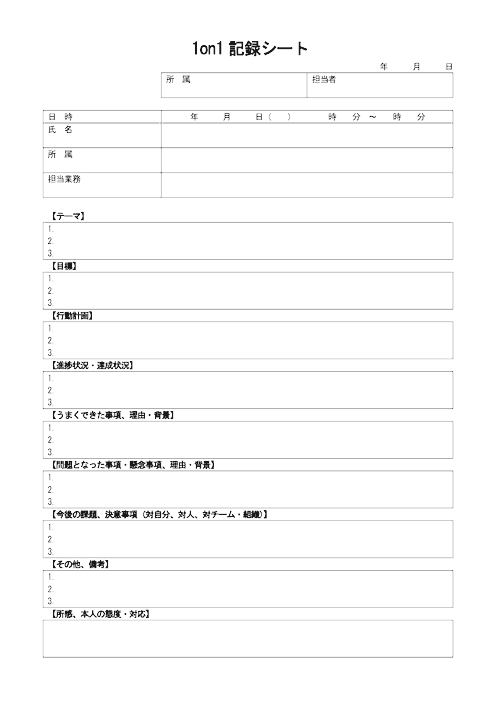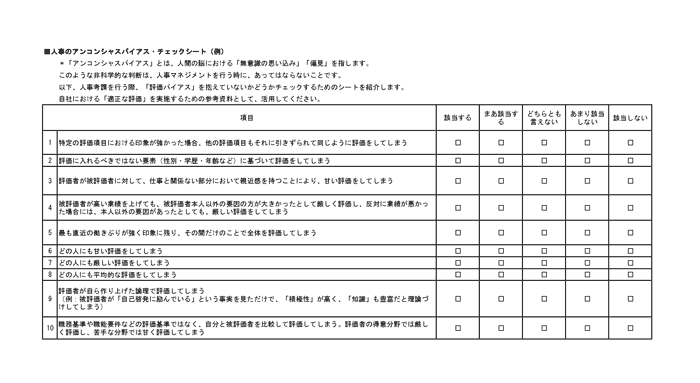フレーミング
フレーミングとは?
フレーミングとは、情報の提示方法(枠組み)によって、受け手の印象や判断が変わること。「枠組み効果」とも呼ばれ、行動経済学や認知心理学の理論に基づいています。同じ事実やデータであっても、プラス面(利益)を強調するか、マイナス面(損失)を強調するかで、受け手の反応は大きく異なります。たとえば、「成功率90%」と「失敗率10%」は同じ情報ですが、前者の方がポジティブな印象を与えやすいのはフレーミング効果によるものです。従業員の行動変容を促す場面において、フレーミングは大きな役割を果たします。
人事施策の納得感を強める
「ポジティブ」と「ネガティブ」フレーミングの使い分け
人事施策への理解と納得感を従業員に与える上で、フレーミングは必要不可欠です。フレーミングには、ポジティブとネガティブ、二つの側面があります。
新しい挑戦を促したい場面では、「挑戦すれば成功の見込みが70%ある」といった、利益を強調する「ポジティブフレーミング」が効果的です。失敗に対する恐れを軽減し、前向きな行動変容を促します。特に、従業員エンゲージメントの向上やワークライフバランスの改善など、従業員のメリットとなる施策を説明する際は、利益や期待できる未来を明確に伝えると、自発的な行動につながります。
一方、「ネガティブフレーミング」は、「この制度を導入しなければ、組織の生産性は20%低下するリスクがある」など、損失回避を訴求します。現状を変える緊急性を伝える際に効果的です。
フレーミングを活用する際は、情報の正確性を担保しつつ、誤解を招く表現を避ける必要があります。事実と異なる過度なフレーミングは、従業員からの信頼性を損ない、長期的なエンゲージメントの低下を招きかねません。
たとえば、給与制度を改定することで、昇給する従業員と減給となる従業員がいるとします。このとき、「平均で5%の昇給」というポジティブな数字だけを強調するフレーミングを用いれば、ネガティブな事実を隠しているという印象を抱かれ、後に大きな不満につながる可能性があります。
フレーミングを適切に活用するためには、事実をねじ曲げず、伝えたいメッセージに応じて、情報の提示方法を戦略的に使い分けることが重要です。
- 参考になった1
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,400以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。
会員登録をすると、
最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!
- 1
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 調査
調査 人事辞典
人事辞典 イベント
イベント