残業時間・ムダな労働時間削減、生産性向上のための
「時短マネジメントシステム」
時短コンサルタント・社会保険労務士
山本 昌幸
Ⅲ. 既存の時短対策では役に立たない
1. 小手先の時短対策
小手先の時短対策として
- 残業の許可制
- 午後●時に強制消灯
- ノー残業デーの創設 等々
これらの対策は導入当初効果が出る場合もありますが、時間経過とともに効果が半減~なくなり、ヒドイ場合には、
- 残業の許可制 → 無許可残業を実施
- 午後●時に強制消灯 → 消灯後に暗い中で作業実施
- ノー残業デーの創設 → 自宅に持ち帰り残業
これらいずれも、会社には申告しないいわゆる「サービス残業」となり、違法状態となります。
2. 「変形労働時間制」等の採用
確かに使用者側にとっては非常に都合の良い制度であり、残業代を抑えるためには是非導入すべき制度ですが、この制度を導入したところで労働時間は1秒たりとも削減できません。
3. 問題には原因がある
そもそも「事象には必ず根拠がある」のです。そして、問題には必ず原因があり、「残業時間発生=問題発生」ですから、「残業時間発生には必ず原因がある」のです。
この残業発生の原因(ムダな労働時間発生の原因)を突き止め、取り除いていかなくてはならないのです。
ちなみに、「三六協定」の“時間外労働(休日労働)をさせる必要のある具体的事由”欄をご覧ください。その欄には、
- 臨時の受注
- 納期の変更
- クレーム対応
というような記載があります。これらは突発的な理由であり、本来、この“突発的な理由”以外で残業や休日出勤させることは問題なのではないでしょうか。
Ⅳ. 時短マネジメントシステム全容
2014年5月号では「適正労働時間実現プロジェクト:時短マネジメントシステム」の流れとして次の図を掲載しました。
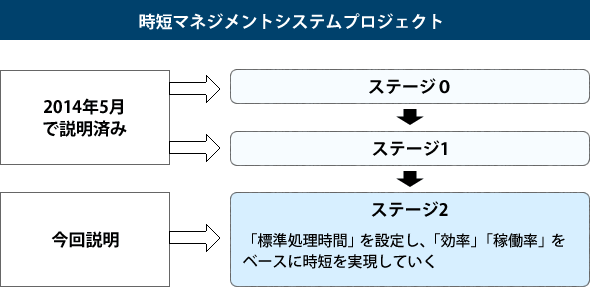
上図で「ステージ0」「ステージ1」の概要を前回すでに説明済みなので、今回はそのおさらいプラスαと「ステージ2」について説明します。
1. 全体像
「時短マネジメントシステムの全容」をご覧ください。
正直、本誌で全容を掲載すべきか迷ったのですが、昨年執筆の続編ということで掲載いたします。なぜ、掲載を迷ったのかというと、全容を鳥瞰することにより「難しいのでは?」と感じてしまう読者の方がいらっしゃると思ったからです。
ただ、多少聞き慣れない文言が記載されてはいますが(“内部監査”とか“マネジメントレビュー”)、内容的にご理解いただける内容です。
2. 成功のカギ

「時短マネジメントシステム」の導入成功の鍵は、何と言っても社長からの全面的なバックアップです。ただ、誤解していただきたくないのは、社長が自ら「時短マネジメントシステム」に取り組むわけではないということです。実際の活動は、プロジェクトチームを結成して進めていくのですが、そのプロジェクトチームとリーダーを全面的にバックアップしていただきたいのです。社長としてこのことが無理であれば、取組みは諦めてください。
以下、実際にプロジェクトに取り組んだ組織の実例を元に解説していきます。
Ⅴ. ステージ0(ゼロ)
1. 社長が覚悟を決め、「方針」の策定、掲示
取組みに先立ち、「方針」を策定したうえで、掲示等で社内に周知してください。同時に取組みの目的を認識・周知する必要があります。目的とは、「適正労働時間の実現」です。適正労働時間とは
- 作業効率=できるだけ高いレベル
- 稼働率=100%
- 妨害時間=できるだけゼロに近く
を実現することです。なおこの時点では具体的な数値目標は明確にできません。
2. 時短への取組みを社内に公表する
不退転の決意で時短への取組みを開始することを社長の台詞で社内に宣言します。
3. プロジェクトメンバーの募集
プロジェクトメンバーは社長自ら選んでもよいのですが、全員は選ばずに、あえて公募することをお勧めします。
また、当取組みは非常に有意義な管理者研修となりますから、そのことを意識したうえでメンバーを人選します。
4. プロジェクトチーム編成、リーダー任命
公募に対する応募者や社長の任命によるプロジェクトメンバーが編成できたら、プロジェクトリーダーを選任します。このプロジェクトリーダーは管理者層から選任します。筆者の関与先では次の要員をプロジェクトリーダーとして選任しました。
- 次期社長
- 次期経営層候補
- リーダーシップを発揮してほしい要員
ここで絶対に選任してはいけない事例として、「ヒマな要員」です。一般的に“デキル要員”ほど時間がありませんので、つい、ヒマな要員を任命しがちですが、この時点で社長の本気度が失墜するでしょう。
また、事務担当者も1名選任します。
5. プロジェクトチームへの事前教育
プロジェクトチームメンバー全員に事前教育を実施します。詳細は、本誌の2014年5月号をご覧ください。
6. プロジェクト遂行に対するリスク洗出し
ここでの“リスク”とは、残業の原因となっているリスクのことではなく、プロジェクト活動への妨害に対するリスクのことです。
当取組みは誰も異議を唱えられない正当な取組みですから(残業やムダ時間削減に異議は唱えられないですね)、表立って妨害はできないのです。だから厄介なのです。
筆者の関与先では次の妨害者がありました。
- 残業手当を減らされては困る従業員
- 自分の担当業務の処理方法を開示したくない従業員
これら従業員の妨害は発生する確率が高いことを意識してあらかじめ対策を施しておく必要があるでしょう。
7. 現状把握
残業時間発生の過去2年間をデータとして把握しなくてはなりません(過去2年にとらわれなくてもよい)。筆者の場合は、収集したデータを必要に応じて「パレート図」「ヒストグラム」により視覚化します。
実はこの現状把握実施の旨を社内周知するだけで、残業時間が削減できた事例がいくつもあります。ただ、これも結果的には小手先の手法であり一時的現象と理解すべきです。
8. 日常の運用管理策の策定
小手先の対策を日常の運用管理策としてPDCAに組み込んで実施します。ただ、あくまで“小手先の対策”ですから、効果は持続しない前提です。そして、「ステージ1」で目標策定後の実施計画に組み入れていきます。
9. 文書管理の仕組み造り、「就業規則」改定
マネジメントシステム監査業務を750回以上実施していると、システムがうまく回っている組織とそうでない組織の違いを明確に理解できるようになります。その違いの1つが「文書管理」です。
「文書管理」について説明しだすと1冊の本になってしまいますのでここでは割愛しますが、要は「必要な文書が必要な時に必要な場所で使用できるようにしておくこと」です。
「文書管理」は、仕組みを構築・運用するうえでの基礎ですから、頑丈な建物を築くべく基礎として「文書管理の仕組み」を策定しなくてはなりません。
10. 取組セレモニー
可能な限り、取引先や顧客を巻き込み、当取組みを本格的に開始する旨を宣言する(ステージ1に移行する)セレモニーを実施します。ただし、セレモニーはホテル等で豪華に実施する必要はなく、社内の会議室や作業場で十分です(取引先を招くとしても)。ホテル等で豪華にセレモニーを実施すること自体、時間とお金のムダですから。
この記事を読んだ人におすすめ

人事の専門メディアやシンクタンクが発表した調査・研究の中から、いま人事として知っておきたい情報をピックアップしました。
会員登録をすると、
最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント












