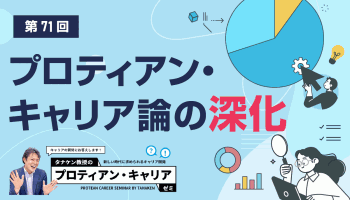タナケン教授の「プロティアン・キャリア」ゼミ【第67回】
キャリア開発理論の最新動向
法政大学 キャリアデザイン学部 教授
田中 研之輔さん
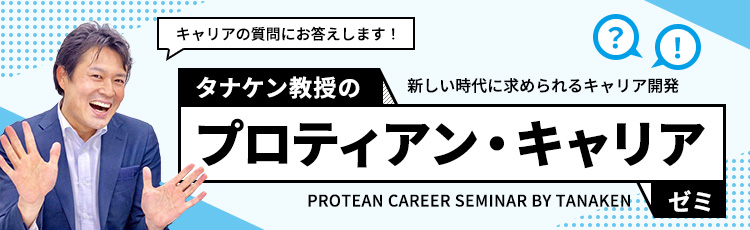
令和という新時代。かつてないほどに変化が求められる時代に、私たちはどこに向かって、いかに歩んでいけばいいのでしょうか。これからの<私>のキャリア形成と、人事という仕事で関わる<同僚たち>へのキャリア開発支援。このゼミでは、プロティアン・キャリア論をベースに、人生100年時代の「生き方と働き方」を戦略的にデザインしていきます。
タナケン教授があなたの悩みを解決します!
キャリア理論は段階的な発展を遂げてきました。19世紀末から20世紀初頭には特性因子理論(パーソンズやホーランドによる職業的適合性の理論)が主流で、「個人と職業のマッチング」に焦点が当てられていました。20世紀後半になるとキャリア発達理論(スーパーのライフスパン理論など)が台頭し、意思決定のプロセスや人生段階に沿ったキャリア発達に注目するようになります。
さらに21世紀に入り、働き方の流動化(ボーダーレスなキャリア時代)の中でキャリア構築理論(Career Construction Theory)が重視されるようになりました。この理論は職業的パーソナリティ(興味・価値観など)、キャリア適応力(変化に対処する力)、ライフテーマ(人生における意味)に焦点を当て、個人が物語を紡ぐようにキャリアを「構築」していくことを強調してきました。
理論は社会変化に応じて発展していきます。労働市場や働き方を取り巻く環境は急速に変化しており、キャリア開発理論もそれに応じて進化を遂げています。特にAI(人工知能)の台頭やDXによる労働市場と変化と新たな働き方への適応として主体的なキャリア形成の重要性が増しています。このような中、キャリア開発理論にも新たな視点が構築されつつあります。
本ゼミでは、このキャリア理論の系譜と発展を踏まえた上で、最先端のキャリア知見であるプロティアン・キャリアを理論的支柱に据えて解説を重ねてきました。最新のキャリア開発理論のトレンドは、これまでの伝統的モデルを土台にしつつ、不確実性への対応や生涯にわたる持続可能性、多様性と包摂、テクノロジーとの融合といった新たな要素を組み込む方向へと変化している点にあります。
キャリアは「物語」
キャリア構築理論は、Mark L. Savickasによって提唱された現代的パラダイムで、個人のキャリアを「物語」として捉え、人生の意味を見いだしながらキャリアをデザインしていくアプローチです。この理論はキャリアカウンセリング実践に広く取り入れられており、「私のキャリア・ストーリー」やキャリア構築インタビューといった質的ツールを用いて、クライエントが自己概念を物語るプロセスを支援します。
近年の研究では、キャリア構築理論の評価ツールの標準化や介入手法の革新が課題として挙げられており、特にデジタル時代に対応した新手法の必要性が指摘されています。例えば、中国の研究者Wang & Li (2024)は、キャリア構築理論の質的ツールや介入(ワークショップ、グループカウンセリングなど)をレビューし、デジタル時代のキャリア介入や評価ツールの標準化が今後の重要な方向性であると提言しています。
実際、デジタル・ストーリーテリング(オンライン上で写真や動画を用いて自分の物語を表現する手法)は、対面でのストーリーテリングに比べてキャリア意思決定の自己効力感を高める効果が報告されており、オンラインによるキャリア構築的アプローチは今後ますます活用されると見込まれます。このように、ライフデザイン・ナラティブの視点は従来以上にテクノロジーを取り入れた形で進化していると言えます(本ゼミ64回も参照)。
キャリアサステナビリティという視点
持続可能なキャリア理論(Sustainable Career Theory)は、近年ヨーロッパを中心に注目を集めている概念で、個人のキャリアを長期的持続性の観点から捉え直すものです。Donald, W. E.らの研究(2024)によれば、持続可能なキャリアとは「個人(資質や健康)、コンテクスト(組織や社会環境)、時間(キャリアの経時間的展開)の3次元の相互作用」として定義されます。
この視点では、キャリアは単なる職務の連続ではなく、ライフステージを通じて変化する個人と環境のダイナミックな相互作用として捉えられます。例えば、グローバル市場の変化によるキャリアショック(予期せぬ出来事)が個人のキャリアに与える影響も重視され、キャリアの回復力(レジリエンス)や適応行動が持続可能性の鍵とされています。
キャリアレジリエンスの維持と回復に不可欠な組織・個人双方にメリットのあるキャリア開発介入(例:従業員のエンプロイアビリティ向上やキャリア自律を促す施策)の重要性が増しています。最新の研究では、持続可能なキャリア理論と関連して「キャリア生態系 (career ecosystem)」(Donald, W. E 2024)という考え方も提唱されています。
これは、個人のキャリアの持続可能性を組織内外のエコシステム(雇用形態の変化、心理的契約、労働市場動向など)の中で捉える枠組みで、キャリア開発(個人側)と人材マネジメント(組織側)の統合的アプローチを模索するものです。まとめるなら、キャリアを長期的・包括的に捉え、健康で持続可能な職業人生を送るための理論的基盤作りが進んでいると言えるでしょう。

社会的公正とキャリア
キャリア開発理論の領域では、社会的公正や包摂の観点もますます重視されています。その代表格が働くことの心理学(Psychology of Working Theory, PWT)で、Blustein, D. (2019) らによって提唱された比較的新しい理論モデルです。PWTは、伝統的なキャリア理論が前提としてきた「選択肢がある程度保障された中での自己実現」とは異なり、経済的困難や社会的制約の中でも人々がディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)を得られるようにする支援を重視します(Arora, N 2024)。この理論では、「仕事の有意味感」や「働くことによる生計維持」といった観点を統合し、特にマイノリティや恵まれない環境にいる人々のキャリア発達に光を当てています。
近年、PWTは各国での実証研究が増えており、「さまざまな文化的文脈で適用可能な理論」としてクロスカルチャー検証も進んでいます。例えば、中国の低所得層学生を対象にPWTの妥当性を検証した研究や、トルコにおけるディーセントワーク概念の調査など、各国の労働文化・経済状況に即した形でPWTの枠組みが用いられています(Kim, H. J 2024)。
その結果、仕事の選択における「ボランタリー(自発的な希望)」と「インボランタリー(環境による制約)」の度合いが人々の心理的ウェルビーイングに与える影響などが明らかになりつつあり、キャリア支援に社会政策的な視座を取り入れる動きにつながっています。また、国際機関や政府レベルでもキャリア支援を社会的公正の手段として位置づける傾向が強まっています。
OECDの報告書(2024年)は、学校におけるキャリアガイダンスが社会階層間の移動性に寄与し得ることを示すとともに、適切な支援がなければ既存の人間関係資本(人的ネットワーク)や文化資本の差異がそのまま生徒のキャリア機会の格差につながり、キャリア支援が「社会移動の促進」にも「格差再生産」にもなり得ると指摘しています。このように、キャリア開発理論は単なる個人の意思決定モデルに留まらず、社会的包摂と公正の実現というマクロの課題とも結びつきながら発展しています。
近年のキャリア開発理論の最先端のトレンドを概観すると、現代のキャリア理論はかつてない複合的なアプローチへとシフトしていることが分かります。個人のパーソナリティや意思決定プロセスに注目した従来理論に加え、ナラティブ(物語)を通じて自己概念とキャリアを統合する視点、キャリアを長期持続可能に発展させるための視点、そして不確実性や偶然を前提としたダイナミックな視点が盛り込まれています。
さらに、AIをはじめとするテクノロジーとの融合が進み、キャリア理論はデジタル時代に適合する形でアップデートされています。大規模言語モデルなど最新のAIはキャリア支援のあり方自体を変えつつあり、それに伴い理論も実践知も進化が必要とされています。
また、グローバル化と多様化の中で、理論の国際的適用や社会的公正への寄与も重要なテーマとなりました。心理学的アプローチと社会構造的アプローチの架橋が図られ、誰もが自己のキャリアを主体的に切り開きつつ包摂的な支援を受けられるような枠組みが模索されています。
今後のキャリア開発理論は、これらのトレンドを踏まえてさらに発展していきます。本ゼミでは、理論の発展と現場の実践との対話を通じて、個人の幸福と社会的ニーズの双方に応えるキャリア理論を構築していきます。一人ひとりのキャリアがテクノロジーにより支えられ、かつその人らしい物語として紡がれ、変化の中でも成長と充実をもたらす――そんなプロティアン志向の理論体系を、2025年以降もますます洗練していきます。
【参考文献】
Arora, N., Perera, H. N., & McIlveen, P. (2024). A cross-cultural examination of career adaptability: A meta-analysis across cultural contexts around the world. Journal of Career Assessment.
Blustein, D. L., Kenny, M. E., Di Fabio, A., & Guichard, J. (2019). Expanding the impact of the psychology of working: Engaging psychology in the struggle for decent work and human rights. Journal of Career Assessment, 27(1), 3–28
Donald, W. E., Ashleigh, M. J., & Baruch, Y. (2024). (Re)Framing sustainable careers: Towards a conceptual model and future research agenda. Career Development International, 29(1), 1–28.
Kim, H. J., Buyukgoze-Kavas, A., Perez, G., & others. (2024). A cross-cultural validation of Psychology of Working Theory with Turkish working adults. Journal of Career Assessment, 33(2).
OECD. (2024). Challenging social inequality through career guidance: Insights from international data (OECD Education Spotlights No.11).
Wang, D., & Li, Y. (2024). Career construction theory: Tools, interventions, and future trends. Frontiers in Psychology, 15, 1381233.

- 田中 研之輔氏
- 法政大学キャリアデザイン学部教授/一般社団法人プロティアン・キャリア協会 代表理事/明光キャリアアカデミー学長
たなか・けんのすけ/博士:社会学。一橋大学大学院社会学研究科博士課程修了。専門はキャリア論、組織論。UC. Berkeley元客員研究員、University of Melbourne元客員研究員、日本学術振興会特別研究員SPD 東京大学。社外取締役・社外顧問を31社歴任。個人投資家。著書27冊。『辞める研修辞めない研修–新人育成の組織エスノグラフィー』『先生は教えてくれない就活のトリセツ』『ルポ不法移民』『丼家の経営』『都市に刻む軌跡』『走らないトヨタ』、訳書に『ボディ&ソウル』『ストリートのコード』など。ソフトバンクアカデミア外部一期生。専門社会調査士。『プロティアン―70歳まで第一線で働き続ける最強のキャリア資本論』、『ビジトレ−今日から始めるミドルシニアのキャリア開発』、『プロティアン教育』『新しいキャリアの見つけ方』、最新刊『今すぐ転職を考えてない人のためのキャリア戦略』など。日経ビジネス、日経STYLEほかメディア多数連載。プログラム開発・新規事業開発を得意とする。
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。
「タナケン教授の「プロティアン・キャリア」ゼミ」のバックナンバー
関連する記事
- 【用語解説 人事辞典】
- キャリア
- シャドウイング
- タフアサインメント
- プロアクティブ行動
- キャリア・オーナーシップ
- リスキリング
- 予言の自己成就
- 積極的不確実性
- キャリア・アダプタビリティ
- LMS


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント