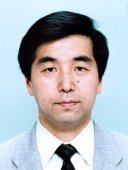社宅 入居基準について
当社では転勤時、出身地(実家のある地域、または本人及びその家族が生活拠点として決めた地域)に異動になった際は社宅入居を認めていません。
しかし、現実には実家を離れている間に環境が変化し、自分の部屋が無くなったり、兄弟が結婚して家族が増えて実家への住まいが困難になったりで、規程と現実がマッチしていません。
現行の規程ではそうなった場合は個人で負担させているため、規程をどう変更すべきか苦慮しています。
投稿日:2018/10/03 10:44 ID:QA-0079527
- ソウムさん
- 大阪府/医療機器(企業規模 501~1000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
出身地を問わず、社宅提供する様、規程を変更されては・・・
▼ 転勤先が本人の出身地であるか否かを問わず、社宅提供する様、関連規程を変更されるのが良いでしょう。
▼ 今後、類似の事案が出る毎に、頭を悩ますことになるのは好ましくないと思います。
投稿日:2018/10/03 13:53 ID:QA-0079535
相談者より
どうもありがとうございました。
投稿日:2018/11/08 10:40 ID:QA-0080274大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
実家のある場所へ転勤した際の社宅貸与
自宅(賃貸、持ち家を問わず)から勤務先に通える場合は、どの社宅規程においても社宅を貸与しません。
一方で、実家から勤務先に通える場合に、貸与しない規程は見たことはありません。
よって、
「実父母、義父母等の住居に居住して勤務先に通勤できる社員から申出がある場合は、社宅を貸与しないことができる」と社宅規程を見直してはいかがでしょうか?
既に、現行規程に拠り不利益な扱となっている社員については、規程を遡及適用することは悪しき前例となりますから、代わりに住宅手当の支給対象としてはいかがでしょうか
投稿日:2018/10/03 16:18 ID:QA-0079540
相談者より
どうもありがとうございました。
投稿日:2018/11/08 10:41 ID:QA-0080275大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
平等性
人事管理の原則の第一は平等性ですから、社宅が与えられる社員と与えられない社員が並立する制度は好ましくないと思います。なので社宅制度をやめないのであれば、全員を対象とするかあるいは、家族(子や親を扶養する)条件にしてはいかがでしょうか。たとえ親子でも同居できない理由がある場合もあり、旧来の家族前提より、扶養申請のような制度で仕分けできる条件なら平等性があります。
投稿日:2018/10/03 22:43 ID:QA-0079556
相談者より
どうもありがとうございました。
投稿日:2018/11/08 10:41 ID:QA-0080276大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、あくまで御社の判断で決められるべき事柄といえます。
つまり、今回に限り事情を考慮の上会社としましても社宅入居をさせたいという事であれば特別に入居を認められてもよいですし、また今後も同様な措置を取られたい場合には規程変更で出身地条件を削除されればよいでしょう。若しくは、社宅不足等で支援が現実困難の場合には現行ルールのままでも法的には差し支えございません。
投稿日:2018/10/04 17:41 ID:QA-0079576
相談者より
どうもありがとうございました。
投稿日:2018/11/08 10:41 ID:QA-0080277大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
現状では、公平性に欠けています。
これでは、個人負担の社員が可哀そうですし、モチベーションも低下することでしょう。
社宅入居は本人の申請とすべきでしょう、その他入居条件、入居資格等全て整合性が取れるように変更が必要と思われます。
投稿日:2018/10/05 16:01 ID:QA-0079617
相談者より
どうもありがとうございました。
投稿日:2018/11/08 10:41 ID:QA-0080278大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント