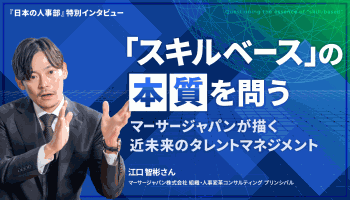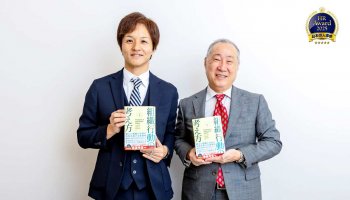日本の人事部「HRアワード2025」受賞者インタビュー
キャリアは会社が与えるものではなく、
社員が自ら創るもの
「個」の主体性を覚醒させる、中外製薬の人事制度改革
中外製薬株式会社 人事部 人事推進グループ
上田 裕樹さん

企業の持続的成長において、社員一人ひとりの主体的なキャリア形成は不可欠な要素です。一方で、実効性のある仕組みの構築に課題を抱える企業は少なくありません。そこで注目されるのが、中外製薬株式会社の取り組みです。2030年に目指す姿「TOP I 2030」の実現に向け、2025年から社員の「個」の力を最大限に引き出すための抜本的な人事制度改革を断行。その核心となるのが、会社主導の異動を原則として廃止し、社員が自らの意思でキャリアを選択するジョブポスティング制度です。その取り組みは高く評価され、「HRアワード2025」企業人事部門 優秀賞を受賞しました。同社ではどのように真の「キャリア自律」を実現しようとしているのでしょうか。人事部 人事推進グループの上田裕樹さんに、人事制度改革の詳細と、文化として根付かせるための戦略について伺いました。
「HRアワード」の詳細はこちら

- 上田 裕樹さん
- 中外製薬株式会社 人事部 人事推進グループ
うえだ・ゆうき/新卒で国内大手食品会社に入社、人事部で制度企画・運用を経験。その後、外資系コンサルティングファームにて人事領域を中心とした業務改善やBPO支援などに従事。2022年より現職にて、全社横断的な人事制度改革、主にジョブポスティング制度の導入をリード。
イノベーションの源泉は“やっぱり人”― ―経営戦略と人事戦略の強固な連動
このたびは「HRアワード2025」企業人事部門 優秀賞のご受賞、誠におめでとうございます。まずは受賞についてご感想をお聞かせいただけますでしょうか。
栄えある賞をいただき、誠にありがとうございます。当社の人事制度改革への挑戦を認めていただいた結果であると受け止めており、大変光栄に思います。
今回の受賞は、改革を推進した経営陣や人事部門だけでなく、変化を前向きに捉え、実際に行動してくれた社員一人ひとりの努力が結実したものだと考えています。この受賞を励みとして、今後も社員一人ひとりが、当社の人財マネジメント方針である「個を描き、個を磨き、個が輝く」を実現できる環境づくりに、一層邁進して参ります。
貴社が、大規模な人事制度改革に踏み切った理由や目的をお聞かせください。
当社のミッションは、「革新的な医薬品とサービスの提供を通じて新しい価値を創造し、世界の医療と人々の健康に貢献する」ことです。世の中には、いまだ治療法が確立されていない「アンメットメディカルニーズ」が数多く存在します。ミッションを実現するため、2030年に目指す姿として「ヘルスケア産業のトップイノベーター像」を定義し、そこからバックキャストする形で10年戦略「TOP I 2030」を設定しました。R&D(研究開発)のアウトプットを倍増させ、革新的な自社グローバル品を毎年生み出せる会社を目指すという、非常に高い目標を掲げています。
そして、イノベーションを創出し、高い目標を実現するために最も重要なのは「人」、すなわち人財だと考えています。経営陣からも「イノベーションの源泉は、“やっぱり人”である」という強いメッセージのもと、経営戦略と人事戦略を強固に連動させることが、当社の人的資本経営の根幹にあります。
「TOP I 2030」という極めて高い目標を達成するためには、これまで以上に社員一人ひとり、つまり「個」の力を高める必要があります。そこで、「個を描き、個を磨き、個が輝く」という三つのコンセプトを柱とした新たな人財マネジメント方針を掲げ、社員の自律・成長・挑戦に焦点を当てた人事制度へと、思い切った改革に踏み切りました。
この方針は、単なるスローガンではありません。社員一人ひとりが会社の成長戦略と個人の想いを重ね合わせながら、自らのキャリアを主体的に描き(個を描く)、必要なスキルや経験を自ら獲得し(個を磨く)、それぞれの舞台で最大限に価値を発揮する(個が輝く)ことを本気で目指すという、私たちの意志そのものです。
全社員の「キャリアオーナーシップ」を覚醒させる、ジョブポスティングという“革命”
改革の中でも、特に「ジョブポスティング」制度は大きな変革だと感じます。具体的な仕組みや実績についてお聞かせいただけますか。
これまで人事異動は、各自の成長プランや評価を鑑み、会社が主導で行ってきましたが、今年から原則すべての任用、昇格をジョブポスティングへと移行しました。空きポジションを社員に公開し、挑戦したい人には自ら手を挙げてもらいます。この仕組みにより、社員の主体的・自律的なキャリア形成を後押しする狙いがあります。またジョブ型人事制度と合わせることにより、挑戦する意欲・実力があれば若手社員でも早期に上位の役職に就くことができるなど、全社での適所適財の加速を目指します。
実際に制度を開始すると、想定をはるかに超える反響がありました。2025年上半期の実績では、約700の募集ポジションに対し、全社員の約2割に相当する約1,600人の応募が集まったのです。結果として募集ポジションはほぼ埋まり、社内異動全体の約7割を占めました。当初は半分程度を想定していたので、社員が自らのキャリアを主体的に築くことへの意欲の高さがうかがえ、大変心強く感じています。
約7割が手挙げでの異動というのは驚異的な数字です。どのような仕組みが、社員の皆さんの主体的な行動を後押ししているのでしょうか。
まず、社内のすべてのポジションが、ジョブポスティング専用のシステム上で完全に可視化されています。社員は誰でも、どの部門にどのようなポジションがあり、どこが空いているのかを検索し、そのポジションの職務内容を記した「ポジションプロファイル(職務記述書)」を閲覧できます。これにより、自分が目指したいキャリアの方向性や、そのために必要な経験・スキル・資格などが明確になります。
応募する際は、自身の職務経歴や成果、5年後・10年後にありたい姿やキャリアに対する価値観や志向などをまとめたレジュメを提出してもらいます。このプロセス自体が、自身のキャリアを深く見つめ直す「棚卸し」の機会として機能していると考えています。実際、応募するだけでも自身のキャリアを考える良いきっかけになった、という声が多く聞かれます。
応募後の選考プロセスはどのようになっているのでしょうか。異動が実現しなかった社員へのフォローも重要だと思います。
選考は、書類審査と面接で行われます。重視しているのは、たとえ選考を通過しなかったとしても、その挑戦が本人の成長の糧になるようにすることです。不合格になることで一時的にネガティブな感情が当然働きますが、それをバネに成長意欲を湧き立たせることができるか否かがジョブポスティング制度成功のカギと考えています。
そのため、不合格となった応募者には、募集部門のマネジャーから具体的なフィードバックを行うことをルール化しています。何が評価され、何が足りなかったのか、今後どのような経験を積めばそのポジションに近づけるのかを丁寧に伝えることで、ジョブポスティング制度が単なる異動のマッチング機能に留まらず、社員にとっての貴重な成長機会となることを目指しています。一人ひとりへのフィードバックはとても手間もかかることではありますが、現場のマネジャーの協力があってこそ成り立つものと思います。
応募する際に、現所属の上司の許可は必要なのでしょうか。一般的には、引き留めに合うケースも聞かれます。
制度の根幹に関わる部分でもあり、社員の積極的な挑戦を後押しするためにも、秘匿性を重視しています。社員が応募した事実は、合格が確定するまで直属の上司には一切伝わりません。また合格後、上司がその異動に対して拒否権を発動することもできません。これは、「キャリアのオーナーシップは社員自身にある」という会社としての明確なメッセージでもあります。
部下が異動することになれば、マネジャーは新たな人員を探さなければなりません。しかし、それ以上に社員が自律的にキャリアを考え、挑戦することを尊重する文化を醸成することが重要だと考えています。また、上記の通りマネジャーは異動についての拒否権がありませんので、これまで以上に自組織のメンバーに対して日頃からエンゲージメントを高めるためのコミュニケーションが求められます。
これほどの変革を、段階的にではなく全社一斉に導入された点に驚きました。何か特別な狙いがあったのでしょうか。
非常に大きな改革であり、現場への負担も多いため、経営層のコミットなしではここまでスムーズには進まなかったと思います。社長の奥田も「一人ひとりの社員がありたい姿を描き、実現のために主体的に成長と挑戦を続ける、その主体性の連鎖こそが連続的なイノベーション創出につながる」というメッセージを発信していますし、各本部のトップも新たな人事制度の狙いについて動画などを通じて社員に展開しました。結果として多くの社員に当事者意識が芽生え、制度に対する理解度や納得度も高まったと思っています。
年齢や役職にかかわらず、多くの方が挑戦されているのでしょうか。
役職やポジションのバリエーションでいうと部長職もジョブポスティングで任用していますし、海外駐在のポジションも募集が出てきました。年齢については、最高齢では62歳の社員が手を挙げ、異動を実現した例もあります。応募のボリュームゾーンは20代から40代ですが、50代、60代の社員も決して少なくありません。年齢にかかわらず、誰もがキャリアの可能性を追求できる環境が整いつつあると感じます。
興味深い動きとして、現時点の処遇や等級を下げる形で、全く異なる職務に挑戦する社員も出てきました。自身の成長やキャリアの幅を広げることを目的に、報酬よりも経験を優先する選択です。グループ会社のポジションにも応募可能で、合格すれば転籍となりますが、実際にそういう事例も出てきています。中には、等級を4段階も飛び越えるケースもありました。これらは、旧来の制度では考えられなかったことで、ジョブポスティングだからこそ生まれたダイナミズムだと考えられます。
募集部門側から社員にアプローチするような機能もあるのでしょうか。
はい。システムには社員が自身の経歴、興味のあるポジションを登録し、募集部門のマネジャーはそれを検索できます。例えば「こういう資格を持った社員はいないか」と探し、社員に対し「このポジションに興味はありませんか」と直接アプローチを送る機能も備わっています。これにより、社員からの応募を待つだけでなく、部門側からも積極的に人財を探しにいけます。当初想定していた候補者以外にも、魅力的な人財を発見し、採用に至るケースも出ていて、適所適財の精度向上に貢献しています。

「ジョブ型」と「複線的キャリアパス」が開拓する、多様な活躍の舞台
ジョブポスティングが有効に機能するためには、各ポジションの役割や責任が明確に定義されていることが前提になるかと思います。一般社員へのジョブ型雇用の導入について、詳しくお聞かせください。
おっしゃる通り、ジョブポスティングとジョブ型雇用は一体のものです。当社では2020年に、まず幹部社員(非組合員)を対象にジョブ型を先行導入しました。約800のマネジメントポジションの職務内容を定義し、適所適財の配置を進めた結果、管理職の若返りや部門間の人材流動性の向上といった成果が確認できました。
この成功を受け、一般社員にもジョブ型を全面的に拡大しました。年功ではなく、役割に応じた公正な処遇を実現することが狙いです。その際に作成したジョブディスクリプションは、研究職を例に挙げると、同じ研究業務でもG3、G4、G6といった等級ごとに求められる職務内容を細かく定義しているため、最終的に約2,000種類にも及びます。
約2,000種類に及ぶジョブディスクリプションというのは膨大な数ですが、どのように作成されたのでしょうか。
すべてをゼロから人手で作成するのは現実的ではないので、AIを活用しました。各チームのメンバーの過去の目標設定や業務分掌、等級定義やコンピテンシー基準をAIに読み込ませ、ポジションプロファイルの草案を生成。それらを基に、本部にいるHRBP(HRビジネスパートナー)が中心となり、現場のマネジャーたちに展開して修正・追記を依頼しました。
作成プロセスで最も困難だったのは、職種が異なっても、同じ等級であれば求められる役割や責任のレベル感を全社で統一することでした。例えば、研究職のG3(等級)と営業職のG3のレベル感がずれていると、報酬の公平性が担保できなくなります。そこでAIも活用しながら、全社のG3等級のプロファイルを横断的に比較し、「この職種のG3は、他と比較して要求レベルが高すぎる(あるいは低すぎる)」といったズレを何度も調整しました。ここがジョブ型の根幹をなす部分であり、最も労力を要した点です。
役割が明確になったことで、社員の意識や行動に変化は見られますか。
私たちがこの仕組みで目指しているのは、社員一人ひとりが自らのキャリアを主体的にデザインできるようになる、ということです。理想としては、例えばある研究職の社員が上位のポジションを目指す際に、システムでその職務要件を確認します。そして、自身の現状とのギャップを把握し、「次はこの資格を学ぼう」、「この実務経験を積みたい」といった、具体的な成長プランを自ら描いていく、そんな主体的な姿を想定しています。もちろん、一朝一夕に実現できることではありませんが、これ以外にもスキルセットや上司との1on1、e-learning、社内キャリア相談室の活用など、さまざまな人事施策が歯車として噛み合い、「個を描く」上での、一つの有効な道具になっていけばよいと思います。
キャリアの選択肢という点では、「複線的なキャリアパスの構築」も重要な施策ですね。
はい。これまでは管理職、つまりマネジメントポジションを目指すキャリアパスが主でしたが、多様な人財が活躍するためには、それ以外の道も必要です。例えばプロフェッショナルポジションについては、TOP I 2030の実現や中長期での事業運営を見据えて事業成長に向け必要な人財を逆算して再定義しました。先に“ポジションの箱 ”をつくっておき、人財育成や採用によって充足させていくことをイメージしています。また、ポジションを作ることで社員が自身のキャリアパスを描く際の目標にもなります。ポジションの数も従来の約100から300へと大幅に拡充し、新しい道筋を社員に示しています。
挑戦を「文化」にするための評価とフィードバックの仕組み
新たな人事制度では、評価制度も大きく変更されたと伺いました。「OKRの思想をベースとした評価制度」についてお聞かせください。
『TOP I 2030』という高い目標の達成には、社員一人ひとりが既存の枠を超えた挑戦をすることが不可欠です。かつて重視された組織内の「連携・協働」に加え、これからは高度な専門性を持つ「個」が主体的に動き、組織の垣根を越えて共創し、新たな価値を生み出すことが求められます。決められた業務をこなすだけでなく、社員一人ひとりが会社の目指す方向と自らの想いを重ね合わせ、失敗を恐れずに挑戦する。そうした働き方がイノベーションの源泉になると考えています。そこで、従来の目標管理制度に加え、OKR(Objectives and Key Results)の思想を取り入れた評価制度を導入しました。
具体的には、職責に基づく必達目標とは別に、より挑戦的な「ビヨンド目標」を任意で設定できるようにしました。重要なのは、このビヨンド目標は達成度で評価するのではなく、失敗を恐れずに高い目標に挑んだプロセスや、その挑戦によって生み出された「価値」を加点方式で評価する点です。たとえ目標が未達に終わっても、減点されることはありません。社員が高い目標を掲げることへの心理的なハードルを下げ、挑戦を奨励するメッセージを明確に打ち出しています。
正直なところ、導入初年度は「どのような目標を立てればいいのか」と戸惑う社員が多かったのが実状です。そこで、まずは部長・課長クラスのマネジメント層が率先して挑戦的な目標を立て、それをメンバーに公開している部もあります。上司がどのような視座で目標を立てているのかを示すことで、メンバーが「自分の役割に置き換えると、こういう挑戦ができそうだ」と考えるきっかけを作ったのです。
特徴的な点としてはさらに、全社員の目標は原則社内で公開され、AIによって検索が可能です。例えば『人事領域のDX』といったキーワードで、関連する目標を持つ仲間をすぐに見つけられます。これにより、部門を超えたコラボレーションを誘発するだけでなく、互いの挑戦から刺激を受け、学び合うことで、組織全体の目標達成力を高めていく効果を期待しています。
「360度フィードバック」も新たに全社へ導入されたとのことですが、どのような狙いがあるのでしょうか。
社員一人ひとりの自律的な成長を支える上で、多角的な視点からのフィードバックは非常に重要だと考えています。特に、これまで当社ではポジティブなフィードバックは見られるものの、改善点を伝えるようなネガティブフィードバックを行う文化が根付いていないという課題がありました。そこで、上司や同僚、他部署の社員など、自分で依頼した複数名から匿名でGood&Moreのフィードバックをもらう「360度フィードバック」を全社で導入しました。自らの足りない部分に気づき、それを補うためにスキルアップする、その成長サイクルをいかに作っていくかが重要だと思っています
こうしたフィードバック、特にネガティブなものを受け取ることに抵抗を感じる社員もいます。そのため、フィードバックの適切な伝え方や受け止め方に関する研修を丁寧に行い、誹謗中傷のような不適切な内容については、AIが検知してフィルタリングする仕組みも導入しています。時間はかかるかもしれませんが、個の成長に向け建設的なフィードバックを互いに贈り合う「Feedback is a Gift」の文化を醸成していきたいと考えています。
年齢にかかわらず活躍できる環境という観点では、「雇用上限年齢の撤廃」も大きな決断だったのではないでしょうか。
はい。定年制は維持していますが、65歳以降も会社が認め、また本人が健康で働く意思があれば、年齢に関わらず担う職務に応じて正社員と同等の処遇を受けられるという制度に変更しています。従来のように会社が退職時期を一律に決めるのではなく、社員が自らキャリアを考え、いつまでこの会社で働くのかを決めることができます。
さらに大きな変更点として、従来55歳で「シニア社員」という区分になり、正社員と異なる制度で運用し給与水準が下がっていましたが、この制度を廃止し、何歳でも正社員と全く同じ等級・報酬制度が適用されるようになりました。これは、年齢で不利にならない「公平さ」と、成果が厳しく問われる「厳しさ」の両面を持つ制度でもあり、あくまで年齢ではなく職務とパフォーマンスで処遇するという方針を徹底し、シニア層の活躍を後押しする制度になると信じています。
制度を“生きたもの”にするための進化と、見据える未来
最後に、今後の展望についてお聞かせください。
ジョブポスティング制度については、AIによるマッチング機能の強化という、さらなる進化を計画しています。社員のスキルや経験、キャリア志向を基にAIが解析し、ポジションをレコメンドするだけでなく、目標とするポジションに就くためのキャリアパスを提示する機能などを実装し、社員が自らのキャリアを戦略的にデザインするための、強力な羅針盤となるツールにしていきたいですね。
また、部門を起点としたキャリア形成の取り組みもさらに加速させていきたいと思います。すでに主体的に動き出している部門もありますが、例えば、自部門の仕事の魅力を伝える動画コンテンツを製作したり、各部門がブース形式で仕事内容をアピールする『社内ジョブフェア』を開催したりと、社員が自身のキャリアを考えるきっかけを積極的に創出していきます。社員の自律性を尊重しつつも、こうした偶然の出会いから新たな可能性が生まれるPlanned Happenstanceのような機会も、会社として意図的にデザインしていきたいと考えています。
将来的には、社内の空きポジションを社外にも公開し、社内外の人財が同じ土俵で選考に臨む形も検討してみたいと思っています。これによって適所適財の最大加速、ならびに「世界の人財とプレーヤーを惹きつける」という当社が描く2030年トップイノベーター像の実現につながると考えます。社員一人ひとりが自律的にキャリアを築く、私たちの取り組みを、日本の企業におけるキャリア形成の新しいスタンダードにしていければそれ以上の喜びはありません。会社はキャリアの機会を提供するプラットフォームであり、それを選ぶのは社員自身であるという厳しい現実と向き合いながらも、挑戦する社員を全力でサポートし、社員に選ばれる会社を目指す。これこそが『患者中心』の実現を人事の側面からリードする私たちの役割だと考えています。

(取材:2025年9月25日)
この記事を読んだ人におすすめ

人事・人材開発において、先進的な取り組みを行っている企業にインタビュー。さまざまな事例を通じて、これからの人事について考えます。
会員登録をすると、
最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!
- 参考になった3
- 共感できる2
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0
- 1
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント