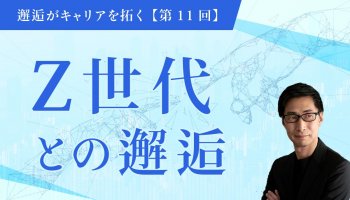「エビデンス至上主義」からの脱却
人事の意思決定を変える、経営学の思考法
東京大学大学院経済学研究科 講師
舟津 昌平さん

東京大学で経営組織論やイノベーションマネジメントを研究する舟津昌平さんは、著書『Z世代化する社会 お客様になっていく若者たち』が話題になるなど、気鋭の経営学者として注目を集めています。舟津さんが最近注目しているのが、エビデンスの扱い方。近著『経営学の技法』では、あらゆることに根拠を求める風潮に警鐘を鳴らし、同時に経営学で用いられる科学的なアプローチを、より汎用性の高いものとして紹介しています。ビジネスマンや人事パーソンの現場で役立つ、経営学由来の思考法とは。舟津さんにお話を伺いました。
舟津昌平さんが登壇するHRカンファレンス2025-春-の講演はこちら
- 舟津 昌平さん
- 東京大学大学院経済学研究科 講師
ふなつ・しょうへい/経営学者、東京大学大学院経済学研究科講師。1989年、奈良県生まれ。京都大学法学部卒業、京都大学大学院経営管理教育部修了、専門職修士(経営学)。2019年、京都大学大学院経済学研究科博士後期課程修了、博士(経済学)。京都産業大学経営学部准教授などを経て、2023年10月より現職。著書に『経営学の技法』(日経BP社)、『Z世代化する社会』(東洋経済新報社)、『制度複雑性のマネジメント』(白桃書房/2023年度日本ベンチャー学会清成忠男賞書籍部門、2024年度企業家研究フォーラム賞著書の部受賞)、『組織変革論』(中央経済社)など。
エビデンスのみを求める現代社会の危うさ
舟津さんは2024年11月に、『経営学の技法』を上梓されました。本書の「社会をよくする道具として、経営学の技法を使ってほしい」というメッセージには、どういう意図があったのでしょうか。
経営学者は「経営学は本当に役に立つのか?」という問いに必ずぶつかります。「会社を経営しているわけでもないのに、経営のことがわかるのか」と言われることも少なくありません。人事担当者が経営学を学んだとして具体的な成果に結びつくのか、という疑問が出るのはもっともなことです。
かつ現代社会では「エビデンス」を重視する傾向が強まっているように感じます。「○○についてこのようなエビデンスがあるため、**すれば効果がある」といった言説が、その典型です。「役に立つ」ことの根拠として、安易に科学が持ち出されている。しかし、この傾向は全面的に支持できるものではありません。
エビデンスに傾倒する背景には、再現性への楽観があるように思われます。「この方法を用いれば、何度でも同じ結果が得られるはずだ」という期待を前提としているという意味です。たとえば生産管理における品質管理プロセスなどはシックスシグマとよばれるように、不良品を出さないマネジメントについて再現性の高さがある程度実証されています。
しかし、人事のように個別性が高く、その状況に至る背景が複雑な領域では、再現性が著しく低下します。仮に、「○○は**に効果がある」というエビデンスが存在したとしても、その効果が得られた状況と全く同じ状況でなければ、その効果を保証することはできません。
そうした再現性や状況依存性への理解が低いままにエビデンスに偏る現代社会の状況は率直に「大丈夫かな?」と心配になります。個別論文の科学的知見に絶対的な信頼を置くのではなく、より大きな視点から「方向性としての正しさ」を捉える柔軟性こそが、あるべき科学的な態度として必要なのではないでしょうか。
近年、たしかに「エビデンスを示せ」という要求が増えているように感じます。その主張が、理屈っぽく聞こえることもあります。
社会はますます、汎用性を無視した専用的な知見を求めているように感じます。以前私は、「モバイルプランナー」というスマートフォンの買い替えに関するマルチ商法的なビジネスに学生がハマってしまう背景や問題を調査し、講義や書籍で取り上げたことがありました。
その際、取材を受けたメディアの方から「先生はモバイルプランナーの専門家ですか?」「モバイルプランナーに関する論文はありますか?」といった質問を受けました。私は経営学者であり、モバイルプランナーの専門家ではありません。今思い返しても滑稽なやり取りでしたが、記者の方は真剣な様子でした。この経験から言えるのは、「専用化」に偏るあまり「そんな人、本当に存在するのか?」という専門家を求める状況に社会が陥っているということです。仮に論文が存在したとしても、研究者の書いた内容を一般の人が理解するのは正直困難でしょうし。
著名な大手メディアの方々ですら、専門的な事柄について論文やエビデンスが存在すれば、それ“だけ”で信頼が担保されると考える傾向がある。学術界で合意された基準とは大きく乖離していて、すごく危なっかしいと感じています。
一方で、経営学で用いられる物事の捉え方や考え方が、ここまで述べたような問題に対する処方箋になるとも思っています。経営学という学問は、人事と同様に多くの変数や制御できない要素が存在する状況を対象として研究されています。そこで、一般の方がエビデンスをどのように読み解けばよいかという汎用的な指針を、経営学で用いられる「技法」を基に提示したいと考えて書籍を執筆しました。

成果主義はなぜうまくいかなかったのか
『経営学の技法』では、汎用的な指針を「三つの思考」として紹介されています。それぞれについて、詳しくお聞かせください
まず取り上げたのが「条件思考」です。ある施策や行動の効果が期待できるのは特定の条件がそろった場合に限る、という考え方です。本書では、条件思考を説明する例として、成果主義を取り上げました。ある企業のケースでは、成果と報酬を連動させることで社員のモチベーションが高まり、生産性が向上すると考え、社員も当初はそれを歓迎していました。しかし、実際には期待された効果は得られず、成果主義は失敗に終わりました。
成果主義は制度だけでなく、分担の明確化、裁量範囲の拡大、成果の厳格化など、さまざまな条件がそろわなければうまく機能しないことが、複数の学者の研究によって明らかになっています。中でも重要な条件は、能力開発の機会の増加という、成果主義とは直接関係がないように思われる要素です。
学術研究においてxとyの因果関係を導き出す際には、背後に何らかの「仮定」や「前提」が置かれることがほとんどです。つまり、エビデンスの導出には、無意識のうちにでも条件が設定されているのです。たとえば、経営学において「ミドルマネジメントは、××において重要な役割を果たす」という研究があったとしても、それがアメリカの製造企業を対象とした調査に基づくものであれば、日本のサービス企業にそのまま適用できるとは限りません。結果はシンプルだとしても、導出の際に前提として置いた条件があるはずなのです。
一見シンプルに「AならばB」という関係に見えるものでも、実際はさまざまな要因が複雑に影響し合って効果を及ぼしている、ということですね。
その通りです。たとえば、長らく続いてきた職能制などの日本の雇用慣行も、年功賃金、終身雇用、企業別労働組合という「三種の神器」が“そろって”いたからこそ機能したと考えられます。人事制度も、他の制度と影響し合い相乗効果を発揮する性質が強いように感じます。
そのため人事施策を検討する際は、施策“単体”で考えるべきではありません。他の施策との関連性を考慮し、互いにどのような影響を与えるのかを見極めることが大切です。既存の施策を変更する場合も、他の施策との相乗効果が期待できるのか、変更によって機能しなくなる施策がないかなど、影響を把握し、調整することが求められます。
これは、二つ目の「両面思考」にも関連します。両面思考とは、物事には長所と短所の両面がある、という考え方です。たとえば、先ほどの成果主義を取り入れた企業の場合、かつては社内掲示板で活発に意見交換や知識の共有が行われていたにもかかわらず、成果主義の導入後は全く機能しなくなったといいます。成果主義はモチベーションの向上をもたらす一方で、「組織市民行動」と呼ばれる助け合いの精神を低下させてしまったのです。自身の業務以外の貢献は評価されず個人の利益につながらないため、他者を助けなくなったと考えられます。
成果主義と掲示板の機能不全に、直接的な因果関係はないかもしれません。しかし、その間に存在する他の要因が連鎖的に作用し、個人主義的な行動を助長した可能性は十分に考えられます。両面思考で人事施策を捉えたら、それぞれの施策が常に望ましい結果をもたらすとは限らず、逆に全く無意味であるということもないはずです。
薬と同じで、期待される効果があれば、望ましくない副作用も起こり得るということでしょうか。
はい。施策のポジティブな面だけを見て判断すると、予期せぬ問題が生じる可能性があります。一方で、リスクやデメリットがあるからやめるべきと断定するのも難しい。
たとえば、新しい人事制度の導入を検討している企業があったとします。検討した結果、既存社員の離職リスクが高まるという理由で導入を中止したり、中途半端な制度改革で留めたりすることは、必ずしも正しい判断とは言えません。
新しい制度の導入で、一時的な損失は避けられないかもしれません。しかし、本当に評価すべき社員が報われるようになり、これから入社する社員が活躍できるなど、中長期的な視点で見て利益が得られるならば、変革を推し進めるべきでしょう。ポジティブな面とネガティブな面の両方を考慮した上で、メリットの方が大きいと判断できるときには実行に移すべきです。
その上で重要なのが、ネガティブな面への対処です。たとえば、成果主義の導入により組織市民行動の低下が発生した場合は、社内掲示板への投稿にインセンティブを設ける、チームや個人の目標に組み込む、行動指針に取り入れて評価対象とする、などといった対策が考えられます。場合によっては、組織市民行動の低下を「容認する」という判断もあり得るかもしれません。企業として何を重視し、何を優先するのかの優先順位を明確にすることが重要なのです。
さらに考慮すべきは、時間軸の要素です。ポジティブな影響であれ、ネガティブな影響であれ、その効果が現れるまでにどの程度の時間を要するのかを予想することが重要です。メリットとデメリットの両方が大きい施策の場合、デメリットが顕在化する前に施策を調整できるかもしれません。時間軸を踏まえた導入方法によって、「想定外だった」という事態を最小限に食い止めることが期待できます。
エビデンスは意思決定を導くものではない
続いて、三つ目の「箴言(しんげん)思考」についてお聞かせください。
箴言とは、戒めとなる言葉や人生の教訓を含む短い句のことで、いわゆる格言です。箴言思考は、蓄積された科学的知見から専門家が箴言の形でエッセンスを抽出し、一般の人でも理解しやすい形で提示しようという考えです。エビデンスと異なり、読み手によって解釈の幅があるとも言えます。

書籍では「リーダーのユーモアが部下のポジティブな感情を喚起し、組織市民行動につながる」という米国経営学会誌に掲載された論文を例に挙げ、科学的知見がもたらす効果の範囲は限定的でありうることを説明しました。
このエビデンスについては、読者の方もすぐさま全面的に支持することはないでしょう。なぜなら、上司のユーモアが部下に受け入れられるためには、良好な人間関係や、共通のユーモアセンスなど、いくつかの条件が前提となることは自明だからです。
また、職場におけるユーモアは内容によっては扱いが難しく、パワハラやセクハラを助長し、職場のモラル低下を招きかねないことが他の研究で指摘されています。ここでも、「条件思考」や「両面思考」が関係しています。
ところがエビデンス信奉が行き過ぎると、「専門家がエビデンスを科学的に示しているので、上司は部下に対して積極的にジョークを言いましょう」という結論になりかねません。そのような極端な解釈を避けるためにも、単一の科学的知見に拘泥するのではなく、複数の科学的知見を束ねたうえで、箴言として捉えることを提案しています。
エビデンスを盾に正義を振りかざすような姿勢は考えものですね。
エビデンスは意思決定を導いてくれるものではありません。判断を下す際には、必ず文脈を考慮する必要があります。たとえば、医療分野は特にエビデンスが重視される領域ですが、臨床では「ナラティブ」も、ナラティブ・ベースド・メディシン(ナラティブに基づく医療)として同様に重視されているといいます。
本書を執筆する過程で、医療におけるエビデンスとナラティブの関係もざっと調べたところ、ある論文に、“maxim”つまり「箴言」が医療で用いられている例が紹介されていました。たとえば「それまで健康だった子どもが下痢で来院しても、大半はウイルス性による一時的なものなので、帰してよい」といったものです。もちろんこれは絶対的なものではありません。「命にかかわるほどのものではない」と100%言いきれるエビデンスは存在しないからです。
医療者はエビデンスを学んで常に知識をアップデートしています。しかしエビデンスに真面目に向き合うほどに「とは言い切れない」「可能性が高い」「この状況ではこうだ」としか言えないものが多いことに気付くはずです。それでは医療が非効率化するばかりですし、患者さんとのコミュニケーションも停滞します。エビデンスを知るからこそナラティブや箴言が重要になるのです。
人事部門が新しい施策を導入する際、従業員から「エビデンスを示せ」と求められることも考えられます。何か良い対処法はありますか。
そもそも、根拠を示したところで納得してくれるのかな、と思ってしまいます。エビデンスの典拠となる学術論文は専門性が高すぎて理解が難しく、批判的な人の多くは読めないし読まない(笑)。施策を理解するためでなく、批判するための叩き棒としてエビデンスを求めている可能性すらあります。その同じ土俵で議論することは、賢い選択とは言えません。またそうした言動の背景には、「言うことを聞いたのに、結果が出なかったら責任を取ってくれるのか」という不安もあるのだと思います。
エビデンスをめぐるコミュニケーションの目的は、従業員らの納得感なのだと思います。施策を通じて組織をどのような状態に導きたいのか、どのような組織でありたいのかという意図を深く理解してもらうことに力点を置くべきであって、エビデンスはあってもよいけど必要条件ではない。施策の意図を理解すれば、従業員は施策に沿った振る舞いをするか、反対の意思を示すか、いずれかの行動をとるはずです。そこからさらに議論を深めていけば、建設的な対話が実現するでしょう。

若者の行動を規定する構造に着目せよ
話題を変えて、著書『Z世代化する社会 お客様になっていく若者たち』についてもお聞かせください。Z世代は社会の影響を強く受けやすいだけで、上の世代も彼らと地続きにあると指摘していたのが印象的でした。
本著は多くの若者への取材に基づいて執筆しました。読者からの反応はさまざまで、肯定的な意見もあれば批判をいただくこともありました。批判の中で目立ったのは、「特殊な事例を取り上げているだけで、一般論ではない」とか、「若者は多様化しているから世代論は意味がない」という主張です。
この主張に対して、一つ例を挙げて考えてみましょう。「ネクタイの存在」を「一般論」として語ることには、誰も疑問を持たないはずです。けれども、ネクタイは基本的に男性が着用するものなので、ネクタイをする人は人口のほぼ半分に限られます。さらに、今日の取材現場(男性3名)を見ると、誰もネクタイをしていません(笑)。そう考えると近年、仕事着のカジュアル化が進んでいるとはいえ、ネクタイは元々限られた人しか着用しないものだったはずです。どういうことでしょう。一般性とは、8割とか9割とかの人が関わることのみを指すのでしょうか。ネクタイは一部の人がしているだけのものだから一般性がないのでしょうか? 服装は多様だから語る意味がないのでしょうか?
ちなみにネクタイ自体は、衣服としての機能性をほとんど持たない装飾品(アクセサリー)に類するといえます。装飾品をもたない民族や社会が一つくらいあってもよさそうだけど、装飾品自体はあらゆる場所に共通して見られる傾向ですよね。「アクセサリーを身につける」行動は、社会的な構造によって規定されると考えることができます。
ネクタイの存在を論じるときに、「ネクタイをつけている人は私の周りにいない」とか「私はネクタイをつけない、一括りにしないでほしい」といった意見は、意味のある批判にはなっていませんよね。
同様に、一見理解しがたいZ世代の価値観や行動も、社会の枠組みによって形成された、社会構造によって規定されたものだと捉えています。たとえば学生のほぼ9割がインターンに参加したり、ガクチカ(学生時代に力を入れたこと)に振り回されたり、会社説明会で黒のリクルートスーツを着たりするのは、自律的に選択したというより、就職活動支援サービスや採用活動を行う企業の学生へのアプローチといった「構造」が、彼らの行動に反映しているからです。
一方で上の世代には、若手社員に対して、もう少し主体性を発揮してほしい、上司や先輩の動きをよく見て臨機応変に対応してほしい、と感じている人が多いようです。
私も学生と接する機会が多いので、その気持ちは理解できますが、これも結局は学校をはじめとする組織の構造によって規定されているところが大きいと感じています。
私はイノベーション研究もしていますが、「大手企業の経営陣は企業家精神に欠ける」といった批判をよく耳にします。経営が安定した大企業では、与えられた仕事をミスなくこなす人が順調に昇進する傾向があることをふまえると、そのような環境で30年ほどキャリアを重ねてきた人が、いきなりリスクを取る思考に切り替えることは難しい、というか無理でしょう。まさに人事制度が社員の行動を規定している例であり、その点では大人も若者と同じなんです。
学生や若手を取り巻く環境に目を向けると、「失敗しない」ことを重視する傾向がとても強い。進学で失敗しない、就活で失敗しない、友達づくりで失敗しない、といった具合です。私も当初は、学生の受け身な態度に対して「なんやねん」と腹を立てていましたが、やがて「おとなしくしてリスクを取らないのが最善策だとどこかで学んだのだ」と気づきました。
学生に講義する立場としては、積極的に手を挙げてほしい、みんなの前で自分の考えを述べてほしいと願っていますが、彼らは学校という社会で過ごす中で、目立つ動きをしないほうが得策だと学んでいます。したがって、行動を規定する構造自体を変えない限り、状況は何も変わりません。たとえば、「叱られることは善である」「失敗から学び、成長することで評価される」といった組織の枠組み、制度、文化が変わらなければ、行動も変わらないでしょう。
無知と混乱の解消に経営学の考えを生かしてほしい
人的資本経営が注目される中で、人事は経営に貢献することが期待されています。人事が経営学とどのような関わることで、組織をよくすることができるのでしょうか。
人事の方から、『経営学の技法』を読んで「整理できた」という感想をいただいたことがあります。人事の仕事における問題や悩みをどのように考えれば良いのか、あるいは何が問題なのかすらわからないという状況に陥ることもあると思いますが、多くの実務的な問題は、特に個人レベルでは「無知と混乱」によって起こることがほとんど。それ自体は悪いことではなく、むしろ当然のことです。
そのような状況を打開するひとつの手段として、Off-JTとして経営学を学ぶ選択肢があるでしょう。たとえば『経営学の技法』を読んでも、「なるほど、こう考えたらいいんだ」「この例は自社の問題と本質が似ている」といった気づきは得られるはずです。私の著書が、人事の方の無知や混乱の解消につながるのであれば、著者として大変うれしく思います。
人事と経営学には、どのような共通点があるのでしょうか。
私が専門とする経営学には、未開拓な領域がたくさんあります。以前は物理学者だった同業の知人は、「物理学はすでにある程度研究しつくされていて、常識を覆すような大発見や画期的な理論は期待しにくいが、経営学はまだ未開拓のはず」と言っていました。物理学は専門外ですが、その言葉には共感できました。
人事も経営学と同様に、まだ解明されていないことばかりでしょう。冒頭で述べたとおり、変数が多く、一般論を導き出すことが難しいという特徴があることも影響しています。この状況をポジティブに捉えれば、さまざまなことに挑戦のできる余地が残されています。人事の方が経営学を学び、社内の問題に対する見方が変わって、実際に組織を良い方向へと導くことができれば、人事自体がとても価値のある仕事になると思います。
まだわからないことが多い一方で、大きな可能性を秘めている人事という分野を、思いきり楽しんでほしい。そして、そこに経営学が少しでも役立つことができたら、大変うれしく思います。

(取材:2025年3月12日)
この記事を読んだ人におすすめ

さまざまなジャンルのオピニオンリーダーが続々登場。それぞれの観点から、人事・人材開発に関する最新の知見をお話しいただきます。
会員登録をすると、
最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント