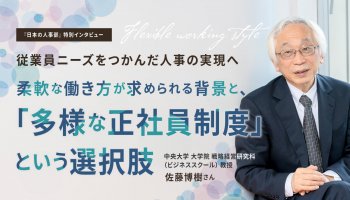これから日本の「働き方」「雇用」はどのように変化し、
人事はどう対応していけばいいのか(後編)[前編を読む]
日本大学総合科学研究所 准教授
安藤 至大さん

『前編』では、現在の日本の働き方や雇用の問題、特に「正規雇用と非正規雇用」「日本的雇用」「長時間労働」などに関して、安藤先生のお考えをお話しいただきました。『後編』は、働き方の多様化が進む中、どのような雇用形態・働き方が求められるようになるのか。また、「年功序列型賃金」「新卒一括採用」などはどうなっていくのかなどについて、具体的なお話を伺いました。
あんどう・むねとも●1976年東京生まれ。1998年法政大学経済学部卒業。2004年東京大学博士(経済学)。政策研究大学院大学助教授などを経て、現在は日本大学総合科学研究所准教授。専門は、契約理論、労働経済学、法と経済学。規制改革会議(2007~2010年)の専門委員、雇用仲介事業等の在り方に関する検討会(2015年~)の委員などを務める。新聞・雑誌への寄稿(日本経済新聞「経済教室」欄など)のほか、著書には『ミクロ経済学の第一歩』(有斐閣・2013年)『働き方の教科書』(ちくま新書・2015年)がある。また、NHK(Eテレ)の経済学番組「オイコノミア」やBSジャパン「日経みんなの経済教室」の講師として活躍するなど、雇用問題に関する分かりやすい解説には定評がある。
雇用形態は、これからさらに多様化する
今後、働き方の多様化が進む中で、「雇用形態」「働き方」はどのように変化していくのでしょうか。また、それに対して人事はどう対応していくべきだとお考えですか。
雇用形態の多様化は、企業の自助努力のほか、「労働者派遣法」「男女雇用機会均等法」など法律の制定・改正によっても促進されました。2015年6月末に政府が発表した「日本再興戦略(改訂2015)」の中でも、多様な働き方の実現について述べられています。そして数年来、多様な正社員の普及・拡大についても言及されてきました。なぜ普及・拡大なのかと言うと、既に多様な正社員が存在しているからです。「限定正社員」とも呼ばれていますが、これまでの「何でもやります。どこへでも行きます。何時まででも働きます」といった無限定の働き方ではなく、仕事内容、勤務地、勤務時間などが契約で特定された働き方を普及・拡大していくことが狙いです。
このような働き方は、以前からありました。分かりやすいのは、昔の銀行の一般職です。ほとんどが女性で、自宅から通える範囲での転勤しかなく、仕事内容も特定されていました。また、トラブルがない限り、基本的に定時で帰ることができました。かつては、このような働き方をする人が一定の割合で存在したのです。一方で総合職は、同じ銀行の中でも残業をいとわず、日本中どこにでも転勤するという無限定の働き方をする人たちでした。
一つの会社の中に複数の人事労務管理制度があるのは、最近始まったことではないのです。ただし、10個や20個も異なる制度があるというわけではありません。社会全体で見た時には多様性があるけれど、個々の企業の中ではうまく回せる程度の数の制度があるというのが、現実的な姿だと思います。
多様な正社員、限定正社員という働き方はこれから増えていくとお考えですか。
増えていくと思います。一方で、これまでの無限定と言われるような働き方も、それなりには続いていくでしょう。全て契約に基づく欧米型の働き方に移行するようなことは、起こらないと考えます。無限定な正社員の働き方がある中で、多様な正社員と言われる人たちが増えていくのがこれからの流れだと思います。
限定正社員という制度について、解雇しやすくするためのものだと言う人もいますが、それはある面では正しいのです。仕事内容を限定して雇用していれば、その仕事がなくなったときに、解雇の要件に当てはまるからです。そうでなければ、契約の原理からいっておかしいでしょう。
物事には一長一短があります。例えば配置転換がない、転勤がないという労働者側にメリットがある雇用形態なら、どこかでそのバランスが取られることになります。以前は雇用保障の程度ではなく、昇進の可能性が低い、給料が安いということでバランスが取られていました。ご存知のように総合職と一般職には、昇進や給料の面で違いがありました。しかし、これからは昇進や給料の面ではなく、雇用保障の範囲で調整されるケースが多々あると思います。
経営環境の変化や技術の進歩に伴い、否応なく失われる仕事が出てきます。一方で、新たに生み出される仕事も出てくるでしょう。これからは、人と仕事のマッチング、つまりは適材適所をいかに実現していくかという視点から、そのために必要な労働異動を人事は支援していかなければなりません。

さまざまなジャンルのオピニオンリーダーが続々登場。それぞれの観点から、人事・人材開発に関する最新の知見をお話しいただきます。
会員登録をすると、
最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント