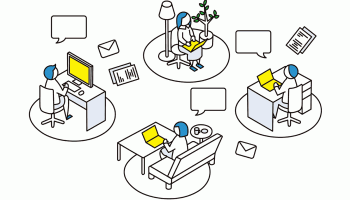ミドル再生のために人事部はいま何をすべきか
明治大学大学院グローバルビジネス研究科教授
株式会社ジェイフィール 代表取締役
野田 稔さん
- 1
- 2
人事部門、経営企画部門が一体となってミドル対策を行う
ミドル再生のための制度や組織、体制づくりについてはどうお考えですか。

どの企業でも人事部門と経営企画部門ってあまり仲が良くないことが多いですよね。実はこれがけっこう問題なんです。私たちコンサルタントは、人材と組織の問題を業務構造から人事制度までシームレスに考えています。HRMの最新理論である「バンドル(束)」という概念によると、評価制度、処遇、福利厚生、昇進昇格、人材育成などの諸施策は「束」になって一人の人間に投入されるため、この束のなかで不整合があると、会社から個人へのメッセージが混乱してしまう。だから人事施策は束として考える、一つひとつ個別に考えてはいけないというのがバンドルの発想です。
たとえばトップが、わが社はもっとチャレンジングにいく、失敗を恐れないと経営方針を掲げておきながら、評価制度が厳しい減点主義だったりしたらどうでしょう。こういう場合、人間は良いメッセージより悪いメッセージを気にする傾向が強いので、どうしても減点主義に囚われてしまう。やる気どころか、会社への不信感さえ抱きかねません。
だから人事部門と経営企画部門が一体となって、組織構造や業務プロセスから変えていかなければいけない、ということなんですね。
それができれば、ミドルの存在を明確な形で認めてあげることは難しくありません。業務構造の改革によって権限を移譲すればいい。相応の権限と責任を与えられて初めて、グリーン車にもビジネスクラスにも意味が出てくるんですから。大切にされている実感を得て、「それなら頑張ろう」という気になるんです。
プレーイングマネジャーとして、管理から実務までさまざまな仕事を並行してこなしているミドルを「多重責務者」と呼んでいらっしゃいます。彼らを疲弊させているこの現状を変えるためには何が必要ですか。
先ほども言ったように、その大変さをまず人事部がしっかりと認めてあげることが大前提です。その上でミドルにすべてをおっかぶせるような働かせ方を改めて、マネジメントの役割再設計を進めるべきでしょう。大企業の場合、部長の管理範囲は大体200人、次長で50人、課長が20人ぐらい。管理する人数は違ってもやることは変わりません。つまり大課長、中課長、小課長がいるようなもので、役割が重なり、無駄が生じやすいのです。
そこに気づき、それぞれの“本業”を明確にした、ある企業の事例があります。まず、部長は、現業は下に任せて、将来の戦略を練る、つまり「未来を創る」ことが役割とされました。一方、課長はオペレーションリーダーに徹して、担当する現場を回すことに集中する。未来だけを見据える部長と現場だけに集中する課長がいれば、当然そこにコンフリクトが生じますね。将来のことよりも明日をどうするのか、いまをどうするのか。この企業では、そこを調整するリンクピンの役割に室長を充てました。現場を巨視的に見て、経営と実務をつなぐ高度なマネジメントです。以前はこういう役割を切り分けずにマネジャー同士で重複してやっていたわけですから、とりわけ現場に近い課長の多重責務化はすさまじかったことでしょう。
じゃあ、こういう全社的な役割分担を誰が決めるのか。これは人事部門だけ、経営企画部門だけではとてもできません。人事部門と経営企画部門が手を組み、さらに現場のトップマネジャーたちも巻き込んでコンセプトを練り上げていく。そういう体制をとるべきでしょう。
ミドル再生の取り組みは、人事部が自らの存在を見つめ直す契機ともなりそうですね。
ぜひそうあってほしいと思います。私たちがHRM論のなかで特に強調しているのは、人事部は人事を執行する部署ではない、ということです。人事を執行するのはあくまでもマネジャー。人事部の仕事はそのお膳立てなのです。すべてのマネジャーにHRMを教育し、彼らを通じて、役割分担などの人事戦略を実現していくのが人事部のあるべき姿なんです。したがって当然のこと、人事部はHRMのプロフェッショナルにならなければいけません。
「主観的定性評価」でミドルの仕事を正しく評価する
ミドルをどう評価すればいいのか、これも難しい問題です。

ある調査によると、1985年当時課長だった人のうちプレーイングマネジャーだった比率は約15%、それが2006年には90%近くまで急増していました。いまのミドルはほとんどプレーヤー化しているわけです。しかしミドルに昔とったきねづかでプレーヤーをやらせると、現場にとって一時的にはカンフル剤になるものの、長続きはしません。現在の評価体系ではどうしても自分の個人成績に目が向いてしまいがち。その分、部下の支援や育成が手薄になるため、組織の足腰は弱っていく一方です。では、どうすればいいのか――私は、ミドルがミドルとしてアイデンティティーを得るためには、自分が預かっている組織そのもので評価されるべきだと考えています。
たとえばラインマネジャーについては、チームとしてのパフォーマンスをもっと評価すべきでしょう。そうすれば自分が売らなくても、部下を支援して売らせようとするし、部下を育てようという意欲も出てくるはずです。人材育成にはとりわけ高い評価を与え、本人の個人成績なんてむしろ見なくてもいいくらい。それがマネジャーに対する正しい認知と評価の一致だと思いますよ。
しかし「人材育成」について、成果を客観的に評価するのは難しいのでは?
評価というとすぐ客観評価、定量評価という話になりますが、たとえばあのトヨタ自動車では定量評価なんかしていませんよ。私が1990年代に訪れたアメリカの多くの投資銀行やコンサルティングファームにも客観的な評価指標はなかったし、驚いたことに評価表さえありませんでした。
評価指標なしに、どうやって評価するのですか?
主観的定性評価です。もともと人が人を評価するということは、主観でしかありえないんですから。批判が怖いから、評価する側が「客観」や「数字」に逃げているだけ。アメリカでも一時期、詳細な評価指標を作って客観評価をしていたようですが、「制度に頼ると、評価する人間が無責任になる」ことに気づいたんですね。不満が出ても、制度のせいにすればいいんですから。でも制度が人を評価するわけではない。人が人を評価するんです。そこを勘違いしてはいけません。だから尊敬する上司に、主観でダメといわれたら納得できる。評価において何よりも大切なのはこの納得感です。しょせん客観評価は、研ぎ澄まされた主観に比べたらずっとレベルが低いということです。人材育成についての評価も主観で十分。数値で判断されるより、しかるべき人から「君はきちんと人を育てているね」と言われたほうが内発的な動機付けが促され、意欲はさらに高まるに違いありません。
だとすると人事部としては、評価する側すなわちマネジャーへの昇格には「人を見る目の確かさ」も考慮する必要がありますね。
その通りです。誰が人を見る目があるのか、人の感情の機微がよくわかっているのか、人事部は日頃から社内にくまなくアンテナを張り巡らせ、見きわめておく必要があるでしょう。人事部の仕事は制度を見ることではなく、人を見ることです。ある大手テレビ局の例ですが、約1300人の社員全員の顔と名前が一致するほど、人事担当者たちが社員一人ひとりのことを理解していました。例えば、ある社員がプロジェクトメンバーを選定する際には、「人事に聞けば、最適な候補者をすぐに紹介してもらえる」といった状態でした。人事部が人をしっかり見ていると、そのようなことが可能になるわけです。
いま人事部には、もっと現場を歩き、ミドルに限らず社員一人ひとりを見ること、知ることが求められているのです。

取材は2008年8月4日、東京・渋谷の株式会社ジェイフィールにて
(取材・構成=平林謙治、写真=中岡秀人)
- 1
- 2
この記事を読んだ人におすすめ

さまざまなジャンルのオピニオンリーダーが続々登場。それぞれの観点から、人事・人材開発に関する最新の知見をお話しいただきます。
会員登録をすると、
最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント