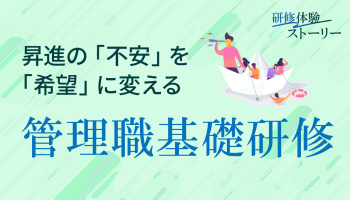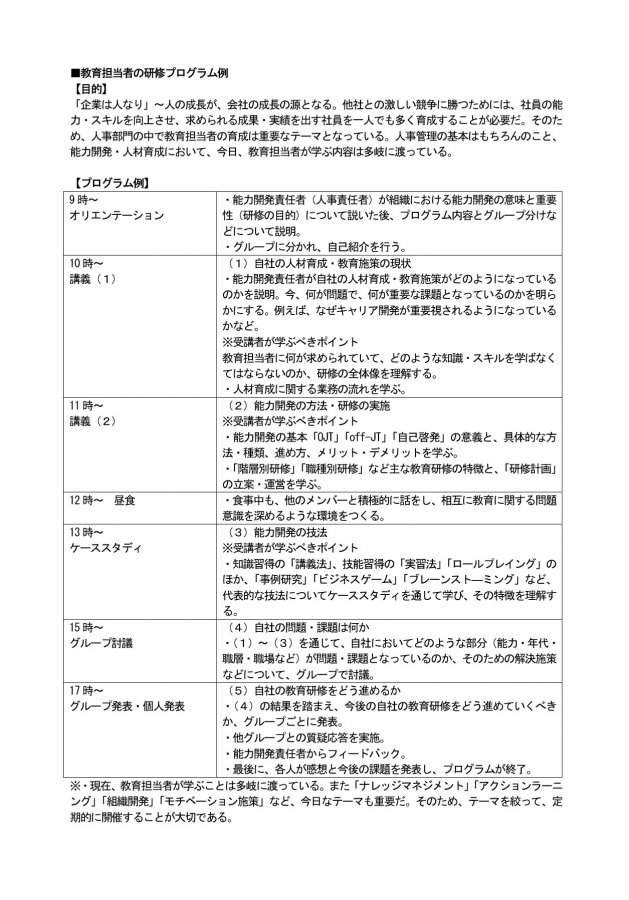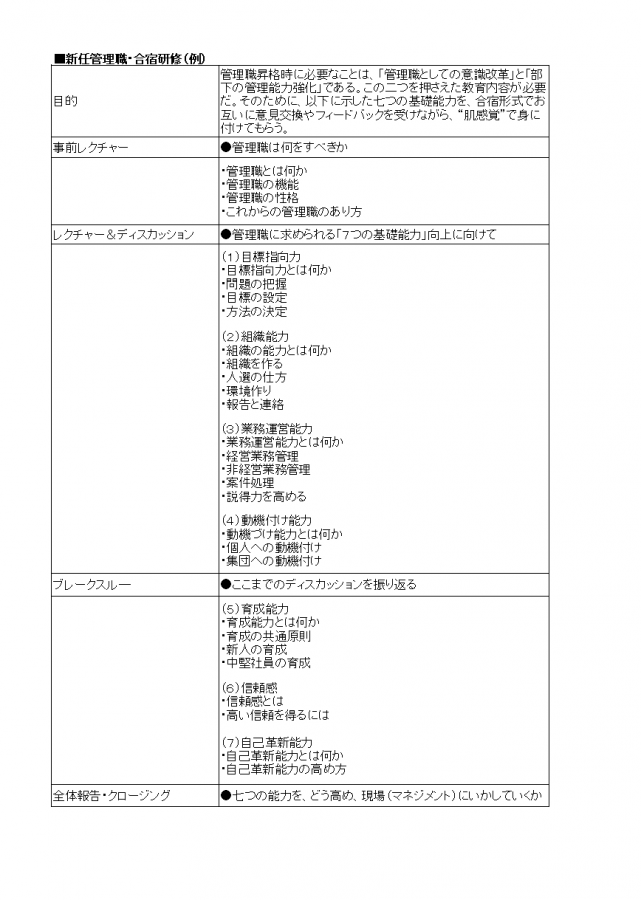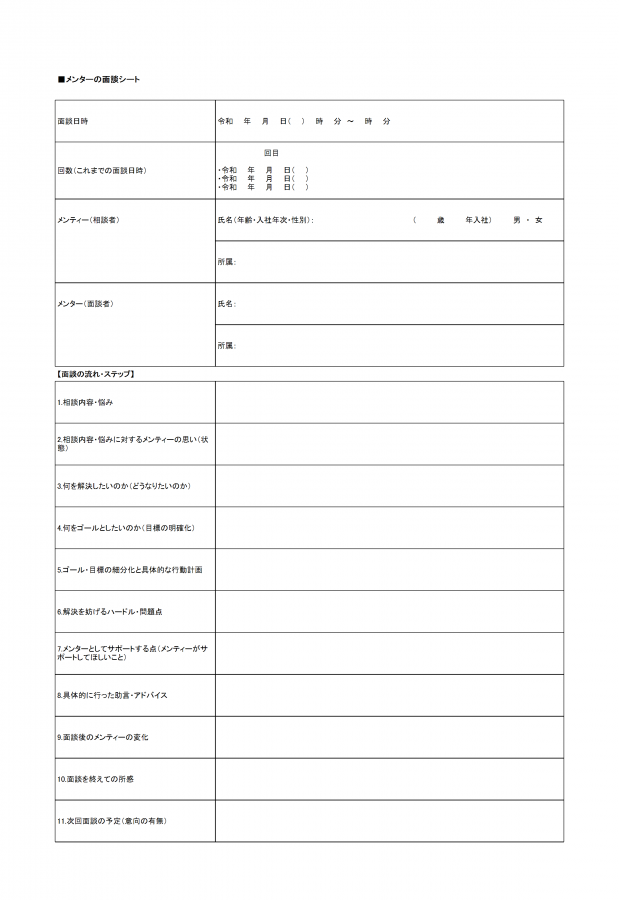マネジメント
マネジメントとは?
マネジメントとは、単なる「管理」ではなく、組織の目標達成に向けて人・物・金・情報といった資源を最適に活用し、成果を最大化する活動全般を指します。目標設定、人材育成、チームビルディング、業務割り振りを通じて、変化に適応しながら組織を持続的に成長させるのが目的です。

マネジメントとは組織の成果を最大化するための活動
ビジネスシーンで頻繁に使われる「マネジメント」という言葉。多くの人が「管理」や「監督」といった意味合いで捉えていますが、その本質はより広く、深いものです。ここでは、マネジメントの基本的な定義と、混同されがちな「マネジャー」との違いについて解説します。
マネジメントの定義・意味と目的
マネジメント(Management)は、直訳すると「経営」や「管理」となりますが、その本質は「組織に属する人や物、資金、情報といった経営資源を効果的に活用し、組織全体の成果を最大化するための一連の活動」を指します。つまり、単に部下を管理・監督するだけでなく、組織が掲げた目標を達成するために、あらゆるリソースを最適に配分し、プロセスを設計・実行し、継続的に改善していくことすべてがマネジメントです。
この概念を体系的に論じた経営学者ピーター・F・ドラッカーは、マネジメントを「組織をして成果を上げさせるための道具、機能、機関」と定義しました。ドラッカーによれば、マネジメントの主な役割は以下の三つに集約されます。
- 組織が果たすべきミッションを達成する
- 組織で働く人々を生かす
- 社会に貢献する
マネジメントは単なる業績管理にとどまらず、人材育成や社会的責任といった多面的な役割を担っています。変化の激しい現代において、組織が持続的に成長していくためには、優れたマネジメントの実践が不可欠です。
会社のマネジャーとの違い
「マネジメント」が活動や機能そのものを指すのに対し、「マネジャー」は、そのマネジメントを実践する「役割」や「役職」を担う人物を指します。マネジメントは「コト(活動)」、マネジャーは「ヒト(実践者)」と捉えると分かりやすいでしょう 。
ただし、マネジメントはマネジャーだけが行うものではありません。役職の有無にかかわらず、チームリーダーやプロジェクトの担当者、あるいは一般社員であっても、自身の業務目標を達成するためにタスクや時間を管理し、関係者と協力することは、一種の「セルフマネジメント」と言えます。
一般的に「マネジャー」と呼ばれる役職者は、自身だけでなく、チームや部署全体の成果に責任を負います。そのため、メンバーの能力を最大限に引き出し、チームとしてシナジーを生み出す、より高度で広範なマネジメントの実践が求められるのです。
リーダーシップとの違い
マネジメントと混同されがちな概念として「リーダーシップ」があります。これらは密接に関連していますが、その本質には明確な違いがあります。
マネジメントが「会社の目標達成のために、資源を効率的に配分し、計画的にプロセスを実行する活動」であるのに対し、リーダーシップは「会社や組織を特定の方向に導き、人々を動機付け、変化を促す影響力」を指します。
端的に言えば、マネジメントは「現状を維持・改善し、効率的に目標を達成する」ことを重視する「管理の側面」が強く、リーダーシップは「新たな方向性を示し、人々を鼓舞して未来を創造する」という「変革の側面」が強いと言えます。
マネジメントの仕事内容と事業における四つの役割
マネジャーが日々行うべき仕事は多岐にわたりますが、中核となる役割は大きく四つに分類できます。組織の成果を最大化するために不可欠な、マネジメントの具体的な仕事内容を詳しく解説します。
1. 目標設定と進捗管理
マネジメントの出発点は、明確な目標を設定することです。会社全体の目標や経営戦略を深く理解し、それを自身が管轄するチームや個々のメンバーのレベルまで落とし込み、具体的で達成可能な目標を設定します。
この際、「SMART」と呼ばれるフレームワークが有効です。
- Specific(具体的で分かりやすいか)
- Measurable(測定可能か)
- Achievable(達成可能か)
- Related(経営目標に関連しているか)
- Time-bound(期限が明確か)
目標を設定した後は、それを達成するための計画を立て、定期的に進捗状況を確認・管理することが重要です。計画通りに進んでいない場合は、原因を分析し、軌道修正を図ります。この一連のサイクル(Plan-Do-Check-Act)を回し続けることが、着実に成果を上げるための鍵となります。
2. 人材育成と評価(1on1・フィードバック)
組織の持続的な成長には、そこで働く人々の成長が不可欠です。マネジャーには、メンバー一人ひとりの能力やキャリア志向を把握し、成長を支援する役割が求められます。
具体的な手法としては、「1on1ミーティング」が近年注目されています。週に1回〜月に1回程度の頻度で、マネジャーとメンバーが一対一で対話する場です。業務の進捗確認だけでなく、メンバーが抱える課題や悩み、キャリアプランなどについて話し合うことで、信頼関係を構築し、個別の成長支援につなげます。
また、適切な「フィードバック」も育成に欠かせません。成果が出た際はその行動を具体的に称賛(ポジティブフィードバック)し、改善が必要な点については、人格を否定するのではなく、具体的な行動や事実に基づいて建設的に伝えることが重要です。公平で納得感のある人事評価を行うことも、メンバーのモチベーション維持と人材育成につながります。
3. チームビルディングと動機付け
個々の人材が優秀であっても、チームとして機能しなければ組織の成果は最大化されません。マネジャーは、メンバー間の円滑なコミュニケーションを促し、相互理解と協力体制を築き上げる「チームビルディング」を主導する役割を担います。
チームのビジョンや目標を共有し、メンバー全員が同じ方向を向いて仕事に取り組める環境を作ることが重要です。また、メンバーの仕事に対する意欲、すなわち「動機付け(モチベーション)」を高めることもマネジャーの重要な責務です。
動機付けには、給与や役職といった「外発的動機付け」と、仕事そのものへの興味関心や成長実感、貢献意欲といった「内発的動機付け」があります。特に後者を高めるためには、メンバーの価値観や強みを理解し、やりがいを感じられる仕事や裁量権を与えることが効果的です。
4. 業務の割り振り(デレゲーション)
マネジャーがすべての業務を自分一人で抱え込むことは不可能であり、非効率です。成果を最大化するためには、業務を適切にメンバーへ割り振る「デレゲーション(権限委譲)」が不可欠です。
デレゲーションは、単なる作業の分配ではありません。メンバーのスキルや経験、キャリア志向を考慮し、「その人にとって少し挑戦的だが、成長につながる仕事」を任せることがポイントです。仕事を任せる際は、業務の目的や背景、期待する成果、与える権限の範囲を明確に伝える必要があります。
デレゲーションを成功させることで、マネジャーは自身が本来注力すべき、より戦略的な業務に時間を使えるようになります。同時に、任されたメンバーは責任感や当事者意識を持ち、新たなスキルを習得する機会を得ることができるのです。
マネジメントで求められる10スキル
優れたマネジメントを実践するためには、さまざまなスキルが求められます。ここでは、特に重要とされる10のスキルを具体的に解説します。これらのスキルは、日々の意識と実践によって磨くことができます。
- 目標設定スキル: 組織目標と連動した、具体的で測定可能なチーム・個人の目標を設定する能力。
- コミュニケーションスキル: 自分の考えを分かりやすく伝え、相手の意見を正確に理解する、双方向の意思疎通能力。
- 傾聴力: 相手の話に真摯に耳を傾け、言葉の背景にある感情や意図まで深く理解する能力。1on1などで特に重要。
- コーチングスキル: 答えを与えるのではなく、質問を通じて相手の中から答えや気づきを引き出し、自発的な行動を促すスキル。
- フィードバックスキル: 相手の成長を促すために、良かった点や改善点を具体的かつ建設的に伝える能力。
- ティーチングスキル: 業務に必要な知識や手順を、相手の理解度に合わせて分かりやすく教える能力。
- 課題解決スキル: 問題の本質を見抜き、原因を分析し、論理的な解決策を導き出して実行する能力。
- 意思決定スキル: 不確実な状況下でも、情報を収集・分析し、組織にとって最善の判断を迅速に行う能力。
- ファシリテーションスキル: 会議やワークショップなどで、参加者の意見を引き出し、議論を整理・収束させ、合意形成を促す能力。
- タイムマネジメントスキル: 自身とチームの業務の優先順位を判断し、限られた時間の中で最大の成果を出すための時間管理能力。
マネジャーが陥りがちな三つの失敗例とその対策
良かれと思って行った言動が、かえってメンバーのモチベーションを下げ、チームの生産性を低下させてしまうことがあります。多くのマネジャーが陥りがちな代表的な失敗例と、その対策について解説します。
失敗例1:マイクロマネジメント
マイクロマネジメントとは、部下の業務に対して過度に干渉し、細かく指示・管理しすぎる状態を指します。多くの場合、その背景には部下を信頼せず、「自分のやり方が一番正しい」という思い込みがあります。
- 問題点: 部下の自主性や判断力を奪い、指示待ち人間にしてしまいます。失敗を恐れるようになり、挑戦的な仕事への意欲もそがれます。結果として、人材育成が進まず、マネジャー自身も細かい業務に追われて疲弊してしまいます。
- 対策: 「管理」ではなく「支援」のスタンスに切り替えることが重要です。業務の目的と期待する成果を明確に伝えた上で、具体的な進め方は部下に任せ、困ったときに相談できる体制を整える必要があります。デレゲーション(権限委譲)を意識し、部下の成長を信じて見守る姿勢が求められます。
失敗例2:部下とのコミュニケーション不足・一方的な指示
多忙などを理由に、部下との対話をおろそかにし、業務連絡や指示だけで済ませてしまうケースです。部下の意見を聞かずに、トップダウンで物事を決定してしまいます。
- 問題点: チーム内に情報格差が生まれ、認識の齟齬によるミスや手戻りが発生しやすくなります。部下は「自分は尊重されていない」と感じ、エンゲージメントが低下。チームの一体感も失われ、風通しの悪い職場環境になり、イノベーションを阻害します。
- 対策: 意図的にコミュニケーションの機会を設けることが不可欠です。定期的な1on1ミーティングやチームミーティングの時間を確保し、「話す」だけでなく「聞く」ことを意識することが求められます。なぜこの業務が必要なのか、その背景や目的を丁寧に説明することで、部下の納得感が高まり、主体的な行動を促すことができます。
失敗例3:人事評価の偏り・えこひいき
自分と気の合う部下や、成果が分かりやすい部下ばかりを高く評価し、他の部下との間に不公平な差をつけてしまうことです。無意識のうちに行っている場合も少なくありません。
- 問題点: えこひいきは、チーム内に深刻な不信感と対立を生み出します。正当に評価されないと感じた部下のモチベーションは著しく低下し、最悪の場合、離職につながることもあります。チーム全体の士気が下がり、生産性の低下は避けられません。
- 対策: 評価基準を明確にし、誰に対しても同じ基準で接することを徹底します。評価の際は、個人的な感情を排し、客観的な事実やデータに基づいて判断する姿勢が重要です。日頃からすべての部下と平等にコミュニケーションを取り、一人ひとりの仕事ぶりや貢献を注意深く観察し、記録しておくことが、公平な評価につながります。
マネジメントの基礎となった二大理論
現代のマネジメント論は、多くの先人たちの研究の積み重ねの上に成り立っています。ここでは、その礎を築いた二人の重要人物、P.F.ドラッカーとアンリ・フェイヨルの理論を紹介します。ドラッカーのマネジメント論
「現代経営学の父」と称されるピーター・F・ドラッカーは、マネジメントを体系化した最も重要な人物の一人です。著書『マネジメント【エッセンシャル版】』は、今なお多くの経営者やマネジャーにとってのバイブルです。
ドラッカーは、前述の通り、マネジメントを「組織の成果を上げさせるための道具」と位置づけました。そして、そのためにマネジャーが果たすべき基本的な役割として「目標設定」「組織づくり」「動機付けとコミュニケーション」「評価測定」「人材開発」の五つを挙げています。これは、マネジメントの具体的な仕事内容の根幹をなす考え方です。
また、ドラッカーは「MBO(Management by Objectives and Self-control)」、すなわち「目標による管理と自己統制」という概念を提唱しました。これは、一方的にノルマを課すのではなく、従業員自らが目標設定に関与し、その達成に向けて主体的に行動することを促すマネジメント手法であり、現代の目標管理制度の原型となっています。
アンリ・ファヨールの経営管理論
20世紀初頭に活躍したフランスの経営学者アンリ・ファヨールは、自身の経営者としての経験から、経営活動全体を六つの活動(技術、商業、財務、保全、会計、管理)に分類し、特に「管理活動」の重要性を説きました。
彼は、管理活動を構成する要素として、以下の「五つの管理プロセス」を定義しました。マネジメントの基本的なサイクルを示すものとして、現代でも広く認知されています。
- 予測(To Forecast and Plan): 将来を予測し、行動計画を立てる。
- 組織化(To Organize): 組織の構造を構築し、人や物を配置する。
- 指令(To Command): 従業員に指示を出し、組織を機能させる。
- 調整(To Coordinate): すべての活動を連結・統一し、調和させる。
- 統制(To Control): 計画やルールが順守されているかを確認し、逸脱があれば修正する。
この管理プロセスは、ドラッカーの理論よりも「管理・統制」の側面が強く、マネジメント活動の全体像を体系的に理解する上で非常に有用なフレームワークです。
時代と共に変化する最新のマネジメント手法
ビジネス環境の変化に伴い、マネジメントのあり方も常にアップデートが求められます。ここでは、近年の潮流となっている新しいマネジメントの考え方や手法を三つ紹介します。
リモートワーク環境下のマネジメント
働き方の多様化、特にリモートワークやハイブリッドワークの普及は、マネジメントに大きな変革をもたらしました。オフィスに集まっていた頃とは異なり、メンバーの働く様子が直接見えないため、従来の管理手法では機能しづらくなっています。
リモートワーク下のマネジメントでは、「成果」で評価・管理することがより一層重要になります。勤務時間ではなく、設定した目標に対する達成度でパフォーマンスを判断するのです。また、コミュニケーション不足を補うために、チャットツールの活用や、定例ミーティング、1on1などを意図的に増やし、透明性の高い情報共有を心がける必要があります。メンバーの孤立を防ぎ、メンタルヘルスに配慮することも、これまで以上に重要な責務です。
イノベーションを生む心理的安全性
「心理的安全性(Psychological Safety)」とは、「このチームの中では、対人関係のリスク、すなわち無知、無能、否定的、邪魔だと思われるような行動をしても安全だと感じられる」状態を指します。Google社の研究によって、生産性の高いチームの最も重要な共通因子として注目を集めました。
心理的安全性が高いチームでは、メンバーは失敗を恐れずに新しいアイデアを提案したり、疑問や懸念を率直に表明したりできます。これにより、イノベーションが生まれやすくなり、問題の早期発見にもつながります。マネジャーには、メンバーの発言を傾聴し、尊重する姿勢を示し、「どんな意見も歓迎される」という雰囲気を醸成する役割が求められます。
アジャイルマネジメント
アジャイルマネジメントは、もともとソフトウエア開発の現場で生まれた「アジャイル開発」の考え方を、組織運営やマネジメントに応用したものです。VUCA(変動性、不確実性、複雑性、曖昧性)と呼ばれる予測困難な現代において、従来のウォーターフォール型(詳細な計画を立ててから実行する)のマネジメントでは、変化に迅速に対応できないという問題意識から生まれました。
アジャイルマネジメントでは、短い期間(スプリント)で計画・実行・学習のサイクルを高速で回し、顧客や市場からのフィードバックを迅速に製品やサービスに反映させていきます。マネジャーは、チームに明確なビジョンを示し、自律的な意思決定を促す「サーバントリーダー」としての役割を担い、チームが最大限のパフォーマンスを発揮してイノベーションが生まれる環境を整えることに注力します。
現代のマネジメントにこそ必要な工学的アプローチとは
〈 プロフェッショナルに聞く 〉

- 長村 禎庸さん
- 株式会社EVeM 代表取締役CEO
多くの企業でマネジメントが「勘」や「センス」として捉えられることで、戦略的なマネジメントを求める経営層と、現場で日々の課題と向き合うマネジャーとの間に溝が生まれています。株式会社EVeMの代表取締役CEOの長村禎庸さんはこの問題に対して、マネジメントは技術であり、訓練を重ねることによって幅広い人が身につけられるスキルだと主張。マネジメントの構造を把握し、「型」を用いて言語化する「工学的アプローチ」を提唱しています。長村さんに詳しいお話を伺いました。
従来のマネジメントは、「人はどうあるべきか」「人の心理とは何か」といった人文学・社会学・心理学の文脈で語られることがほとんどでした。しかし、そうした一般論は現場で応用しにくく、私も一人の実務家として課題を感じていました。
多くの企業で用いられるマネジメントのフレームワークは、出来事を「説明する」ことには長けています。しかし、それを使って何か具体的な「結果を生成する」ためのものではありません。マネジャーが具体的な行動に移すための指標・業務フロー・言葉など、「マネジメント実務の解像度」にまで踏み込んだ議論が、圧倒的に不足しているのです。
実際にマネジメントに悩んでいる人の話を聞くと、言葉は違っても悩みの本質は同じであるケースが少なくありません。そこでマネジメントに一定の「型」を用いて、論理的にアクションまで導く工学的な捉え方を提案しています。
「型」とは、多くの事例を抽象化した最大公約数的なフレームワークではありません。ある一人の具体的な課題を解決するために作ったものが、他の人にも適用できるかを検証して構築します。この「課題を解決する」ことから逆算したアプローチが、再現性を生むのです。
「マネジメントができている状態」を言語化し課題を特定
マネジメントすべき立場の人が、マネジメントの定義を言語化できていないケースが多く見られます。明確な定義がないと、目的に対して適切な手段を選ぶことができず、リソースを無駄にしてしまいます。
「マネジメントができている状態」が言語化されていれば、「できている状態」と照らし合わせて現状を評価できます。営業担当者であれば、「売上目標1億円に対し、現在7000万円。未達の要因はこれなので、次はこういうアクションを取ります」と話すのが当たり前です。マネジメントも同様で、「マネジメントができている状態」に対して、現状を評価し、ボトルネックを突き止め、施策を実行する、という思考プロセスが必要です。
目標との差を埋めるために必要な行動に、特殊なスキルは不要です。例えば、「フィードバックを誠実に行う」「適切な表現で部下に伝える」など、的確な行動を一つひとつの課題に対して繰り返すことで「マネジメントができている状態」に近づきます。
こうした工学的なアプローチは重要ですが、マネジメントは対人の仕事なので、感情に寄り添う人文学・社会学・心理学の側面が不要なわけではありません。感情面へのアプローチは難しく感じるかもしれませんが、マネジメントできている状態を言語化して定期的な内省を繰り返す過程で、身についていきます。
つまり、マネジメントのスキルを習得するには、「マネジメントができている状態」を構造的に捉えて言語化したものをベースとし、人の感情面にも意識を向けながら、ひたむきに繰り返し行動することが必要です。これを継続できれば、勘やセンスに依存せずとも、むしろ誰でもマネジメントを担えるようになると私は考えています。
マネジメントの役割を「タスク」から「課題解決」へ再定義
これからのマネジャーに求められるのは、「役割を正しく認識すること」だと考えています。マネジメントとは、「メンバーが成果を上げるためのサポートをする仕事」です。管理職をタスクや評価の単なる担い手として捉えれば、いわゆる「罰ゲーム」になってしまいます。しかし、一人ひとりの能力を最大化し、チームの生産性を上げ、事業の成長、ひいては企業の利益・社会的インパクトを最大化する仕事だと捉えれば、これほど意義深く、面白い仕事はありません。
マネジメントは、訓練すれば誰もが身につけられる「技術」です。「マネジメントができている状態」という基準」を知り、課題解決のプロセスを繰り返していけば、誰でも必ず一定のレベルで成果を出せるようになります。まずはその認識を持つことが、マネジメント成功のカギになります。
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,400以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。
会員登録をすると、
最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 調査
調査 人事辞典
人事辞典 イベント
イベント