日本企業が生き残るための
「ダイバシティ・マネジメント」
早稲田大学大学院商学研究科助教授
谷口真美さん
世界規模での競争が進み、どんな業界も「変化」と「スピード」が求められる時代になりました。少子化や団塊世代の大量定年に伴う労働力の不足も心配されていて、そのような状況を見越して、女性や若手社員を積極的に登用していこうという日本企業が増えています。しかし早稲田大学大学院助教授の谷口真美さんは、企業が「変化」と「スピード」と「人口減少」の時代を乗り切るためには、新しい人材を登用するだけでは不十分で、新しい人材を生かす経営こそが必要だと説きます。それは「ダイバシティ・マネジメント」の経営にほかならないと言う谷口さんに、詳しくうかがいました。

たにぐち・まみ●1996年神戸大学大学院経営学研究科博士後期課程修了、博士号取得。広島経済大学専任講師、同助教授、広島大学大学院社会科学研究科マネジメント専攻、助教授を経て、2003年から早稲田大学大学院商学研究科助教授。2000~2001年、アメリカ・ボストン大学大学院組織行動学科エグゼクティブ・ラウンドテーブル客員研究員を務める。共著書に『ジェンダーと企業経営』(東洋経済新報社)、著書に『ダイバシティ・マネジメント』(白桃書房)などがある。
目的は企業全体のパフォーマンスを上げていくこと

これからの時代、日本企業は「ダイバシティ・マネジメント」が必要だと言われますが、「ダイバシティ・マネジメント」とは何かと問われて、きちんと答えられる経営者はそう多くないような気がします。「ダイバシティ」は「多様性」と訳されることが多いですが、つまり、多様性を重視した経営ということでしょうか。
「ダイバシティ・マネジメント」をきちんと説明すると、「変化対応能力が求められる時代に、一人ひとりの多様性をいかして、創造性・モチベーションを高め、多面的な思考をとりこみながら、市場に対して柔軟に適応できる組織に変革するマネジメント手法である」ということになります。長い説明ですが、ダイバシティという言葉そのものが非常に捉えにくい概念ですから、「ダイバシティ・マネジメント」と言われても、何をすればいいのかわからない。それが多くの経営者の実感だと思いますね。
ダイバシティ・マネジメントによって、企業の何が変わりますか。
ダイバシティ・マネジメントの目的は、それによって企業全体のパフォーマンスを上げていくことにあります。その目的に向かって、どのような組織が望ましいのか、そこを考えていくことがダイバシティ・マネジメントなのです。女性や若手、外国人を登用することがダイバシティ・マネジメントだと、そんなふうに考えている人がいるかもしれませんが、それによって社内が活性化するとか、女性社員が生き生き働くようになるとか、そういうことはダイバシティ・マネジメントの目的ではありません。これまでの企業のCSRの取り組み──法令を遵守して多様な人材を採用し、昇進させていこうという取り組み──とは、全く違う概念だと言えますね。
性別や人種による差別をなくし、さまざまな属性を持つ人々を組織の中に入れていきましょうという考え方ではない、ということですか。
全く違います。経済のグローバル化が進み、変化が激しい時代に、それに対応していくための柔軟な組織づくりのツールとなるのが、ダイバシティ・マネジメントです。
ダイバシティ・マネジメントには、4つのパラダイム──「抵抗」「同化」「分離」「統合」──があります(図参照)。「抵抗」というのは、性差や人種の違いをはじめとする多様性に対して、何のアクションも起こさない企業行動のこと。企業は、多様性へのプレッシャーがほとんどないと考えて、多様性を回避、拒否するという反応を示します。「同化」というのは、システムを変えずに、個々の持つ違いを、今あるシステムの中に取り込んでいこうとすること。具体的に言うと、「男女雇用機会均等法ができたので、女性を採用しなくちゃいけないから採用しましょう」というような企業行動が、それにあたります。「同化」はどちらかというと、組織防衛的に多様性を取り入れようというのであって、戦略的ではありません。ひとことでいうと「仕方がないから多様性を取り入れよう」という段階から進んで、戦略的に「多様性をやったほうが効果が高い」という考え方を取り入れるのがダイバシティ・マネジメントです。
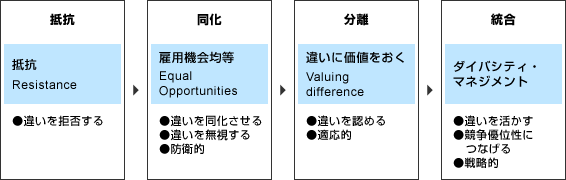
アメリカでは1970年代後半から80年代にかけて、個々の持つ違いを組織の中に取り込むのではなく、違いそのものに価値を置いて、それを生かそうという考え方が出てきました。パラダイムで言うと、「分離」のあたりですね。具体的には、ある地域でスパニッシュ系の人口が非常に増えたとしたら、その地域に積極的にスペイン語の堪能な人材を配置していく。中国市場に進出したら、地域のトップに中国人を据える。こういう、非常に市場合理的で戦略的な考え方です。

「分離」からさらに発展した「統合」とは、どういう状況を指すのでしょうか。
「分離」の段階でも、ある程度の変化に適応することは可能です。でも、それだけではパフォーマンスの向上に限界が出てきてしまいます。特定のビジネスユニットだけに特化して多様性をとりいれるだけでは、既存の組織にはなんら変化をもたらさないからです。個々の違いを認めるだけにとどまらず、そこから学べるものは学び、組織のしくみづくりに生かしていくのが統合の段階。あらかじめ、戦略的に組織の中にそうした異分子を抱え込んでおくことで、大きな変化が起きても柔軟に対応できるようにするのです。
「表層的な」ダイバシティと「深層的な」ダイバシティ
「違い」を組織の中に取り込む。人材を多様化すると言った場合に、どういう違いに注目すればいいのでしょう。単に、性別や人種に注目するだけで良いのでしょうか。
多様性と言っても、実はその次元が2つあるんです。「表層的な」ダイバシティと「深層的な」ダイバシティ。表層的なダイバシティというのは、ジェンダー、つまり男女の差であるとか、人種・民族、身体障害の有無など、どちらかというと目で見てすぐにわかる違いのことですね。これに対して、深層的なダイバシティというのは、働き方や育ってきた地域、家族の環境、価値観、経験、役職、宗教など、外から見ただけでは、なかなかわからない違いを指します。
ダイバシティ・マネジメントの効果という点から見た場合、表層的なダイバシティと深層的なダイバシティでは、違いが出てきます。表層的なダイバシティというのは、どちらかというと、対外的効果が高く、すぐに成果が出やすい。女性や外国人が新しく社長に就任したと言えば、「組織が変わった」と誰にでもわかりやすくアピールできるし、マーケティング効果、顧客イメージのプラス効果が高い。
一方、深層的ダイバシティというのは、共に働く人たち、つまり、組織の内部にゆっくりと浸透し、影響を与えていきます。ですから、プロダクトイノベーションであるとか、プロセスイノベーションに対する効果を期待するのであれば、むしろこちらが重要です。
組織変革をアピールしたり、マーケティングの効果を狙ったりする場合は表層的ダイバシティで、プロダクトイノベーションは深層的ダイバシティと整理できますね。ところが今は、この2つの次元のダイバシティが混同して議論されてしまっていて、そのことがダイバシティ・マネジメントの誤解にもつながっている気がします。
ダイバシティ・マネジメントの効果を計る尺度はありますか。実際に、それによってパフォーマンスが上がったということをどうやって調べるのでしょうか。

企業ごとに、バランスカードやダイバシティ・スコアカードというものを作って、それで見ていきます。何かをやったから、その効果がいつ頃現われるというのを予測するのは非常に難しいので、そのスコアカードに基づいて定期的にデータをとるわけですね。具体的な尺度としては、株価や売上、顧客満足度、顧客イメージがあります。ダイバシティ・マネジメントはそうした結果変数に結びつく一つの要素でしかなく、因果関係というよりは、相関関係を調べると言ったほうが正確です。
ただし、確実に言えることが一つあって、それは、こうした試みができるのは、トップのリーダーシップが強い会社だということです。ですから、ダイバシティ・マネジメントに取り組んでいるか否かは、トップのリーダーシップを測るものさしにはなるかもしれません。
「同質」を重視した経営ではM&A時代に生き残れない
ダイバシティ・マネジメントの必要性は、1980年代後半から90年くらいにかけて、アメリカで議論されるようになったと聞いています。何かきっかけはあったのでしょうか。
1987年にアメリカ労働省が出した『Workforce 2000』というレポートが引き金になっています。このレポートが出た当時、その内容が衝撃的だったとも言われていて、非常に有名なレポートです。
何が衝撃的だったのでしょう?
労働力について、今後、急速に高齢化・女性化していくだろうと。その結果、労働力人口の中心を占めていた白人男性の割合が、新規参入者で言うと、47%から15%程度にまで極端に減るだろうと予測したんです。
そのレポートでは同時に、テクノロジーブームが起こってアメリカの労働者が製造業からサービス業に大きく移行していくだろうとも予測しました。その結果、現在持っているのとは全く異なるスキルレベルが必要になる。働く人の読解力や数学的な論理性、ロジカルな物の考え方といった、知的スキルを高くしていかないといけないと警鐘を鳴らしたんです。
そして、その通りになった……。
ええ。予測のほとんどが当たりましたね。それで、企業のほうも、何とかしなければいけないとあわてて出しました。労働力の構成比も変わるし、必要とされるスキルも変わってくるわけですから、人事や組織戦略を大きく見直さないといけない。それで、組織を見直すための具体的なツールとして利用され始めたのが、ダイバシティ・マネジメントだったというわけです。
産業構造も変わるし、労働力の構成比も変わっていく。それに合わせて組織も変わっていかなくてはいけないという状況は、今の日本にも当てはまる気がします。
日本の場合、アメリカとは比べものにならないほど少子化が進んでいますから、より深刻でしょう。なのに、危機感は当時のアメリカより薄い気がします。団塊世代が引退するから大変、もっと女性を使わなくちゃいけないというくらいは意識していても、実際には、「そのために組織まで変える必要はない」と考えている企業経営者が多いのではないでしょうか。経営者の危機感と、将来を見据えた人事戦略という点において言うと日本はアメリカよりも10~15年は遅れていると思います。
経済のグローバル化が進む中で、ダイバシティ・マネジメントの弱さは即、日本企業の弱さにつながります。国内にとどまって、日本人だけを相手にマネジメントすればうまくいくことも、海外で有効に人材を活用しよう、マーケットを拡大しようとなると、うまくいきません。日本企業が生き残るためにも、経営者の意識を変えていくことがとても重要だと感じます。
アメリカでも、80年代後半からダイバシティ・マネジメントの必要性が指摘されていたにもかかわらず、企業が本気で動き出したのは2000年に入ってからだったと聞きます。何がアメリカ企業の重い腰を動かしたのでしょうか。
大きかったのはグローバル化の波。世界的規模でのM&A(企業の合併・吸収)が盛んに行われるようになったことでしょう。それで、考えている場合じゃないぞとなった。これは、日本でも同じではと思います。M&Aは増えていますし、今後もますます増えていく。その時に、ダイバシティ・マネジメントの考え方を理解していないと、とても苦労することになると思います。
まったく異なる組織文化とか、まったく異なる仕組みを持った企業どうしが合併した時に、どうやってパフォーマンスを上げていくかというのは、異なる人材をどう生かすかというのと同じなんです。日本では、大手銀行の合併に象徴されるように、合併はしたものの、組織や人事の仕組みはそのままというケースが少なくありません。企業名も、ただつなげただけで、中身はそのまま、何も変わらない。これでは合併しても、単に図体が大きくなったというだけで、それ以上の相乗効果はあまり期待できません。
日本企業は人材の「同質性」こそが強みだ、という考え方もあります。

アメリカ企業も、70年代くらいまでは同質性を重んじてきたんです。IBMを甦らせたことで知られるルイス・ガースナーさんが初めて本社の経営会議に出た時、みんな白いシャツを着ていて、「なんだ、ブルーのシャツを着ているのは僕だけじゃないか。どうしてみんな同じ格好なんだ?」と不思議に思ったという話は有名です。この話には後日談があって、2回目の会議にガースナーさんが出席したら、今度はみんなブルーのシャツを着てきたというんですね(笑)。
同質性を重んじる社風は、日本企業に限らず、ある程度の大企業でピラミッド型の組織にはよく見られることです。同質であるほうが、コミュニケーションをとりやすいことは確かですし、いったん結論を出してしまえば、素速く動ける。日本企業が非常に素速く市場に対応し、新商品を出すことができたのは、この同質性があったからだとも言えます。
ビジネスの環境がそれほど大きくは変わらずに、変革がそれほど必要でなかった時代には、たぶんそれでうまくいったんです。けれど、次々に企業の合併が起きて、市場の環境も大きく変化していく時代には、組織のあり方も臨機応変に変わっていかなければなりません。年配者の経験だけでなく、常識にとらわれない若い人たちの発想や、異質なバックグラウンドを持つ人のユニークな発想が必要になってきます。企業はそういう人の声をうまく取り入れる組織的な仕組みがないと、継続的にパフォーマンスを上げていくことはできないし、結局は競争に破れてしまうでしょうね。
「イオン」では登用した人材を組織的にフォローしている
今、ダイバシティ・マネジメントに乗り出している日本企業はありますか。
松下電器や日産自動車、イオングループなどは早くから取り組んでいますね。とくにイオンでは、ウォルマートやカルフールなど外資の日本市場への参入をきっかけに組織改革に乗り出しました。女性の登用に始まり、若手社員や異業種経験者など、バックグランドのダイバシティにまで注目して、売上を伸ばそうとしています。
イオンの取り組みで画期的だったのは、新しい人材を積極的に登用しただけでなく、彼らを組織的にフォローしたことです。日本企業が異質な人材を登用する場合、たいていは華々しく登用するけれど、その後のフォローがほとんどありません。うまくいかないときは、登用された個人の能力が足りなかったせいだ、ということになるんですね。これでは成果が上がるはずない。周囲と軋轢が起こるのは、個人のせいではなく、仕組みのせいですよ。登用した新しい人材を生かすためには、それなりのコミュニケーションツールや仕組みを整えることが必要だという考え方が、大事なんです。
多様化するには、それなりの心構えと準備が必要ですか。
もちろん。それに、多様性にはプラス面とマイナス面があります。同質性の良さと多様性の良さ、その両方を意識しなければいけない。
日本企業の強みが、これまでの同質性に裏打ちされたものであり、多様化したらその強みを失ってしまうのではないかという経営者の声をよく聞きます。私も、全ての日本企業にダイバシティ・マネジメントが必要だと言うのではありません。どの企業の、どの部門を多様化すべきなのか。あくまでケース・バイ・ケースで考えていくべき問題だと思っています。
たとえば、製造工場の作業現場に多様な人材を配置する必要はないかもしれません。熟練の社員が若手の社員を指導するというやり方がうまくいっていれば、そのままでかまわないのです。一般的に、どういう分野で多様性がプラス面に働くかと言えば、やはり戦略とマーケティング、それに人事でしょう。戦略的な意思決定をする部署、場面では、多様な人材がいたほうが新しい発想が生まれやすくなるのは確かですから。
ダイバシティ・マネジメントを実施していくうえで、注意する点はありますか。
やはり、バックラッシュ(揺り戻し)でしょうね。ダイバシティを実現しようとすることによって、既存の社員の中に不利を被る人が必ず出てきます。アメリカで言うと、ホワイトカラーの白人男性、日本では正社員の男性あたり。彼らにすると、ある意味、これまであった既得権益が奪われてしまうわけですから、どういうふうに彼らを納得させて、彼らの既得権益をなるべく侵さないように、上手くビジネス全体としてパフォーマンスを上げていくか。そこが、一番難しい。
90年代以降、正社員の数と非正社員の数が逆転したり、新卒採用を控えた結果、企業の年齢構成がいびつになったりと、実態の面で言えば、組織はすでに多様化しています。

もう、待ったなしの状況だとは言えますね。エイジ・ダイバシティや、勤続年数のダイバシティは、今すぐに考えなくてはいけない。中途採用も増えていますし、派遣やパートの活用も進んでいます。違ったバックグラウンドの人材が一つの企業に入っている状況は、すでにあるのです。
外部の人材をどう生かすかという点でも、ダイバシティ・マネジメントの考え方は役に立ちます。企業がパフォーマンスを上げていくには、彼らのスキルレベルをきちんと把握するということが、とても重要なんです。なのに、スキルに関してはエージェント任せで、企業はコストを下げるために外部を活用するという考え方しか持っていない。グローバルな舞台で本気でやっていこうとするならば、新しい人材をどう使うかばかりではなく、既存の人材が本来もっている「違い」をどう見極め、いかしていくかということも、真剣に考えなければいけないでしょうね。
(取材・構成=村山弘美、写真=羽切利夫)
取材は2006年1月30日、東京・新宿区の早稲田大学にて
この記事を読んだ人におすすめ
-

林 祥晃さん: 「やっちゃだめ」から「やっていい」への変革がやる気を引き出す 社員の主体性を覚醒させる「よい同調圧力」とは
-

小野善生さん: 管理職を救う鍵は、フォロワーとの関係性にある――新時代のフォロワーシップ開発論と人事の役割
-

ファイザー株式会社: すべての異動が公募により決定 従業員のキャリア自律を支援する、ファイザーの「ジグザグ成長キャリアパス」とは
-

株式会社コスモスホテルマネジメント: “日本に恋する”外国人材が活躍 37の国・地域がもたらす多様性の強みとは
-

木下達夫さん: 世界中の現場で学んだ「人事は運用が8割」 一人ひとりのポテンシャルをアンロックして、パナソニックから日本の人事を変える

さまざまなジャンルのオピニオンリーダーが続々登場。それぞれの観点から、人事・人材開発に関する最新の知見をお話しいただきます。
会員登録をすると、
最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0
- その他1
- 1
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント







