【監督行政が“ブラック企業”対策強化】
今こそ確認しておくべき、長時間労働者の「健康管理」の実務
労働衛生コンサルタント
村木 宏吉
4. その他、企業が注意すべき実務上の留意点
(1)健康管理部門と人事労務管理部門の連携
健康診断の結果によっては、労働者の残業や休日出勤の制限をしなければなりません。また、保健指導や面接指導を行わなければなりません。したがって、健康管理部門と人事労務管理部門との連携は重要です。健康管理部門単独では対応できません。
(2)プライバシーの保護

健康診断結果に含まれる健康情報は、重要なプライバシーです。その保護は企業にとっても重要です。
まず、健康診断データを見ることができる社員(役員を含む)を限定します。誰でも健康診断データにアクセスすることができるようでは、受診を拒否す る労働者が増える要因となるでしょう。さらに情報漏洩の禁止(退職後含む)、違反した場合の罰則を定めておくべきでしょう。この規定の存在は、受診する労 働者に安心感を与えることにもつながります。
(3)時間外労働及び休日労働の協定届
三六協定届は、労働基準監督署が長時間労働を行うであろう企業を把握する第一歩です。労働基準法違反にならないよう長めの時間外労働時間を定めて協定を締結、届け出ること自体は、法令違反を予防するわけですから悪いことではありません。
しかしながら、厚生労働省告示「時間外労働の限度に関する基準」に規定する限度いっぱいの協定を受理した労働基準監督署としては、届出した企業を“要注意事業場”にリストアップせざるを得ません。
このような内容の協定届を提出することは無理からぬことですが、「必要最小限」という考え方は必要です。
(4)三六協定届を提出しないとどうなるか
三六協定届を提出すれば労働基準監督署の立入調査を受けかねないからと、提出そのものをしないでおこうと考える企業もありそうです。
しかし、そのようなことをすれば、そもそも時間外労働・休日労働を命じることが違法行為となり、過労死等事案で労災認定がされた場合に「労災保険が出ることになってよかった」では済まなくなります。
なぜなら、事業主の法令違反が原因で発生した労働災害に対して労災保険給付がなされた場合、給付額の40~100%の範囲で費用徴収をすることとさ れているからです(労働者災害補償保険法31条1項3号)。労働基準法に違反して行われた長時間残業が原因で脳・心臓疾患が発症したとなれば、相当高額の 費用徴収が行われる可能性を否定できません。特に近年、会計検査院が費用徴収の未実施を厳しく指摘していますから、労働基準監督署としては、費用徴収をし なければならない状況にあるということをご理解いただく必要があるでしょう。
(5)パワハラ・セクハラについて一言
パワハラ・セクハラ行為を原因とする精神疾患により、労災保険給付の請求をするケースが増えています。
民法715条1項は「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用 者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない」と定め、同2 項で「使用者に代わって事業を監督する者」も同様の責任を負う旨を規定し、同3項で「使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない」と定め ています。
労災保険給付であれば、業務が主たる要因と認定されれば労災保険支給をし、そうでなければ支給しないという100かゼロかの結果になりますが、民事 訴訟においては、責任割合に応じて賠償責任を負うこととされています。つまり、労災保険給付の対象とならない事案であっても、民事訴訟では、会社側に損害 賠償責任が生じることがあるわけです。
そこで、民法715条3項です。パワハラ・セクハラ事案を起こした張本人は、会社が負担した賠償金額について、求償(弁償)に応じる義務があるということです。その旨を就業規則等に規定しているでしょうか。
近年、労災補償請求のみならず、民事損害賠償請求訴訟等が増加しているパワハラ・セクハラ事案の抑止のため、研修の実施と併せて見直していただきたい事項です。
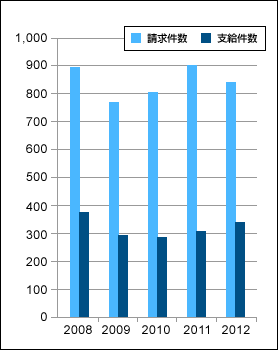
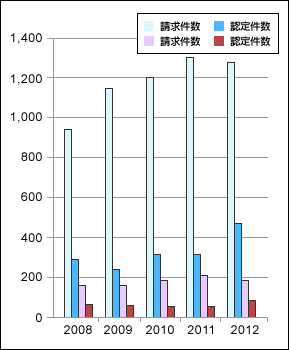
5. 行政指導を強化する意図は企業と保険制度の存続にある
今回のブラック企業に対する労働基準監督署の立入調査と行政指導は、限定的な法違反に関するもののように思われます。
しかし、企業の将来にわたる存続を考えた場合、従業員の健康管理に関する問題を先送りするのではなく、現在の問題として捉えていただく必要がありま す。すなわち、就業規則等の整備をどうするか、長時間労働を命じたりセクハラ・パワハラを行ったりした張本人に対する求償をどうするか、ということです。

厚生労働省においては、我が国における企業の存続と、労災保険がパンクしないようにとの二つの観点から業務を行っており、それが「行政指導の強化」という結果につながっていることをご理解いただく必要があります。
行政の取組みの邪魔をすることが企業のためになるかのように考えている社会保険労務士等も一部にいらっしゃいますが、それでは結果として顧問先企業の存続は危ぶまれることになりかねません。
本当の意味で企業のためになる仕事とは、行政のブラック企業対策の取組みと相反するものではないということをご理解いただきたいと思います。

むらき・ひろよし ● 1977年(昭和52年)に旧労働省に労働基準監督官として入省。北海道、東京、神奈川局の各労働基準監督署および局勤務を経て、2009年(平成21年)に退職。町田安全衛生リサーチ代表。労働衛生コンサルタント。元労働基準監督署長。労働基準法、労働安全衛生法、労災保険法等の著書多数あり。近著に「社労士のための建設業安全衛生コンサルティング実務マニュアル」(日本法令)がある。
この記事を読んだ人におすすめ

人事の専門メディアやシンクタンクが発表した調査・研究の中から、いま人事として知っておきたい情報をピックアップしました。
会員登録をすると、
最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント












