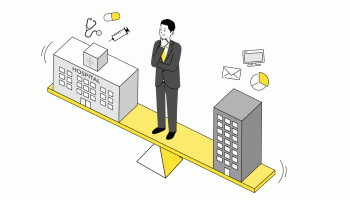がん患者等の就労支援
ガイドラインと企業対応
森本産業医事務所 代表
森本 英樹
1. 治療と職業生活の両立とは
平成28年2月に厚生労働省から、「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」 1)(以下、「ガイドライン」という)が公表されました。
治療と職業生活の両立という言葉を理解しやすくするため、まずは事例をご覧ください。
(事例1)
製造業に勤める40歳の人事担当課長の山田さん。健康診断後に、現場で働く課長の田中さんから連絡がありました。部下の従業員木村さん(55歳)の胸のレントゲンに影が見つかり、直ちに病院を受診して精密検査を受けるように産業医より説明があったとのこと。その後、木村さんは1ヵ月間の間に7日間の有給休暇を取り精密検査を受けました。そうこうするうちに、診断書が田中課長経由で人事に入ってきました。「診断名:肺がん 40日間の療養を要する」とのことで、木村さんは手術を行うことになりました。
木村さんの手術から35日後、木村さんは「そろそろ復職したい」との旨を電話で田中課長に伝えてきました。田中課長が体調を確認したところ、木村さんは「昨日退院しました。手術でがんは取りきれたようです。日常生活は大丈夫だけれども、薬の副作用で眠い時がある。1日に数回痛みでうずくまりそうなことがあるが、それ以外は大丈夫。家にいても退屈だし、仕事のカンも鈍るから仕事をしたい。体力は仕事をしながら戻していく。これ以上休んで会社に迷惑をかけることはできない」と言います。
田中課長は、いつも熱心に働いてくれていた木村さんが戻ってきてくれることを嬉しく思いつつも、仕事ができるのか不安でもあります。現在、有給休暇は残っておらず、病気欠勤の状態です。
(事例2)
最近、みぞおちと背中が痛いと周囲に言っていた50歳男性の営業職の佐藤さん。病院で検査をすることを決断し、病院に行ったところ胃がんが発覚。さらなる精密検査が必要とのことで、断続的に10日の休みをとりました。
精密検査が終わった直後のある日、佐藤さんは暗い顔をして上司の井上さんのところを訪れ、「手術ができない状態と言われた。抗がん剤治療をすすめられて、数週間毎に1日の点滴が必要と言われました。通院日以外で体調がよければ、仕事をしてもよいと主治医より言われています」と報告しました。井上さんは、突然のことでどう返事してよいかわかりませんでした。佐藤さんの体調も心配ですし、いつまでこの状態が続くのか、新たな人員を人事に依頼すべきかも気になっています。
2. 両立支援のためのガイドライン作成の背景
本事例では2例とも悪性腫瘍(がん)を例示しました。国立癌研究センターがん対策情報センターによると、生涯でがんにかかる人は、男性で62%、女性で46%です 2)。また、20歳で入社した人が60歳までにがんと診断される確率は、男性で8%、女性で11%(70歳までならば、男性21%、女性18%とさらに拡大)です 2)。過去の調査において、100人以上300人未満の企業では、私傷病で1ヵ月以上連続して休んだ/就業制限が必要であった従業員がいた割合は80.6%でした 3)(図1)。この数値は読者からすると、予想以上に多いと感じられるのではないでしょうか。
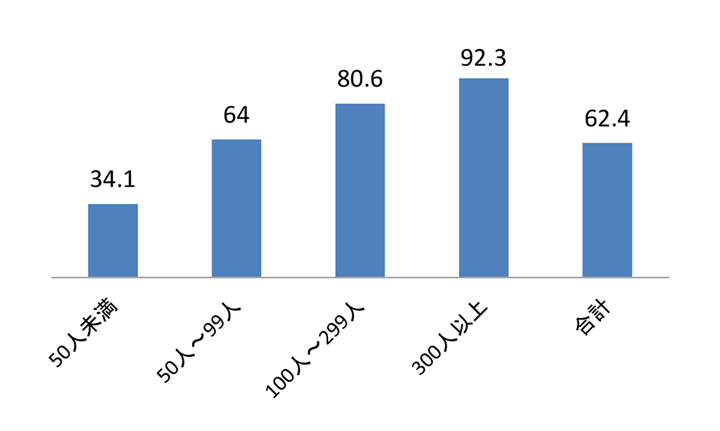
また、医療の進歩に伴い、がんは必ずしも不治の病ではなくなってきています。現在、がんを抱えながら仕事をする人は、約32.5万人いるとされています 4)。その一方で、がんにかかった従業員の75%は就業継続を希望しているにもかかわらず、21%~34.7%が退職に至っているという状況 5)、がんにより病気休職に至った方のうち42.7%が退職しているという状況 6)もあります。また、89.5%の事業場が休業した従業員の配置転換や雇用管理等に苦慮したと回答している調査 3)もあります(内訳の上位3項目は、病気や治療の見通しがわからない、復帰可否の判断が難しい、代替要員の確保が難しい)。
がんは50歳代から急激に増加し、年齢を追うごとに増える特徴があります。65歳まで働くことが一般的になっている現在、企業は貴重な戦力を維持・確保するためにも、がんをはじめとする持病を持つ従業員への対応を進める重要性が増しています。また、両立支援が必要な病気はがんには限りません。難病は完治が難しいものの、一定の就業上の配慮があれば問題なく仕事ができることがあります。これらの疾患を持つ方々へも類似の対応が必要になります 7)。
3. 両立支援が必要な疾病とその特徴
両立支援が必要な病気として、今回厚生労働省が発表したガイドラインでは、「がん、脳卒中、心疾患、糖尿病、肝炎、その他難病など、反復・継続して治療が必要となる疾病であり、短期で治癒する疾病は対象としていない」とされています。
これらの病気の特徴としては、
- 定期的な検査・通院治療が必要であること
- 治療効果により、時に治療方針の変更が必要になり、通院頻度が変わること
- 病状の悪化等により、突然の入院・自宅安静が必要になる場合があること
があります。
留意点としては、主に以下のことが挙げられます。
- 病気には重症度や個人差があるため、病名だけでは一概に判断できないこと(同じ病名であっても治療で完治する場合もあれば、現在の医療では元気で過ごすことができる期間を延長することを目的とせざるを得ない場合もある)
- 病気とその後の治療方針により必要な配慮が多種多様であり、画一的な配慮を定めることが困難であること。このため、会社が医師より医学的な見地から意見を聴取したうえで、必要な配慮を決定する必要があること
- 仕事も多様、かつ多岐にわたるため、主治医は患者や職場から業務についての情報提供を受けない限り、患者がどのような職場で働き、何に留意すべきかの助言が困難であること。つまり、主治医と職場との双方向性のコミュニケーションが必要であり、それを仲介するためには産業医をはじめとする産業保健スタッフが適任であること
- 医学的な適性を踏まえずに就業上の判断を下した場合には、過剰配慮や過少配慮が生まれがちであること、また時間的な経過に伴う病状や体調の変化によって、就業上の配慮が変化すべきであるのに、対応ができていない場合があること(例えば、医学的には車使用が可能な健康状態であるのに使用禁止が継続されている、もしくは車の使用を避けるべき状態であるのに車を運転している)

人事の専門メディアやシンクタンクが発表した調査・研究の中から、いま人事として知っておきたい情報をピックアップしました。
会員登録をすると、
最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント