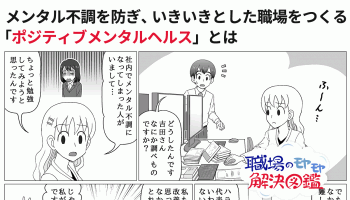鳥貴族が25%の離職率を11.1%まで改善できた理由とは
人事部門が新入社員をフォローし、離職のサインを早期にキャッチ
株式会社エターナルホスピタリティグループ グローバル人財部 タレントマネジメント課 課長
久保山 豪さん

国内660店舗を超える「鳥貴族」などを運営する、エターナルホスピタリティグループ。約10年前、年間30店舗以上のペースで店舗拡大を図っていましたが、入社1年目の社員においては25%という高い離職率により計画の実行が危ぶまれていました。そこで、採用と定着を両輪で回す離職率防止の取り組みを実施。2024年には、離職率を11.1%まで改善することに成功しました。離職率が高い傾向にある外食産業で、同社はどのようにリアリティー・ショックを防ぎ、「離職のサイン」を早期にキャッチしているのでしょうか。エターナルホスピタリティグループ グローバル人財部 タレントマネジメント課 課長の久保山豪さんにうかがいました。

- 久保山 豪さん
- 株式会社エターナルホスピタリティグループ グローバル人財部 タレントマネジメント課 課長
くぼやま・たけし/中央大学経済学部卒業後、リクルート代理店に入社。法人営業担当として、IT・不動産・金融・外食・医療など幅広い業界の採用を支援する。営業管理職、新規事業責任者を経験し、2013年に鳥貴族ホールディングス(現エターナルホスピタリティグループ)へ入社。以後、新卒・中途採用全般の企画・実行を経て現職。採用・教育全般と人事制度の企画・運営を担当。
人員不足で出店計画が停滞。人事部門が新入社員を定期的に訪問
外食産業は離職率が高いイメージがあります。離職防止のため、どのような施策に取り組まれてきたのでしょうか。
私がエターナルホスピタリティグループ(旧:鳥貴族ホールディングス)に入社した2013年当時、「鳥貴族」は今ほどの知名度がありませんでしたが、年間30店舗ほど新規出店しており、上場を見据えてさらなる店舗拡大を計画していました。しかし、新卒・中途あわせて、入社1年目の社員の離職率は25%。採用しても、短期間で4人に1人の社員が退職してしまう状況だったため、店舗社員の不足が大きな障壁となっていました。
採用スピードを上げれば増員できますが、人の入れ替わりが激しかった当時の状況では、新入社員の育成が追いつかず、かえって離職率を上げてしまうリスクがありました。「離職率改善」は採用と同時に取り組むべき大きな課題であり、具体的な解決策を考えなければならないと強い危機感を抱きました。
離職防止のために、具体的にどのような施策に取り組まれてきたのでしょうか。
例えば、店舗に配属された新入社員の面接を担当した採用担当者が定期的に訪問するフォロー制度があります。2015年に始め、10年以上続けています。
当時の人財部部長の江野澤が店舗を統括している営業部出身で、「営業部門だけでは店舗の新入社員をフォローしきれていない」と感じていたのがきっかけでした。「採用担当者が現場に訪問し、新入社員をフォローするのはどうか」という意見が出ました。
しかし、人事担当者の人数は限られているので、全店舗を訪問し続けるというのは現実的ではありません。そこで、新卒・中途を問わず「入社1年以内の社員」に絞り、特に離職が多い傾向のあった入社3ヵ月目のタイミングで店舗を訪問することにしました。
職場に対して疑問や不安を抱えていても、直属の上司である店長には「相談しづらい」と感じている新入社員は少なくありません。一方、面識がある採用担当者であれば、安心感があり、店舗で一緒に働くことがなく程よい距離感があるので、相談しやすいのではないかと考えました。店舗に訪問することで、現場の雰囲気や、新入社員がなじめているのかどうかを目で確認できます。この施策は、行うことが決まった翌週には実行に移しました。
フォローをはじめたとき、どんな反応がありましたか。
最初は店長や他の社員に少し驚かれましたが、新入社員は想像以上に喜んでくれました。また、営業出身の江野澤は現場にも精通していることで知られているため、店舗側にもすぐに受け入れてもらうことができました。
当時の新入社員が今では多くの店舗で店長を務めていて、人事担当者が店舗に顔を出すのは「当たり前」という雰囲気になっています。
新入社員をフォローする上で心がけていることはありますか。
新入社員から相談されることが多いのは、店長の「指導方法」や、ちょっとした意見の食い違いなど、コミュニケーション不足より起こる問題です。人事担当者は、店長か新入社員のどちらかをフォローするのではなく、二人が良い関係を築けるように、その二人の間にある関係をフォローすることを心掛けています。店長と新入社員、どちらか一方が100%間違っていることはない、と考えているからです。
例えば新入社員の「相談に乗る」というと「不満を引き出す」と捉えられがちですが、「店長のいいところはどこですか?」とあえて良い点を聞き出すようにしています。相手の悪い点ばかりを口にしていると、ネガティブなイメージが増大していくだけですよね。ポジティブな部分にも目を向けてもらい、関係が改善できるようにサポートしています。
また、店舗のリアルな雰囲気や人間関係を把握できるよう、実際にお客様が来店されている営業時間中に訪問するようにしています。
離職のサインを捉えるパルスサーベイの導入
新入社員の状況を把握する施策は他にもありますか。
入社1年目の社員を対象に、現在の状態を把握するためにパルスサーベイを実施しています。毎月数問のアンケートに答えると、社員の状態が「晴れ」「曇り」「雨」という3段階で明示されるものです。「突然の退職」をなくすために導入しました。
新入社員が退職を検討していると事前に察知できれば、人事部門や周りの社員でフォローできます。パルスサーベイの結果を受け、採用担当者たちが毎月、フォローミーティングを開催。「晴れ」「曇り」「雨」の状態やアンケートに記載されたコメントをチームで共有し、どのようにサポートすべきかを話し合ったり、「雨」から「晴れ」に変化した人に何が起こったのかを共有したりしています。
パルスサーベイでは、「業務の負担」と「人間関係」の二軸のエンゲージメントを把握することができます。それにより、社員が退職に至るまでの心の動きが見えてきました。退職した社員の結果を分析したところ、まず業務負荷が上がり、その後人間関係が悪化する傾向があることが分かりました。つまり、忙しくなると心の余裕がなくなり、コミュニケーションを取る機会が減って人間関係が悪化し、退職につながる、という流れでした。また、多くの仕事を任され始める入社3ヵ月目以降あたりから業務負荷が高くなることもわかりました。
「雨」マークが出た社員に対しては、どのような対策を講じていますか。
まず社員の上司の方にアプローチします。もちろん「雨マークが出ていること」は伝えずに、雨マークの判定が出た社員について「最近、〇〇さんはどんな様子ですか」とヒアリングします。上司に働きかけることで、社員とのコミュニケーションを促すのです。
次に、人事担当者が、「雨」の判定が出た社員と対話します。「店長があなたのことを褒めていたよ」と伝えるなど、上司である店長とポジティブな関係になれるようにサポートしながら、抱えている不満や悩みを上司に相談するように促します。
また、新入社員に店舗が掲げている目標を尋ねることもあります。目標への理解が浅い場合は、「上司が何を目指しているのかを知らなければ、フォロワーシップは発揮できないよ」と、上長と目線を合わせることの重要性を伝えるようにしています。
それでも新入社員が退職してしまった場合は、店長に対するケアを欠かしません。店長だけの責任にするのではなく、人事部門も一緒に改善点を考えるようにしています。
リアリティー・ショックを防ぐため、会社の実態を隠さず発信
貴社は離職防止の取り組みと同時に、採用活動にも注力しています。定着率の高い人材を採用するために、心掛けていることをお聞かせください。
「鳥貴族に定着し、活躍する人しか採用しない」ことにこだわっています。
鳥貴族は、深夜帯勤務もある外食企業です。求人へのエントリーが集まりづらい中で、応募者を全員採用すれば、目先の「人員不足」は解消されるかもしれません。しかし、人数だけを追いかけて多くの社員を採用しても、すぐに退職してしまっては意味がないと考えています。
そこで、グループ統一で明確な基準に沿って評価できるよう、事前に質問項目や評価基準を設定した上で実施する「構造化面接」を導入。鳥貴族で活躍している店長が持っている要素のうち、入社後に身に付けることが難しい要素を見極められる質問項目を作成しました。
さらに、面接官個人の主観に左右されないよう、複数の面接官が集まる選考会議を週に一度開催し、議論した上で採用可否を決めています。例えば、面接官は自分と似たバックグラウンドを持つ求職者を高く評価する傾向があります。バイアスがかかっていないかどうかを話し合うことで、個人の主観的な判断に偏らないような仕組みにしているのです。
また、新入社員が「リアリティー・ショック」に陥って早期離職しないよう、採用面接の時点で会社や仕事内容の実態を隠さずに伝えています。
例えば、「きっと想像しているよりも業務が忙しい」ということ。絶え間ない追加注文に対応するために素早くテーブルの食器を片付けるなど、店員が積極的に動き続ける必要があります。また、活気あふれる店内を演出する「あいよー!」といった掛け声は「まるで体育会の部活のよう」と表現しています。
理念や社風についても同様です。当社の理念である「うぬぼれ」は「焼鳥屋で世の中を明るくしていきたい」というわたしたちの想いです。「うぬぼれを意識したら、こういう行動をすべきだ」というように、社員同士の日常的な会話に登場するほど浸透しており、行動指針として機能しているものです。鳥貴族ならではの社風と求職者の考えにギャップが生まれないよう、求人広告や面接では、「なぜ鳥貴族が『うぬぼれ』を大事にしているのか」を丁寧に伝えています。
- 【参考】
- リアリティー・ショックとは

人事部門の役割は、社員同士の「関係づくり」を支えること
そういった施策の成果をどのように感じていますか。
私が入社した2013年当時、入社1年目の離職率は25%でしたが、2015年から離職率改善に向けたフォロー制度に取り組み、2024年度には営業部門全体の離職率は11.1%にまで改善しました。パルスサーベイや店舗への訪問により、新入社員の心の動きの把握に努めたことで、組織の実態や文化に合った施策を設計し、結果につなげられたのだと感じています。
今後、人材の定着率を上げるためにさらに注力しようと考えていることはありますか。
離職率は今後も注視する必要がありますが、今後はグループ全体の社員の定着を実現する施策を考えていきたいですね。例えば、現在、パルスサーベイの対象は新入社員だけですが、「異動により職種が変わった社員」にも拡大しようと考えています。異動自体が退職につながるケースは少ないのですが、店舗から本社への異動などは環境が大きく変わるため、新しい職場になじめないことがあります。入社時期に関係なく、大きな環境の変化があった社員の状況を把握することで、エンゲージメント向上につなげたいと考えています。
人材の定着に課題を抱える人事担当者の方々に向けて、メッセージやアドバイスをお願いします。
離職率を改善するために何から着手すればいいのかが分からなければ、現状を把握することから始めてみてはいかがでしょうか。定着率向上の取り組みは、人事部門だけでは進められません。現状を正確に示したデータがあれば、課題を抱えている部門や周囲の協力を得られやすくなり、職場改善のスピードが上がります。
人事担当者は、組織内で問題が起こった際に、上司と部下、店舗とバックオフィスといった各所の「間」に立ち、調整を図るのも役割です。しかし、本当に良い組織とは、「間」に人事担当者がいなくても、当人同士で問題を解決できる組織ではないでしょうか。大変難しいですが、だからこそ組織にそうした風土を醸成できるよう、人事担当者が社員同士の「関係性づくり」をサポートするという意識をもって、常日頃からたゆまぬ行動をしていくことが必要だと考えています。

(取材:2025年10月2日)

人事・人材開発において、先進的な取り組みを行っている企業にインタビュー。さまざまな事例を通じて、これからの人事について考えます。
会員登録をすると、
最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント