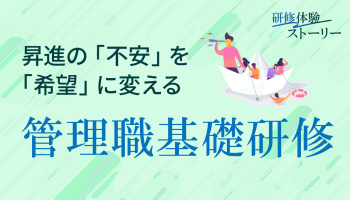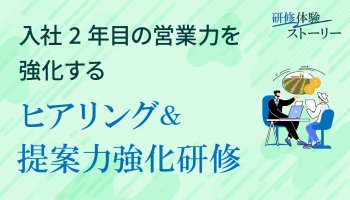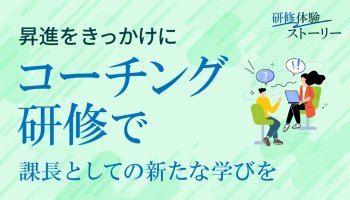~『日本の人事部』スタッフが受講した~ 研修体験ストーリー
課長昇進へ視座を高める「課題設定力研修」

マネジャーに昇進すると、マネジメントやプロジェクト推進など、プレイヤー時代とは異なる行動を期待されるようになります。『日本の人事部』を運営する株式会社HRビジョンでは、営業スペシャリストとして評価されたCさんが課長代理に昇進。個人成績だけでなく組織課題にも対応できるスキルを身に付けるべく、課題設定力研修を受けることになりました。多くの管理職向けの研修から、Cさんに合う研修をどのように選んだのか、選定理由や研修内容、受講後の成果まで、受講者Cさんと研修発注者であった営業課長の話を交えてレポートします。
- 営業課長
営業課長。営業部2課で9人のマネジメントを担う。
- Cさん
HRビジョンの中途入社9年目。営業職のスペシャリストとして課長代理に昇進した。営業課長のサポートとして、若手メンバーへの指導やメンターも担う。
受講背景
企業全体の育成、Off-JT方針
当社では、階層別や職種別の定期研修に加え、キャリア志向や個々人の課題感に応じて、随時研修を実施しています。自社メディア企画や新しい商品開発を手がけ、ビジョンを推進する人材を育てるうえで、社員が必要としたタイミングで支援できることが必要だと感じているからです。
「課題設定力研修」導入までの流れ
課題設定の体系的な手法を学び、商品開発や組織運営を推進してほしい
営業課長
研修導入のきっかけは、Cさんが係長から課長代理に昇進したことでした。課長代理には、営業のスペシャリストとして売上を出すことはもちろん、商品開発や課員の営業力強化などをけん引することが求められます。とくに当社は、グループの中で新規事業開発を担っていて、新しいアイデアを出して実行することが求められます。メンバーは能動的にさまざまな意見や課題を上げてくれるのですが、多様な意見を取りまとめて実現させるにはスキルが必要です。
そこで、問題や課題の捉え方、解決方法の一つの基準を学ぶことで、商品開発や組織運営に生かしてほしいと考えました。
管理職向けの短期公開講座を比較検討しました
営業課長
研修を探す際、まずはインターネットで「管理職 研修」「課長 研修」などのキーワードで検索し、候補をリストアップしていきました。
研修期間は1〜2日間の短期がいいと考えました。Cさんは高いパフォーマンスを出しているので、長期間職場を離れると影響が大きいためです。短期間でもきちんとノウハウが身につくよう、ワークがあるかもチェックしました。
公開講座に限定すると、意外にも数が少なく、最終候補は四つになりました。網羅的にスキルを学べる「次世代リーダー研修」「管理職のための説明力向上研修」「クリティカルシンキング研修」「課題設定力研修」の四つです。この中からCさんが選んだのが「課題設定力研修」でした。
Cさんは部署を越えた社内関係者が参加するプロジェクトのリーダーを担っています。プロジェクトメンバーからはさまざまな課題や意見が上がってきますが、どのように意見を整理して優先順位をつけたらいいか、どう関係者を巻き込んだらいいのかが課題になっていました。Cさんは本研修のカリキュラムを確認し、「問題と課題の違いとは」など今の自分が知りたい内容が多いと感じたようです。
<選定した五つの理由>
- 期間が1~2日間
- 公開講座
- 受講者本人に課題感があるテーマ
- 課題解決のフレームワークを学べる
- ワークが組み込まれている
「課題設定力研修」の内容
開催日・形式:2024年3月21日、オンライン
オンライン形式で、ネットワーク環境も問題なく、快適に受講できたそうです。Cさんによれば、研修資料の閲覧方法がやや煩雑だったということです。
カリキュラム:
- 1. 課題とは何か
- (1) 「問題」 と 「課題」の違いとは
- (2)問題意識の根源にある感情的なもの
- 2. 今なぜ「課題設定力」が求められるのか
- (1) 「目指すべき姿」が明白だった時代の終焉
- (2) 生産性の高い仕事には課題設定が不可欠
- 3. 課題設定の進め方
- (1) 問題の「発見」と 「解決」の間に位置づけられる「課題設定」
- (2) 課題設定に必要な3つのスキル
- 4. 1問題発見スキル~予断を排しあるべき姿からものを見る
- (1) 問題発見における謙虚な視点
- (2) ブレのない問題発見のための「As Is-To Be」モデル
- (3) 問題の3タイプ~「問題となっているもの」だけが問題ではない
- (4) 問題を正しく捉えるための視点~問題発見の4P
- (5) 「見えている問題=課題」を疑うクリティカルな視点
- 5. 2問題分析スキル~問題を切り分け対処しやすくする
- (1) 求められる「論理的思考力」
- (2) 分析のステップ1~「分ける」
- (3) 分析のステップ2~「深掘る」
- (4) 分析のステップ3~「俯瞰する」
- 6. 3課題設定スキル~本質的な問題 (イシュー) を見極める
- (1) イシュー(Issue)とは何か~よい課題設定のための考え方
- (2) 課題の質を上げるための視点
- (3) 本質的でない意見に対する対処の仕方
- 7. 問題解決に求められる巻き込み力
- (1) 求められる論理性と共感性
- (2) 段階を追って活動を展開・定着させる
- (3) 問題解決の主体者であり続けるために
- 8. まとめ
費用:一人当たり30,500円(税抜)
後払いのため、ゆとりをもって社内決裁できたことは良かったと思います。
「課題設定力研修」研修の効果
問題への向き合い方がわかるようになりました
Cさん(営業職9年目)
研修を受けてよかった点は大きく二つあります。一つは問題解決のフレームワークを学べたことです。物事を考える際は縦と横の軸で捉える必要があります。縦軸は現場、管理職、社長など立場による目線の違い、横軸は時間軸です。
プロジェクトメンバーで話し合い、全員で合意したことを提案しても、管理職や社長の視点が抜けていれば、最終的に通らないことがあります。そのため、研修で多くの視点で考えることを学べてよかったです。
公開講座では、他の会社の方々と一緒にワークに取り組みました。自分ではなかなか答えが浮かばないときに、すぐに答えを言える人がいて「自分はまだまだだ」という気付きもありましたね。
研修を受けてからは、何か問題に対処するとき、理想の状態を考えてから現状を整理して問題を把握する、という手順を踏むようになりました。フレームワークを学んだことで、次に自分が何をするべきなのかが明確になったのです。これまでは暗闇の中で一筋の光を見つけるような気持ちで解決方法を考えていたのですが、今はまず周囲を見渡してから進んでいけるようになり、心理的に楽に問題解決ができるようになりました。
さらに知りたいと思ったのは、具体的な事例です。研修の中では講師の方が関わった事例を教えていただいたのですが、他の事例も知ることができると、より知識を定着させやすいと感じました。
少し不便だと感じたのは、研修テキストが指定されたブラウザーでしか閲覧できなかったことです。WordやPDFなどのファイル形式であれば、さらに使い勝手がよいと思います。
学んだフレームワークを生かし、課題解決の推進役になってほしい
営業課長
研修受講前のCさんは、「課題解決のために何をしたらいいかがわからない」「どこで躓いているのかがわからない」という状態でした。研修受講によって、どのようなロードマップで課題解決を進めればよいのかが理解できたようです。研修受講後は、「課題解決フローのうち、出発点である『問題の洗い出し』に自信がない」と課題を特定できるようになっていました。
ただ、いきなり実務で活用する自信がなさそうでしたので、まずは「問題の洗い出し」の練習をしてもらうことにしました。題材は、自分が一番わかっている「自分自身」についてです。すると、かなりの数の問題点が出てきました。この数が視点の多さを意味しています。研修を受けたことで、フラットに自分自身の問題を洗い出せるようになったのです。
研修を通じて、期待していた通りの学びができてきたので、フレームワークを生かしながら問題を整理し、自信をもって課題解決を推進してほしいですね。
ご受講ありがとうございます
研修提供企業
この度は当社公開講座をご受講いただき、ありがとうございます。研修テキストについて、ご不便をおかけし申し訳ありません。オンライン受講の際、研修テキストはお申込み時点で、電子テキスト(ブラウザ使用)と冊子テキストのいずれかをお選びいただくことが可能ですので、今後ご受講をご検討の際は、用途にあわせてお選びいただければ幸いです。

自社に合う研修を探しても、いざとなると、なぜか躊躇して決め切れない……。どのような観点で検討すればいいのでしょうか?実際に研修を受講したスタッフと、研修を企画導入した担当者の体験を基に、研修設計や外部研修の導入・選択のヒントに迫ります。
会員登録をすると、
最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント