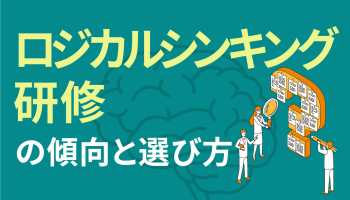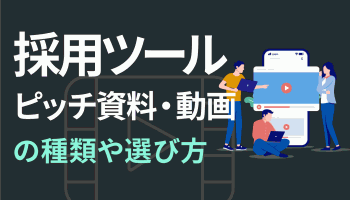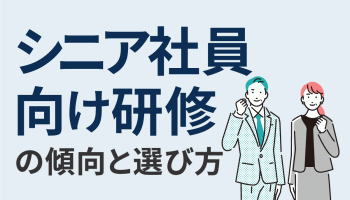「内定者フォロー」とは ~その目的
内定辞退者を出さない

内定者フォローの最大の目的は、辞退者を出さず、全員の入社を実現することである。せっかく時間と費用をかけて内定を出しても、辞退された瞬間にそれまでのすべての活動が無駄になってしまうからだ。
現在は「就職氷河期の再来」といわれ、内定者が辞退して他社に流れるケースは減少している。しかし、そういった状況下でも、辞退につながる要因は以前よりむしろ増えている。
1)内々定の早期化
新卒採用の早期化・長期化によって、春頃に内々定を出す企業もあるが、この場合、入社までの内定期間は約1年にも及ぶ。これだけ内定期間が長いと、内定者には、不安や迷い(内定ブルー)が生じる可能性が高くなる。
2)新卒採用の長期化、ネット化
量よりも質を重視する採用が一般的になった結果、春採用で良い人材を十分に確保できなかった企業が、夏以降も引き続き採用活動を行うケースが増えている。 これは、迷いが生じている学生にとって、受け皿が増えたことを意味する。また、その情報がネットを通じて、簡単に入手できる環境も整っている。
3)学生の二極化
「買い手市場」といわれる現在の採用戦線だが、一部の優秀な学生に複数の企業から内定が集中することもある。このように個人として「売り手市場」となっている学生には、内定後でもピンポイントで接触してくる企業が少なくないことを、認識しておく必要がある。
4)企業理解が不十分
早い段階で内々定が出た学生ほど、十分に企業理解ができていない。内々定を出した後も継続的に接触し、理解を深めさせていかないと、他社に流れる可能性が 増すことになる。また、無事に入社したとしても、企業理解が浅いままでは、モチベーション低下や早期離職につながりやすい。
5)学生の意識変化
現代の学生は、親たちが終身雇用や年功序列といった、既存の制度の崩壊に直面する様子を見て育った世代である。そのため、会社組織への依存心が強くなく、 物事の判断を自分軸で行う傾向が強い。いったん内定した企業でも、自分に合わないと思えば、あっさりと志望を転換することも十分にありうる。「内定者一人 ひとりが自社をどう見ているのか」にまで踏み込んで、フォローしていくことが大切である。
入社前教育
内定者教育には二つの側面がある。一つは、入社してから必要になる知識などを事前に身につけさせるため。もう一つは、社員の教育・育成に熱心である ことを内定者に伝え、ビジネスライフのさまざまな予備知識を得てもらうことで、学生の不安を払拭するためだ。現状では、内定者に対して強制的な研修を課す ことはできないので、多くの企業では、後者を中心とした自発的な内定者研修を支援する形をとっている。
内定者研修では、本来の教育効果以外にも、課題の提出などで人事担当者との接触が生まれ、社員を介して企業理解が深まること、自分に対して投資して くれているという満足感から企業へのロイヤリティーが高まることなどが期待できる。最終的には、内定辞退者を減らすことにもつながる。
同期意識の醸成

最近の学生は、人間関係に非常に敏感だといわれ、同期にどのような人物がいるのか、高い関心と不安を抱いている。内定期間中に同期と交流する場を設けることで、その不安を取り除くことができる。 いったん不安がなくなると、同期同士には結束が生まれる。内定辞退の発生を、未然に防ぐ効果も期待できるだろう。また、同期の一体感が醸成されると、入社後の新人研修やそれに続くOJTなどでも、同期同士で支えあうといったプラスの効果が生まれる。
入社への期待感、モチベーション強化
内定辞退に通じる不安や迷いは、情報不足が原因となっていることが多い。昨今の学生は、具体的な仕事内容まで細かく理解したいという欲求が強いため、十分な情報を発信することで、不安や迷いを、入社に向けての期待感や高いモチベーションに変えていくこともできる。
* *
このように内定者フォローには、単に内定辞退者を出さないためだけではなく、入社後の育成をスムーズに行ったり、ミスマッチを防いだりするという目 的もある。新卒採用は決して内定を出して終わりではない。入社、教育、育成と続く一連の流れの1プロセスとして、内定者フォローにも積極的な意味を見出し ていくことが重要である。
■新卒採用.jp―内定者フォロー
『日本の人事部』編集部が取材・作成。「新卒採用―内定者フォロー」の活用方法や業界の代表的企業の最新情報などコンテンツが満載。
企業の「新卒コンサルティング」の傾向と対策がわかるサイト 『新卒採用.jp―内定者フォロー』はこちら。
この記事を読んだ人におすすめ

人と組織の課題を解決するサービスの潮流や選定の仕方を解説。代表的なサービスの一覧も掲載しています。
会員登録をすると、
最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント