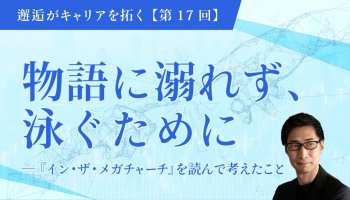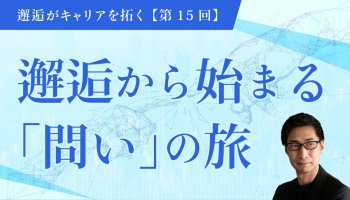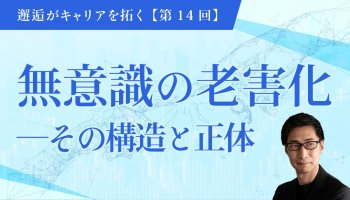邂逅がキャリアを拓く【第16回】
見えないものに挑む~『グラスハート』と『ブルーピリオド』の考察から~
YKK AP株式会社 専務執行役員CHRO
西田 政之氏
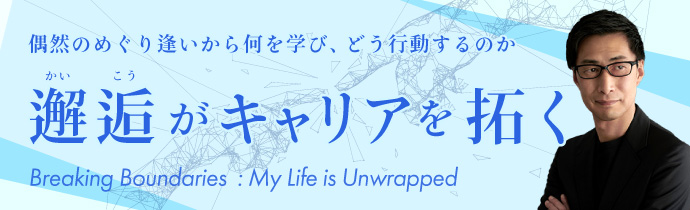
時代の変化とともに人事に関する課題が増えるなか、自身の学びやキャリアについて想いを巡らせる人事パーソンも多いのではないでしょうか。長年にわたり人事の要職を務めてきた西田政之氏は、これまでにさまざまな「邂逅」があり、それらが今の自分をつくってきたと言います。偶然のめぐり逢いや思いがけない出逢いから何を学び、どう行動すべきなのか……。西田氏が人事パーソンに必要な学びについて語ります。
人間の物語は、常に「見えないもの」との格闘から始まります。Netflixの配信ドラマ『グラスハート』と映画『ブルーピリオド』は、題材も舞台も異なりますが、その核心は同じです。それは「目に見えない何かへ、全身全霊で向かう」という、人間の最も人間らしい行為への讃歌です。
『グラスハート』では、登場人物たちが言葉にしきれない感情や衝動を抱え、それでも前へ進もうとする姿が描かれます。『ブルーピリオド』では、絵という手段を通して、自分でもつかみきれない「生きている感覚」を探し続ける若者の姿があります。両者に共通するのは、成果や評価といった「測れるもの」よりも、測れない熱量や誠実さに物語が寄り添っていることです。
音楽に人生を賭ける若者たち
『グラスハート』で印象的なのは、音楽に向き合う若者たちの集中と葛藤です。彼らは正解のない音を探し、互いの感情を響かせ合いながら、何度も音を合わせ、立ちはだかる数々の障害を乗り越えていきます。しかし物語の終盤に、解散の危機という最大の試練が訪れます。そこにあるのは、技術の向上や名声の獲得ではなく、「自分たちだけにしか生まれない音」にたどり着こうとする執念です。
佐藤健演じる孤高の天才ミュージシャン・藤谷が、天賦の才能からあふれ出る音を拾い集めながら、深夜のスタジオにこもる姿も描かれます。効率も採算も度外視……現代のビジネスでは「非合理」ですが、その非合理こそが彼を唯一無二にしています。
哲学者マルティン・ブーバーは『我と汝』で、人間は「対象」として相手を扱うときではなく、「汝」として全存在で向き合うときに、最も深い関係が生まれると述べています。彼らが音を合わせる瞬間は、まさにこの「我と汝」の関係に近い。そこでは評価ではなく、響き合う存在として受け止める。この関係性は、組織における信頼や創造性の源泉とも重なります。
企業に置き換えれば、市場が求める「わかりやすいヒット曲」ではなく、まだ世にない音楽を探すR&Dチームのようなものです。目先のKPIには結びつかないけれど、その探究が未来の基幹事業を生む。この構造は製品開発だけでなく、人材育成にも通じます。すぐに成果を出す社員ばかりを評価すれば、組織は安定するけれど停滞します。本当の成長は、測れない試行錯誤の中で育まれるのです。
キャンバスと向き合う孤独
一方『ブルーピリオド』は、眞栄田郷敦演じる主人公・矢口八虎が、安定的に優れた成績を持ちながらも「生きている実感」を求めて美術の道に踏み出す物語です。八虎が初めて夜明けの渋谷を描いたシーンは、観る者に強烈な既視感を与えます。あの「何かをつかんだ瞬間」の感覚。それは、昇進でも金銭的報酬でもなく、自分が本当に求めていた表現を見つけた瞬間に訪れます。
しかし、その後に訪れるのは、孤独な修練と果てしない比較の連続です。周囲には自分よりうまい人が山ほどいる。進路の保証もない。頼れるのは、自分の中の確信だけです。
哲学者ハンナ・アーレントは『人間の条件』で、人間の自由は「行為(Action)」の中にあり、その本質は予測不可能性にあると述べています。八虎の挑戦はまさにこの「行為」です。未来は見えず、結果も保証されなくても、動き出すことでしか新しい世界は開けません。
見えないものと向き合うリスク
社会は「見える成果」を好みます。数字、資格、受賞歴。しかし、二つの作品の登場人物たちが挑んでいるのは、それらとは真逆の「見えない賭け」です。ビジネスパーソンとしても、この姿勢は痛いほどわかります。キャリアのある時点で、誰しも“見えないもの”と向き合わざるを得ない局面に出会います。私にとっても、それは制度や組織をつくる仕事を超え、「人の生き方」と向き合う瞬間でした。
『ブルーピリオド』の中で象徴的なのは、八虎の右腕に現れたじんましん。いつもは理性的で器用に生きてきた彼にとって、美術の道は初めての本気の葛藤でした。その葛藤が「右腕のかゆみ」というかたちで可視化されたのです。講師から「自分勝手に楽しむ力が足りていない」と指摘を受けた直後に症状が出たことも偶然ではありません。
人間の身体は正直です。精神の緊張や不調は、じんましんや頭痛、不眠などとして確実に現れます。この“サイン”にどう向き合い、どう受け止めるかは、心理学的にも社会行動学的にも難しいテーマです。無視して突き進めば症状は強まりますが、過剰に反応すれば挑戦は止まります。ビジネスでも同じです。心身の兆候を読み取り、必要な調整をしながらも前進を止めない――このバランス感覚は、成果を出し続けるための重要な能力です。

ピュアであること、そして全力で挑むこと
両作品に共通する感動は、「純粋さ」が持つ異常なほどのエネルギーです。
『ブルーピリオド』の八虎がキャンバスに向かうとき、『グラスハート』の若者たちが音を重ねるとき、そこに打算はありません。むしろ、その純粋さゆえに、失敗や挫折の確率は高まります。それでもなお、全身全霊を注ぎ込む。この「バカみたいな純粋さ」は、経営においてしばしば軽視されます。しかし、変革期の組織には、計算された戦略だけでなく、純度の高い情熱が不可欠です。数字の裏にある「熱」を見抜き、そこに投資する。それができる経営者や人事は、短期的な成果を超えて未来をつくることができます。
私はこれまで、人間の極限状況を描いたヴィクトール・E・フランクルの『夜と霧』を、座右の書として繰り返し読んできました。そして、今回二つの作品に触れ、別の角度から「人間とは何か」に迫る機会を得ました。
『夜と霧』は、第二次世界大戦中にナチスの強制収容所へ収監された経験をもとに、極限の絶望の中でいかに生きる意味を見いだし、人生の目的を明確にしていくのかを描いています。これに対して、二つの作品は、日常という一見安全な領域で、それでもなお「見えない何か」に全力で挑む人間の姿を描いています。そこにあるのは、生死の瀬戸際ではなく、「意味の瀬戸際」です。何のために生きるのか、自分は何者なのか? その問いは、戦場や収容所だけでなく、都会の片隅や美術予備校の教室、そして音楽スタジオでも等しく突きつけられます。
邂逅が生む問い~生きるとは何か
私のコラムのテーマである「邂逅」は、偶然の出会いでは終わりません。その出会いが、自分に新しい問いを芽生えさせるとき、初めて邂逅はキャリアを拓く力に変わります。今回、二つの作品との出会いが投げかけた問いは、以下の通りです。
「見えないものに挑む勇気を、自分はまだ持っているか?」
「純度を保ちながら、成果を出し続けることは可能か?」
この問いは、私の職業的日常にも直結しています。人事の仕事では、制度設計や評価指標の改善という「見える成果」が求められる一方で、人間の成長や組織文化の醸成という「見えない成果」も追わなければなりません。見えないものを軽視すれば、組織は短期的成果主義に陥ります。見えるものばかり追えば、魂は摩耗します。両者のバランスを保つためには、信念という羅針盤が欠かせません。
結局、生きるとは何か? この問いは、哲学書よりも、時に一篇の物語が鋭く切り込みます。生きるとは、「まだ見ぬ自分」に出会うための旅です。『ブルーピリオド』の八虎は絵筆を握るたびに、過去の自分とは違う何かを描こうとします。『グラスハート』の人物たちも、音を重ねるたびに新しい自分を探し続けます。それは、変化し続けることの肯定であり、同時に過去を超える自分への挑戦でもあります。
私もまた、キャリアの節目でこの問いを突きつけられてきました。転職、組織改革、副業、塾運営、森林保全、そのすべては「まだ見ぬ自分」に出会うためのプロセスだったと今では思います。そして、この旅には終わりがない。人間は、問いを持ち続ける限り、変わり続けられる存在なのです。
【参考】
『グラスハート』
原作:若木未生『グラスハート』シリーズ(幻冬舎刊)
企画・共同エグゼクティブプロデューサー:佐藤健
監督:柿本ケンサク/後藤孝太郎
制作:Netflixオリジナル
『ブルーピリオド』
原作:山口つばさ『ブルーピリオド』(講談社「月刊アフタヌーン」連載)
監督:萩原健太郎/脚本:吉田玲子
制作プロダクション:C&Iエンタテインメント、製作:映画「ブルーピリオド」製作委員会
配給:ワーナー・ブラザース映画

- 西田 政之氏
- YKK AP株式会社 専務執行役員CHRO
にしだ・まさゆき/1987年に金融分野からキャリアをスタート。1993年米国社費留学を経て、内外の投資会社でファンドマネージャー、金融法人営業、事業開発担当ディレクターなどを経験。2004年に人事コンサルティング会社マーサーへ転じたのを機に、人事・経営分野へキャリアを転換。2006年に同社取締役クライアントサービス代表を経て、2013年同社取締役COOに就任。その後、2015年にライフネット生命保険株式会社へ移籍し、同社取締役副社長兼CHROに就任。2021年6月に株式会社カインズ執行役員CHRO(最高人事責任者)兼 CAINZアカデミア学長に就任。2023年7月に株式会社ブレインパッド 常務執行役員CHROに就任。2025年6月より現職。日本証券アナリスト協会検定会員、MBTI認定ユーザー、幕別町森林組合員、日本アンガーマネジメント協会 顧問も務める。
この記事を読んだ人におすすめ
-

タナケン教授の「プロティアン・キャリア」ゼミ【第76回】 キャリアショックと感情知性―AI導入が醸す、人事という仕事の本質―
-

松﨑 毅さん: 人事施策は60点でいいからまず共有し、みんなで100点に練り上げていく 時代の流れをつかみ「実現力」へとつなげる、人事の「先見性」と「決断力」
-

ポラス株式会社: 学ぶことも業務――就業時間内の受講、評価制度との連動 ポラスが学びの文化を醸成した企業内大学の仕組みとは
-
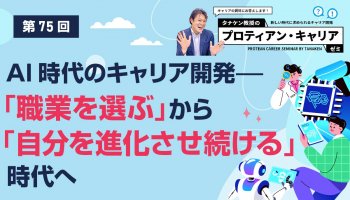
タナケン教授の「プロティアン・キャリア」ゼミ【第75回】 AI時代のキャリア開発――「職業を選ぶ」から「自分を進化させ続ける」時代へ
-

タナケン教授の「プロティアン・キャリア」ゼミ【第74回】 “このままでいいのか”の先へ──ミドルシニア・リスキリング

HR領域のオピニオンリーダーによる金言・名言。人事部に立ちはだかる悩みや課題を克服し、前進していくためのヒントを投げかけます。
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる2
- 理解しやすい0
- 1
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント