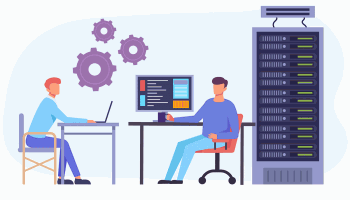【真の残業削減を実現する】「営業職」の労働時間短縮のための業務見直しのポイント
時短コンサルタント・社会保険労務士
山本 昌幸
I. 「長時間労働」を取り巻くリスクにはどんなものがあるか?
1. 事業場外みなし労働時間制はもう使えない?
「阪急トラベルサポート事件」の最高裁判決では、海外旅行派遣添乗員に対する事業場外みなし労働時間制の適用が否定されました。このことは営業職員を抱え、事業場外みなし労働時間制を採用している企業にとって対岸の火事ではなく、今後、通達等により、当該営業職への事業場外みなし労働時間制の適用について大きな制約を受ける可能性があることに鑑みて、自社の問題として対応する必要があります。
2. 事業場外みなし労働時間制は企業にとって「都合の良い制度」ではない
事業場外みなし労働時間制について、勝手に都合の良い解釈をしている企業に遭遇することが、よくあります。
そもそも、「事業場外みなし労働時間制」とは、労働者が事業場外で労働することにより、労働時間の把握・算定が困難な場合に採用する制度ですが、時として「時間外手当を支払いたくないので、みなし労働時間制を採用したい。そのためにはどのような現状であればよいか?」と質問されるケースがあります。ひどい場合には、「どのような現状であることにすればよいか?」との質問を受けることもあります。

これは、助成金申請でありがちなケースに類似しています。助成金も、企業が講じる諸施策がその支給要件に該当している場合(もしくはそれに近い場合を含む)に申請するものであって、助成金をもらうために策を講じてその要件に無理やり該当させるというものではありません。
このように、事業場外みなし労働時間制の採用であれ助成金受給であれ、企業における運用が適切でないと判断されるような事実が認められる場合には、後日、事業場外みなし労働時間制の適用が否定されたり、不正な助成金受給と判断されたりする場合があります。
今回の最高裁判決は、このような都合の良い解釈をしている企業や、事業場外みなし労働時間制を採用しているからと言って長時間労働が発生している実態を放置し、残業削減に取り組む意識のない企業や管理職、労働者の姿勢に大きな一石を投じるものでしょう。
3. なぜ、長時間労働はなくならないのか?
長時間労働がなくならない理由は、そもそも企業に「長時間労働をなくす気がない」からでしょう。なぜなくす気がないのでしょうか? 大きな理由のひとつに、この事業場外みなし労働時間制の採用があると思われます。
事業場外みなし労働時間制を採用している多くの企業では、就業規則上、「所定労働時間(通常の就業時間)働いたものとみなす」という規定になっているようです。すると、営業職員がダラダラと長時間働いても効率良く働いて労働時間を削減しても、所定労働時間(もしくは通常必要とされる時間)働いたものとみなされ、支払う賃金の額に増減がありません。
その結果、営業職員の拘束時間(ここではあえて“拘束時間”と表記します)が休憩時間を含めて9時間であろうが12時間であろうが、企業が営業職員に支払う賃金の額は変わらないので、あえて拘束時間を削減する必要性も感じないのです。もちろん、CSR(企業の社会的責任:corporate socialre sponsibility)の観点からは非常に好ましくないため、CSRに敏感な企業においては、事業場外みなし労働時間制を適用している営業職員に対して何らかの対策を施していると思われますが、企業全体からみると少数にとどまると言えます。
4. 長時間労働に伴うリスクとは?
事業場外みなし労働時間制の採用により、支払う賃金の額に増減が生じないからと言って、長時間労働をさせる法的リスクまでなくなるわけではなく、むしろ非常に高いと言えます。そのリスクとは、(1)安全配慮義務違反と(2)事業場外みなし労働時間制の適用が否定された場合に発生する割増賃金の支払いです。
事業場外みなし労働時間制を採用していても、営業職員が脳・心臓疾患を発症したり、メンタルヘルス不調になったりした場合、その原因の一端に長時間の拘束があり業務起因性が認められれば、安全配慮義務違反を問われる可能性があります。また、事業場外みなし労働時間制の適用が否定された場合、その適用が無効と判断されるのか取消しになるのかの違いはあれ、企業は対応を迫られることになります。
さらに、2010年4月に施行された改正労働基準法により、1ヵ月に60時間を超える時間外労働を行う場合の割増賃金率が50%以上となりました。現在は中小企業への適用は猶予されていますが、「改正法附則3条」には、「施行後3年を経過した場合において、(中略)施行の状況、時間外労働の動向等を勘案し、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」とされており、本年4月時点では4年経過しています。また、昨年9月に実施された「第103回労働政策審議会労働条件分科会」でも議題に上っており、現在も議論が続けられています。
他にも、1ヵ月の時間外・休日労働時間が45時間を超えると健康障害のリスクが高まるとして、労働安全衛生法および労働安全衛生規則、通達等で労働者の健康管理に係る措置を講じるよう定めていますので、それらへの対応も必要です。
以上のことから、企業は、事業場外みなし労働時間制の対象としている営業職員の労働時間短縮に取り組む必要があると言えます。
5. 「小手先の労働時間短縮」では問題を根本的に解決することはできない
本稿では、小手先ではない営業職の根本的な労働時間の短縮手法について解説したいと思います。ちなみに、筆者の言う「小手先の労働時間短縮」とは、事業場外みなし労働時間制はもとより変形労働時間制等を指します。なぜなら、これらの制度は、採用したところで労働者の労働時間そのものは少しも削減することができませんが、企業が支払う残業代だけは削減できる、企業にとってのみ都合の良い制度だからです(企業にとっては非常にありがたい制度ですので否定はできませんが)。また、「残業申告制」の採用や「ノー残業デー」の設置等も単なる対処療法であり、これらも“小手先の手法”と言えるでしょう。
確かに“小手先の手法”でも効果が出ることはあるのですが、本来、「問題には必ず原因がある」のです。ですから「残業時間の発生=問題発生」と捉えて、その原因を明確にしたうえで対策を施すことが、真の労働時間短縮方法であると言うことができます。
なお、本稿で紹介する対策は、営業職員に限らず、すべての職種を対象とすることが可能であることを付け加えておきます。
この記事を読んだ人におすすめ

人事の専門メディアやシンクタンクが発表した調査・研究の中から、いま人事として知っておきたい情報をピックアップしました。
会員登録をすると、
最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0
- その他3
- 1
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント