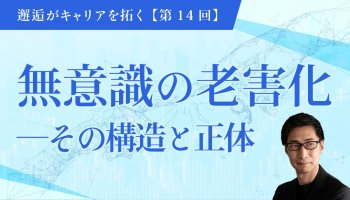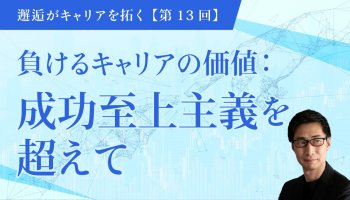邂逅がキャリアを拓く【第17回】
物語に溺れず、泳ぐために
――『イン・ザ・メガチャーチ』を読んで考えたこと
YKK AP株式会社 専務執行役員CHRO
西田 政之氏

時代の変化とともに人事に関する課題が増えるなか、自身の学びやキャリアについて想いを巡らせる人事パーソンも多いのではないでしょうか。長年にわたり人事の要職を務めてきた西田政之氏は、これまでにさまざまな「邂逅」があり、それらが今の自分をつくってきたと言います。偶然のめぐり逢いや思いがけない出逢いから何を学び、どう行動すべきなのか……。西田氏が人事パーソンに必要な学びについて語ります。
今年の夏の暑さがピークを迎えた頃、朝井リョウさんの小説『イン・ザ・メガチャーチ』を読みました。そして、ちょうど同じ時期に手に取ったのが、難波優輝さんの『物語化批判の哲学』という本です。この二冊を続けて読んだことが、私にとっては大きな“思いがけない邂逅”になりました。
どちらの本も、人間が「意味」や「語り」にすがって生きる存在であることを真正面から扱っています。『イン・ザ・メガチャーチ』では、ファンダムやSNSの共感が、もはや宗教のように機能する現代が描かれています。一方、『物語化批判の哲学』は、人間が何でも物語化してしまう性(さが)を見つめながら、「語ることの優しさ」と「語りすぎることの危うさ」を哲学的に掘り下げています。まったく異なる文体の二人が、奇しくも同じ問いを発しているように感じました。
「やってこなかったこと」が還ってくる
『イン・ザ・メガチャーチ』を読んで、最も胸に残ったのは冒頭の一節でした。
(本文3頁)
この言葉に、私は強く共感しました。胸にグサッときた、という表現の方が正確かもしれません。努力や蓄積が報われる、という古典的な「物語」を、私たちはどこかで信じています。しかし、変化のスピードが激しい現代では、“やってこなかったこと”が突如として扉を開くことがあります。
これまで避けてきた挑戦、見送ってきた他者との関係、軽んじてきた感情。そうした「空白」や「欠落」が、ある日ふと、人生の中心に還ってくる。朝井さんのこの一文には、そんな“逆流のリアリティ”が息づいているように思いました。
哲学者 ハンナ・アーレントは「人間の行為とは、予測できない結果を生むものだ」と語りました。行動の果実は、努力や計画だけでは説明できない。だからこそ、過去の“未完の部分”に光を当てる朝井さんのまなざしが、私にはとても新鮮でした。
物語に救われる、という安心と危うさ
人は、意味のない出来事に耐えられません。だからこそ、どんな出来事にも「意味」や「筋書き」を与えようとします。アーレントが言うように、人間は“意味づける動物”なのです。
しかし、難波さんの『物語化批判の哲学』が教えてくれたのは、「意味づけ」はしばしば“現実の豊かさを削ぐ行為”でもある、ということです。物語化は、混沌(こんとん)を整理する力である一方で、切り取られなかった部分、つまり、理解できなかった痛みや曖昧さを、「なかったこと」にしてしまう危険をはらんでいます。
『イン・ザ・メガチャーチ』の登場人物たちは皆、その“物語の安心”にすがりながら、自分を保とうとしています。そして、朝井さんはその先にある“信じさせられる構造”を描き出しています。誰かの物語に乗ることで、安心は得られても、自由は失われていく。私たちは、自分を救うつもりで、他者の物語の中に閉じ込められてしまうことがあるのです。
“語られる私”から“語る私”へ
哲学者 ポール・リクールは、「人は自分の人生を語ることで、初めて自己を理解する」と言いました。しかし現代の私たちは、“語ること”を他人やシステムに委ねる傾向が強まっています。SNSのアルゴリズムや会社の評価制度が、私たちの“語り”を先回りしてくれる。気づけば、自分の物語は「語られるもの」になっています。
会社での評価やSNSの反応が、自分の意味づけを代行してくれる。便利で安全ですが、そこには「自分の物語を自分で語る苦しみ」が失われています。朝井さんの作品は、その構造の冷たさに静かな警鐘を鳴らしています。語らないことで楽になる一方で、人は“生きている実感”を失っていく。物語を語る力を手放した社会は、思考する力をも同時に失っていくのかもしれません。
このテーマは、組織にもつながります。企業理念やミッションステートメントは、本来“共に考えるための物語”です。それがいつの間にか“信じるための教義”に変わるとき、組織は思考よりも忠誠を求める場になってしまいます。
理念浸透は人事部の役割の一丁目一番地です。現場でときに耳にする「理念に共感できる人だけが残ればいい」という純粋培養の方針は、聞こえはよくとも、“疑う自由”を奪いがちです。アーレントが言うように、思考は自分自身との対話です。理念もまた、対話の場であるべきです。信じることと疑うこと、その両方が許される場所こそ、健全な組織の証ではないでしょうか。
物語とどう距離をとるか
難波さんは「物語化をやめよ」とは言いません。むしろ「物語から距離をとりながら、それでも語る」ことの大切さを説いています。それは、泳ぎに似ています。
水に身を任せすぎると沈みますし、力を入れすぎると前に進めません。適度に力を抜き、呼吸をしながら進む。物語との関係も同じです。信じすぎず、疑いすぎず。物語の中で世界を感じながら、ときどき顔を上げて現実の空気を吸う。
この「泳ぐ」比喩を読んだとき、私は永井均さんのエッセイ『水中の哲学者たち』を思い出しました。永井さんは、哲学するとは「水の中で息をしようとすること」だと言います。水面上に出て安全な場所から語るのではなく、上下の区別もつかない水中で、もがきながら思考を続ける。それは、完全に沈むことを恐れず、それでも呼吸を試みる営みです。
難波さんのいう「泳ぐように語る」と、永井さんの「沈みながら考える」は、方向は違っても根は同じだと思います。どちらも、「息を止めない」ことを大切にしている。物語に溺れず、しかし切り離さず、呼吸を続けること。思考とは、まさにそうした“呼吸のリズム”に似ているのかもしれません。
『イン・ザ・メガチャーチ』の登場人物たちは、その呼吸を忘れていました。物語に没入し、現実を見失い、他人の“信仰”に飲み込まれていきます。だからこそ、この小説を読む私たちは、「どうすれば溺れずに泳げるのか」を考え直すことになるのです。
浅井さんはエッセイ『そして誰もゆとらなくなった』の中で、笑いと排泄の力で社会の偽善を軽やかに暴きました。下品さを通して、人間の本音をさらけ出しています。対して『イン・ザ・メガチャーチ』は、整った文体の中で、同じ暴力性を描いています。汚れを笑って見せる代わりに、“清潔さの中の狂気”をえぐり出しているのです。
この二つの顔を思うと、人間の不完全さが少し愛おしく感じられます。人は「汚れたまま信じたい」し、「笑いながら祈りたい」。その両方を行き来するのが、人間らしさなのだと思います。朝井さんがその極のあいだを自在に往復しているからこそ、彼の作品には深いリアリティが宿っているのだと感じます。
物語を生きる、ではなく、物語と生きる
キャリアも人生も、物語として語りたくなります。しかし、あらかじめ用意された物語をなぞるだけでは、誰かの信仰の中で生きているのと変わりません。
「語る」とは、信じながら同時に疑うことです。言葉にした瞬間、現実はいつも少し逃げていきます。それでも語る。それが人間の誠実さであり、自由への試みだと思います。
『イン・ザ・メガチャーチ』は、共感が信仰に変わる社会を描きながら、その外側で息をするための“呼吸法”をそっと教えてくれます。信じるために語るのではなく、語りながら信じ方を探す。その不安定さの中に、私たちはまだ生きています。
【参考・引用文献】
朝井リョウ著『イン・ザ・メガチャーチ』
朝井リョウ著『そして誰もゆとらなくなった』
難波優輝著『物語化批判の哲学』
永井均著『水中の哲学者たち』
ハンナ・アーレント著『人間の条件』
ポール・リクール著『時間と物語』

- 西田 政之氏
- YKK AP株式会社 専務執行役員CHRO
にしだ・まさゆき/1987年に金融分野からキャリアをスタート。1993年米国社費留学を経て、内外の投資会社でファンドマネージャー、金融法人営業、事業開発担当ディレクターなどを経験。2004年に人事コンサルティング会社マーサーへ転じたのを機に、人事・経営分野へキャリアを転換。2006年に同社取締役クライアントサービス代表を経て、2013年同社取締役COOに就任。その後、2015年にライフネット生命保険株式会社へ移籍し、同社取締役副社長兼CHROに就任。2021年6月に株式会社カインズ執行役員CHRO(最高人事責任者)兼 CAINZアカデミア学長に就任。2023年7月に株式会社ブレインパッド 常務執行役員CHROに就任。2025年6月より現職。日本証券アナリスト協会検定会員、MBTI認定ユーザー、幕別町森林組合員、日本アンガーマネジメント協会 顧問も務める。
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる1
- 理解しやすい0
- 1
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 調査
調査 人事辞典
人事辞典 イベント
イベント