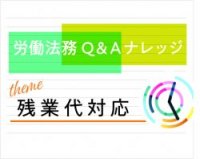固定残業代の計算根拠について
当社では、固定残業代40時間分を基本給、諸手当とは別に支給しています。
昨年度から支給を開始し、時間単価を【基本給+諸手当】の金額から計算し、2024年度の平均所定労働時間から固定残業時間を法定内20.33時間、法定外19.67時間と定め各個人の固定残業代を計算しました。
疑問点
①毎年月の平均所定労働時間は変わりますが、固定残業代の計算根拠を【法定内20.33時間、法定外19.67時間】と就業規則で定めても問題無いでしょうか。(固定残業時間40時間分が8万円だったとして、月の残業時間が8万円を超えた場合は別途1分単位で支給する前提です。)
②この計算式ですと、実際には40時間分では無い年もあるという認識です。例えば今年度であれば、2024年度よりも弊社の所定労働時間が短いため、時間単価が上がり、差としては微々たるものですが、固定時間は40時間には満たないです。逆に時間単価が2024年度よりも低くなれば実質固定時間は40時間を上回る場合もあると思います。
実質固定残業時間が40時間に満たない場合は従業員の不利益にはならないため問題は無いと思っておりますが、40時間を上回る場合は不利益に該当するでしょうか。また、このような運用は従業員からの同意があれば可能でしょうか。
③上記運用が可能であった場合、求人サイトなどには(○○円 固定残業40時間相当)のような表記でも問題無いでしょうか。
④上記運用が法的に問題があるということでしたら、固定残業代の計算根拠を固定して、毎年計算をし直す必要がない運用方法などはございますでしょうか。固定残業代の取り扱いについては法令で定められているものではなく、固定分を超えた未支給分を支払う(未払いの残業代が無いように気を付ける)、法定の上限を超えないようにするという労働基準法の時間外労働に関する法令に則れば比較的自由に設計ができるものであり、上記運用でも問題無いと思っているのですが…。
ご回答のほどよろしくお願いいたします。
投稿日:2025/04/26 19:19 ID:QA-0151540
- オキナワノジムさん
- 沖縄県/旅行・ホテル(企業規模 11~30人)
この相談を見た人はこちらも見ています
-
みなし残業について 質問ですが、当社では 月30時間分のみなし残業代(125%)を支給しております。みなし残業の30時間の中には、30時間分の残業代、平日深夜、休日、休日深夜... [2009/05/15]
-
休日にかかった深夜残業 いつもお世話様です。さて、質問させてください。当社は土日はお休みなのですが、たとえば金曜に残業をして、そのまま土曜の深夜2時まで残業した場合、土曜になって... [2008/06/24]
-
法定内残業をみなし残業に含むことはできますか 午前休を取得して、残業した場合の法定内残業(所定外で100%支払う分)はみなし残業に含めることはできますでしょうか。 [2018/08/03]
-
半日勤務時の残業について みなし残業導入時の残業について質問させてください。当方では月30時間分の残業代を支給しております。残業代は、時給×1.25×30時間で算出しております。半... [2017/02/28]
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
「平均所定労働時間」が変動しても、「法定内20.33時間・法定外19.67時間」で固定して就業規則に定めることは可能か?→ 可能です。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.「平均所定労働時間」が変動しても、「法定内20.33時間・法定外19.67時間」で固定して就業規則に定めることは可能か?→ 可能です。
就業規則等で「固定残業代の対象時間(例:法定内○時間+法定外○時間)を固定して」明記するのであれば、その時間数の根拠が合理的に説明できる限り、毎年平均所定労働時間が変動しても直ちに違法にはなりません。また、超過分を1分単位で別途支給する運用をしていれば、未払残業代問題もクリアできます。ポイントは、「固定」しても、超えた分はきちんと支払う」 ことです。
2.実質的に「固定40時間」を超える年も出るが、問題はないか?
また、従業員の同意があれば運用可能か?
→ 結論:実質40時間未満になった場合 → 問題なし(従業員にとって有利なので)
実質40時間を超える場合 → 原則、不利益変更になる可能性があるため、「就業規則の変更手続き+従業員への周知・合意」が必要になります。今回のケースでは「平均値で計算し、多少の年ごとのズレは微々たるもの」と想定されていますので、極端なズレ(例えば実質固定時間が42時間や43時間など)にならない限り、事前に「固定時間数は平均に基づき設定しており、年により実質時間が上下する可能性がある」と周知・合意を取っておけば運用可能でしょう。ただし、年によって10%以上超える(44時間、45時間相当)などになった場合は、再度、慎重な対応(例えば固定残業時間の見直し)が必要です。
3.求人広告に「○○円 固定残業40時間相当」と書いてよいか?
→ 基本的に問題ありませんが、注意点ありです。表記する場合、以下を必ずセットで記載してください。固定残業代に相当する金額と時間(例:8万円・40時間分)
超過分は別途支給する旨、固定残業代に含まれる業務内容の例示(可能なら)
つまり、
(1)「固定残業代8万円(法定内20.33時間+法定外19.67時間、合計40時間分)を含む」
(2)「超過分は別途1分単位で支給します」
と明記すれば、問題ありません。
4.そもそも「毎年計算し直す」ことなく、固定した運用ができる方法はないか?
「固定残業代の時間と金額を一定」としてしまい、年次の所定労働時間に合わせない運用が可能です。つまり、毎年の所定労働時間を反映しない
「常に○時間分、○○円を支給する」と定めておく、ただし、超過分は必ず別途支払う。これなら、「毎年再計算し直す」作業が不要になります。
(もちろん、社会情勢が大きく変わったりしたときは、見直し検討は必要です。)
質問者様の認識通り、労働基準法では「固定残業代制度自体を禁止」しているわけではないので、労基署からの指摘リスクも、設計と運用を正しくやれば極めて低いです。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/04/28 09:46 ID:QA-0151550
相談者より
当方の認識の通りで安心しました。ご回答ありがとうございます。
投稿日:2025/05/01 11:07 ID:QA-0151651大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問のケースについて、回答させていただきます。
1.ご記載の内容で就業規則に定めることは問題ございません。
2.固定残業代は、〇時間分の法定外(又は法定内)の所定労働時間に対して、
〇円を支払うという性質であり、対象となる時間がベースになります。
よって、残業基礎単価を求める際の、所定労働時間が年によって変動すれば、
残業基礎単価も変動しますので、固定残業代は、年によって変動しなくては
なりません。貴社の会社規程に沿った対応が必要ですので、一概に、
労働者の同意があれば問題ないと言えるものではございません。
3.概ね問題になることは無いかと思いますが、法定内20.33時間、法定外19.67時間
と記載を詳細に分けていただいく方が適切であります。
4.固定残業代を毎年、変動しないようにするには、残業基礎単価を求める際の、
所定労働時間を、社員が有利になるよう少し余裕を持った短い時間にて、
固定することが代表的かと存じます。つまり、残業基礎単価を求める際の、
所定労働時間は、〇時間に固定化する方法でございます。
投稿日:2025/04/28 10:02 ID:QA-0151555
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、固定残業代の支給内容をどのように設定されるかに関しましては会社が任意で定める事柄ですので、それ自体で問題とはなりません。(※問題となるのは、下記の2で示す場合です。)
2につきましては、40時間を超える場合に問題となるのではなく、40時間を超える・超えないに関わらず、実際の残業時間に基づく賃金計算の額が固定残業代の額を上回る場合に問題となります。例えば、実際の残業時間の内訳が「法定内20.33時間、法定外19.67時間」とは異なり法定外の比率が高い場合ですと、仮に40時間の残業時間しか勤務されていなくとも固定残業代の額には不足が生じますので、不足分について追加の賃金支給が必要となります。こうした支給がされなければ、賃金全額払いの原則違反となりますので、労働者の同意が有っても違法行為として認められません。
3につきましては、1と同様にそれだけで問題とはなりません。
4につきましては、毎年平均の勤務時間等から細かく算出し設定されても実務上は殆ど無意味ですので、単純に各20時間ずつに固定される等計算し易い内訳にされるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2025/04/28 18:38 ID:QA-0151577
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
みなし残業について 質問ですが、当社では 月30時間分のみなし残業代(125%)を支給しております。みなし残業の30時間の中には、30時間分の残業代、平日深夜、休日、休日深夜... [2009/05/15]
-
休日にかかった深夜残業 いつもお世話様です。さて、質問させてください。当社は土日はお休みなのですが、たとえば金曜に残業をして、そのまま土曜の深夜2時まで残業した場合、土曜になって... [2008/06/24]
-
法定内残業をみなし残業に含むことはできますか 午前休を取得して、残業した場合の法定内残業(所定外で100%支払う分)はみなし残業に含めることはできますでしょうか。 [2018/08/03]
-
半日勤務時の残業について みなし残業導入時の残業について質問させてください。当方では月30時間分の残業代を支給しております。残業代は、時給×1.25×30時間で算出しております。半... [2017/02/28]
-
時短勤務者の残業時間 育休を取っていた方が時短で復帰しまして、休憩1時間を含め1日7時間勤務となりました。ただ、時間通りにあがることはほぼほぼ難しく、毎日30分~1時間ほどの残... [2017/06/07]
-
週40時間超の割増賃金は固定残業代に含まれるか 所定労働時間が週40時間を超えて勤務した場合、超過時間は25%の割増賃金を支払わなければならないかと思います。固定残業代(みなし残業)を取り入れている場合... [2025/01/06]
-
法定内残業と法定外残業の合算時間が固定残業時間を超える場合 初めて相談させていただきます!弊社では、みなしの固定残業が35時間分設定してあります。35時間以上の残業をした場合は超過分を支給しておりますが、下記の場合... [2023/11/07]
-
深夜残業代計算について 本題のタイトルで一つ教えてください。(30時間のみなし残業)時間外残業代や深夜残業代の計算についてですが、正しい考え方を教えていただきたくお問い合わせしま... [2021/10/04]
-
みなし残業について
みなし労働について みなし残業を導入する事で、使用者にみなし労働たから残業するようにと残業指示を出すことは可能でしょうか?特に昨今は休業のこともあり、休業以外の出勤日は残業さ... [2020/06/27]
-
固定残業制 私の会社は現在、一部の社員に固定残業制を導入しています。仮に残業時間20時間に30000円とします。先日社長が、残業時間が20時間に満たない者は残業代を支... [2020/08/31]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント