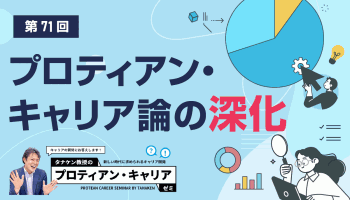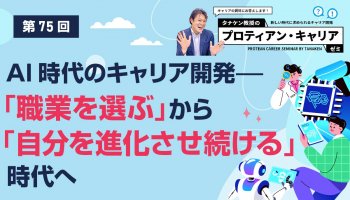タナケン教授の「プロティアン・キャリア」ゼミ【第70回】
最先端のキャリアAIドック:個人と組織の持続的成長を導くキャリア開発の新境地
法政大学 キャリアデザイン学部 教授
田中 研之輔さん
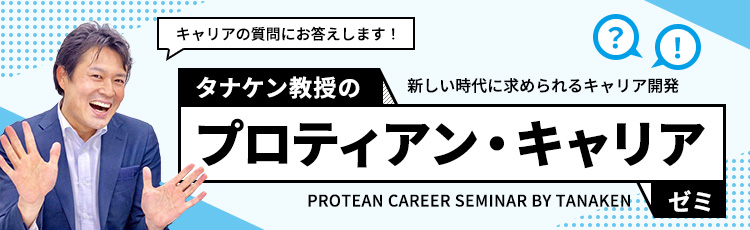
令和という新時代。かつてないほどに変化が求められる時代に、私たちはどこに向かって、いかに歩んでいけばいいのでしょうか。これからの<私>のキャリア形成と、人事という仕事で関わる<同僚たち>へのキャリア開発支援。このゼミでは、プロティアン・キャリア論をベースに、人生100年時代の「生き方と働き方」を戦略的にデザインしていきます。
私たちを取り巻くキャリアの風景は、いま大きく変貌しつつあります。終身雇用や年功序列といった “前提”はすでに揺らぎ、人生100年時代においては「働く」と「生きる」を重ね合わせながら、自らのキャリアを再構築していくことが求められています。
現代のキャリア形成が、かつてないほどの流動性と複雑性に直面する中で、働き方の多様化、副業・兼業の一般化、人生100年時代の到来などにより、従来のキャリア支援の枠組みは根本的な見直しが欠かせません。そのような変化の中、今回のプロティアン・ゼミで取り上げてみたいのが、私がいま最も可能性を感じている「キャリアAIドック」です。
まず、従来のキャリアドックがいかなる問題点を抱えていたのか、それに対していかにAIによる再定義が進められているのかを、最新の理論と技術動向に基づいて解説します。そして、個人と組織の双方におけるキャリア支援の在り方が、AIによってどのように変容しうるのか、その可能性と課題を明らかにしていきます。プロティアン・キャリアの理念と共鳴しながら進化する「キャリアAIドック」の最前線の動向を見ていくことにしましょう。
キャリアドックの意義
キャリアドックとは、企業が主体となって従業員のキャリア形成を支援する仕組みであり、厚生労働省が提唱する「セルフ・キャリアドック制度」にその源流を持ちます。医療における人間ドックになぞらえ、「キャリアの定期健診」と位置づけられており、社員一人ひとりが自身のキャリアを定期的に見直し、未来に向けた成長戦略を描くことを目的としています。人生100年時代を迎え、働き方が多様化する中で、個人が自律的にキャリアを形成する力を高め、同時に組織としての人材活用力を強化するための重要な施策とされています。
キャリアドックの中核には、キャリアコンサルティングの実施があります。国家資格を有するキャリアコンサルタント、あるいは社内に配置された面談担当者が、個別に面談を行い、本人のこれまでの職務経験、価値観、志向性、不安、将来の希望といった情報を丁寧に掘り下げていきます。この対話を通じて、個人は自己理解を深め、現在の業務との適合度や将来的な可能性を認識することができるようになります。面談の結果は、個人にとってのキャリア方針の明確化につながるとともに、組織にとっては人材育成や配置戦略を考えるうえでの貴重な情報資源となります。
キャリア面談は単独で行われるのではなく、組織の教育研修体系や人事制度と連動して実施されることが理想とされています。たとえば、面談後には、自己理解をさらに深めるキャリアデザイン研修や、必要なスキルを補完するリスキリング講座などが用意されることもあります。将来的な配置転換や職務拡張に向けた育成プランの設計と接続されることで、キャリア開発支援が単なる「自己啓発の奨励」ではなく、「戦略的人材開発」として機能するのです。
導入のタイミングとしては、年齢やキャリアの節目が意識されます。たとえば、入社3年目の若手社員にはキャリアの定着を促すため、30歳前後では中期的な成長戦略を立てる契機として、40代ではマネジメントや専門職としての深化を見据え、50代ではセカンドキャリアの設計や役職定年後の活躍に備える時期として実施されることが多くなっています。また、育児復職者や病気休職からの復帰者といった、ライフイベントに伴うキャリア変容の局面においても、キャリアドックは効果的な支援手段となります。
実際にキャリアドックを導入した企業からは、さまざまなポジティブな効果が報告されています。若手社員の離職率が低下した事例、中堅社員の越境的な異動や新規プロジェクトへの参加が促進した事例、また、50代社員のキャリア再起動が図られた事例などが挙げられます。これらの成果は、キャリアドックが単にキャリアを“考える機会”を提供するだけでなく、“行動変容”を後押しする役割を果たしていることを示しています。

キャリアドックの課題
一方で、キャリアドックにはいくつかの課題も指摘されています。第一に、実施が一過性のイベントにとどまりがちである点です。年に一度の定点観測に終始し、継続的なフォローアップや学びの機会に結びつかない場合、個人のキャリア形成に実効性を持たせることは難しくなります。
第二に、面談の質のばらつきも課題です。面談者のスキルや経験に依存する部分が大きいため、的確な支援が提供されないケースもあります。
第三に、組織の人事戦略との連動が不十分であると、個人のキャリアの気づきが組織の施策に反映されず、結果として「やって終わり」になってしまう危険性もあります。
こうした限界を踏まえ、近年ではキャリアドックをデジタル技術でアップデートする動きが加速しています。特に注目されているのが、「キャリアAIドック」への進化です。
キャリアAIドックとは何か
キャリアAIドックとは、生成AIや機械学習を活用し、個人のキャリア資本、志向性、業界適合性、未来可能性を動的に可視化・提案する、極めて高度なキャリア支援システムです。従来のキャリアドックが「人による問診と面談中心」であったのに対し、AIドックは「データ主導・個別最適化・継続支援型」である点が大きな特徴です。
進化のポイントは以下の三点に集約されます。
静的から動的へ:スナップショット的な診断から、時間軸を含めたキャリア変容の追跡・予測へ。
主観から客観へ:自己申告型から、言語データ・行動ログ・スキルマップなどを含めた多次元解析へ。
画一から個別へ:テンプレート的フィードバックから、個人の価値観・人生戦略に沿ったパーソナライズド支援へ。
このように、キャリアAIドックは従来のドックの「深化」であると同時に、「変革」でもあります。
理論的背景:プロティアン・キャリアとキャリア・エンゲージメント
キャリアAIドックは、現代のキャリア理論に基づいた設計がなされており、なかでも「プロティアン・キャリア理論」(Hall, 2004)および「キャリア・エンゲージメント理論」(Hirschi, 2014)との親和性が高いです。環境変化に応じて自己変容し続けるキャリア観をベースにしたプロティアン・キャリア知見とAIによる価値観抽出・トレンド分析との連携によって、「その人らしさを軸にしたキャリアシナリオ」の提案が可能となります。
さらに、キャリア・エンゲージメントの概念を通じて、キャリアへの関与度や心理的没入状態を測定・可視化することで、内発的な成長意欲を喚起し、行動変容を促進する機能を持ちます。もちろん、今後のAI活用には、「透明性」「説明可能性」「人間中心性」が不可欠です。キャリアAIドックの開発・運用においても、以下の倫理的指針が求められています。
キャリアAIドックは、「キャリアドック」からの飛躍的進化であり、一時的なブームではなく、個人の成長と組織の持続性を支える新たな社会インフラの一翼を担いつつあると私は考えています。人生100年時代において、自らのキャリアを内省し、データに基づいて再設計する習慣は、医療における「健康診断」と同様に、社会に定着していきます。その時、キャリアAIドックは、すべての働く人にとっての「キャリアナビゲーター」として機能することとなるでしょう。
プロティアン・ゼミでも、キャリアAIドックの動向について、今後も取り上げていきます。それではまた次回に!

- 田中 研之輔氏
- 法政大学キャリアデザイン学部教授/一般社団法人プロティアン・キャリア協会 代表理事/明光キャリアアカデミー学長
たなか・けんのすけ/博士:社会学。一橋大学大学院社会学研究科博士課程修了。専門はキャリア論、組織論。UC. Berkeley元客員研究員、University of Melbourne元客員研究員、日本学術振興会特別研究員SPD 東京大学。社外取締役・社外顧問を31社歴任。個人投資家。著書27冊。『辞める研修辞めない研修–新人育成の組織エスノグラフィー』『先生は教えてくれない就活のトリセツ』『ルポ不法移民』『丼家の経営』『都市に刻む軌跡』『走らないトヨタ』、訳書に『ボディ&ソウル』『ストリートのコード』など。ソフトバンクアカデミア外部一期生。専門社会調査士。『プロティアン―70歳まで第一線で働き続ける最強のキャリア資本論』、『ビジトレ−今日から始めるミドルシニアのキャリア開発』、『プロティアン教育』『新しいキャリアの見つけ方』、『今すぐ転職を考えてない人のためのキャリア戦略』など。日経ビジネス、日経STYLEほかメディア多数連載。プログラム開発・新規事業開発を得意とする。
この記事を読んだ人におすすめ

HR領域のオピニオンリーダーによる金言・名言。人事部に立ちはだかる悩みや課題を克服し、前進していくためのヒントを投げかけます。
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント