日本の人事部「HRアワード2025」受賞者インタビュー
「組織行動の考え方」が届ける“元気”
HRの未来は「心理と感情を束ねる場づくり」
にある
髙橋 潔さん(立命館大学総合心理学部教授、神戸大学名誉教授)
服部 泰宏さん(神戸大学大学院経営学研究科教授)
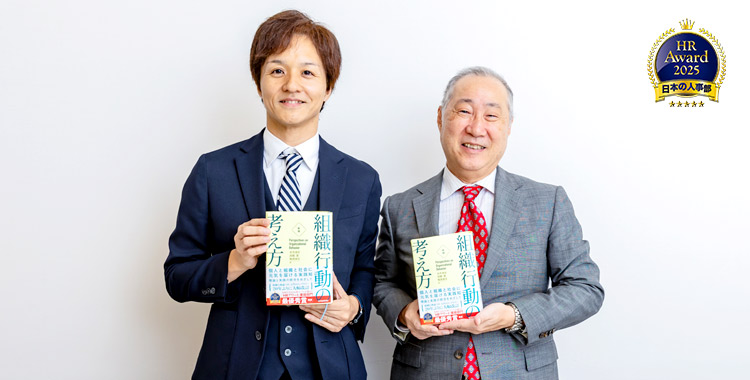
人事の仕事に限らず、あらゆる仕事がAIにより代替されていく中で、「人間にしかできないこと」の価値はどこに宿るのでしょうか。また、日々の業務に追われ、組織の「元気」を取り戻したいと願う人事パーソンやマネジャーは、何を学び、どう行動すべきでしょうか。
この問いに、20年の時を経て全面改訂された名著『新版 組織行動の考え方』(東洋経済新報社)が答えます。本書は、「HRアワード2025」書籍部門 最優秀賞を受賞。組織行動論の知識を体系的に網羅するだけでなく、組織に「元気」を取り戻すというメッセージを副題に掲げています。著者である髙橋潔さんと服部泰宏さんに、改訂にかけた熱い思いや、これから人事部門が担うべき「未来へのビジョン」について伺いました。
「HRアワード」の詳細はこちら

- 髙橋 潔さん
- 立命館大学総合心理学部教授、神戸大学名誉教授
たかはし・きよし/立命館大学総合心理学部教授、神戸大学名誉教授。1960年大阪府生まれ。慶應義塾大学文学部卒業後、ミネソタ大学経営大学院にてPh.D.を取得。神戸大学大学院経営学研究科教授などを経て現職。専門は組織行動論、産業心理学。著書に『人事評価の総合科学』(白桃書房)、『ゼロから考えるリーダーシップ』(東洋経済新報社)、『経営とワークライフに生かそう! 産業・組織心理学(改訂版)』(共著、有斐閣)などがある。

- 服部 泰宏さん
- 神戸大学大学院経営学研究科教授
はっとり・やすひろ/神戸大学大学院経営学研究科教授。1980年神奈川県生まれ。神戸大学大学院経営学研究科博士課程後期課程修了。博士(経営学)。滋賀大学経済学部准教授、横浜国立大学大学院国際社会科学研究院准教授などを経て現職。専門は人的資源管理論、組織行動論。著書に『日本企業の心理的契約』『採用学』など。
組織に「元気」を届ける改訂版 20年を経て変わらない「共著」の流儀
『新版 組織行動の考え方』のHRアワード最優秀賞の受賞、おめでとうございます。まずは、本書を改訂された経緯についてお聞かせください。
髙橋:このたびは栄誉ある賞をいただき、ありがとうございます。改訂の話が出たときに旧版を主導的に執筆された金井先生と相談し、新たな執筆者を加える必要があるという話になりました。そこで、さまざまな候補の中から服部先生にお引き受けいただき、新版を出すことになりました。
服部:私がまだ大学院生の頃に、最初に手に取った組織行動論の本が旧版の『組織行動の考え方』でした。旧版は、人事の基礎理論である組織行動論の教科書として、長く愛されてきた名著。時代が回ってこのような形で携わることになるとは、自分のキャリアの積み重ねを感じます。金井先生と髙橋先生が積み上げてきたものがあるため、「変なものを書くぐらいなら出さない方がいい」という覚悟で臨みました。
- 【参考】
- 組織行動論とは|日本の人事部
本書の副題は「個人と組織と社会に元気を届ける実践知」ですが、“元気”という言葉を入れた真意は、どこにあるのでしょうか。
髙橋:旧版のベースになったのが、一橋ビジネスレビュー誌の「元気の出る経営行動科学」という連載でした。当時から、主導的に執筆された金井壽宏先生の意思として、「元気」というキーワードが根底にあったんです。
新版を執筆するにあたり全体の流れをまとめたときに、個人と組織が仕事で元気になることが、ひいては社会全体が元気になることにつながるというテーマが根底に流れていたたため、副題として打ち出すことにしました。
服部:金井先生は、MBAの授業で「OB(組織行動)の授業は楽しくなきゃだめだ」「危機感ばかりを煽るのは経営ではない」と、常々おっしゃっていました。組織行動論には、アカデミックが陥りがちな「学びの苦しさ」ではなく、受講者が「元気になっている」と感じられる、ある種の宿命的なものがあると考えています。科学的な厳密さを残しつつも、学びを楽しいものにするという精神性が、「元気」という言葉に込められています。
本書は3名による共著ですが、学術書としては珍しい執筆スタイルを取られたと伺いました。
髙橋:旧版の執筆時から、第一筆者が口火を切り第二筆者に原稿を渡して、お互いに「容赦なく相手の文章を直す」というスタンスを取っていました。当時の僕の文章は論文調で固かったのですが、金井先生から直されるプロセスを経ることによって、金井先生の文章のような「肌にしっとりとなじむ」柔らかい文章へと変化していくのは面白い体験でした。
この執筆スタイルにより、それぞれの著者の「くせ」や「色」が消え、まるで一人で執筆しているかのような統一感が生まれ、読みやすい本になります。今回は、その「真の共著」の流儀を服部先生にも体験してもらいたいという思いもあり、この方針を貫きました。
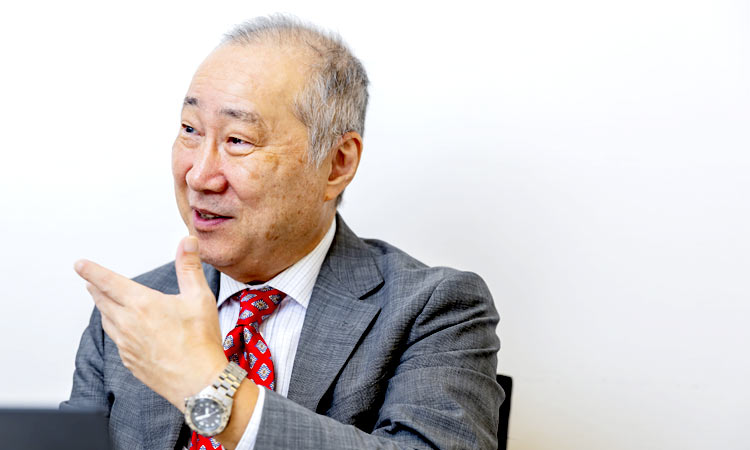
服部:学術書を共著で出版する場合、それぞれが専門分野の章だけを執筆して合体するスタイルが一般的です。しかしこの方式では、各執筆者が見ている世界が一致せず、議論が断片的になってしまう恐れがあります。「それぞれの章は面白いが、全体を通じて訴える何かに欠ける」ということになりがちです。
あえてお互いの文章を修正し合うことで、私が見ている世界と、髙橋先生が見ている世界が重なり、矛盾せずにより深い議論が生まれる。この共著のスタイルは手間がかかりますが、学問や議論が細分化しがちな現代において、互いの視点を補完し合うという点で非常に意味があったと考えています。
600ページを超える大著を執筆する中で、旧版から「変えたい点」や「新しく書き足したい点」はどのようなところでしたか。
髙橋:旧版でも組織行動の中核となるテーマは扱っていましたが、現代における組織行動で扱うべきテーマをもれなくカバーするため、六つの章を新たに書き下ろしました。情報が古い部分はすべて新しくし、論理的な流れも再構築しました。本書全体として、個人からチーム、そして組織へという流れになっており、ストーリーを感じて読めるものになったと思います。
また、新版では東洋経済新報社の担当編集者である佐藤さんの提案で、旧版の横書きから縦書きに変更しています。最初はただ原稿の縦横を変えるだけと高をくくっていましたが、横書きの英語に頼って観念的に説明してきたものを、話の流れを活かして縦書きにすることによって、理論と実践の違いや、西洋と東洋のものの見方の違いを意識するようになります。苦労しましたが、そのかいがあって、旧版と比べると一般的な読み物としてさらに親しみやすくなったと感じています。
日本的経営の思想と東洋の知恵
本書では、東洋思想や日本の文学作品が随所に引用されている点が非常にユニークです。グローバルスタンダードな経営理論が席巻する中で、どのような意図があったのでしょうか。
髙橋:金井先生と私は海外で学位を取得し、欧米の知識を輸入して、商社マンのような立場で日本に新しいものを紹介してきました。今回の改訂に際して、組織行動という分野全体を一歩引いて見て、欧米の理論をそのまま時代に合わせてアップデートするだけでは物足りない、という感覚があったのです。
海外の事例や概念が、日本の現場に合わないという読者の声もありました。そこで、金井先生に対する「恩返し」も込めて、新版にはアジア的要素を取り入れるべきだと考えたのです。
組織行動論のベースは欧米の研究です。そこに日本の思想や東洋哲学をフィットさせるのは簡単ではありません。しかし、今こそ立ち返るべき必要があると思い、多くの方になじみのある渋沢栄一の思想や、孔子と老子を中心とした中国古典、仏教的な「利他の精神」などのエッセンスをちりばめました。
服部:日本の経営学のスタンスには、アメリカの理論を徹底的に追求する方向性と、良くも悪くも日本の独自性を追いかける、いわば議論の「ガラパゴス化」を是とする方向性があります。本書が取る立場はどちらでもなく、アメリカの理論を日本の土壌に合わせる「土着化」を目指しています。つまり、欧米から学ぶべきところは学びつつ、全く同じことをするのではなく、日本独自の風味を加える「中庸」のスタンスです。

髙橋:稲盛和夫さんや松下幸之助さんなど、日本のものづくりを牽引(けんいん)した創業者は、「利他の精神」で経営を捉えています。近江商人の「三方よし」の考え方も同じです。仏教と神道が自然に結びついた日本では、「利他のこころ」が経営を支える哲学となっているのです。
渋沢が新札の顔となり、『論語と算盤』も再ブームが起きています。渋沢が孔子の『論語』から学んだように、中国の古典から学び続けてきたこの国の成り立ちも踏まえて、東洋的な考え方を学び直すことが重要です。
人事パーソン・マネジャーのための「知的活動」としての組織行動論
本書は「実践知」であるとうたわれています。日々の業務に追われる人事担当者やマネジャーは、この本をどのように活用すべきでしょうか。
髙橋:本書は学術的な側面があるため、すぐに身につく知識やスキルを意識して書いているわけではありません。私たちが目指しているのは、モチベーション、リーダーシップ、キャリア、組織文化など、職場で日常的に経験する事象に対して、理論的アプローチがあることを理解してもらうことです。
理論があるということは、すでに先人たちが深く考えてきた知恵があるということ。この本を活用すれば、日々の仕事で直面する人・組織の課題を俯瞰(ふかん)して、自分なりの意見をまとめることができます。そうした知的活動を続けることで、たとえMBAに通わなくても、部門やチームを率いていく人材になれると信じています。
服部:“いい本”というのは、読む人のレベルによって与えてくれる学びが変わる本だと思っています。私自身、学生時代に旧版の『組織行動の考え方』を読んだ時と、今、教授として執筆に携わり、改めてこの本に相対した時では、学びが全く異なります。
読者によって、この本の活用法は変わってくるでしょう。学部生や初学者にとっては、リーダーシップやモチベーションの理論をシャワーのように浴びることで、アイデアを広げることに役立ちます。
人事パーソンの方にとっては、この本を読んでモヤモヤが残るぐらいの方がちょうどいいと考えています。本で得た理論を基に、実践の場で「ちょっとこれを使って考えてみよう」と、これまでの常識を揺さぶる道具として活用してほしいですね。
足りない6章を書き下ろし、全16章の教科書として完成
旧版は10章でしたが、新版は16章に増えています。どのような章を追加されたのでしょうか。
髙橋:採用、ストレス、マネジメント、チームワーク、人材育成、組織文化の章を書き下ろしました。本書一冊で組織行動の科目がもれなくカバーできるようになったと思います。
新たに加えた章のうち、私は第6章「組織に欠かせない感情とストレスのメンテナンス」と、第10章「マネジメントとリーダーシップは双子なのか」、第13章「人を伸ばす組織の考え方」を主に担当しました。
第6章では、梶井基次郎の『檸檬』を冒頭に取り上げながら、職場でのストレスに関する理論を展開しています。組織行動論でストレスを扱うのは、経営学から離れ、心理学に寄り過ぎているような感覚があるかもしれません。しかし、人事部の方の多くが職場のメンタルヘルスにかかわる昨今、この章は避けては通れませんでした。
第10章では、マネジメントとリーダーシップの違いを明確化しました。リーダーシップの模範が見られない職場では、マネジャーとリーダーの役割が混同されがちです。両者の違いを明確にした上で、リーダーシップのリテラシーを身につけることを意図しています。
第13章では、リスキリングやリカレント教育について論じています。欧米やアジアの諸外国では、経営層にMBAやPh.D.保有者が当たり前にいるのに対し、日本のビジネス界は知らず知らずに低学歴国となっている現状を論じています。
服部さんが主に執筆を担当された章についても、要点やポイントをお聞かせいただけますか。

服部:私は第2章の「働く個人の初期値を見定める――人材採用の考え方」、第12章「ヨコのつながりを活かす――マネジメント手法としてのチームワーク」、第14章「組織に息吹を吹き込む――組織文化と組織開発」の章を担当しました。
組織行動論の教科書に「採用」の章が入ることも非常にまれです。旧版では「評価」の章が入っており、これも組織行動論の本で語られるのは斬新なことでした。その背景には、「組織行動論は実践としての人事と密接に関わっている」という、お二人の先生の強い想いがあったように思います。今回も、オーソドックスな欧米の研究に限らず、「これはぜひ伝えておきたい」というものを新版でも随所に入れ込んであります。
さらに、新しい理論の萌芽と言うべきものも加えています。例えば、モチベーションの4章で登場する「夢理論」は、アメリカの心理学会では誰も知らないものですが、非常に面白い考え方だと思います。
AI時代の「人事」の価値:アウトソースできない心理と感情を束ねる
AIが人事評価や採用を代替しつつある昨今、テクノロジーが進化するほど、逆説的に「人間にしかできないこと」の価値が問われています。お二人が見据える組織において、「人事」の仕事の価値はどこに宿るのでしょうか。
髙橋:人材の採用、評価、育成といった業務は、AIに限らずアウトソースされる運命にあると考えています。したがって人事部門は、アウトソースできない人の心理や感情、そこから生まれるビジョンを束ねる「場」を作るのがよいのではないでしょうか。
この国で実現してほしい未来は、組織のいたるところで、明日の組織のあり方やビジョンが、ワイワイガヤガヤ話し合われていること。そうした「ワイガヤの場」をうまく作り上げていくことが、これからの人事に求められると考えています。
グローバルな観点では、人材の海外化を促進し、「おもてなし」やサービスなどのエッセンシャルワークを軸に、外貨を稼ぐ必要があると感じています。回転すしやラーメンチェーンが、またプロ野球選手やサッカー選手の活躍が、海外で新たに日本を感じる機会であり、国際化の先陣を切っています。日本の人材を海外に派遣し、仕事や生活、学校のサポートをし、人材の交流を促進することが、人事の新たな仕事になるかもしれません。
服部:神戸大学の経営学部の先生方が大切にしてきたのは、経営学とは「良いことをうまくやる」ことを考える分野だということです。
「うまくやる」というのは、パフォーマンスを上げるためのハウツーや効率性、費用対効果を考えることです。一方で、「良いこと」をやるという視点が組織行動論では大切にされてきました。
例えば、ただ単に離職率を下げたいだけなら、極端な話、社員を「洗脳」すればいいかもしれません。しかし、それは「良いこと」とは言えないでしょう。私たちが本当に考えるべきなのは、金もうけだけではない「みんながワクワクするような目標」や、「大きなことを成し遂げるための夢」を組織が抱けるかどうかなのです。「良いこと」を定義することこそ、AIにはできず、現時点では人間の方が得意とする領域です。
これからの人事パーソンに求められる役割は、「われわれの会社は何をしたいのか」「社会に届けたい“良いこと”とは何か」といった、哲学や倫理に近い問いに向き合い、組織の進むべき道、すなわちビジョナリーなものをしっかりと言葉に紡いでいくことではないでしょうか。
元気を取り戻したい人事パーソン・マネジャーへのメッセージ
日々の業務に追われている人事担当者やマネジャーに向けて、お二人からメッセージをいただけますでしょうか。
服部:人事パーソンの皆さんには、「分かっている」「知っている」という感覚を、あえて一度かっこに入れてほしいと思います。
面接を10年も経験すれば、「面接とはこういうものだ」と分かった気になってしまいますし、部下との1on1を数年続けていると、「ああ、こんな感じね」と思ってしまいがちです。これは、自信につながる良いことでもありますが、同時に学びを止めている側面もあります。
経験の長い方ほど、一度まっさらな状態に戻って新しい考え方や理論に触れてみてください。「常識を揺さぶる」作用があります。時に難しく感じる部分があっても構いません。「本当にこれでよいのか」と立ち止まって、改めて考えることが、結果的には日本の人事を良くしていくことにつながると思っています。
髙橋:繰り返しますが、これからの人事の役割は、アウトソースできない人材の心理や感情、ビジョンを、人事部門が組織の意思を代表して束ねていく「場」を作ることです。
仕事は不安やストレスの元ではなく、学びや喜び、やる気、感謝といったポジティブな心理を豊かにしていくものだと捉えてほしいですね。組織の未来のビジョンを、みんながワイワイガヤガヤと語り合い、夢を見られるような、楽しい雰囲気の職場を作ってほしい。それが、未来の組織を牽引する人事の姿だと信じています。

※写真右側は東洋経済新報社の担当編集者・佐藤敬さん
(取材:2025年10月17日)
この記事を読んだ人におすすめ
-

宇田川元一さん: 変革とは「自分たちであり続ける」こと――父への思いを越えて、「構造的無能化」を論じることが必要だった
-

名古屋鉄道株式会社: 名古屋鉄道の「介護離職ゼロ」に向けた挑戦 「まずは気軽に相談してほしい」という、人事部からのメッセージ
-

中外製薬株式会社: キャリアは会社が与えるものではなく、社員が自ら創るもの 「個」の主体性を覚醒させる、中外製薬の人事制度改革
-

西田政之さん: CHROに求められるのは制度の設計ではなく「関係性の土壌」を育むこと YKK AP 西田氏が語る“組織の気象予報士”としての人事哲学
-

木下達夫さん: 世界中の現場で学んだ「人事は運用が8割」 一人ひとりのポテンシャルをアンロックして、パナソニックから日本の人事を変える

さまざまなジャンルのオピニオンリーダーが続々登場。それぞれの観点から、人事・人材開発に関する最新の知見をお話しいただきます。
会員登録をすると、
最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!
- 参考になった2
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0
- 1
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント







